書き下し文「平家物語」
※読みは間違っている場合もありますのでその際はご指摘くださるとうれしいです
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹(しゃらそうじゅ)の花の色、盛者必衰(じょうしゃひっすい)の理(ことわり)を顕(あらわ)す。おごれる人(もの)も久しからず、ただ春の夜(よ)の夢のごとし。猛き人も遂には滅びぬ、偏(ひとえ)に風の前の塵(ちり)に同じ。
遠く異朝(いちょう)をとぶらへ(え)ば、秦(しん)の趙高(ちょうこう)、漢の王莽(おうもう)、梁(りょう)の周伊(しゅうい)、唐の禄山(ろくさん)、これらは皆旧主先皇(きゅうしゅせんこう)の政(まつりごと)にも従は(わ)ず、楽しみを極め、諌(いさめ)をも思ひ(い)入れず、天下の乱れん事を悟らずして、民間の愁ふる(うれうる)所を知らざりしかば、久しからずして、亡じ(ぼうじ)にし者どもなり。近く本朝(ほんてい)をうかがふ(う)に、承平(じょうへい)の将門(まさかど)、天慶(てんぎょう)の純友(すみとも)、康和(こうわ)の義親(よしちか)、平治の信頼(のぶより)、これ等(ら)は驕れる(おごれる)事も猛き(たけき)心も、皆(みな)とりどりにこそありしかども、まぢかくは、六波羅(ろくはら)の入道前(さきの)太政大臣平朝臣(たいらのあそん)清盛公と申しし人の有様、伝え承る(うけたまわる)こそ、心もことばも及ばれね。
その先祖を尋ぬれば、桓武天皇第五の皇子(おうじ)、一品(いっぽん)式部卿(しきぶのきょう)葛原親王(かずらはらのしんのう)九代の後胤(こういん)、讃岐守(さぬきのかみ)正盛( まさもり)が孫(そん)、刑部卿(けいぶきょう)忠盛朝臣(ただもりのあそん)の嫡男(ちゃくなん)なり。かの親王(しんのう)の御子(みこ)高見の王、無官無位にして失せ給ひぬ(たまいぬ)。その御子(おんこ)高望王(たかもちのおう)の時、初めて平(たいら)の姓(せい)を賜って、上総介(かずさのすけ)になり給ひし(たまいし)より以来(このかた)、忽ち(たちまち)に王氏を出でて人臣につらなる。その子(こ)鎮守府(ちんじゅふ)将軍良茂(よしもち)、後には国香(くにか)とあらたむ。国香より正盛に至るまで六代は、諸国の受領(ずりょう)たりしかども、殿上(てんじょう)の仙籍(せんせき)をば未だ許されず。
しかるを忠盛(ただもり)備前守(びぜんのかみ)たりし時、鳥羽院(とばのいん)の御願(ごがん)得長寿院(とくちょうじゅいん)を造進(ぞうしん)して、三十三間の御堂(みどう)をたて、一千一体の御仏(みほとけ)を据ゑ奉る(すえたてまつる)。供養は天承(てんしょう)元年三月十三日なり。勧賞(けんじょう)には闕国(けっこく)を賜ふ(たまう)べき由(よし)仰せ(おおわせ)下されける。折節(おりふし)但馬国(たじまのくに)のあきたりけるを賜(た)びにけり。上皇(じょうこう)御感(ごかん)のあまりに、内(ない)の昇殿を許さる。忠盛三十六にて初めて昇殿す。雲の上人(うえびと)これをそねみ、同じき年の十二月二十三日、五節(ごせつ)豊明(とよのあかり)の節会(せちえ)の夜(よ)、忠盛を闇討(やみうち)にせんとぞ擬(ぎ)せられける。
忠盛これを伝へ(え)聞きて、「われ右筆(ゆうひつ)の身にあらず。武勇の家に生まれて、今不慮の恥にあは(わ)んこと、家のため身のため心憂(う)かるべし。詮(せん)ずるところ、身を全うして君(くん)に仕ふ(つかう)といふ(う)本文(ほんもん)あり」とて、かねて用意をいたす。参内(さんだい)の初めより、大きなる鞘巻(さやまき)を用意して、束帯(そくたい)の下にしどけなげに差し、火のほの暗き方(かた)に向かつ(っ)て、やは(わ)らこの刀を抜き出だし、鬢(びん)に引き当てられけるが、氷なんどのやう(よう)にぞ見えける。諸人(しょにん)目をすましけり。
そのうへ、忠盛が郎等(ろうどう)、もとは一門たりし木工助(もくのすけ)平貞光(たいらのさだみつ)が孫(そん)、進三郎大夫(しんのさぶろうだいふ)季房(すえふさ)が子、左兵衛尉(さひょうえのじょう)家貞(いえさだ)といふ(う)者ありけり。薄青(うすあお)の狩衣(かりぎぬ)の下に萌黄縅(もえぎおどし)の腹巻を着、弦袋(つるぶくろ)つけたる太刀(たち)脇ばさんで、殿上の小庭に畏つて(かしこまって)ぞ候ひ(そうろい)ける。貫首(かんじゅ)以下(いげ)怪しみをなし、「うつほ柱(空柱)よりうち、鈴の綱(つな)の辺(へん)に、布衣(ほうい)の者の候ふ(そうろう)は何者ぞ。狼藉(ろうぜき)なり。罷(まか)り出でよ」と六位をもつて(もって)言は(わ)せければ、家貞(いえさだ)申しけるは、「相伝(そうでん)の主(ぬし)備前守(びぜんのかみ)の殿(どの)、今宵(こよい)闇討にせられたまふ(う)べき由(よし)、承り候ふ(たまわりそうろう)間、そのならんやう(よう)を見んとて、かくて候ふ(そうろう)。えこそ罷り(まかり)出づまじけれ」とて、畏つて(かしこまって)候ひ(そうろい)ければ、これらをよしなしとや思は(わ)れけん、その夜(よ)の闇討なかりけり。
忠盛(ただもり)御前(ごぜん)の召しに舞は(わ)れければ、人々拍子(ひょうし)を変へて(かえて)、「いせへいじはすがめなりけり」とぞはやされける。この人々は、かけまくもかたじけなく、柏原(かしわばらの)天皇の御末(おんすえ)とは申しながら、中ごろは都の住まひ(い)もうとうとしく、地下(ぢげ)にのみふるまひ(い)なつ(っ)て、伊勢の国に住国(じゅうこく)深かりしかば、その器物(うつわもの)に事寄せて、「伊勢平氏」とぞ申しける。そのうへ(え)、忠盛目のすがまれたりければ、かやう(よう)にははやされけり。いかにすべきやう(よう)なくして、御遊(ぎょゆう)もいまだ終は(わ)らざるに、ひそかに罷(まか)り出でらるるとて、横だへ(え)差されたりける刀をば、紫宸殿(ししんでん)の御後(ごご)にして、かたへ(え)の殿上人の見られける所に、主殿司(とものづかさ)を召して、預け置きてぞ出でられける。家貞(いえさだ)待ち受けたてまつ(っ)て、「さて、いかが候ひ(そうろい)つる」と申しければ、かくとも言(こと)はまほ(お)しう思は(わ)れけれども、言ひ(いい)つるものならば、殿上までもやがて切り上(あが)らんずる者にてある間、「別(べつ)のことなし」とぞ答へ(え)られける。
現代語訳「平家物語」
祇園精舎の(無常堂の)鐘の音は、諸行無常(万物は刻々と変化していくもの)の響きがある。(釈迦入滅(しゃかにゅうめつ)の時に白色に変ったという)沙羅双樹の花の色は、盛んな者もいつか必ず衰えるという道理をあらわしている。権勢を誇っている人も、永久には続かない。それは春の夜(よ)の夢のようなものだ。勇猛な者も最後には滅びてしまう。それは全く風の前の塵と同じだ。
遠く外国に例を求めれば、秦の趙高(ちょうこう)、漢の王莽(おうもう)、梁の周伊(しゅうい)、唐の安禄山(あんろくざん)、これらの者は皆、もとの主君や前代の皇帝の政道にも従わず、ぜいたくの限りを尽くし、人の諌めを受け入れようともせず、天下が乱れることを悟らず、民衆の憂いも顧みなかったので、長続きせず滅亡してしまった者たちである。また近くわが国の例を見ると、承平(じょうへい)の平将門、天慶(てんぎょう)の藤原純友、康和(こうわ)の源義親、平治の藤原信頼、これらの人は権勢を誇る心も勇猛なことも、皆それぞれ甚だしいものだったが、やはりたちまち滅びた者たちである、ごく最近では、六波羅におられた入道前の太政大臣平の朝臣清盛公と申した人のありさまを伝え聞いてみると、想像することもできず、言うべき言葉もないほどだ。
その先祖を調べてみると、清盛公は桓武天皇の第五皇子・一品式部卿葛原親王の九代目の子孫にあたる讃岐守の正盛の孫であり、刑部卿忠盛の朝臣の嫡子(ちゃくし)である。あの葛原親王の御子(みこ)の高見の王は、官職にもつかず位階(いかい)もなく亡くなられた。その御子の高望の王の時に、はじめて平の姓をいただいて、上総介になられてから以後すぐに皇族を離れて臣下の列に加わった。その高望の王の子の鎮守府の将軍良望は、後に国香と名を改めた。その国香から正盛に至るまでの六代の間は、諸国の受領だったが、まだ殿上人として宮中への昇殿を許されなかった。
ところが、忠盛が備前(岡山県)の守(かみ)だったときに、鳥羽院の御祈願寺(ごきがんじ)、得長寿院を造進し、三十三間堂を建てて、一千一体の御仏像(ごしんぞう)を安置申し上げた。寺院落成は天承(てんしょう)元年三月十三日だった。そのほうびとして、鳥羽院が国司(こくし)が欠員になっている国をお与えくださると仰せ下さった。ちょうどそのときに但馬国((たじまのくに,兵庫県の一部)が空いていたのをお与え下さった。上皇(鳥羽院)は、忠盛の功績に御感心のあまり、内裏(だいり)への昇殿をお許しになった。しかし、殿上人たちはこれをねたみ、同じ年の十二月二十三日、五節豊明の節会(せつえ)の夜(よ)に、忠盛を暗殺しようと話し合った。
忠盛はこれを人づてに聞き、「自分は文官(ぶんかん)の身ではない。武人(ぶにん)の家に生まれて、今、思いもしない恥を受けては、家のためにも自分のためにも情けないことだ。『自分の身を無事に守って主君にお仕えする』ことこそが本分(ほんぶん)である」と思い、前もって対策を立てた。参内(さんだい)するはじめから大きな鞘巻(さやまき)を用意し、束帯(そくたい)の下に人から見えるようにだらしなく差して、灯(あかり)のほの暗い方に向かって、静かにその刀を抜き出し、鬢(びん)に当てた。それが氷などのように冷たくいかにもよく切れそうに見えた。人々は驚いて目を凝らして見た。
その上、忠盛の家来に、もとは同じ平家一門で木工助(もくのすけ)の職にある平貞光の孫・進三郎大夫季房(しんのさぶろうだいふすえふさ)の子で、左兵衛尉(さひょうえのじょう)家貞という者がいた。その男が、薄青(うすあお)の狩衣(かりぎぬ)の下に萌黄縅(もえぎおどし)の腹巻を着て、弦袋(つるぶくろ)をつけた太刀を小脇にはさんで、殿上の小庭にうやうやしく控えていた。蔵人頭(くろうどのとう)をはじめ、人々はみな怪しく思い、「うつほ柱の内(ない)の鈴の綱(つな)あたりに布衣(ほうい)を着た者が控えているのは何者か。無礼千万である。早々に出て行け」と、六位の蔵人(くろうど)に命じて言わせたが、家貞は、「先祖代々お仕えしている主君・備前守殿が、今宵、闇討ちにお遭いになるのではとお聞きし、その成り行きを見届けるために、こうして控えているのです。何としてもここを出て行くことはできません」と言って、そのままうやうやしく控えていた。殿上人たちはこのようすに具合が悪いと思ったのか、その夜(よ)の闇討ちは行われなかった。
忠盛が鳥羽院の御前(ごぜん)に召されて舞いを舞ったところ、人々は奏楽の拍子(ひょうし)を変えて、「いせへいじはすがめだよ」とはやし立てた。平氏の人々は、口に出すのも畏れ(おそれ)多いが、桓武天皇の御子孫でありながら、その後は都の暮らしも縁遠くなり、地下人(ぢげびと)としてのみ行動するようになって、伊勢の国での暮らしが縁深くなっていた。そのため、伊勢の国の特産物である焼き物にかこつけて、「伊勢平氏」と言ったのだ。その上、忠盛は目がすがめ(やぶにらみ)だったので、そのようにはやし立てたのだった。忠盛はどうしようもなく、御宴の遊びもまだ終わらないうちにこっそりと退出しようと、紫宸殿(ししんでん)の北側の、殿上人が近くに見ている所で主殿司(とものづかさ)を呼び、腰に横にして差していた刀を預けて退出した。家貞は忠盛を待ち受け、「ところで、ごようすはいかがでございましたか」と申したので、忠盛はかくかくしかじかと言いたかったが、本当のことを言えば、家貞はただちに殿上の間に切り込みかねない者だったので、「格別のこともない」と答えた。
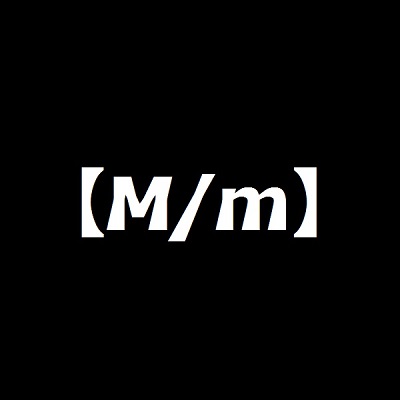

 TOP
TOP