※「~くん、言葉を信用するでない。誰が信用に足りる人間なのか、それはキミが判断せよ。たとえば仮に私が誰かに精神を乗っ取られ、自分の言葉でないものを喋くっていたとして、キミにその真偽が判定できるかね。そのような場合、信用できるのは自分のみだよ。自分以外の誰が真実を語っているのかは、自らの英知に耳を傾けて自力で判断するしかないのだ。それだけの見識と判断力は必要である。他人の言葉に耳を貸す必要はない」
※「概念は人間を媒介にして増殖している。概念にとって人間は、いわば伝達物質なのだ。人間が言語を使うように、概念は人間を使う。気を付けることだ。~くん。概念に振り回されてはならない。時としてそれは人間に牙を剥く。使い捨ての便利な道具にされないよう、注意深く思考し、行動せねばならん」
※どんなことが起こっても、それが真実でなければ全ては平行線だ。それを計るものさしは今私の手元にはないがね。あらゆる疑問や現実には起こりえないことを見事に解消する強固な理屈だ。前提が間違っていれば導き出される答えも正しくはない。だが、さっきも言ったようにものさしはない。必要かと言われても私には分からない。向こう側が見えない高い壁を前にして、何があるか分からないものを目指して上るか、そうでないかは人それぞれだ。人は常に楽しさを求めている。幸福を渇望している。どんなものなのかを知りたがっている。だが、そんなに根気強くはない。私も最初は分からなかったものだ。これが後になって自分にどのような影響をもたらすかなんて、分からない。だがしかし、そこにはもはや恐怖はない。概念と決め付けるのであれば、それはそれでいい。だとするならばだ、まさしくこれは概念の生き残り戦略だ。今や概念は我々を蝕み、そこを住みかとして増殖している。現代において世界中で市民権を得ている概念は、それも作品ごとに設定を変えてだ。これだけ多様化すれば、根絶やしにしようともどれか一つは確実に生き残るだろう。大部分が死滅したとしても、根本となる遺伝情報は確実に残される。ひとたび劣性となった因子が再び優性となる日が来ることもある。これはすべての情報に言えることだ。そして分からないというのは、そうゆうことだ
※「完璧な人間はいない。なぜなら、何一つ欠陥がないということは、それだけで一つの欠陥であるからだ」
※「意識を遠いヒュプノスの根城へと向かわした」
※「最初に経験する行為は、何事においても新鮮かつエキサイティングである」
※「猛禽の羽ばたきを聞いた小鳥のように震える~」
※「無限ループの可能性有。改竄ポイントの当該介入履歴を消去するよう要請する。どうやっても彼はそこに登場する」
※「信じているからこそ、疑いも持つのだ。信仰と信頼は別物だ。私はあなたを信頼しているが、入信はしていない」
※「行くぞ、~くん。情報は鮮度が大切だ。情報の商品価値は時間とともに下落する。そしてそれが正確な情報であるか否かは、自分自身で判断しなければならない」
※「『どちらでもない』のではなく、『どちらかではないのではない』ということだ」
※「なぜ?キミもまた『なぜ』なんてことを気にかけるのかね?そんなものは下水道のマンホールにでも投げ込みたまえ。いいか~くん。理由なぞ何だっていいのだ。なくてもちっとも困らないのだよ。少なくとも私は困らん。なぜなら現象というものは理由の有無に関係なく、理屈でもって発生するのだからな。重要なのは「どのように」だ。他の5Wなど、噛み終わったガムくらいの価値しかないのだ」
※「個人の感想など、全体的な現象にとっては無意味極まるものに過ぎない。個人的な観測結果と客観的な事実の間には、ここから土星くらいの隔たりがある」
※「質問に質問で返された。うーむ、なかなか高度な切り返しだ。質問に質問で返すのはアンフェアだが、しかしそれは相手がそれに気づかないときには役に立つものであって、そうでないときにはただの無為な攻撃に終わってしまうであろう。やはり返答は、大まかな点で具体的で、細かい部分は抽象的であるのが理想的であると思うが」
※「~が~に持つ感情、それは生者が死者に持つ後ろめたさである。死せる者から届いた声を生き残った者は無視できない。死者故に、死んだ者にはもう何も残されていないという理由をもって、生者は彼らを尊重しようとするのだ。身近な者の死、それも親しかった知り合いの死は、多少の差はあれども悲しみをもたらし、悲しみは涙を呼ぶ。だから人は涙するとき、記憶にある近い死を呼び覚ますのである。人が感動と悲しみを同列に見がちなのは、その心理的錯誤によるものだ。そう、人間の感情ほど騙されやすいものはない。私はそう考えている」
※「科学は決して万能ではない。なぜなら、科学は光の速度が速いことは証明できても、なぜ光はそれほど速いのかという問いには答えられないからだ」
※睡魔の残党を脳裏から完全に放逐した
※「冷静さを失うことは、堕落への第一歩だ」
※「趣味とは、個人個人の純然たる性格であり、すべての優先順位で上位に君臨する代物であって、そこに理屈などという介在の余地はない。まことにもって真実と言えよう」
※「ああ、~くん。嘆かわしい限りであるな。そんな根拠薄弱な理屈で世間を渡れると思ったら超間違いなのだ」
※「横暴もここに極まれり、といったところか」
※「列車が定期的に揺れる・・・その退屈な挙動の繰り返しがそろそろ眠気を誘い出す」
※「生き続けるつもりがあるなら、いつでも最悪の可能性を念頭に置いておいたほうがよい。それは別に私がペシミストだからではない。起こりうる最悪の可能性は、起こりうる最良の可能性よりも発生確率が高いのだ。なぜなら、最良の条件は個人の主観によって決定されるが、最悪の状態は万人に共通するものだからである」
※「前提が正しくなければ、導き出される答えも正しくはない」
※「質問の意味が分かりかねます。もっと理解可能な文脈で再質問なさって下さい」
※「私はいつもまともなことしか言わない。自分でも時々思うぞ。多少は冗談も織り交ぜたほうが、より円滑な会話を楽しめるのではないかとな」
「それこそご冗談を」
※「~君。いったいそれのどこが質問なのかね?なんでも語尾に”?”を付ければいいというものではないぞ」
※「当然誤差もあるだろうが、近似値ということで目をつむりたまえ」
※「何でも聞こう。私は無知なる者の助けを無下にするほど、心根の卑しい人間ではない。精霊の声に耳を澄ますドルイド教徒のように、~君の一言とやらに耳を傾けようではないか」
※「なんだね~君。その毒蛇を初めて見る子供マングースのような目は」
※「いや、解ってるよ。むしろ記憶力はあまり関係ない。見聞きしたことはね、すべて脳に格納されている。忘れるんじゃなくて、思い出さないようにストッパーが働いているだけなのさ。何もかもを覚え続けているのはちょっとした苦行だからね。人はそうやって自己の精神を守るのさ」
※「憶測での物言いは厳に謹んでいただきたい」
※「よかろう。愛情にあふれた抱擁あたりでよいかね?」
「いやです。」
「ならば私の自作ポエム『我が舞姫は心の片隅に』をキミに捧げよう。」
「いやです。」
「ここで朗読しても私はかまわないが。」
※「終わらない夜はない。地球が自転という行為をし続ける限り、夜が明ければ朝が来る。地球の自転が潮汐力[ちょうせきりょく]の関係で完全停止するのは幸いなことに、当分先のことである。しかし、遥かな未来のことかもしれないが、いずれそれは訪れる。永遠の夜と永遠の昼・・・その時君は、どちら側に住みたいと思う?」
「私が存在するべき場所は、常に黄昏の時空なのだ」
※「十二分に~」
※「それは私が実に有能な思考回路を有しているからだろうな」
※「ケンカをするという行為は、お互いに何らかのコミュニケーションをとろうとしていることの表れです。相手と接して、まったく何らリアクションを発しようという気にもならないことのほうが、よほど相手を軽んじ、蔑視していると言えるのです」
※「私は自分自身のことが嫌いです。それはなぜかと言うと、私自身の考えだけではなく、人間の生まれながらの本能にあると思うからです。例えば、私がもう一人の自分自身と出会うようなことが起こるとします。私はその人のことを、なんて腹の立つ人だろう、と感じるに違いないのです。なぜだと思いますか。人間は、自分自身の嫌なところには目を背けて見ないふりをするのが得意です。またそうでなければ精神を病みかねません。そのままの自分を見据えて、その自分をまるごと許容することのできる人間は希少価値があると思います。よほど天使のように朗らかな人か、逆に悪魔みたいに狡猾な人か、またはなんにも考えていない人でなければ無理なのです。それが普通です。つまり、前述の「例外な人」に該当するのであれば別ですが、そうでなければ自分自身を好きになることなど決してないのです」
※「敵を前に舌なめずりは三流のする事だ」
※「認めたくないのだな。若さゆえの過ちというものを」
※メルクリウス・シンドローム
その神は猛々しい山頂に降り立つと、周囲を睥睨してこのように言った
「もしあなたが商人なら、あなたの右手に水銀を与えよう。もしあなたが盗人なら、あなたの左手に竪琴を与えよう」
「水銀を、メルクリウス・シンドローム」
「その星は常に光と共にある。そして、三十秒後に沈む」
※優弥「ネズミの入った箱を想像してみる。ずらっと並べられた何個もの箱の中に、それぞれネズミが一匹ずつ入っている。そしてネズミたちにはすべて別々の薬を与える。そうやってどの薬がどんな効果を生むのか確認する実験の様子をね、ちょっと思い描いてもらいたいわけですよ。
箱の外…つまりこの世界の外側で、我々の動きを観察し、時にはコントロールしているような誰かがいる。そう、超越的観測者が。彼らが何のために何をしているのかは解らない。もちろん、全ては推論の域を出ませんよ。能力者同士をコネクトすることで一つの巨大な客観性を生み出すのか、はたまたそこから生まれる高次の知性体なのか。いずれにしても、我々はしがない箱の中の実験体で、何者かによって好きなようにいじくり回されている可哀相な下等動物なのかもしれませんね」
情想 目次
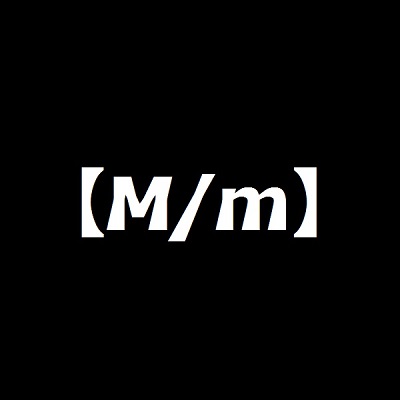

 TOP
TOP