サミュエル・バトラーといえば、チャールズ・ダーウィンの「自然選択説」による進化論を否定した人で有名である。その代表作にユートピア小説『エレホン』や半自伝的小説『万人の道』などがある。ほかにも『サミュエル・バトラ覚書抄(原題:ノートブックス)』など
自らを「アンファン・テリブル」と称したバトラーは、イギリスの人文系文化の担い手としての役目を果してきた最後の階層であった牧師の家に生まれ、その教養を十分吸収した上で、自然科学と文学芸術が同居した最後の舞台に登場し、両分野にまたがる事の出来た、きわめて広い視野を持つ特異な作家であった。生活のために定期刊行物に載せる文章を書きながら、専門分野を限定せずに幅広く、際物ではない永続する価値を持つ作品を求めた。このスタンスが、芸術作品は一般的に、いかにして後世に残っていくかという興味深い思索に彼を導いたばかりではなく、彼に当時の文壇から一定の距離を保たせた
『生命と習慣』
ダーウィン進化論の自然選択説の意味をいち早く理解できたバトラーは、その含意の危険性をも同時に察知することができた
自然が偶然に依存する変異を選択するのであれば、そこには方向も目的も存在しないばかりではなく、生命は外から規制される単なる機械的なプロセスに過ぎないことになる。精神や意志や心は宇宙から追放され、生物はあまねく機械になってしまうではないか。しかし、機械は何の為にあるのか。人間の手足の延長としてあるのではないか。ということは、逆に人間の手足は機械の一種として捉えてもいいかもしれない、とバトラーは考えた
われわれが必要に迫られて機械を造るのと同じ理由で手足は造られたのではないか。しかし、機械と違って手足はわれわれの知らないうちに出来ている。これは記憶により形態が造られた例である
人間の話したり、歩いたり、読んだり、書いたりする技能は誕生後に獲得されるが、これらは本能と呼ばれていいものである。しかし、飲み込んだり、呼吸したりする動作は、誕生前から存在するものであり、それは人類よりも古い動物の祖先の記憶に由来するものである。さらに、消化したり、血液が循環したりするのは最も古い習慣に由来し、無脊椎動物にまでさかのぼる。/この無意識の記憶をバトラーは彼の進化論の中心に据えた
バトラーはさらに話を進めて、世代を通して受け継がれる記憶の問題を論じる。/個々人は経験なしでどうして経験の記憶を持つのか。ここで個人の同一性の問題が生じる。人間は歳をとってから生まれたての赤ん坊時代を振り返っても何も覚えていないように、記憶はなくても、生まれたての赤ん坊は胎児に、さらには受精卵へと繋がりを持っている。つまり親と子は同じ人格ということになる
胎児は、連想により記憶が呼び覚まされるまで眠っている先祖の行為の記憶を持つ。習慣は記憶に基づき、遺伝現象の根底を形成している。人間は進化するにしたがい異なる習慣を身に着けることになるが、古い習慣ほど無意識となる一方、新しい習慣は意識的になり、それを獲得するために試行錯誤の努力が必要となる。したがって誕生とは、生命の始まりなどではなく、意識的な記憶の獲得のために無意識の記憶を離れる瞬間である。/このように進化とは決して外から人間に働きかけるものではなく、内側の知る欲求、生きる欲求、意志や必要の感覚によって創り出されるものであるとバトラーは結論している。バトラーの進化の理論では、すべて創造された物は消滅せず、時の経過とともに変転する
『新旧の進化論』
『新旧の進化論』でまずバトラーが試みたことは、前作『生命と習慣』で披瀝した独自の進化論の史的位置付けである。それを彼はダーウィン進化論に対峙するものとして打ち出そうと試みた。すなわち、「自然選択」を排除した進化論である
注意すべきは、バトラーが進化論を論じる際に、「目的論的」という場合、それは神の、つまり外的なデザインからくる目的ではなく、生物がそれ自身のなかに持っているとされる目的を意味していることである。したがって、バトラーが『新旧の進化論』で使用している「目的論」という概念と言葉は、彼独自のものと言っていい
バトラーは、このようにしてキリスト教の目的論も、「自然選択」説の非目的論も避け、目的論的進化論を過去の進化論から<学びとった>のである。その説は、彼が前作『生命と習慣』で披瀝した独自の進化論の要諦である、親子の連続、無意識の記憶に基づく習慣の説と無理なく繋げることができた
進化論に関するアフォリズム
「習性的特質が遺伝するという理論に真理があるとするならば――誰がそれを疑い得るか――目と指は、肉体に表示された志願[アスピレーション]、もしくは言葉にほかならない」<サミュエル・バトラー>
「生は、絶頂にまで高まる波である。死においてはそれらは微塵に砕ける。しかしながら直ちにその一つ一つは生の海に吸い込まれて、同じようにまた砕けるそのときまで、うねうねと寄せて来るあとの世代の形成に助力する」<サミュエル・バトラー>
「諸君が死ぬときどんなことが起こるか。諸君が生まれるときどんなことが起こるか。後者の場合においてわれわれは生まれるのであり、前者の場合においてわれわれは死ぬのである。だが、それより深く立ち入ることは不可能である」<サミュエル・バトラー>
「私は年少の頃、生について唯一確かなことは、いつかは死ぬということである、と考えるのが常であった。今では私は、生について唯一確かなことは、死というようなものは無い、と考える」<サミュエル・バトラー>
「死において、われわれは生命を失いはしない。われわれはただ個人性を失うだけだ。死後、われわれは、われわれ自身ではなくて、他人の中に生きる」<サミュエル・バトラー>
知覚の反復沈降
物事を深く知るにつれて、その知識について意識する度合いが減っていくというサミュエル・バトラーの主張。つまり、知識(あるいは行動・知覚・思考の習慣)が精神のより深いレベルへと沈降してゆくプロセスが見出されるということ。禅の修業は、このプロセスの進展にねらいを定めた非常に明瞭な例だが、そればかりでなく、この現象は、すべての芸術と、すべての技能獲得のプロセスに関わるものである
『エレホン』
a エレホンの世界
(1) 機械の発明と改良は根絶されている。その理由は、昔の大学教授が「いずれ機械の生活力は人間のそれを上回ることだろう」と予言したから
(2) 不健康は罪。病気になったら監獄行き。さらに、あらゆる不幸、たとえば友人喪失とか破産なども、聞く者を不快にさせるが故に、社会に対する犯罪とされ処罰の対象となる。患者の周りの人たちは、患者が病気に罹ったことを悪い悪いと噂するばかりで、治そうとしない。母親は妊娠すると不健康になるため、妊娠してから子どもを生むときまで姿を隠蔽する。また子どもも歩いたりものを言ったりできるようになるまでは姿を見せないようにしておかれる。また、醜悪なのも罪とされる
(3) 家に火をつけるとか、暴力をふるうとか、逆に我々の世界で犯罪になるようなことをした場合は病院に入れられて矯正者によって看護を受け、激しい不道徳の発作に罹っていることを友人に心配される。不道徳的欠陥は、人格あるいは環境の不幸の結果であるとみなされ、犯罪とはみなされない
(4) 出生児は両親に煩いをもたすので、親はその不幸の原因を出生児に突きつける。前生(生まれてくる前/未生児の国といわれる)では立派な給養を受けていて、不平を起こす原因はなかったが、自分の根性曲がりと苛立ちから、いつしかこの世に出てきたいという欲望を抱いたとされる。そして未生児は、自分に何も悪いことをしもしない不運な人達を苦しめ煩わすことにとりかかるために生まれてきたとされる。子どもが生まれて三日目か四日目あたりに、両親の知り合いが皆集まって宴会が開かれ、そこで知り合いたちは出生児によって与えられた損害をなぐさめるために両親へ贈り物をする習慣がある。赤ん坊は産婆に連れてこられて、皆が赤ん坊を罵倒し始める。その生意気なことを責め、自分の犯した悪に対してどういう償いをするつもりか、一体どうして世話と栄養を受けようと考えているのかと尋ねる。赤ん坊は産婆につねられてたいてい泣き出す。それは、有罪を承認するしるしとして、好いことだと考えられている。/子どもは早くから親に独立させられる。子どもは幼いときから金をかせぎ始めて、親に拠りかからないようにならなければならないとされる。そしてそれが達せられたとき、はじめて本当の愛が親子の間で生まれたのだ、とされる。/しかしエレホン人はあの世の王国[=冥界]の存在についてはずいぶんと無関心である。彼らは、見えない王国の存在を否定するのは悪いが、存在以上のことを知っているふりをするのも悪いと言うのである。したがってエレホン人は、人間の死んだ後についての信仰を持たない。エレホン人は生まれる前の人間の姿には強く関心を持って神話を作り上げたが、死んだ後に何が来るかについては全く想像力を持たないのである
(5) 金をたくさん稼ぐことは非常に良いことだとされている。それだけ彼が社会に奉仕したということの証になるからだ
(6) 動物の権利について。動物を殺して食べてはならない。動物も人も同等の立場にあって尊厳がなされているからだ。自然死や他の動物に殺された動物を偶然に発見した場合はこれを食してもよい。/
植物の権利について。動物も植物もすべて祖先は共通であった。そして、だから植物も動物と同じく生きていると考えられるべきだ。だからして、果実を木からもぎとって食べてはいけない。/これらの動物と植物の権利の法律に従った昔のエレホン人は餓死しかかった
―
(α) (2)と(3)から、肉体の病気(身体的な不健康)を咎めて犯罪(精神的な不健康)を咎めない傾向にあることがわかる。体調や気持ちが良いかどうかをお互いいつも確認する。それで不調だと言ったならば、すぐに相手に慰められることになる
(β) 機械の書で述べられていること――機械の今後の進化(たとえば機械に意識が宿る可能性についてなど)と機械に依存しすぎている人間について――に関して、機械を道具の形で人間の動物としての機能を拡張するものとして捉えられているとみる観点は興味深い。自然神学者のウィリアム・ペイリーは、時計にデザイナーがあるのと同じように宇宙にも考案者としての神がいるはずだとし、神の仕事を自然の中に見出すことを説いた。「機械」を「神」と置きかえて考えてみればおもしろいだろうし、またそうしてみればバトラーのペイリーの自然観への揶揄とも考えられることになる
b 登場人物
・私[=主人公/ヒッグズ]
・チョウボク
・イラム(監獄で主人公を世話してくれた娘。主人公と恋愛していた)
・ノスニボル氏(女。エレホンの中でも有数の金持ちの有名人。しかし他人の金を費消[横領]したので、その道徳的な罪のために、矯正者によって治療を受けている)
・アロウヘナ(ノスニボル夫人の娘。夫人の二人の娘のうち、妹)
・ズロラ(ノスニボル夫人の娘。夫人の二人の娘のうち、姉)
・マハイナ(ズロラの友人。酒癖が治らない女。しかし本当は、自分の病弱を隠蔽するためにアルコール中毒という道徳的罪を犯しているように見せかけている)
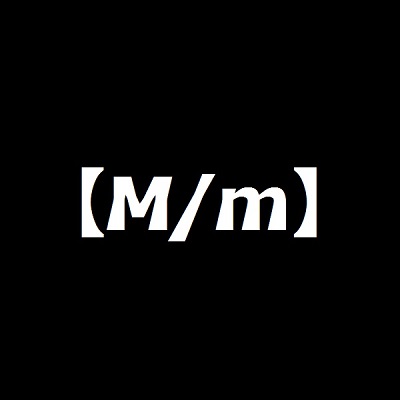

 TOP
TOP