疾患、病気について
目次
統合失調症
統合失調症とは、精神機能の分裂が起こる病気で、精神病理学あるいは臨床単位上の診断・統計カテゴリーの一つである。以前は精神分裂病と呼ばれていた。この症状の担当診療科は精神科であり、精神科医が診察に当たる。明確な病因は未だに確定されておらず、発病メカニズムは不明であり、いずれの報告も仮説の域を出ない
/a 症状
症状においては多彩な精神機能の障害が見られる
a-1 思考過程の障害
・話せない状況:思考に割り込まれると神経過敏や鬱状態になり、考えが押し潰されて、まとまらない話になってしまう。思考が潰れることで今までやってきたことは何だったのかという自己喪失に陥る。
・的外れな応答(他人の質問に対し、的外れな答えを返す):周囲の人間から、話をよく聞いていない人物と見なされることがある。
・独言・独笑:幻聴や妄想世界での会話があるが、ただ無闇に言葉を羅列することもありそれを教科書では「言葉のサラダ」(サラダのように好き勝手に点在している様子から)と言っている。
a-2 思考内容の障害(妄想)
・被害妄想:「近所の住民に嫌がらせをされる」「通行人がすれ違いざまに自分に悪口を言う」「自分の臭い体臭を他人が感じている」
・関係妄想:周囲の出来事を全て自分に関係付けて考える。「あれは悪意の仄めかしだ」「自分がある行動をするたびに他人が攻撃をしてくる」
・注察妄想:常に誰かに見張られていると感じる。「近隣住民が常に自分を見張っている」「盗聴器で盗聴されている」「思考盗聴されている」「監視カメラで監視されている」
・追跡妄想:誰かに追われていると感じる。
・心気妄想:重い体の病気にかかっていると思い込む。
・誇大妄想:患者の実際の状態よりも、遥かに裕福だ、偉大だ等と思い込む。
・宗教妄想:自分は神だ、などと思い込む。
・嫉妬妄想:配偶者や恋人が不貞を行っている等と思い込む。
・恋愛妄想:異性に愛されていると思い込む。仕事で接する相手(自分の元を訪れるクライアントなど)が好意を持っていると思い込む場合もある。
・被毒妄想:飲食物に毒が入っていると思い込む。
・血統妄想:自分は天皇の隠し子だ、などと思い込む。
・家族否認妄想:自分の家族は本当の家族ではないと思い込む。
・物理的被影響妄想:電磁波で攻撃されている、などと思いこむ。
・妄想気分:まわりで、なにかただごとでないことが起きている感じがする、などと思いこむ。
・世界没落体験:妄想気分の一つ、世界が今にも破滅するような感じがする、などと思いこむ。
a-3 知覚の障害
実在しない知覚情報を体験する症状を、幻覚という。幻覚には以下のものがあるが、統合失調症では幻聴が多くみられる一方、幻視は極めて希である。
・幻聴:聴覚の幻覚。幻聴はしばしば悪言の内容を持ち、患者が「通りすがりに人に悪口を言われる」、「家の壁越しに悪口を言われる」、「周囲の人が組織的に自分を追い詰めようとしている」などと訴える例は典型的である。
・幻嗅:嗅覚の幻覚
・幻味:味覚の幻覚。幻味、幻嗅などは被毒妄想(他人に毒を盛られているという妄想)に結びつくことがある。
・体感幻覚:体性感覚の幻覚
・知覚過敏:音や匂いに敏感になる。光がとても眩しく感じる。
幻覚を体験する本人は外部から知覚情報が入ってくるように感じるため、実際に知覚を発生する人物や発生源が存在すると考えやすい。そのため、「悪魔が憑いた」、「狐がついた」、「神が話しかけてくる」、「宇宙人が交信してくる」、「電磁波が聴こえる」、「頭に脳波が入ってくる」などと妄想的に解釈する患者も多い。
a-4 自我意識の障害
自己と他者を区別することの障害。自己モニタリング機能の障害と言われている。すなわち、自己モニタリング機能が正常に作動している人であれば、空想時などに自己の脳の中で生じる内的な発声を外部からの音声だと知覚することはないが、この機能が障害されている場合、外部からの音声だと知覚して幻聴が生じることになる。
・考想操作(思考操作):他人の考えが入ってくると感じる。世の中には自分を容易に操作できる者がいる、心理的に操られている、と感じる。進むと、テレパシーで操られていると感じる。
・考想奪取(思考奪取):自分の考えが他人に奪われていると感じる。自分の考えが何らかの力により奪われていると感じる。世の中には自らの考えがヒントになり、もっといい考えを出すものもいると感じる。進むと、脳に直接力が及び考えが奪われていると感じる。
・考想伝播(思考伝播):自分の考えが他人に伝わっていると感じる。世の中には洞察力の優れたものがいると感じる。その人に対して敏感になっている。進むとテレパシーを発信していると感じる。
・考想察知(思考察知):自分の考えは他人に知られていると感じる。世の中には自分の考えを言動から読めるものがいると感じる。進むと、自分は考えを知られてしまう特別な存在と感じる。自らのプライドを高く認められずに、被害的にとらえてしまう。進むと、構想が自己と他者との間でがテレパシーのように交信できるようになったと考え、波長が一致していると感じる。
a-5 意志・欲望の障害
・興奮:妄想などにより有頂天になっている。また自分が神か神に近きものまたは天才と思い一種の極限状況にある場合もある。
・昏迷:意識障害なしに何の言動もなく、外からの刺激や要求にさえ反応しない状態。統合失調症の場合は表情や姿態が冷たく硬い上、周囲との接触を拒絶反抗的であったり(拒絶症)、終始無言(無言症)、不自然な同じ姿勢をいつまでも続ける(常同姿態[カタレプシー])。
・拒食
・自発性の低下:自分ひとりでは何もしようとせず、家事や身の回りのことにも自発性がないことが多い。言われればやるという時期が来るがそれがしばらく続く。
・意欲低下:頭ではわかっていても行動に移せず、行動に移しても長続きしない。
・無関心:テレビも見ようとせず、世の中のこと、家族や友人のことなどにも無関心でよく知らない。
a-6 感情の障害
・感情鈍麻:感情が平板化し、外部に現れない。
・疎通性の障害:他人との心の通じあいが無い。
・カタレプシー:受動的にとらされた姿勢をとりつづける。
・緘黙:まったく口をきかない。
・拒絶:面会を拒否する。
・自閉:自己の内界に閉じ込もる。
・不安感・焦燥感・緊張感
・躁状態:何でもできる気分・万能感、金遣いが荒くなる、睡眠時間が少ないなど。
a-7 思考の障害
・常同的思考:同じ行為・言葉などが持続して繰り返される。周囲には目的がわからず、意味を訊くと一般的に理解不能である。何か言いたいことがあるが言葉にできずにいる。ここに病気になった要因がある可能性がある。抽象的に説明できないことにもある。具体的な事例を知らないがために、周囲にとっては意味不明の言動となることがある。
・抽象的思考の困難:抽象的にひとつにまとめきれないで分裂気味な乱雑な思考である。エントロピー的である。
・連合弛緩:連想が弱くなり、話の内容がたびたび変化してしまう。単語には連合がある。わかりやすく言えば単語の意味での関係でのグループ(連合)がある。この連合が弛緩して全然関係のない単語を連想することである。しかし落語にあるようなダジャレは連合弛緩でない。連想が関係を未視しているのである。
・両価性:判断基準が確立せず、左右の価値の違いや金銀の価値の違いなどがわからず、どちらもという状態をいう。
a-8 認知機能障害
認知機能障害は統合失調症の中核をなす基礎的障害である。認知機能とは、記憶力、注意・集中力などの基本的な知的能力から、計画、思考、判断、実行、問題解決などの複雑な知的能力をいう。この障害ゆえに、作業能力の低下、臨機応変な対処の困難、経験に基づく問題解決の困難、新しい環境に慣れにくいなど社会生活上多くの困難を伴い、長期のリハビリが必要となる。
リストカット
リストカットをする人の心理について
/a 心理
リストカット=自分を傷つける行為には、いくつもの意味が重なっている場合がある
・自分を罰したり、消し去りたいと思う強い自己否定
・しかしそんな自分を誰かにふり返ってほしい、あわれんでほしいと願う気持ち
・痛みを感じ、流れ出す血を見ることで、罰を受けたのだから、もう少し生きていいという安堵感
これらの根底にあるのは、自分を毀損することで、かろうじて自分を保とうとする、もっとも卑下された自己愛なのである。つまり、自分の心の寂しさや苦しさに気づいてほしいという、他者に向けたサインなのだ
/b 人格
リストカットをする子は、例外なく自分が嫌いである。しかし自分としてしか生きられない現実があるため、とても辛く、その空虚さを埋めるために、自分ではなく他人に自分の存在価値を見出そうとする。だから人にふり向いてもらうために必死になる。しかしすべてが好意的な結果を生むとは限らない。したがって絶えず不安定な状況にあるうえ、求める気持ちが通常より強いため、他人の言葉や態度に敏感になりやすく余計ダメージを受け、深く傷ついてしまう。「私は誰からも愛されていない」「私は生きている価値のない人間なんだ」と、自分自身に対する怒りがこみ上げ、それを鎮めるために、あるいはそんな自分を罰するためにリストカットをおこなってしまうのである
/c リスカを繰り返す原因
だからといって、リストカットをするたびにやさしく介抱したり、やさしく話を聞いてあげたりすると、事態を悪化させてしまうだけだ。やった本人は、周囲が大騒ぎしてくれることをひそかに望んでいる。そしてリストカットをするとやさしくしてもらえるという構図を作ってしまい、結果的にその行動を強化してしまうのである。これがリストカットを繰り返す原因である。原因は本人ではない。周囲の対処が間違っているだけなのだ
/d 防衛法
リストカットをしないようにすることが何よりも大事だが、もしリストカットが起きてしまった場合には、その行為だけに目を向け、諭したり、𠮟ったりするのは逆効果である。かといってその時に優しくしただけでもその子の心の闇を取り除くことはできない。もうしないと約束させたとしても、それはこちら側のその場限りの自己満足に過ぎない。大事なのは根本的な問題の解決である。まずリストカットをしたそのときはできるだけ大騒ぎせず、事務的に必要最低限の手当てだけをし、話は後日に改めて機会をもつのが望ましい。一番大事なのはその話し合いの場である。リストカットという行為にばかり焦点を当てるのではなく、背景にある気持ちやその子の置かれている状況のほうに目を向ける。リストカットをした原因を取り除くこと、つまりその子の「自分の存在価値を見出す=親や他人との人間関係の修復」に力を注ぐべきである。そのためには本人の気持ちを理解し、それをしっかりと受け止め、寂しさや傷ついた思いを汲み取ろうと意識すること。リストカットという言葉を使わずにリストカットをした原因を間接的に汲み取り、その具体的な原因が分かったなら、それを解消できるように周りが努力することが大切である。しかし、親が「傷ついたのは自分のほうだ」と心のどこかで思っている限り、状況は変わることはない。子どもの痛みをどれだけ見てあげられるか、そう心から思うように親や周囲がまず向き合い方を変えるのが先決である。そして、子ども自身の自己否定感情を無くすために、子どもを肯定的に受け止めてくれる人と、信頼ある人間関係を築き、そうした関係を積極的に体験させることでその子の人間関係の質は徐々に変わりはじめるはずだ
大事なのは解決ではなく原因の解消である。原因を探り、それを肯定的で扱いやすいものに変化させることが、意味をもった人生への再構成につながる
小児虐待
アメリカでは、産みの親が子どもを虐待することをバタードチャイルド症候群と呼んでいる。バタードとは虐待されているという意味だが、この虐待には、叩くなどの身体的虐待、食べ物を与えないという栄養的虐待、性的虐待、感情的虐待などが代表としてあげられる
/a 小児虐待する親の心理
小児虐待の原因の多くは、親の未成熟な人格にある。児童を虐待する親は彼ら自身、幼児期において暴力被害者だったといわれている(50%前後)。この親たちは自分が子ども時代に親から虐待されながら育った反動として、自分の子どもは理想的に育てようと決心してそれを実行する。理想的に、というところにこだわるのだ。しかし、理想どおりに振る舞う子どもはほとんど存在しない。子どもが理想どおりに振る舞わないことが重なると、失望落胆のあまり子どもに暴力を加える。つまり、挫折感、欲求不満、怒りなどを経験したとき、かつて親から自分が与えられた、その意味では一番親近性の強い、つねる、殴る、蹴るという行為を選択してしまうのだ
/b 性的虐待
少女たちが実父・養父・実母などからうける性的虐待は、少女の心を傷つけ、非行少女など大人になるまえに歪んだ人格を形成してしまうことが多い。それほど少女たちにとってはトラウマになりうる事件なのだ。少女たちは、虐待行為には嫌悪感・拒否感を抱いているが、行為者としての父親には愛憎半ばの両面感情をもっている。そして彼女らに共通しているのは、物理的に長期入院や家出・離婚といった場合と、心理的な面からの母親の不在。母親たちは娘の訴えによって性的虐待が発覚しても、たいていすぐに信じようとはしない。その理由は、第一に、自分をかばい防衛する必要上娘を信じない場合。第二に、夫が社会的に罰せられることで世間的な非難を受けることへの恐れ。第三に、一家の経済的な稼ぎ手として夫に依存している。第四に、娘に自分の代わりに夫に性的サービスをつとめさせることで夫をつなぎ止めたいので、見て見ぬふりをするためだ。いずれにしても、母親が共犯者となることで、娘たちは完全に孤独地獄に陥る。とくに自分を保護してくれるはずの母親が頼りにならないことを知ることで深く傷つく
アルコール依存症(“グレゴリー・ベイトソン書付”)
/a 原因の方向性
アルコール依存症の原因または理由を、アルコールが入っていないときの患者の生活の中に探るべきであるとする考えが、一般の風潮としてある。あの人は醒めた状態で、未熟である、マザコンである、受動―攻撃的である、成功への不安にとりつかれている、プライドが高すぎる、あるいは単に弱い、だから酒に溺れた、という言いかたがされている。しかしこうした言説が、どのような根拠からアルコール依存症へと結びつくのかという論理に言及しているところは見受けられない。この常識的見解には問題点がある。アルコール依存者の醒めた生活が、なんらかのかたちで彼を酒へ――酩酊へのコースのスタート地点へ――追いやるのだとしたら、彼の陥っている醒めのスタイルが強化されるような治療を行っても、症状の軽減も統御も、望むことはできないはずだ。原因の方向性を探るためにここから新たな見解を提示していこう。彼の醒めのありかたが、飲酒へと彼を追いやるのだとしたら、その醒めには、なにかしらのエラー(病)を、酔いが(主観的な意味で)修正しているはずだ。つまり間違っているのは彼の醒めの方であり、酔いの方は、ある意味で正しいということになる。つまり、世間の狂った前提への反抗として飲酒に走るのではなく、世間によってつねに強化されつづけている“自分自身の狂った前提”からの脱出を求めて飲酒に走るということ。この違いが重要だと思う。したがってこの新たな見解では、醒めと酔いの関係が、ふつうの議論とは逆転したものになっている。酔いが醒めに対する(主観レベルでの)矯正の機能を担っているという立場をとっている
/b 敗北の認識論
依存症の人間をかかえた家族や友人は、「もっと強くなれ」「酒の誘惑に打ち勝て」と叱咤する。これらの言葉が、現実に何を意味するのかは定かでないが、重要なのは、依存者自身が、醒めているあいだは、自分の弱さにこそ問題があるのだと一般に考えている点だ。彼はわが魂の指令官になれると、少なくともそれがあるべき姿だと、信じている。これを、依存症の更生に唯一誇るべき成果をあげている「アル中匿名会」(以下AA)では、意志の力でボトルの誘惑に抵抗しようとすものに対する軽蔑の意味で使われている。AA共同創立者の一人で、みずからアル中患者であった、ビル・W氏の手になる有名な「12のステップ」は、その第一のステップで、酒との戦いというばかげた神話に鋭くメスを入れている。アルコールとは戦えない、そんな力は自分たちにない、ということを認めるのが、更生への第一のステップとして明記されている。しかし多くの患者はこれを「降伏」と解しており、そのために多くの患者はそこへ踏み上がることができない。その状態にあるうちはダメだ、とAAは見る。患者は、ひとしきりの覚醒が続いたあと、また自己制御とやらを持ち出して、誘惑との架空の戦いを始めるばかりなのだ。彼らが認めようとしない、あるいは認めることができないのは、酔っていようが醒めていようが、アルコール依存者の自己の全体が、「アル中パーソナリティ」なのであり、そういう自己が、アル中と戦うなどということが自己矛盾なのだという点だ。AAはこれを的確に把握している。「あなたの意志で直そうとすることは、靴紐を引っぱってあなた自身を持ち上げようとするのと同じです」と。この“敗北”を認めるというのは、患者が敗北の経験から変化の必要を悟るというだけではなく、敗北することそれ自体がすでに変化の第一ステップなのだ。この第一のステップは、降伏ではなく、認識論(エピステモロジー)の変化――世界のなかのパーソナリティについての知のあり方の変化――と言うべきだ。この変化が誤った認識論からより正しい認識論への変化となっている点に、特に注目したい
/c 治療法
ここでは治療法を書くが、まずアル中依存者の特徴を述べてから治療法を考えたほうが分かりやすい。その意味でこの項は“アル中依存者の特徴と治療”といった意味をもつ
c-1 負のプライドを捨て去る
彼らに具わっているのは、負のプライドだ。このプライドが、本人が過去に為しとげた何かをめぐって成立するコンテクストのなかで醸造されたものでないことは明らかだ。このプライドは、なんら誇るべき実態を持たない。強調点は「オレはできたぞ」ではなく、「オレはできるぞ」にある。「オレにはできない」という命題を受け入れることができず、取りつかれたようにチャレンジを繰り返す姿がここにある。ここでAAの言う「自惚れ」が頭をもたげる。「大丈夫さ、一杯くらい・・・。」そして気がつけば、いつもの泥酔という次第。賭け(リスク/「一杯くらいは平気さ」)にプライドを求め、それを生活原理とすることは、自己の破滅を求めることと変わらない。酒を飲まずにいられたことで、酒を飲まずにいられることの意味が変化する。最初のうちは、酒を断っていられることが、自分のプライドを満足させた。しかしそれができてしまうと、「一杯のリスク」なしに彼のプライドは満足しない。つまり禁酒の継続によって、飲酒と禁酒をめぐるコンテクストの構造が変化するのだ。治療においては、このコンテクスト構造の変化を全力を挙げて阻止することに向けられている。「お前の本性はすでに酒びたりなのだ」と諭すことで、アルコール依存症を患者の自己の内側にしっかりとセットする。負のプライド(アル中的プライド)を捨てるために、患者自身に、アル中であること、そして飲酒に抵抗するなどということがばかげた自惚れであるということを自覚させることだ
c-2 治療的ダブルバインド(“グレゴリー・ベイトソン書付”)
あえて症状の増加する方向へ患者を押しやるという、「治療的ダブルバインド」と呼ばれるテクニックを使う。セラピストが、アルコール依存者をそそのかして、「コントロールされた飲酒」を試みさせ、コントロールできないことを自分で悟らせる
c-3 底を極める
「底が極まる」という現象に、AAは非常に大きな価値を与えている。落ちるところまで落ちていないアル中患者は、救われる見込みが少ないとされる。ふたたびアルコールへ戻っていく人間のことを、彼らはよく「まだどん底まで落ちていない」という。どん底をなめさせる経験は、いろいろなものがあるだろう。アルコール性せん妄症の発作、酩酊時の記憶の喪失、夫婦関係の破綻、失職、回復の見込みなしという診断。どん底で味わうパニックの性格を浮き彫りにしていると思われる一節を、AAの文書から引用しよう
「わたしたちは他人を『アル中』だと宣告したりはしません。あなたが『アル中』かどうか、自分でテストすることをお勧めします。バーに入って、自分の飲みかたをコントロールできるかどうか、試してごらんなさい。飲み出してから、あるところでいきなりグラスを置いて席を立つことができるかどうか。一度ではだめです。何度か繰り返しやってみないといけません。自分に正直であれば、答えはすぐに出てくるでしょう。あなた自身がいまどんな状態にあるのか正しく知るために、危険は覚悟のうえで、この自己診断をやってみてください。」
これはいわば、滑りやすい道で、ドライバーにブレーキをかけさせるというのと同じである。「底を極めた」アルコール依存者のパニックは、自分がコントロールしていたと思っていた乗物が、暴走を始めたことを知った人間のパニックそのものだ。ブレーキだと思っていたものを踏むと、車はさらにスピードを増す。そのとき人は、「自分プラス車」という、どう見ても自分より大きなシステムの存在を、パニックとともに知る
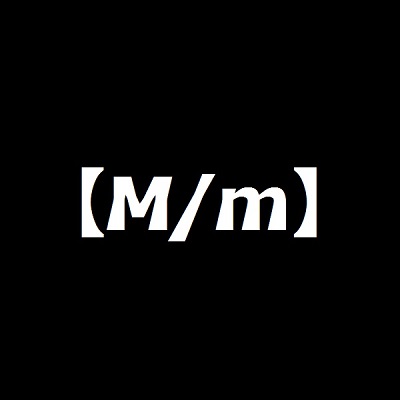

 TOP
TOP