深層心理とは、言いかえれば無意識ということになる。無意識とは、人間の心的過程には本人が意識していない動機が働いている、意識・知覚していない意識のことである。フロイトはそうした無意識的な心理過程を探求する方法を精神分析と呼び、精神分析学を“意識には直接達し得ざる、より深き心的過程に関する学説”として規定した。このフロイトの「精神分析学」を、E・ブロイラーが「深層心理学」と名づけたといわれている。フロイトは無意識についてこう言った
「人間の心は、たとえてみれば海面に浮かぶ氷山のような構造をもっている。海面に出ている部分は意識であり、海の部分にくらべて目には見えないが、はるかに大きな部分を占めているのが無意識である」
<ジークムント・フロイト>
今日、私たちの身辺に起きているさまざまな心の問題も、意識下に潜む無意識の深層を手がかりにしなければ、明らかにすることができない問題がいたるところに横たわっている。ではなぜ無意識は表面化(意識化)されないのか。フロイトは、無意識的な精神のある部分は、意識とは相容れない、矛盾するような内容だからだと考えた。つまり、意識がそれを認めたくないからだということである。無意識が表面化しようとする力を“意識化”とすると、意識が無意識を締め出す反対の力が“抑圧”となる。抑圧とは、自分自身が認めたくない欲求(たとえば、許されない性的な欲求、他人への攻撃欲求など)やその欲求と結びついた考え、感情、または受け入れ難い過去の記憶やそれにともなう感情などを意識から締め出し、無意識の中に閉じこめておこうとする心理作用のことである。無意識は常に海面の外に出たがっているのだが、抑圧によってその大部分が深層に潜んでいる。私たちはこの働きによって、危険な欲求、考え、記憶などが存在しないかのように振る舞うことができる。私は知らない、考えたことがない、忘れてしまったという働きは、多くの場合この働きの結果なのだ。しかし、抑圧されたものはそのまま消えてしまうわけではない。ずっと無意識の世界に残存していて、夢や神経症の症状として現れたりするように、ともすればふたたび意識のなかに浮上しようとする傾向をもっているのだ
そもそも精神とは何か。すべてを知りうることはまだ容易ではないが、少なくとも分かっていることはある。それは、精神は自己の意識や対象のモノを含めた関係性の全体的を意味するのではないかということだ。「これはチョークだ」と言うときは、自己の意識が対象のチョークをチョークであると認識した上で発せられるものである。意識の認識のしかたによっては、チョークをペンだと言ったりシマウマだと言ったりすることもあるだろう。いやむしろ、チョークと呼ばれているそのものが“チョーク”であるというのは、人間のオントロジーの中の存在の定義上という、ごく狭い概念にすぎない。精神は、チョークを見てチョークであると認識するという、対象も含めた意識―対象の全体的な関係性の上に成り立っている。自己意識の認識論(エピステモロジー)のみで精神を語り得ることはできない。その精神の一端を成しているのが、たとえば“意識”であったり“情報”であったりする。なお情報の“対象”というのは、ある情報がチョークについてのものであるとき、その“チョーク”を指すものだが、情報以前の“物そのもの”は、精神を語るとき何ら関与してこない(その意味で実在しない)
深層心理のなかでも、他の心理に分けられるものはできるだけ他の心理に分けることにする。なぜなら、心理分析のほとんどが、深層心理を参考にしているからである。また、心理学以外の深層心理もここに書くとする
関連:“カール・グスタフ・ユング書付”/“ジークムント・フロイト書付”/“アンナ・フロイト書付”
目次
- 1 無意識の意識化
- 2 人はなぜ悩むのか
- 3 罪悪感
- 4 意識体験としての自我
- 5 自意識過剰
- 6 意識が知ること(“グレゴリー・ベイトソン書付”)
- 7 アイデンティティ[自己同一性]
- 8 エリクソンのライフサイクル論
- 9 自己愛と対象愛
- 10 甘え
- 11 不協和解消
- 12 非類似の嫌悪
- 13 八方美人
- 14 欲求依存承諾
- 15 口唇愛期的性格
- 16 接触行動の心理
- 17 好悪の原始的傾向
- 18 意識とは何か
- 19 基本的な四つの心理
- 20 ミラーリング効果
- 21 必要と敏感
- 22 シンデレラ・コンプレックス
- 23 女装する人間の心理
- 24 山アラシ・ジレンマ[アンビバレント=両面感情]
- 25 三次元の視覚像の生成プロセス
- 26 基本的信頼
- 27 錯覚
- 28 母親固着
- 29 ストレスと反動
無意識の意識化
無意識の意識化を図るにはa,b二つの方法がある
a 思い出される
一つは、思い出される=意識化されることである。催眠をかけられた人は、催眠中の経験を覚醒後には覚えていない。しかし、それは見かけだけのことで、その事を知っているはずだと何度も強くいわれると、ついには記憶を呼び戻すことができる。今は忘れている過去の出来事を思い出させることができれば意識化が可能である
b 自由連想法
意識化にもう一つ重要なこと、それは、患者自身が自分の問題を言語化するということである。すなわち、言語化=意識化することにほかならない。その結果、考案されたのが自由連想法というものである。これは、患者が医師に背を向ける形で寝椅子に横になり、「どんなことでも心に浮かんだことを、それがどんなにくだらないこと、ばかげたこと、いいにくいこと、不愉快なことでも、包み隠さず何から何まで話す」という方法である。患者はこの方法の繰り返しによって、意識的な抑圧を次第に緩和し、やがて抑圧という防衛の力をも弱め、意識化できるようになる
c 意識的コントロール
自分の感情をコントロールするためには、まずその感情を意識できることが必要である
区別したいものは、その境界線をはっきりさせるために、あえて浮き彫りにして意識するようにしてみる。たとえば女性に対して「かわいい」という理由で何でもかんでも許してしまう男性がいたとする。男性はそれではだめだと思って、女性に対して「かわいい」という観念を抜いて男女関係なく平等に向き合おうとする。そのためには、「かわいい」と思ったときにその思いを意識するようにすると、「その感情を抜いたときにどういう状態になるのか」を把握することができるようになる。区別するには、まずその境界線を知り、両者を分け隔てられるようにコントロールできることが必要である。それを助けるのが意識なのだ
c-1 意識の無意識化
意識して無意識にする。中立にする。これは思い入れや先入観が強すぎて困ると意識した場合において、意識してそれらを取り除いて中立な観点から見ることが可能である
人はなぜ悩むのか
動物や乳幼児には悩みがない。しかし人間は、よりよい生き方を求めて、ますます悩む存在になっていく。そしていつか悩まなくなるときが来るだろう。だが好奇心があるかぎり、悩むことは人間の宿命であると思う。しかし、現代人は“悩みを悩む”ことが少なくなっているのではないだろうか。現代は、地道な努力より、情報獲得の早さ次第でほぼ物事の勝利が決まるような時代、主体的な目的意識がなくとも、人生の大半は生きていける時代だ。就職に際しても、内向的で暗い人間は一般に好まれない。こういった状況を見ると、時代そのものが悩みを受容しなくなっているのかも知れない。悩むこと自体は人間本来の自然な姿だといえるが、悩み方が問題なのだ。自分の悩みとうまく距離をとって、悩みを客観視することが大切である。悩みを悩むとは、悩みを昇華させることともいえる。神経症などにかかる人は、悩みに呑みこまれ、悩みのなかで自分を見失っている人たちである
罪悪感
日常語で「すまない」「悪かった」などと表明される心の状態、すなわち罪悪感は、人が社会の規範や要請に背いたとき、自分に罪があるとして非難し責める感情である。相応の罪悪感をもつことは精神の健全さを示す指標であるが、人によっては良心のあり方が異なり、過剰な罪悪感や罪悪感欠如のケースもみられ、このような場合には、何らかの病理が予想される。激しく自分を責める人、逆にすべての責任を他人に転嫁する人などがいる。特に厳しく自分を責める人は、愛する対象へ向けられた非難・攻撃が方向を変えて自分に向けられたものだと解釈される。さらに、特殊なものとして神経症の無意識的な罪悪感がある。内面深くには罪悪感が潜在していて、それがたとえば、頻繁に手を洗うという強迫的行為として現われ、「罪の洗い流し」を象徴的に表現しているのである
意識体験としての自我
私たちは日常生活において“私”を体験し、“私”が存在すると確信しているが、そうした“私”が自我と呼ばれるものなのである。学問的にはおおむね二種類に区別することができる
・本人の意識体験としての自我であるか、人の行動の説明原理として仮定された自我であるか
・主体としての自我であるか、客体としての自己であるか
――
フロイトやユングの扱った自我は“人の行動を説明するために仮定された”“主体としての自我”である。それに対し、“意識体験としての自我”を問題にした代表的な学者に、K・ヤスパースとW・ジェームズがいる
a K・ヤスパースの意識体験としての自我
ヤスパースは主体としての自我がいかに体験されるかについて考察した。主体として体験される自我は、通常の意識生活において副次的に体験される比較的不明瞭な意識体験だが、それが比較的明瞭に意識される場合を、彼はとくに自我意識と呼んだ。そして、ヤスパースによれば、自我意識は次のような標識をもっている
(1) 能動性(私が活動している)
(2) 単一性(私はいつも一つである)
(3) 同一性(昨日の私も今日の私も同じ私)
(4) 対立性(私は他者とは異なる私)
b W・ジェームズの意識体験としての自我
一方、ジェームズは、意識体験としての自我を主体としての自我と客体としての自己に区別した。以来、この二つの区別は心理学の領域では自明のこととなった。彼の理論では、主体としての自我は「知るものとしての自我」であり、純粋自我ともいわれている。客体としての自己は「知られるものとしての自己」であり、これには、物質的自己、社会的自己、精神的自己が含まれる
自意識過剰
私たちが自分を振り返るとき、「知る自分」と「知られる自分」と、たしかにこの二重性を体験することができる。したがって、自分についての意識は、客体としての自己についての意識内容と、自己を観察する自我そのものへの意識作用とに区別される。そして、自意識が過剰になるということは後者の現象であり、体験として知られた自己に主体としての自己が集中しすぎることだといえる。一般に、自意識がはっきりしてくるのは青年期になってからで、それは「知られる自分」と「知る自分」の分裂意識という形で現われてくる。思春期の発達期を迎えるころから、青年は自分の身体や容貌、能力や性格、両親の職業や社会的、経済的地位などが気になりはじめ、にわかに自己への関心が高まり、他人と比較しての自己を観察するようになる。自己探究と自己形成への道がはじまるのだ。しかし、逆に青年の関心が自己の領域から一歩も脱出できず、すべてが自分に関連する事柄として受け取られるといったことも生じる。周囲の人々の眼を異常に気づかい、劣等感や自己嫌悪をともなって、他人から受けたちょっとした非難によって自尊心をひどく傷つけられたりする。このように、あまりの自意識過剰は、それが自己形成への努力の結果であるにもかかわらず、逆に豊かな自己形成を妨げる結果になってしまうのである
意識が知ること(“グレゴリー・ベイトソン書付”)
精神過程全体のうち、意識の占める割合は必然的にかなり限られたものであることは事実だろう。意識は十分に抑えられた状態で、はじめて精神プロセスの役に立つわけだ。習慣によって無意識に事が運ぶことで、思考と意識の節約がもたらされる。知覚のプロセスに意識が割り込めないのも、理由は同じだ。意識は何を知覚したかを知ればいいのであって、どのように知覚したかを知る必要はない。そんなことをしても、精神全体にとって得にはならないのだ。意識できない一次過程が基本にあるからこそわれわれは機能できるのであって、そうでなくても機能できると考えることは、脳が違った構造を持つべきだと主張するのに等しい
アイデンティティ[自己同一性]
アイデンティティ[自己同一性]という概念は、1951年アメリカの精神分析学者エリクソンが提唱したもので、日本語では、自己定義、主体性、存在証明などさまざまな訳語があてられているが、心理学では一般に同一性という用語が用いられている。アイデンティティは、青年時代にもっとも強く希求される。人間は児童期までの両親への依存を断って自立が必要になったとき、初めて自分は何なのかという考えに至る。つまり、両親から離脱した青年は自分自身の価値観を確立しようと努め、その過程を通して社会とのつながりを意識しはじめる。そこで青年の意識は拡大され、社会での自己の位置づけ、社会的な自己定義が必要性を帯びてくるのである。人間は他者とのかかわりあいのなかで多くの「~としての自分」をもち、そこから随時選択しながら生きている。これらがうまく秩序づけられ、統合されていればその人には安心感があり、アイデンティティは確立していると見ることができる。アイデンティティの形成には、その時代の精神的風土の影響を強く受ける。よって、社会の変動が激しく、価値観が多様する時代にあって、世の中で何が重要で、何に価値を見いだすべきかの答えは一つだと断定することができないような、いわゆる選択の自由が求められる時代においては、アイデンティティの形成は困難であるといえる
/a モラトリアム人間
モラトリアム人間とは、アイデンティティを確立しないまま、既成社会の大人への同一化を拒んでいる状態の人間をいう。つまり、青年期が引き延ばされている状態である。精神分析学者の小此木啓吾によれば、モラトリアム人間には二つのタイプが存在するという。一つは、いかなる党派・組織にも帰属せず、何事にもお客様的存在で主体的にはかかわらないで、暫定的なかかわりが優先する気分派でありながら、社会からの脱落派ではないタイプである。もう一つは、組織帰属型の人間のなかに住む「内なるモラトリアム人間」である。組織に帰属し、その役割を果たしながら、なお積極的には組織にかかわらず責任を回避し、現在の自分を本当の自分とは考えていないようなタイプの人間である
エリクソンのライフサイクル論
エリクソンのライフサイクル論の特徴は人生全体を図示することである。エリクソンは人の一生そのものを発達として、「人間は心理―社会的には生涯発達し続ける」という観点から、人生八段階によるライフサイクル(人生周期)論を提唱した。ライフサイクルの各段階の特徴は、段階ごとの課題の達成が成功した場合と失敗した場合の対語によって記述され、それは、各段階には、課題が達成されるかどうかの危機が存在していることを意味している。しかし、各段階において必ず成功しなければならないわけではなく、失敗も体験する中でより多くの成功体験を経験して育っていくのが理想であるとエリクソンは言っている。また、前段階の発達課題は次段階の発達段階の基礎となるので、エリクソンの発達課題からなるライフサイクルはピラミッド型でよく表される。さっそくそのライフサイクル論をみていこう
・○○期 ○:「成功した場合に得られるもの」対(対立命題)「失敗した場合に得られるもの」⇒それらの葛藤によってあるいはその過程で生まれるもの(基本的な自我の特性)
・乳児期 Ⅰ:「基本的信頼」対「基本的不信」⇒希望
・乳児期初期 Ⅱ:「自律性」対「恥、疑惑」⇒意志
自律性を身に付けられるかが重要で、もしそれができなかった場合は恥ずかしいという思いを体験する。最初の自立は、幼児期のトイレット・トレーニングのころにはじまる。肛門の括約筋のコントロールと関連して、はじめて意志する自分が芽生え、このころから、自分を支配する他者(母親)との葛藤がはじまる
・遊戯期 Ⅲ:「自主性(積極性)」対「罪悪感」⇒目的
自分の自主性を高めるために積極的に行動するようになる。それによって目的意識が養われる。男の子の場合は正面攻撃によって積極行動し、女の子の場合は自分を魅力的にすることによって対象を引きつけようとする傾向がある
・学童期 Ⅳ:「勤勉性」対「劣等感」⇒適格
この頃は、学校で急速に知識や技能を修得し、さらに他人との集団関係についても学んでいく
・青年期 Ⅴ:「同一性」対「同一性混乱(同一性拡散)」⇒忠誠
自分と社会とのかかわりについて考え、アイデンティティ(同一性)を確立しようとする。また、両親からの離脱を願う自分とまだまだ依存していたい自分との間で葛藤する時期でもある
・前成人期 Ⅵ:「親密」対「孤立」⇒愛
今までにない親密、つまり異性との恋愛を経験することが愛の確立につながる。これに失敗すると孤独をもたらす
・成人期(中年期)Ⅶ:「生殖性」対「停滞(自己没頭)」⇒世話
いわゆる人生の午後ともいわれるが、結婚して子どもを生み、育てていくことに関心をもつ。、社会的な業績や芸術的な創造もこの中に含まれる。身体的な衰え、社会的な役割の上昇停止、子どもの親離れ(母親的役割の解放または剥奪)、夫婦関係の再調整など、いろいろな側面で人生の転回点が訪れる。しかしその安定と不安定、獲得と喪失のはざまの中にいるからこそ、自己の真の自立も見いだせるチャンスであるといえる
・老年期 Ⅷ:「統合」対「絶望、嫌悪」⇒英知
最後に自分の人生を振り返り、肯定的に統合することで幸福的英知を抱き、生涯を終える
自己愛と対象愛
P・ネッケは、自分自身の肉体を愛の対象とする性的倒錯をナルシシズム(自己愛)と呼んだ。フロイトはこの用語を、リビドーが自己に向けられた心的状態とする広義の解釈をし、人間の精神性的な発達は自体愛から自己愛へ、そして対象愛という順序をたどるとした。一方、その後の精神分析学者たちの多くは、自己愛は人間の根源的な欲求であり、健康な自己愛の満足が必要だと主張している。たとえばエリクソンは、乳児期の母子間に愛し愛される相互性がうまく成立したとき、子どものなかに自己への自信と信頼(自己愛)が生まれ、これが後の健全な人格の成長の基盤になるといっている。これが顕著になったいわゆる自己愛人間には、誇大感、称賛を求める自己本位の思い込み、失敗を認めない、周囲の批判に対して極度に傷つき被害的になる、共感性の欠如、他人と深くかかわらない、自己中心性などといった特徴をもっている。私たちは、他人を愛しているように見えても究極の関心は自分にあるような人を大勢見かける。そのような人たちはまだ完全に対象愛を実践しているとはいえない。例えば、子どもの将来のためといって子どもを有名校への受験に駆り立てる母親や、恋人のためといって自己を犠牲にする行動は、一見対象愛に見えるが、自己愛に基づいていることが多々ある。真の対象愛とは自分のコントロール欲求を最小限にすることでしか実現できない。この自己愛が対象愛(他者愛)に変化するということが、相手の満足と安全が自分自身の満足と安全と同じ重要性をもつようになることなのである。恋愛から結婚に移行する過程においても、自己愛が他者愛に変化してほしい、という心理状態が働いている
甘え
甘えとは、親または心理的に親と同じ意味をもつ人に対し、相手から愛され、相手との一体感をもつことを求める欲求のこと。その起源は、乳児が、母親と自分とが別の存在であることを体験して、その失われた母親との一体感を回復しようとする欲求にさかのぼるといわれている。この欲求は受動的で、その満足が相手に左右されることから、恨みの感情をはらんだ両価的な特徴をもっている。つまり甘えの強いものほど逆に傷つき、被害的になりやすく、攻撃へと転ずる可能性も秘めているため、結局甘えは克服しなければならない欲求といえる。特に成人になってからの甘えには、甘えることによって相手を思うままに支配しようとしている欲求がみえる。それは冷酷無比である
不協和解消
自分の考えと行動が不一致のとき、不快の感情が生まれる。そうなると、どちらかを変えようとする。通常は考えに合わせて行動を変える。しかし、行動が変わらないときは、行動に合わせて考えを変える。考えと行動を一致させようとする心理を不協和解消という
非類似の嫌悪
人は自分と意見が違う人は嫌いになる心理がある。これを非類似の嫌悪という。類似性が好意を生むのに対し、非類似は嫌悪を生む。ではなぜ自分の意見に反対する人に強い嫌悪感をもつのか。それは自分の意見が反対され、否定されると、自分の価値を否定されたように感じるからである。私たちは自分を肯定することによって、自信をもって生存することができる。なので生きていく力を否定するような反対意見をいう人には強く反発し、嫌悪感をもつのだ。また、人は自分が悪いとわかっていても、素直に受け入れることができないものなので、自分が悪いことを自分で認めざるを得なくなると、自らの自己評価が下がり、イヤな気分になってしまう。人からの批判は自己否定されることと同じであるといえる。自己否定されると自己嫌悪に陥って落ち込むか、相手を嫌悪するかのどちらかになる。つまり、批判による相手への嫌悪感は、自己否定に対してそれを心理的に取り戻すための反発心であり、自分を守るための防衛本能であるといえる
八方美人
心の底で漠然と、他人は実際の自分を好きではないと感じている八方美人は、迎合している自分は他人に好かれていると錯覚している。八方美人が知らねばならないことは、もしこの世の中で自分が好かれるとすれば、それは、実際の自分以外にはないのだということである。虚勢を張っている人間も、このことを心に銘記すべきである
a 八方美人になってしまう理由
(1) ほめられたいから
ほめる人は好かれるが、なぜ八方美人は好かれないのか。確かに人はほめられることは心地よいと思うのだが、そこには“自己限定(特別感)”の属性が付加していることが条件なのである。つまり、自分だけほめられる、言い換えれば自分だけほめられたいと思っているものなので、誰でもほめている八方美人は歓迎しないのだ
(2) 嫌われるのが怖いから
八方美人が誰にでもいい顔をするのは、その人の人格を尊重しているからではなく、嫌われるのが怖いからである。八方美人=自己の他者化
欲求依存承諾
何かをする、何かを選ぶ、何かを使い続ける、何かに依存する。このことにおいてまず一番基本かつ強力な属性がある。それが欲求である。ドレッシングを買う。それはなぜか。ドレッシングが欲しいからである。数あるドレッシングの中からこのメーカーのこのドレッシングを毎回買い続ける。それはなぜか。そのドレッシングが一番美味しいからである。欲求依存承諾とは、相手の欲求をまず満たすことで承諾誘導するものである。この承諾法には種類がある。一つは相手の欲求が何かを見極めること。そしてそれを満たすことで依存させるものである。もう一つは相手の欲求を作り出すこと。つまりサラダを用意することである。いずれの種類にも共通するコツがある。欲求依存承諾の真骨頂といっていい。それは、まず相手の欲求を一つ満たすことである。病院は実によくできているといえる。人は病気をする。少し体調が悪くなることは誰にでもあることだ。それを治すのが病院。そしてそれは病院でしか治せない。患者が医者に期待することはただ一つ。病気を治してほしいということだけだ。患者は数ある病院の中から一つを選んで行ってみる。ではそこの医者が病気を治したとしよう。患者は健全になり、医者は感謝される。しばらく経ってまた何かの病気にかかってしまった患者はどうするだろうか。真っ先に前に治してもらった医者のところへおもむくはずだ。そこでの医者から患者への「こうしたほうがよい」「この薬を使ったら治る」というアドバイスに対する患者の受けとめ方は、最初に通院したときと今回とではどう違うか。今回のほうが「先生の言う通りにしたら治るだろう」と信じる気持ちは大きいはずである。このように、一度相手の欲求を満たせば、そのあとで多少欲求を満たせなかったり満たせたりバラつきがあったとしても、対象への欲求は増大する傾向がある。それは依存へと発展する。依存となった場合、効果のはっきりしないような怪しさ満点のものでも、それを求め続けてしまうこともあり得るのだ。例えば、顧客があるブランドの石鹸を使って肌がすべすべになったり、にきびができにくくなったりしてはっきりと望ましい効果が出た場合、顧客はその石鹸のブランドの他の商品、シャンプーや化粧水や美容液なども買い揃えるだろう。しかしそれらにはっきりとした効果が出る、いわゆる優良品かどうかの確証などない。しかし顧客は現にそれらの商品を買ったのである。そして実際にシャンプーや化粧水にはっきりとした効果が出なかったそこそこの商品だった場合でも、顧客がそれらをおいそれを使うのをやめられるかどうかはまた疑問であるといえる。なぜなら、石鹸が彼ら(彼女ら)の欲求を満たしているからである。欲求依存承諾にはもう一つコツがある。それは欲求を満たすもの以外の周りのものの価値を下げたり無くしたりして閉鎖的・独立的な状況を作り上げることである。先ほどの石鹸を例に挙げると、安価な市販の石鹸の中に高価だが効果が高い石鹸を掲げる、市販品だが実店舗には置いてなくネット限定販売である、安心の老舗製薬会社が肌のためを考えて作った石鹸、そして極めつけはネットユーザーの評判が良いことなどである。このように効果の薄いものは効果の高いものの後につくことによってその恩恵を受けることができる。人間は圧倒的な知性と理性をもっているが、欲求本能に即したものにはまだまだ原始的なものである。もう一つ例を上げる
(例)
相手の立場になって物を見る発想をしたピザのデリバリー商法が成功している。それは、ピザを電話で注文すると、指定の時間に必ずデリバリーするという新しい商法である。さらに面白いのは、一分でもデリバリーが遅れると700円お引きしますとPRしていること。そこでピザの会社はギリギリの時間にピザを届ける。お客さんはギリギリの時間になってくると「シメた、もうすぐ700円儲かるぞ」と時計を見ながら、まるで競馬のレースを見ているようなスリルを味わっている。特に、最初に一回だけ、遅れて700円儲かったとなれば、客はそれ以後何度もピザを注文するようになるだろう
口唇愛期的性格
おしゃべりな人ほど、実は甘えん坊で、おだてや親切に弱い傾向がある。フロイトの性格形成に照らし合わせれば、この種の人は口唇愛期[こうしんあいき]的性格の人ということになる。フロイトによれば、口唇愛期的性格とは、何らかの理由で、乳幼児期(口唇愛期)にこだわりをもって育ったことに原因があり、形成される性格であるという。この性格の人は、ゼロ歳児の赤ちゃんにたとえられる。赤ちゃんは全面的に母親に依存し、お母さんのおっぱいに口を当てて栄養を補給する。すべての快感を口から得ているわけである。このことから、人に対する依存心が強く、愛されることに敏感で、愛されたいと強く望む傾向が強いといえる。また、世話好きで人の面倒見がよく、絶えず口を使う。つまり、しゃべったり食べたりすることが好きなのである
a 応用
慣れたセールスマンは、おしゃべりな女性を狙うという。おしゃべりな女性ほど実は甘えん坊で、おだてや親切に弱い傾向があるからである。初対面でもよく話す人は、自己主張が強い人のように見えるが、その深層心理には強い依存性が隠れているので、人間関係がつくりやすい(口説きやすい)と思って間違いない。だが、早口でおしゃべりな人は、「よく考えてから話す」という手続きをとらないために失言も多いし、自己主張も強いといえる。口説きやすそうに見えても、実は赤ちゃんのようにわがままな人だから、少し注意は必要かもしれない
接触行動の心理
身体的タッチ(接触行動)は愛情の表現やセックスの欲望の表現である。さりげないタッチは相手に好感を与える。恋愛中の男女の場合、女性は腕を組みたがり、男性は手をつなぎたがる
好悪の原始的傾向
人間は、というより、人間を含めたすべての動物は、自分の好むもの、自分の欲求を叶えてくれるもの、自分にプラスになるもの、快適な気分にさせてくれるものに対しては、それを獲得するために近づこうとする傾向がある。つまり、自分にとってプラスの目標に対しては接近行動をとり、逆に嫌いなもの、イヤなもの、危険なもの、怖いもの、気持ちの悪いものに対しては、すべての動物がそこから逃げ出し、できるだけ早くその場を去ろうとするのである。これは動物の原始的反応であり、本能的行動である。これを好悪の原始的傾向という。この心理があるために、自分を避ける人に対して、「きっと嫌われている」と思ったり、自分のことを嫌っている人に対して、私たちはその人を好きになれずに嫌いになってしまうのである。嫌われないためには、なんとなくで人を避けるような行動は避けるほうがよいのと、相手に嫌悪感を抱いてもそれを表に表さないことが大切であるといえる(嫌悪の報復性“好意の返報性のルール”)
意識とは何か
脳が決めるメカニズムには、情報の重みづけがある。情報は平等に入ってくると、手がつけられない。たとえば外を歩くときでも、目に見えるものを全部、頭に入れているわけではない。だいたい自分の見たいものしか見ていない。見たくないものは見えていない。その重みづけを、日常的には意識という。意識は自分の脳がどう働いているかということに対する、ある種のモニターで、そのモニターは重みづけについて、ある表現をしている。意識というモニターは、それを好き嫌いといっている。つまり好きなものは脳の中で強い重みがついているので、非常に強く印象に残っている。また同様に嫌いなものに対しても危機感を募らせるため強く印象に残りやすい。脳がいう意識では、好きと嫌いは対称関係(反対関係)にあるのではなく類似関係にあるといえる。では好き嫌いの対称関係にあるものは何か。それが無関心である
基本的な四つの心理
a 同化作用(類似の法則)
よく似ているものは、同じ力を持つだろうと思い込む心理
b 暗示作用
あることをしたらいいことが起こった人の話を聞いたりして、自分も同じことをすればきっとうまくいくだろうと信じ込む心理。過去にやったことでうまくいったことを繰り返すと次もよくなると思い込むのも同じ心理による
c 普遍的無意識の作用
血を見ると怖い、夜が怖いといった、すべての人間がもっている共通の原始的な心理。円形の図形を見ると気持ちが落ち着いたり、海を見ると気持ちが静まるといった作用もこれに似ている
d 伝染作用(接触の法則)
その人がいつももっているもの、身につけているものには、その人自身と同じようにつながりをもっていて、大好きな人の髪をもっておればその人を所有しているのと同じ状態になるという心理。イヤな人を呪い殺したいとき、むかしの人はその人の髪の毛やツメを火の中で焼いたり、その人が愛用していたものを焼くことによって、呪い殺すことができると考えた
ミラーリング効果
好感を寄せている相手の仕草や動作を無意識のうちに真似てしまうこと。また、自分と同様の仕草や動作を行う相手に対して好感を抱くことをミラーリング効果という。意識している、していないに関わらず、「真似る」「模倣する」といった行為は、相手に対する尊敬や好意の気持ちを表現したものとして認識される。つまり、自分の仕草を真似る人=仲間・味方といった形で記憶・認識される
/a ミラーリング好悪
人には、自分の顔やからだの特定の部分に「自信のある好きな」部分がある。相手がその気にしている部分をもっていたり綺麗だったりするとその人に好意を抱きやすい。例えば、歯並びや、歯に自信がある人は、歯の美しい相手に一目惚れしやすい。そして歯並びが悪い人や口臭のする相手には、普通以上に嫌悪感を抱きやすいといえる
必要と敏感
ずるさ、冷たさ、隠された憎悪は弱さに敏感である。なぜなら、それらは弱さを必要としているから。必要としているからこそ、敏感に弱さを見分ける
シンデレラ・コンプレックス
女性には、男性によって守られたい、救われたいとの依存欲求が存在する。これをシンデレラ・コンプレックスという。父親からかわいがられながら支配され、それを黙認する母親から“従順にしていればいい子だ”とのメッセージを補強されて育つ女の子は、主体的な動きをしようとするそのときどきで親の反対にあい、自主性の芽を摘み取られて成長する。親の声が内面化され、自己決定を行うことに罪悪感を感じるのがシンデレラ・コンプレックスである。また、女性には、仕事や子育てなどを通じて育まれる“女性としての自信”や“自らを自立した女と思う”自立欲求がある。この自立欲求には周囲から称賛されたいという思いのほかにも、自分に自信をつけるために自立し、自立によって自信を生む意味もあると思う。女性にはこの自立欲求と依存欲求が同時に存在している
女装する人間の心理
女装する人の心理には、女装することで男性は性的興奮を覚え、マスターベーションを行いながら男性である自分が女性として男性を興奮させていると空想する。日常の生活では、このような男性は自分を男性として性的同一視できるが、心理的には女装することで一時的に女性になるわけだ。その一方で、ストレスの高い現代生活からの息抜きとして女装する人たちも存在する。彼らはふつうの社会生活を送りながら、仕事が終わると同僚と飲みに行くような感覚で女装クラブに集う。そこで好みの女装をして変身願望を満たし、同時に女として男性を魅了しているという空想に浸り、性的興奮を経験する。そして一定の時間がくればまた背広に着替えて何事もなかったかのように家路につく。彼らは果たして性的異常者だろうか。考えてみれば、お気に入りのアイドルの写真を壁に飾って、それを見ながらマスターベーションする思春期の性に重なる部分があるのではないか
山アラシ・ジレンマ[アンビバレント=両面感情]
二匹の山アラシが寒い夜を過ごしていたとする。寄り添って暖め合おうとするが、近づきすぎるとお互いのもつ棘[とげ]で身体を痛めてしまう。離れれば寒さに震えてしまう。そこで二匹はそれぞれの個体を快適に維持でき、しかも相手の体温が感じられる距離を求めて、ついたり離れたりを繰り返した。これを人間の男女の愛の関係に置き換えると、ついたり離れたりする状態は、愛と憎しみの関係になる。フロイトは、人間のもつ相手に対しての相反する感情、とくに愛と憎しみなどの強い感情は同時に存在することに気づいた。つまり、私たちは相手に対して関心や愛着があればあるほど、強い愛情を抱くと思われているが、その愛情には憎しみが含まれている。愛情の深さだけ、憎しみも深いといえるのだ。人間はこのアンビバレンス(両面感情)を仮克服(一時的克服)することで成熟にいたる。心理学の教科書などでは、アンビバレンスとスプリッティング[分裂]」を対置して、「人は幼児期には往々にして両親についてスプリッティングな見方をするが、成長するにしたがってアンビバレントな見方をするようになる」といったような説明をしていることもある。ここで言うスプリッティングとは、「ママが大好きだから、パパは大嫌い」というような精神状態。対象ごとにひとつの感情だけが割り振られている状態。何かの拍子に母親の事を嫌いになると、今度は「ママは大嫌いだから、パパが大好き」といった精神状態に切り替わるような状態。そのような精神状態が、年齢を重ね、精神が成長するとともにアンビバレントな状態になると、しているのである。すなわち大人になると一般的に「ママには好ましいところもあるけれど、好ましくないところもある。パパにも、好ましいところがあるけれど、同時に好ましくないところもある」という見方をするようになる、という説明である
/a 突発的アンビバレンス
アンビバレンスとは、ある対象に対して、相反する感情を同時に持ったり、相反する態度を同時に示すこと。この状態は人にとってどっちつかずで不安になるので、人は無意識に望ましくない感情のほうを無意識下に抑圧する。しかし抑圧された感情は消えるわけではないので、望ましい感情を強く意識したとき(口に出したときなど)に同時に無意識下から相反する感情が上昇してくる。フロイトは愛情の深さだけ憎しみも増すという愛憎のアンビバレンスを提唱したが、例えば手助けした人に感謝されたときにその人に対して怒りの感情がわきあがる場合がある。そんな自分を諌めて口ではもっともなことを言う。突発的アンビバレンスは、抑圧されていない望ましい感情が強く意識されたときに反動的に抑圧された相反感情がわきあがるのである。それは決して慈善的な自分に不安があるから上がるわけではない。もともと心のなかに望ましくない感情があるだけなのだ
三次元の視覚像の生成プロセス
アダルバート・エイムズが行った実験の成果。視覚神経が捉えた情報から立体的イメージが作られるときのプロセスには、遠近法などの数々の数学的前提が組み込まれているが、それらの運用は完全に無意識のレベルで進められており、そのプロセスを意志によってコントロールすることはできない。ヴァン・ゴッホが独特の遠近法で描いた椅子の絵を前にして奇異な感覚に襲われるとき、われわれは無意識にとっての自然な見え方をほのかに意識する
基本的信頼
人が幸せに生きていくには、人から愛されることや周囲から認められることが大切だと考える人は多い。もちろんそれらを必要としない人もいるが、大半の人は愛されることや人に受け入れられることには強い欲求がある。これを「基本的信頼」という
幼少期に子どもが母親から様々な影響を受ける中で、基本的信頼はもっとも必要不可欠な要素である。子どもはここで母親から愛されることの快感や周囲に自分の価値を受け入れられることの喜びを学び、しだいにこれらをもっと得ようとする欲求を高めていく。しかし、この基本的信頼が欠けると、大人になったときに過剰な母親固着が見られたり自分を低く評価してしまうなど、歪んだ性格の固定化にもつながりやすい。基本的信頼は子どもにとってとても大切なことであるが、大人にとっても不足したものを補うようになくてはならない要素である
この世には、あなたが失敗しても、決してあなたに失望しない人がいる。あなたの成功失敗に関係なく、あなた自身を受け入れてくれる人がいる。あなたがその人に抱く感情、それが基本的信頼である。これはたいてい母親であることが多いが、この基本的信頼が有る恋人同士や親友同士ではより強固な関係が構築される
a 基本的信頼を生み出す三つの要素
(1) 自分が無能であっても受け入れてもらえる
(2) 相手の期待を実現できなくても受け入れてもらえる
(3) 相手と違っても受け入れてもらえる
錯覚
錯覚とは、感覚器に異常がないのにもかかわらず、実際とは異なる知覚を得てしまう現象のこと
不注意性錯覚:対象物への注意が不十分のために起こる錯覚。見間違い、聞き違い、人違いなど、われわれが日常経験する多くの間違いを含んでいる
感動錯覚:暗くて怖い場所を歩いていると、物の影が人影に見えたり、何でもない物音を人の気配に感じることがある。恐怖や期待などの心理状態が知覚に影響を与えるものである
パレイドリア:雲の形が顔に見えたり、しみの形が動物や虫に見えたりと、不定形の対象物が違ったものに見える現象に代表される。対象物が雲やしみであることは理解しており、顔や動物ではないという批判力も保っているが、一度そう感じるとなかなかその知覚から逃れられない。熱性疾患の時にも現れやすい。変像とも言う(例:人面魚、火星の人面岩、トリノの聖骸布など)
生理的錯覚:数多く知られている幾何学的錯視や、音階が無限に上昇・下降を続けるように聞こえるシェパード・トーン[無限音階]などのように、対象がある一定の配置や状態にあると起こる錯覚。誰にでもほぼ等しく起こる
母親固着
防衛、確実性、愛情を与えてくれる力を狂気のごとく希望することよりも、より自然なことが人間にありえようか。人は安全と確実と愛情を確信出来るものを得るためなら、そのために猛烈なエネルギーを注ぐ。これを母親固着という。人が幸せを求める原動力もこの母親固着によるものが大きい。安全、確実、愛情、これら全ては、これを包摂する本能である「快楽[快楽原則]」に基づいている。例えば愛情は、快楽の上に愛情があるのであって、愛情が先行してあるわけではない。赤ちゃんは母親に最初から愛情を抱いているわけではなく、抱っこされたり、幾度となくおっぱいからミルクをもらううちに、快楽を与えてくれる母親に対して愛情が芽生えてゆくという流れの解釈になる。そして快楽原則に端を発するものは、常にその土台に快楽原則があり、自己の快楽が主導となっている点に注目である。傘を犠牲にして雨から身を守る、動物を捕まえてその肉を焼く、奥さんと子どもが悲しむと分かっていても不倫をしてしまうといったように、自己の快楽を満たすためには他を犠牲にするのもやむを得ないと私たちは潜在的に悟っている。快楽というのは野放しにしておくと本当に青天井なので、社会的規範から逸脱しないように、いつも理性と戦っている
(例) 真に愛することの意味
相手を最高に愛するには、少なからず自己を犠牲にしなければならない。これについて、ゲーテは次のような具体的な愛の形を提言している
「愛する人の欠点を愛することのできない者は、真に愛しているとは言えない」
<ゲーテ>
ストレスと反動
理性によってエスが抑圧されているとき、人はストレスを感じる。そのストレスが何らかの形で発散されることを「反動」という。反動には直接的反動と間接的反動がある
無意識に出てしまう仕草や突発的な反動形成、彼氏にフラれてカラオケで声を枯らして歌うなどは間接的反動に分類される
(直接的反動の例) 自分自身で抑制・制限をかけていた場合に、ふとその制限を一切払って全力で挑戦してみたいという反動にかられることがある。ダイエット中の人がおよそ半月分のおかずを作ったとする。そのおかずを15回に分けて食べるつもりなのだが、ふと今ここで全部食べてやろうという衝動にかられることがある。抑えている欲求が見え隠れする心的作用である
また反動というだけあり、直接的反動の程度は制限をかけていない通常時のそれを上回るケースが多い
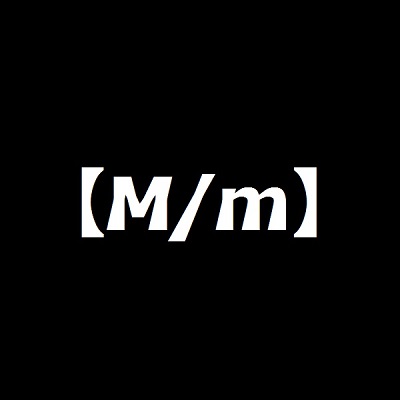

 TOP
TOP