目次
アルコール依存症
/a 原因の方向性
アルコール依存症の原因または理由を、アルコールが入っていないときの患者の生活の中に探るべきであるとする考えが、一般の風潮としてある。あの人は醒めた状態で、未熟である、マザコンである、受動―攻撃的である、成功への不安にとりつかれている、プライドが高すぎる、あるいは単に弱い、だから酒に溺れた、という言いかたがされている。しかしこうした言説が、どのような根拠からアルコール依存症へと結びつくのかという論理に言及しているところは見受けられない。この常識的見解には問題点がある。アルコール依存者の醒めた生活が、なんらかのかたちで彼を酒へ――酩酊へのコースのスタート地点へ――追いやるのだとしたら、彼の陥っている醒めのスタイルが強化されるような治療を行っても、症状の軽減も統御も、望むことはできないはずだ。原因の方向性を探るためにここから新たな見解を提示していこう。彼の醒めのありかたが、飲酒へと彼を追いやるのだとしたら、その醒めには、なにかしらのエラー(病)を、酔いが(主観的な意味で)修正しているはずだ。つまり間違っているのは彼の醒めの方であり、酔いの方は、ある意味で正しいということになる。つまり、世間の狂った前提への反抗として飲酒に走るのではなく、世間によってつねに強化されつづけている“自分自身の狂った前提”からの脱出を求めて飲酒に走るということ。この違いが重要だと思う。したがってこの新たな見解では、醒めと酔いの関係が、ふつうの議論とは逆転したものになっている。酔いが醒めに対する(主観レベルでの)矯正の機能を担っているという立場をとっている
/b 敗北の認識論
依存症の人間をかかえた家族や友人は、「もっと強くなれ」「酒の誘惑に打ち勝て」と叱咤する。これらの言葉が、現実に何を意味するのかは定かでないが、重要なのは、依存者自身が、醒めているあいだは、自分の弱さにこそ問題があるのだと一般に考えている点だ。彼はわが魂の指令官になれると、少なくともそれがあるべき姿だと、信じている。これを、依存症の更生に唯一誇るべき成果をあげている「アル中匿名会」(以下AA)では、意志の力でボトルの誘惑に抵抗しようとすものに対する軽蔑の意味で使われている。AA共同創立者の一人で、みずからアル中患者であった、ビル・W氏の手になる有名な「12のステップ」は、その第一のステップで、酒との戦いというばかげた神話に鋭くメスを入れている。アルコールとは戦えない、そんな力は自分たちにない、ということを認めるのが、更生への第一のステップとして明記されている。しかし多くの患者はこれを「降伏」と解しており、そのために多くの患者はそこへ踏み上がることができない。その状態にあるうちはダメだ、とAAは見る。患者は、ひとしきりの覚醒が続いたあと、また自己制御とやらを持ち出して、誘惑との架空の戦いを始めるばかりなのだ。彼らが認めようとしない、あるいは認めることができないのは、酔っていようが醒めていようが、アルコール依存者の自己の全体が、「アル中パーソナリティ」なのであり、そういう自己が、アル中と戦うなどということが自己矛盾なのだという点だ。AAはこれを的確に把握している。「あなたの意志で直そうとすることは、靴紐を引っぱってあなた自身を持ち上げようとするのと同じです」と。この“敗北”を認めるというのは、患者が敗北の経験から変化の必要を悟るというだけではなく、敗北することそれ自体がすでに変化の第一ステップなのだ。この第一のステップは、降伏ではなく、認識論(エピステモロジー)の変化――世界のなかのパーソナリティについての知のあり方の変化――と言うべきだ。この変化が誤った認識論からより正しい認識論への変化となっている点に、特に注目したい
/c 治療法
ここでは治療法を書くが、まずアル中依存者の特徴を述べてから治療法を考えたほうが分かりやすい。その意味でこの項は“アル中依存者の特徴と治療”といった意味をもつ
c-1 負のプライドを捨て去る
彼らに具わっているのは、負のプライドだ。このプライドが、本人が過去に為しとげた何かをめぐって成立するコンテクストのなかで醸造されたものでないことは明らかだ。このプライドは、なんら誇るべき実態を持たない。強調点は「オレはできたぞ」ではなく、「オレはできるぞ」にある。「オレにはできない」という命題を受け入れることができず、取りつかれたようにチャレンジを繰り返す姿がここにある。ここでAAの言う「自惚れ」が頭をもたげる。「大丈夫さ、一杯くらい・・・。」そして気がつけば、いつもの泥酔という次第。賭け(リスク/「一杯くらいは平気さ」)にプライドを求め、それを生活原理とすることは、自己の破滅を求めることと変わらない。酒を飲まずにいられたことで、酒を飲まずにいられることの意味が変化する。最初のうちは、酒を断っていられることが、自分のプライドを満足させた。しかしそれができてしまうと、「一杯のリスク」なしに彼のプライドは満足しない。つまり禁酒の継続によって、飲酒と禁酒をめぐるコンテクストの構造が変化するのだ。治療においては、このコンテクスト構造の変化を全力を挙げて阻止することに向けられている。「お前の本性はすでに酒びたりなのだ」と諭すことで、アルコール依存症を患者の自己の内側にしっかりとセットする。負のプライド(アル中的プライド)を捨てるために、患者自身に、アル中であること、そして飲酒に抵抗するなどということがばかげた自惚れであるということを自覚させることだ
c-2 治療的ダブルバインド(“グレゴリー・ベイトソン書付”)
あえて症状の増加する方向へ患者を押しやるという、「治療的ダブルバインド」と呼ばれるテクニックを使う。セラピストが、アルコール依存者をそそのかして、「コントロールされた飲酒」を試みさせ、コントロールできないことを自分で悟らせる
c-3 底を極める
「底が極まる」という現象に、AAは非常に大きな価値を与えている。落ちるところまで落ちていないアル中患者は、救われる見込みが少ないとされる。ふたたびアルコールへ戻っていく人間のことを、彼らはよく「まだどん底まで落ちていない」という。どん底をなめさせる経験は、いろいろなものがあるだろう。アルコール性せん妄症の発作、酩酊時の記憶の喪失、夫婦関係の破綻、失職、回復の見込みなしという診断。どん底で味わうパニックの性格を浮き彫りにしていると思われる一節を、AAの文書から引用しよう
「わたしたちは他人を『アル中』だと宣告したりはしません。あなたが『アル中』かどうか、自分でテストすることをお勧めします。バーに入って、自分の飲みかたをコントロールできるかどうか、試してごらんなさい。飲み出してから、あるところでいきなりグラスを置いて席を立つことができるかどうか。一度ではだめです。何度か繰り返しやってみないといけません。自分に正直であれば、答えはすぐに出てくるでしょう。あなた自身がいまどんな状態にあるのか正しく知るために、危険は覚悟のうえで、この自己診断をやってみてください。」
これはいわば、滑りやすい道で、ドライバーにブレーキをかけさせるというのと同じである。「底を極めた」アルコール依存者のパニックは、自分がコントロールしていたと思っていた乗物が、暴走を始めたことを知った人間のパニックそのものだ。ブレーキだと思っていたものを踏むと、車はさらにスピードを増す。そのとき人は、「自分プラス車」という、どう見ても自分より大きなシステムの存在を、パニックとともに知る
意識が知ること
精神過程全体のうち、意識の占める割合は必然的にかなり限られたものであることは事実だろう。意識は十分に抑えられた状態で、はじめて精神プロセスの役に立つわけだ。習慣によって無意識に事が運ぶことで、思考と意識の節約がもたらされる。知覚のプロセスに意識が割り込めないのも、理由は同じだ。意識は何を知覚したかを知ればいいのであって、どのように知覚したかを知る必要はない。そんなことをしても、精神全体にとって得にはならないのだ。意識できない一次過程が基本にあるからこそわれわれは機能できるのであって、そうでなくても機能できると考えることは、脳が違った構造を持つべきだと主張するのに等しい
転移
人はすべての物理的観念的(実体形式)なものを知覚または扱ったりするときに、コンテクストという対対象用の観念を随伴させる。コンテクストは“意味”のようなもので、対象に背景(輪郭)を与える。逆にコンテクストなしには言葉も行為も物体もまったく意味を持ちえない。新たな他者に出会ったとき、その人がどんな人かというコンテクストを必ず付ける。彼を“父”として見なしたり、もしくは“反父”として見なしたりといったぐあいだ。このような「見なし」を「転移」という。私は転移を「人間のコンテクスト随伴の本能」として広義に定義したい。例えばきのう私たち二人の間に何か起こったとしよう。するとそのことが、今日の互いに対する反応のしかたを形づくるわけだが、これも本質的には、過去の学習からの転移にほかならない
コンテクストは背景そのもので、それは“予測”であり、“期待”である。そして背景を忍ばせる行為のことを転移という。階段をのぼるとき、そこに階段があるということが分かっているからのぼることができるのだ。目の前に階段があってそれをのぼるという一連の行為のなかには、認識のコンテクスト、予測のコンテクスト、そして期待のコンテクストがそれぞれはたらいているのである。これは意思決定のプロセスにつながる
習慣の無意識化
無意識の中に含まれるのは、意識が触れたがらない不快な事柄だけではない。もはや意識する必要のないほど慣れ親しんだ事柄も多く含まれるのだ。身についたことは、意識の手を離れ、そのことで、意識の経済的な活用が可能になる。芸術家が腕(スキル)を見せるとき、彼は自分の無意識に沈めた事柄に関するメッセージを伝えているのである。ただし、それを無意識からのメッセージというのは適当ではない。問題は、しかしそれほど単純ではない。無意識レベルに沈めたほうが得な知もあれば、表面に残しておかなくてはならない知もある。総体的に言って、外界の変化にかかわらず真であり続ける知は沈めてしまって構わないが、場に応じて変えていかなくてはならない行動の制御権は確保しておかなくてはならない。「シマウマは獲物である」という命題はライオンの無意識に沈めて構わないが、個々の状況で個々のシマウマを相手にしたときの個々の動きは、その場特有の地勢やそのシマウマ特有の逃走戦術に合わせて修正できるようになっていなくてはならない。恒久的に真であり続ける関係性についての一般事項は無意識領域に押しやり、個別例の実際的処理に関わる事項は意識領域に留める、という答えがシステムの経済的要請からでてくるのである。思考の前提は沈め、個々の結論は意識の上に残しておくのが得策である
/a 獲得形質と遺伝の見地からみるエントロピー
ソマティックな(体細胞レベルでの)制御とジェネティックな(遺伝的レベル)制御の相互の切り換えを行う場合、どのような要因からそれが働くのかを考察する。その要因を導き出す指標として、「エントロピー(“用語解説”)」を考えてみたい。生物体においてエントロピーを考えるには、生物形態―秩序―拘束―ストレス―負のエントロピーという一連の概念群をこれに対置させるとわかりやすい。すなわちエントロピーとは柔軟性に関わる概念である。生存の観点からみて、“割が合う”ようにエントロピー(柔軟性)を最適値へ補正するという行為が、ソマティックな(体細胞レベルでの)制御とジェネティックな(遺伝的レベル)制御の相互の切り換えにおいて行われていると考えられないだろうか。柔軟性という指標は、まさに先ほど述べたシマウマに対するライオンの適応的学習の例にそっくりだ。ジェネティックな制御へ切り換えた後は、もはや柔軟性を保持している必要が半永久的になくなるといってよい。高山に住みついた種のメンバーは、高山特有の気候や低い気圧等に対する適応を遺伝的決定に任せても損はない。ソマティックな変化の売り物である可逆性が必要でなくなっているのだから。逆に柔軟性がある場合というのは、変動する環境的条件にソマティックな変化をもって適応している場合を指す。変動や逆行を繰り返す状況への適応はソマティックな変化に依るほうが遥かに得策である。また、ソマティックな変化はごく表面的なものに留めておく必要がある。そうでないと、個々の生物へ負担がかかりすぎることにもなる。一口にソマティックな変化といっても、そこには深さの段階がある。ある男が海抜ゼロメートルのところから四千メートル級の山に登ったとすれば、よほどの体調でない限り、息は喘ぎ、心臓は激しく高鳴るだろう。これが一時的な緊急事態であるのなら、このような直接的可逆的な変化で対処するのが正しい。しかし高山の大気圧というような今後変化する見込みのないものへの適応を、喘ぎと心悸高進で行うというのは、柔軟性のはなはだしい無駄使いだ。この場合は、逆戻りしにくいレベルで適応するのが好ましい。柔軟性をセーブするために、ある程度の可逆性を犠牲にするのは損なことではない。そうすることで、喘ぎと心悸高進とを、高山上で更にがんばる状況が出てきた時のためにとっておくことができる。そこで順化と呼ばれる現象が起こる。ソマティックな制御からジェネティックな制御への政権交代だ。その男の心臓は変化を蒙り、血液中のヘモグロビン量は増加し、肋骨が囲い込む容積も呼吸の具合も変わる。これらの変化は喘ぎよりずっと可逆性に乏しい。今度は平地に降りた時に、その男は何らかの不快感を覚えるだろう。表面的なレベルで個々の直接的、具体的な要請に対処する体細胞的適応と、より深い(抽象的)レベルで全体的な要請に対処する体細胞的適応が、階層構造をなしているといえる。この点は学習の場合とまったく同様だ。学習においても、狭い範囲の事実や行動に即応する第一次学習と、コンテクストまたはそのクラスに応じた変化を獲得していく第二次学習とが、同じようなヒエラルキー構造をなしている。この点については先ほどのシマウマとライオンの例を見ていただくか、学習とコミュニケーションの階型論(“グレゴリー・ベイトソン書付”)を参照されたい
順化が数多くの前線(心筋、ヘモグロビン、胸部の筋システム等)における数多くの変化を巻き込みつつ達成されるのに対し、緊急措置の方は、ふつう個別的でその場限りのものだという点にも注意されたい。順化するとは、生物が深いレベルでの固定性を支払って(手に入れ)、表面的な柔軟性を買いとる(手放す)ということである。順化を果たした人は、喘ぎと心悸高進とを熊に出会った時のために貯えておくことができるが、低地に住む旧友を訪ねる時は不快感を味わわなくてはならない
ダブルバインド
精神分裂症は依然として心の病のなかで最も大きな謎のひとつであり、その性質も原因も治療法も、ほとんど解明されていない。ダブルバインド理論は、グレゴリー・ベイトソンが提唱したもので、コミュニケーションの分析、とりわけ論理階型理論に基づいた精神分裂症の理論である。ダブルバインドに捉えられた人間は、その中で分裂症的症候が育まれるというのがこの理論の骨子である。家庭にみられる呪縛的状況はまた社会生活において周りの人とのコミュニケーションの中にもみられることがある
このダブルバインドには必ず一人の犠牲者が必要である。また、ダブルバインドが犠牲者に課せられるときは繰り返しの経験によって育まれる。決してトラウマのような一回で成立するものではない
ダブルバインドを簡単に言うと、たとえば母親によって子どもが二重拘束、つまり身動きのとれない心理的葛藤の状態となることをいう。母親が子どもに対して何かをするようにといい、と同時にそれはしてはいけないと命令すること。禅の修行において、師は弟子を悟りに導くために、さまざまな手口を使う。そのなかの一つに、こういうのがある。師が弟子の頭上に棒をかざし、厳しい口調でこう言う
「この棒が現実にここにあると言うのなら、これでお前を打つ。この棒が実在しないと言うのなら、お前をこれで打つ。何も言わなければ、これでお前を打つ。」
分裂症者の人間はたえずこの弟子と同じ状況に身を置いている。しかし彼は悟りとは逆の混乱の方向へと導かれる。禅の修行僧なら、師から棒を奪い取るという策にも出られるだろう。そしてこの対応を、師が「よし」と認めることもあるだろう。しかし分裂症者がそのような選択をとることは不可能だ。相手との関係に対して大胆になることは彼は許されていないし、彼の母親と禅師とでは、その目的も意識も大きく違っているのだ。ダブルバインド状況に囚われたものは誰もみな、論理階型の識別能力に支障をきたす
そもそも母親はなぜ矛盾した二つのメッセージを送るのか。子どもは母親にとって喜ばしいものであるとともに不安の種でもあり、自分の思うとおりにいかないときに敵意すら感じる。しかし、その敵意を上手に受け入れられない。その結果、敵意は抑圧され、自覚されないままになる。そうした抑圧に気づかないまま母親は子どもに敵対的な行動(~してはいけないという教育など)をとるが、子どもを愛しているとも感じているので敵対行動をとるときに、愛情深さを装う行動も随伴させる。このように母親の子どもに対するアンビバレンスなメッセージがかえって子どもを混乱させてしまうのだ。これは両者を置き換えてもいえることだと思う。つまり母親の存在も子どもにとっては重要なことで、喜びの種となる一方、怒らせてしまわないか、愛されなくなるのではないか、などという不安の種も付きまとっている。この分裂症を育む家庭の状況は、ダブルバインド理論の中核をなす重要なところであるので、ベイトソンの記述も織り交ぜてもう一度よく噛み砕いていこう。ここに書くのは分裂症を育む家庭状況の一般的特徴であることを確認のこと
・母からの愛を感じて近寄っていくと母が不安から身を引いてしまう、そういう母親をもつ子がいる。つまり、子の存在が母親にとって特別の意味をもち、子との親密な場に引き入れられそうになると母親の中に不安と敵意が起こるという状況がある
・わが子に対して不安や敵意を持っていると認めることができない母親がいる。彼女はそうした感情を否定するために、子どもを愛していることを強調する行動を子どもの前でとる。そしてそのとき子どもから返ってくる反応が、自分を愛情に満ちた母親として見るものでない場合、彼女はその場から身を引いてしまう。ここで「愛を強調する行動」とは、必ずしも「優しさを示す行動」を意味しない。子どもを「いい子にしつけるための適切な行動」も、そのなかに含まれる
・母子関係の間に割り込み、矛盾のしがらみに捉えられた子どもの支えになるような存在――洞察力のある強い父親など――がいない
これらのことにおいて問題なのは、彼女(母親)が、自分の不安を、子どもとの距離の調節によって制御しているという点にある。彼女は子どもの反応を用いて、自分の行動が愛によるものであることを確証しようとする。しかしその“愛”は装われたものであるから、子どもは母親との関係を維持するために、彼女のコミュニケーションの真実を見破ってはならないという状況にはまりこむ。母の本当の気持はこうであり、優しさを表わすメッセージの方は、母の心をそのまま示すのではなく、それとは違った論理階型に属するということを受け入れるのは、子どもにとって破滅的なことだ。それを受け入れずにすますために、子どもはメタなレベルのシグナルについての自分の理解を体系的に歪める必要に迫られる。例を考えよう。母親が子どものことをうとましく思い(いとおしく思っても同じだが)、子どもから身を引かずにはいられない気持に襲われたとき、彼女は、「もうおやすみなさい。疲れたでしょう。ママはあなたにゆっくり休んでほしいの」とでも言うだろう。言葉になって明確に発せられたこの“愛”のメッセージには、言葉でいうとしたら「お前にはうんざりだ、わたしの目に入らないところに消えておしまい」とも表現される感情を否定する意図が含まれている。ここでもし子どもが彼女のメタ・コミュニケーションのシグナルを正確に識別すれば、母が自分をうとましく感じ、しかも優しいそぶりでだまそうとしている事実に直面しなくてはならない。メッセージの等級を正しく区別する学習をすることで、罰を受けるのだ。子どもは、母に嫌われていることを受け入れるより、自分が疲れていることを認めてしまうことに傾くだろう。これは、自分の身体から得られるメッセージに関して、自分自身をあざむいて、母親のあざむきに加担するということだ。母親との生活を守るために、子どもは他者からのメッセージばかりか、自分自身が体感するメッセージについても誤った識別を行うように駆りたてられるのである。もちろん、このようなことが数回おきたぐらいで子どもが受け取るメッセージの論理階型の識別能力に狂いが生じダブルバインドを課すことになるわけではない。しかしダブルバインドは、犠牲者の経験に繰り返し現われるテーマであり、トラウマのように一回の経験が心の深みに傷を与えるというのではない。繰り返される経験の中で、ダブルバインド構造に対する構えが習慣として形成されるのだ
ダブルバインドの状況を時間的視点から見た場合、二つのタイプに分けられる。被験者が二重のメッセージを受け取るときが“同時”であるケースと、同時ではない時間差があるケースだ。同時に相反する二重のメッセージが送られる場合は、「言葉」対「パラ言語やキネシクス等の非言語コミュニケーション」の例が多い。言葉では「面白い!笑える!」と言って興味を示しているような人が、表情や目はまったく笑っていない、など。一方、時間差があるケースというのは、例えば洋服屋に友人とショッピングに行ったときのこんな会話に表れている
友人「(ショーケースの服を)見て! この服すごい可愛いと思わない!? 私こういう服好きだわ。あなたにもきっと似合うわよ!」
私「そうね、私もこういう明るい服は好きだわ。」
友人「んー、でもやっぱ似合わないかもね」
この友人は似合う・似合わないという相反する事を見事に言ってのけているが、そこには時間差が生まれている。つまり同時にこのメッセージが伝えられたわけではない。こういうケースでもダブルバインド(二重拘束)は立派に成り立つといえる
――
分裂症者の母親は、なぜこのような特別のやり方で子どもを制御し支配せずにはいられないのか。ある若い女性の分裂症者が、最初のセラピーの場で開口一番語った次の言葉は、その問いにかなり決定的なヒントを与えているように思われる
――「母は結婚しなくてはならなかった。そしていまわたしはここにいる。」
この発言は治療医に対して次の意味をもった
・この患者は法で容認されていない妊娠の結果生まれた
・その事実が(患者の意見では)現在の彼女の精神病と関係している
・彼女の発言の「ここに」という言葉は、「治療室」と「この世」との両方を指している。患者は、自分を生むために、罪を犯し苦しんだ母親に対して永遠に償われることのない精神的負債を感じている
・「結婚しなくてはならなかった」という言葉は、母親の結婚が強制によるものであること、そして周囲の圧力によって結婚を強いられた母親が、それに対する怒りの気持を娘にぶつけたことを示している
母親の患者に対するコミュニケーションには、いつも次のような無言のメッセージがつきまとっているようだった。「わたしは人を愛し、人から愛され、自分に満足している人間である。おまえはわたしのようであるとき、わたしが言った通りにふるまっているときは人から愛される人間である。」ところが同時に言葉と行動とで、彼女は娘にこうも仄めかしていた。「おまえは身体も頭も弱く、わたしとは違っている。正常ではない。こうしたハンディキャップがあるのだから、おまえにはわたしが、わたしだけが必要なのだ。そしてわたしはおまえの面倒を見てあげよう、おまえを愛してあげよう。」こうして、患者の一生は、自立と経験に向かおうとして、そのたびに母の胸に引き戻される、ゼロからの出発の連続という形相をとったのである(これが、ダブルバインド理論が、接触が排斥に結果し、排斥が接触に結果するブザーの回路と類比している一面である。「接触がなされれば接触は切れる」と記述されるブザーの回路を、ベイトソンは自然界に起こるパラドックスの基本形として、よく説明の小道具に使用した)
/a ダブルバインドにおける自己防衛
a-1 リテラルな対応の自己防衛
ダブルバインド状況に捕らえられた人間は、分裂症的な行動を、自己防衛の方策として示すことがある。相互に矛盾するメッセージを与えられ、それに対してなんらかの答えを返さなければならない、しかもその矛盾について何も言えないという状況に陥ったとき、比喩として述べられた発言をリテラルな(字句通りの)ものとして受け取ることは珍しくない。例えば、勤務時間中に帰宅したサラリーマンのもとに同僚が電話し、気軽な調子でこうたずねた。「おい、どうやって家に帰ったんだ?」するとその男は「いや、車でさ」と答えた。ここで同僚の問いは、「勤務時間に家で何をやっているんだ」という比喩的な意味を担っているのだが、男はそれにリテラルな受け答えをしてしまったのである。同僚としては、友人の行動を咎める立場にはないので、あたりさわりのない――メッセージが意図するところと発話の文字通りの意味とが食い違う――隠喩表現をとった。そして、自分が当然非難を受ける立場にあることを自覚して張りつめた精神状態にある男は、その語句のレベルに忠実な受け答えに走ったわけである。これは緊張状態に追いやられた人間には一般的に見られる反応で、証人として法廷に立った人間も、きわめて逐語的な受け答えに終始することが知られている。分裂症の人間はつねに、こうした緊張状態に置かれており、リテラルなレベルへの固執を習慣として抱え持っている。そのため、リテラルな対応がまったく不適切な(たとえば相手が冗談を言ったような)場合でも、自己防衛的な受け答えに終始する
a-2 隠喩表現の自己防衛
また、ダブルバインドに捕らわれていると感じているときの分裂症者は、また、自分のほうからも、リテラルな表現ともメタフォリックな表現ともつかないメッセージを発する。たとえば、担当医が約束の時間に遅れてきたとする。患者はそれを医師が自分を軽視していることの表われだと感じても、それが事実であるという確信はもてない。とくに医者がこちらの気持ちを察して遅刻を詫びた場合、非難してはいけないと思う。それをしたくても、「どうして遅れたんですか? きょうはわたしを診たくないと思ったからですか?」と尋ねたのでは、非難になってしまう。そこで彼は隠喩のモードに切り替え、「以前わたしの知り合いが船に乗り遅れて、彼の名前はサムといいましたが、そのとき船はもう少しで沈んでしまうところでした・・・」とやり始める。このメタフォリカルな物語を、相手は遅刻についてのコメントとして取る場合もあるだろうし、そう取らない場合もあるだろう。そこが、まさに隠喩を使うことの利点であるわけだ。隠喩を使うことで、医師なり母親なりを非難したのかしなかったのかを、相手の解釈に委ねてしまうことができる。ここでもし医者が、隠喩に込められた非難を受け取れば、そのとき患者は、自分の行った発言が隠喩だったということを安心して認めることができる。逆に医者が、「君のしたサムの話は、どうも本当の話ではないようだね」とか言って、物語に込められた自分への非難をそらしてしまおうとすれば、患者は「そうじゃない、サムは本当にいたんです」と言い張ることができる。このように、隠喩への切り替えは、ダブルバインド状況から身を守る保全の策として捉えることができる。しかし同時に、そうすることで、患者は非難の気持を確実に伝えることができないという状況に陥る。医師が自分の話の隠喩的な意味を読んでくれればいいのだが、そうでない場合、「これは隠喩だ」というメタ・メッセージを発せられない患者は、隠喩による語りを極端なものにしていく方法しかとれない。つまり、今度はサムがロケットに乗って火星に行くというような話にもっていくようになる。隠喩が使われているということを示す通常のシグナルに代えて、隠喩の中の空想性を強調し、それによってそれが隠喩だということを伝えようとするのである
/b 防衛法
子どもがダブルバインドから逃れる方法は、母親によって放り込まれた矛盾状況について発言できるようになること。子どもがダブルバインドに陥っている状況というのは、母・世間・過去の経験・(常に不安な)自分などによる“支えの喪失”である。お互いが自分の思ったことを言える環境をつくり、そしてお互いのメタ・メッセージを理解し受け入れる努力をしつづけなくてはならない。しかし、子どもが母親に対して素直にコミュニケート(メタ・メッセージの伝達が歪むことなく)できるようになるためには、母親自身の精神が改善されなければならない。支配―服従の関係で子どもを意のままに従わせようとするのではなく、子どもにすぐに見返りを求めない不変の絶対愛を注ぎ続けること。相手の態度によって自分の相手に対する愛の大きさが左右されるようなら、それは本当の愛とはいえない。それがたとえ親と子の間の愛であってもだ。そして、支配するということは、子どもを自分の都合のいいように無理やり従わせること。それは母親が子どもに対して一方的に怒鳴っているような状態と同じだ。さんざん叱りつけたあと子どもの前で嘆くのは、子どもを殴っていることと同じなのだ。それは子どもの性格を大きく歪ませることにほかならない。母は、子どもの素直な言い訳を聞き、平等な立場で対話をし、子どもが心から納得するように諭すことが、一番子どもが理解する方法である、ということを知らなければならない。子どものメタ・メッセージを抑えこむのではなく、嘘偽りない素直な対話の中で心から納得し信じるようになることが、信頼し信頼される関係を作ることを知らなければならない。そしてもし親子間でそのような状態にあった場合、子は親を心から尊敬するようになるはずである
/c 治療的ダブルバインド
治療的ダブルバインドはダブルバインドを積極的に利用することで精神治療に役立てようとするもの。矛盾する指示に対する二者択一的な状況に、相手を置く点では通常のダブルバインドと同じであるが、そのどちらを選んでもよい結果となる(勝つ)ようにする点が異なる。またもう一つの違いは、医者自身は自己存在を賭けたぎりぎりの闘争に関わっていないということ。したがって医者は、患者にとって苦痛の少ないダブルバインドを仕掛け、そこから患者が徐々に抜け出してくることを手助けしていくことが可能となる
c-例
フリーダ・フロム=ライヒマン博士の担当した患者は、強度の分裂症をきたした若い女性で、七歳のときから、たくさんの恐るべき神々が世界に住みついて自分を支配するという、複雑な宗教を編み出していた。治療を始めようにも、「神Rが、あなたと話をしてはいけないと言います」といって拒否される。ライヒマン博士はこう答えた。「はっきりさせましょう。わたしにとっては神Rは存在しないし、あなたの考えている世界も一切存在しない。でもあなたにとっては存在するわけで、それをあなたから取ってしまおうとは思わない。思ってもできるはずはないでしょう。あなたの世界のことはまるで見当もつかないのだから。だからあなたの世界に合わせて話をしようと思うの。ただ、あなたに分かってほしいのは、私がそうするのは、わたしにとってあなたの世界が存在しないことを、あなたに理解してもらうためだということ。さあ神Rのところへ行って、わたしたちは話し合わなくてはならないと言ってらっしゃい。そうすれば許しがもらえるはずです。わたしが医者だと言いなさい。それからあなたは七歳から十七歳まで九年間も彼の王国にいたけれど、助けてはもらえなかったともね。そうしたら神Rは必ず、おまえたち二人にそんなことができると思うならやってみろと、許しをくれるにちがいない。わたしは医者で、それをやりたがっているんだって話してらっしゃい。」ここで治療医が患者を治療的ダブルバインドに追いやったという点を確認しておきたい。この患者がもし、自分の神の存在に疑いを抱くようになれば、それはすでに博士の言うことを聞き入れて治療に同意したことと等しい。逆に彼女の神の実在を言い張れば、その神のところに行って、彼より強力だと主張する医者のことを告げなくてはならない。どのみち、博士と関係することを認めることになってしまうわけだ
/d ダブルバインドを考察する
ここで「静穏の祈り」という文書を引用しよう
「神よ、変える術なき物事には黙して従う静穏さを授けたまえ。変える術のある物事には立ち向かう勇気を授けたまえ。そしてふたつの違いを見分ける智慧[ちえ]を授けたまえ。」
ダブルバインドの体験が、苦悩と絶望とによって、心の深いレベルにある認識論的な前提を打ち砕くものであるとするなら、その傷を癒し新しい認識論(エピステモロジー)を育んでいくためには、なんらかの意味でダブルバインドの逆をなす経験が必要だという論が立つ。ダブルバインドは、ある状況に貼りつくしかないという、ひとつの選択不能性の極みである。とすれば、「静穏の祈り」が、なによりも選択の清澄性の希求である必然性は、よく理解できる
ダブルバインド状況は日常のそこかしこで起きている。それらは人々の苛立ちの一端になっているようだ。精神分裂者が治療する場、つまりサイコセラピーの場でも、病院内の環境でも、ダブルバインド状況は生み出されている。病院側の患者に対する“善意”が、はたして患者のためになるものかどうか疑問視せざるをえない。病院は患者のために存在するのと同様に、同程度にあるいはそれ以上に病院のスタッフのためにも存在するのだから、そこで「患者のため」という名目で、職員の居心地を一層良くすることを目的とする活動が続けられる時には、矛盾も生じるだろう。病院側の目的に沿うように組織された制度を、「患者のため」と宣告することは、患者にとっての分裂症的状況を永続化していくことにほかならない。しかし患者は自分が騙されたと感じている事実を直接口にしたり、態度で表わしたりすることができない。ひとつユーモラスな実例がある。ある病棟で、献身的で“思いやり”のある医師が自室のドアに「ドクター室――いつでもノックしてください」と書いた札をかけておいた。するとひとりの従順な患者が、ドアの前を通るたびに必ずノックしていった。この医師は仕事が手につかなくなり、とうとう降参して札を外したということである
/e トランス=コンテクスチュアル
会話のなかで、人が人にメッセージを送るというときには、受け手にとって送り手のメッセージのコンテクスト[メタ・メッセージ]が二重またはそれ以上に捉えられることがある。トランス=コンテクスチュアルとは、メッセージが二重またはそれ以上の意味を持つときの状態を指す。しかしこれを、メッセージが持っている複数の意味というのは誤り。厳密にはメッセージそのものには意味は含まれない。伝達される過程において送り手が含むメタ・メッセージと、受け手が解釈する論理階型のコンテクストが関係をもったときに初めてメッセージに意味が含まれるのだ。ここにおける意味とは、一つは送り手のメタ・メッセージであり、もう一つは受け手の解釈そのものである。ただ実際、受け手のメタ・メッセージの論理階型への振り分けがどのように(一重にはたまた二重に)なるのかは受け手自身の解釈の仕方によって異なるといえる。したがってトランス=コンテクスチュアルな状況を生み出すのは、送り手のどんなメタ・メッセージにも関わることはなく、全て受け手に委ねられる。そういう意味では、トランス=コンテクスチュアルは受け手の精神過程の一つでもあるといえそうだ。複数のコンテクストをまたにかけて豊かな人生を送る人がいる一方で、複数のコンテクストの衝突による混乱から生きる力を失ってしまう人たちもいる。トランス=コンテクスチュアルをうまくさばくことができない、つまり複数のコンテクストを衝突させて自ら拘束状態を作り上げてしまう人たちがダブルバインドに陥るのである
/f 自発的ダブルバインド(“ジークムント・フロイト書付”)
やらなければならないと思っていても、なかなかやり始めることができないといった場合はよくあることだろう。こういった場合、無意識では「やりたくない」という心理がはたらいている。しかし本人はそれを認めたくないために自覚しないのだ。だから自分でも気づかない
ノブレス・オブリージ
ノブレス・オブリージとは、高貴な身分には相応の義務が伴うという考え方。このような考え方はあまねく大きい概念、たとえば個人の性格ではなく国民性と結びつくような特徴がある。アメリカやイギリスに見られるような二元的(イギリスにおいては三元的な場合もある)な行動の定型の一つである<支配―服従>の上下関係が、ドイツでは決してそのようではないというところにはこのノブレス・オブリージが関係している。つまり、あからさまな服従の行動が、アメリカやイギリスと変わらないほどタブー視され、その代わりに、行進する兵士に見られるような毅然とした無表情が現われる。服従の側に回る屈辱を耐えやすくする変形プロセスが、なにかしらの形で存在するはずだが、その手掛かりのひとつを、ドイツ人の一生の歩みをテーマとする研究から得ることができる。ドイツ南部出身の男性がインタビューに答えて語ったところによると、少年時代に彼が親から受けた扱いは姉とまったく違っていた。自分に対しては過大な要求がなされるのに、姉はなにかと大目に見られる。自分はいつも規律に厳格に従わされるのに、姉はずっと自由なふるまいが許される。インタビューアーは、姉に対する羨みの気持ちを抱いたかどうか探ってみたが、返ってきたのは、服従することが男の子の名誉なのだという断固たる答えだった。「女の子には、期待がかけられていません。男の子は、人生への備えが必要ですから、やるべきことはきちんとやることが、きびしく課せられるのです」。これはノブレス・オブリージの、興味深い例といえる
推移的[推移関係]
例えば経済的価値の場合、学歴(y)が収入(z)につながり、学校での成績(x)が学歴につながるとき、xはzにつながることからつねに価値を持つ。このような形式にあるx、y、z間の関係を推移的という。哺乳動物の社会では、変数Bの増加が必要とされ、変数Aの増加がBの増加に通じるときも、Aの増加は好まれないということがよく起こる
変奏の冗長性
芸術や技術における正確さという要素は、普遍的な技術の高さを示すものとして有効だ。しかし職人などが表現するより高き技術の属性には、こうした正確さの上に、レベルの異なる冗長性がくる。低次の画一性を変奏するところに高次の冗長性が生まれるのだ。ある箇所の葉を別の箇所の葉とどう違えるのか。そしてそれを違えながらも、その違いがそれ自体なんらかの冗長的な繰り返しのなかに――つまりより大きなパターンのなかに――収まるためには、全体をどうあしらったらいいのか。実際のところ、第二のレベルを成立させることこそ、第一レベルにおける制御の必要性と機能がある。この絵かきは、その気になれば葉を均一に描くことができる、という情報を鑑賞者が受信できなければ、その均一性が変奏されることの意味が消えてしまう。この原理は美的現象を考える上で基本になるものである
(例) つねに一定の音色を出せるバイオリン弾きだけが、音色の変化を芸術的効果のために使うことができる
統覚習慣の取り込み
どんな学習のコンテクストも、自論に適合するよう、それがもつある面だけを引き伸ばして過度に強調するなら、どんな学習理論にもうまく収まってしまう。これは学習理論を統覚習慣で置き換えてみても同じことがいえる。つまり、どんな統覚習慣であっても、事象のシークェンスを引き伸ばし、ひねりを加え、区切り方を調整することで、ほとんどどんなものでも、そこに取り込むことが可能である
対称型関係と相補型関係
相補型の関係も、対称型の関係も、行動が次第に激しさを増していくプロセスを展開させやすい(これをグレゴリー・ベイトソンは「分裂生成」と呼んだ)。これら病的発展性を秘めた一方向的変化が現われる原因は、対称型のシステムにも相補型のシステムにも、冷却(修正)機能を欠いた、正のフィードバック機構が組み込まれている点にある。対称的テーマと相補的テーマとが、このように互いを打ち消すはたらきを示すが、その理由は、両者が論理上の「逆」をなすことに求められるだろう。純粋に対称的な軍備競争で、国家Aは、国家Bの力を査定し、その値がより大きなものであるときに、軍備増強に駆りたてられる。Bの方が自国より弱いと見たときには、努力はゆるむ。ところが、Aがこの関係を相補的なものとして枠づけている場合には、これと完全に逆の現象が起こる。Bが弱いと見たときにこそ、Aはスパートし、一挙制服を画するのである
/a 対称型関係[対称的]
二者関係において、AとBの行動が(AとBによって)同じものとして見られ、しかもAの行動の強まりがBを刺激してその「同じ行動」を強め、逆にまたBの行動がAの「同じ行動」を促進するようなかたちで二つが連係しているとき、それらの行動に関して両者の関係は「対称的」であるという。例えば、軍備競争、隣人同士の見栄張り、スポーツ競技、ボクシング・マッチ等々は、一般に見られる対称的な関係であるといえる
/b 相補型関係[相補的]
一方、たとえば見る行為と見せる行為とが互いにフィットするように、AとBの行動が同じでないが相互にフィットするものであり、しかもAの行動の強まりがBの行動の強まりを呼ぶようなかたちで両者が連係しているとき、それらの行動に関して両者の関係は「相補的」であるという。例えば、支配―服従、サディズム―マゾヒズム、養育―依存、見る―見せる等々は、一般に見られる相補的な関係のかずかずである
――
対称型関係と相補型関係を、サイバネティクス・システムの見地から詳しく分かりやすく説明している記事があるのでそちらも参照されたい
外部リンク:ベイトソン理解のために 2 – 社会学しよう!
学習とコミュニケーションの階型論
コミュニケーションには常にメッセージがあり、そのメッセージにはコンテクスト(他の事象との関係のあり方のセット・まとまり、メッセージの意味する背景{メタ・メッセージ})という概念が存在する。メッセージのもつ(いくつかの)意味とでもいうべきか。このコンテクストが過去に人に取り込まれた場合、それを思い込みと呼ぶ。その過去のコンテクストにコミュニケーションにおけるメッセージが依拠しているところは多いといえる。コンテクストがどのようにして人に取り込まれるのかを考えたときに、グレゴリー・ベイトソンは「学習」という概念が密接に関わってくると考えた。学習とコミュニケーションの階型論はグレゴリー・ベイトソンが提唱したものである。学習には「ゼロ学習」「学習Ⅰ」「学習Ⅱ」「学習Ⅲ」「学習Ⅳ」の論理階型が存在する(ここでは学習Ⅳの説明は省く)。まずはレスポンデント条件付けとオペラント条件付けについて説明したあと、各学習階型の説明に当たっていこうと思う
a レスポンデント条件付けとオペラント条件付け
レスポンデント条件付けとは、無条件刺激(唾液分泌や瞬きなど、生理的反射の刺激)と条件刺激を反復して対呈示し続けることで反応を変容させる学習理論の一つ。パブロフの犬が代表例だろう。犬に無条件刺激(餌を見ると唾液をだす)に条件刺激(ベルを鳴らす)を反復して繰り返すことで犬はベルを鳴らすだけで唾液を出すようになる
一方オペラント条件付けとは、報酬や罰といった意図的な刺激を与えることで反応を変容させる学習理論。何か課題を達成した際に報酬を与え、達成できなかったときに罰を与えることで対象者の行動頻度をコントロールしていくような条件付けになる
b ゼロ学習
まずゼロ学習とは、「一定の刺激に対する反応が一定しているケース。刺激と反応のつながりが遺伝的に決定されている場合。失敗から学ぶことがない同じ反応を示す(ストカスティック{語源であるギリシャ語のstochazeinは「的をみがけて弓を射る」の意。そこから、出来事をある程度ランダムにばらまいて、そのなかのいくつかが期待される結果を生むように図るという意に転じられる}要素を含まない)」という性質をもつ。学習による後天的なものによって身に付けられたものではない遺伝的な反応のこと。例えば、泣くと涙が出る、膝小僧を叩くと足が前に突き出るといったような自然生理的なものなど
c 学習Ⅰ
次に学習Ⅰとは、簡単にいうと繰り返される習慣によって無意識的反応になった「慣れ」を指す。パブロフの犬が例として分かりやすい。犬は普通、ブザーを鳴らしたからといって、よだれをたらすことはない。しかしブザーを鳴らしてから肉粉をあげ続けると、犬はいつしか、肉粉に対してたらしていたよだれを、ブザーの音にたいしてもたらすようになる。これは犬が「ブザーが鳴ると肉粉がもらえる」ということを学習したからだ。このように、同じ反応を示すようになるまで習慣化された一連の反応は深く無意識領域に押しやられる。そうなると習慣、さらに押しやられると依存という形態をとっていくようになる
d 学習Ⅱ
学習Ⅱでは、学習Ⅰで学ばれることのなかったコンテクスト自体を学ぶことで、反応をもたらすべき状況を自ら学習するようになる。学習Ⅰでは、ブザーの音に対して(肉粉がもらえると思い)よだれをたらす反応をみたが、そのブザーが鳴る状況(部屋の様相{その部屋に連れて行かれる}、ブザーを鳴らす人をみる、体をバンドで拘束される、など)をみてよだれをたらすべき状況であると学習することが学習Ⅱにあたる。その際、ブザーが鳴る状況であると認識する要因となった状況[コンテクスト・マーカー]がどれであるのかが考察される。部屋の様相なのか、それともブザーを鳴らす人をみることだったのか、はたまた体をバンドで拘束されたことだったのか。それか、コンテクスト・マーカーについてもう少し抽象的にこう言ってもよい。犬がラボ実験というものの性格を知って、それに従って行動する場合、その学習の要因となるものは、そこが実験室であるという認識に頼ることをしなくても、実験室における他の状況(実験室特有の臭い、動物を固定しておくスタンド等々)が補助的な刺激(認識の助け)となって、「このコンテクストの中では、常にこのことを“正しい”としなくてはならない」という意味を与えることである。この点、実験を行う側の大学院生も同じかもしれない。人間であれ動物であれ、実験という関係で結ばれた両者の前には、コンテクストのしるしが山積みされているのである。コンテクスト・マーカーは多くの場合、複数の状況の積み重ねによってコンテクスト・マーカー自体の確実性が増す性質がある
このように、学習Ⅰは有機体によって反応が引き出されるのに対し、学習Ⅱは有機体(ブザー)がもたらす状況(コンテクスト)を学習するということが起こっている。この学習がコンテクスト(関連づけ)を学習するというコンテクスト(犬がよだれをたらしやすくなる状況を学習したというコンテクスト)なのだ。対人関係におけるコミュニケーションと思い込み[前提]の諸問題はこの学習Ⅱの階型で起こっている。よく怒られる人は、他人が別の他人を怒っている状況に遭遇したとき、自分も怒られていると思い込む。サングラスをかけた父親に殴られたことのある人は、以後サングラスをかけている人を見るたびに恐怖を抱く。また対人関係以外の場合でもよくみられる。みかんを初めて食べておいしいと思った人がみかんを頻繁に食べるようになる、など。さて、学習Ⅱではもう一つの学習をしている。それは「一次学習で学習することができる」ということについての学習で、これをベイトソンは「学習の学習」といった(いろんな意味で)。あなたが何かを「学習した」と思ったときには、必ずニつのことを学習している。実際に体験して学習したことと、そのように「体験して学習することができる」ということを学習している。これが学習Ⅰと学習Ⅱの関係のもう一つの側面である
e 学習Ⅲ
そして学習Ⅲでは、学習Ⅱで埋め込まれた前提(思い込み、コンテクスト)、そのしみついている前提の入れ替えに挑戦することを指す。これまでの学習Ⅰ~Ⅱは反復によって習得されていくものだったが、もしその習得(習慣化)された前提が矛盾している場合、その前提を解消し、新しく正しい前提にすり替える必要がある。例えば先ほどの、よく怒られる人は、他人が別の他人を怒っている状況に遭遇したときに、自分も怒られていると思い込むという前提。真実に、他人が別の他人を怒っている状況は自分を怒っているわけではないので、この前提(習慣)は矛盾している、誤ったものであるといえる。ウィリアム・ブレイクは「矛盾なきところに前進なし」という言葉を残している。このⅡのレベルにおける矛盾がダブルバインド(“グレゴリー・ベイトソン書付”)と呼ぶものにほかならない。それらの前提が無意識のもので、また自己妥当性を持つことを考えてみれば、すり替えに成功し患者を立ち直らせることは、それだけで大変なワザであると言わなくてはならない
当事者が今自分の身に起こっている出来事のコンテクストについて考えるということはある。しかし学習Ⅱでは、当事者が提示されたコンテクストに気づくか気づかないか、という認識レベルでの話だった。したがって当事者が「どのコンテクストが今の出来事に正しく一致しているだろうか」と考える余裕はなかったのだ。自分が置かれている状況のコンテクストについて考えるというのは高度な生物でないとなかなかできないだろう。学習Ⅱにおけるパブロフの犬について言ってしまえば、犬は肉粉がもらえるということだけを考えるのに精一杯で、なぜ今自分に肉粉が与えられるのかという置かれている状況についてのことまで頭は回らなかったのだ。学習Ⅲは、コンテクスト・マーカー、行動と結果、成功と失敗などの目に見える出来事的な数々を指標とし、「今自分がやっているこのコンテクストは状況に対してはたして正しいのだろうか、答えと一致しているのだろうか」と省察していくことから、正しいコンテクストを導き出す過程の学習といえそうだ(指標とする出来事的な数々は、単一の経験ではなく複合的な認識ができなければ学習Ⅲは達成されない)。その意味では学習Ⅲとは“コンテクストの識別についての学習”であるといっていい
e-例 学習Ⅲの例
ここで学習Ⅲの例を挙げよう。ハワイの海洋研究所で、一頭のイワハイルカを使い、「イルカの訓練法をお見せします」と銘打った一般公開のショーが催されたことがある。このイルカ嬢には予め、調教師の笛が鳴れば餌がもらえる、そして笛が鳴った時に自分がしていたことを後でまたやれば、再び笛が鳴って餌がもらえることを学習させてあった。「彼女が水槽に入ります。私は彼女の動きを観察し、もう一度やってもらいたい動作を選んで、それを行った時にホイッスルを鳴らして餌をあげます。」餌をもらったイルカは、ふたたびその動作をやってみせ、また強化の餌を与えられる。これを三度も繰り返せば、ショーとしては十分だろうから、イルカは退場して、二時間後の次の公演を待つことになる。この時彼女は、先程の動作をホイッスル、水槽、調教師とつなぎ合わせて、ひとつのパターンを、コンテクスト構造を、やってくる情報をまとめあげるための一組の規則を、すでに習得しているわけである。だが、このパターンは、一回のショー、一つのエピソードにしか通用しない。調教師としては、繰り返し訓練法を見せる必要があるわけで、それに対応するには、イルカは一回の出来事の連続がつくる単純なパターンを壊して、各回のパターンの集合全体に対応できなくてはならない。コンテクストの向こうに、より大きなコンテクストのコンテクスト(出来事の連なりの連なり方)があるのであって、そのことに気づかぬ限り、期待された行動をとりえないわけだ。“オペレント条件づけ”のやり方を客に見せるために、調教師は、二回目のショーでは一回目とは違った動作を選ばなくてはならない。イルカは舞台に登場するや前回のしぐさをまたやってみるが、今度はホイッスルが鳴らない。調教師は次にイルカが顕著な動作をするのを待っている。例えば尾びれで水槽を打つという動作(これは不満を示すのにイルカのよくやるものである)。すると今度はこの動作が強化され、イルカはこれを繰り返す。しかし三度目の公演では、尾びれで水槽を叩いてみても報酬は得られない。こんなことを繰り返すうちにイルカは、舞台に出てくる度に、何かこれまでとは違った、新しい動作をすればよいことに気がついた。次に舞台に上がった彼女はショーが始まるや、いきなり八つの演技を入念にやってみせた。そのうち四つは、この種のイルカでは観察されたことのないものだった。複数のコンテクストを結び合わせるコンテクストに対処する方法を、遂に学習したのである。ここに論理階型の一段高い学習が行われている。一つの論理階型からその次の一段高い論理階型へのステップは、個々の出来事に関する情報から出来事のクラスに関する情報へ、あるいは個々のクラスを考えることからクラスのクラスを考えることへのステップである。このことはあらゆるケースに当てはまる。今のイルカの場合、自分が新しい動作の求められている状況にあることを学習するには、単一の経験――成功であれ失敗であれ――からでは不可能だったことはお解りだろう。コンテクストについての学習は、互いに異なるコンテクスト、自分の行動とその結果とが各試技ごとに異なる二つ以上のコンテクストを引き比べることで得られる情報を待って、初めて可能になる。異なるメンバーを集めた一つのクラスが設定される中で、初めてそこに共通する規則性が引き出され、見かけ上の矛盾が超克されるのだ
論理階型にまつわる思考の混乱は、人間の世界でもごくふつうに起こる。素人の間でも専門家の間でも、数々の概念が誤った論理階型に押し込められたまま大手を振って歩き回っている。例えば“探究”という概念。電気ショック装置のついた箱を多数用意してネズミの前に並べても、ネズミの探究心を殺ぐことは決してできない。この事実に心理学者たちは頭を抱えているようだ。いくら罰しても、ネズミの学ぶことは、一度電気ショックを受けた箱の中は突っつくまいということだけで、箱というものの中を突っつくべきではない、ということは一向に学習しないのである。ここには個別的なものについての学習と一般的なものについての学習とが、きれいな対比をしている。箱というものの中は探るべきではないということを学んでしまうことが、ネズミにとっていかに好ましくないことか、少しばかり感情移入をしてネズミの視点からものを見れば、すぐに気づくことだ。箱に鼻を突っこんでショックを受けた経験の意味するところは、その箱の中を探ってみたことでそこにはショックが待っているという情報を得ることができた、という肯定的なものに他ならない。探究の“目的”は探究自体の是非を知ることではない。探求の対象に関する情報を得ることである。探求自体を扱うケースと個々の具体的なケースとでは性質がまったく異なるのである
“犯罪”というような概念の性質について考えてみるのも面白い。われわれは、ある行為そのものを指して、またはその行為の中に含まれるものを指して、“犯罪”と呼んでいないだろうか。そしてあたかも犯罪行為とわれわれが呼んでいるもの(またはその部分)を処罰し続けていくことによって、この世から犯罪が消えてなくなるかのように考えて行動してはいないだろうか。“犯罪”とは、実は“探究”同様、一つの行為と次の行為とがまとめあげられる、その様態を指す言葉である。したがって個々の行為を処罰することで犯罪が消滅すると期待するのは浅薄[せんぱく]である。何千年もの間、犯罪学を名のる学問は、ごく単純な論理階型の誤認をひきずってきている
――
以上、学習の階型論について述べてきた。しかしここで述べられていない学習Ⅲにおける具体的な前提すり替え戦術や、ゼロ学習~学習Ⅲのより分かりやすい説明などが述べられているたいへん優秀な記事があるので、ここからはぜひそちらのほうを参考にされたい
外部リンク:第9回/「思い込み」から離脱する方法 – Webマガジン factree
サイバネティックスにおける自己
サイバネティックスでは、通常“自己”として理解されているものが、試行錯誤のシステム全体の、ごく小さな一部なのであり、思考し行動し決定するのは、この大きなシステムであることを主張する。このシステムは、あらゆる時点でのあらゆる決定に関与するあらゆる情報経路を包合するものだ。“自己”と呼ばれるものは、この広大な連動プロセスのごく一部を切りとってきて、偽りの物象化を施したものにすぎない
違いを作る違い
「違いを作る違い」とは、グレゴリー・ベイトソンが気に入っていた言葉で、言い直すと「違っていることが『わかる』ほどの違い」。「違い」を見つけるには、「違い」が知覚されなければならない。なので「違いの分かる違い」が情報になる。たとえ、「違い」は存在していても、それが観察者に知覚されなければ、「情報」にならない。情報にならないということは観察者にとって「存在しない」ということである。システムというのは、いろいろな情報が伝わったり、途絶えたりして生きている。情報は「違い」で伝達されるため、「違い」がなければ情報にならない。「他と違う」ことが情報なのだから、違っていることは重要なことなのだ
μファンクション[マイクロファンクション]
μファンクションとは、コミュニケーションにおいて、関係のパターンを伝えるメッセージのはたらき。グレゴリー・ベイトソンが、ネコが「ミゥー」、「ミュー・ミャウ」と泣いたことでこの働きの重要性を教えてくれたことに、ネコに敬意を表してμと命名した。人は言語を扱えるため、「メッセージについてのメッセージ」という意味の「メタメッセージ」の中に、関係のパターンを含めてしまってもいいと思う。しかしイルカやネコなどの哺乳動物は、言語を習得していないため、関係のパターンを伝える相互の関係を第一の関心事としてコミュニケーションをする必要がある。冷蔵庫のドアをあけるとネコが寄ってきて鳴き声を上げる。このときネコは、「レバーがほしい」とか、「ミルクをくれ」とか、特定的なメッセージを送っているのではない。もちろんあなたには、ネコのほしがっているものが具体的に何なのか分かるかもしれない。それを正しく言い当てて、「よしよし待ってな」と冷蔵庫から出してやるということはあるでしょう。しかしネコの鳴き声が実際に伝えているのは、あなたとの関係のあり方についてのメッセージである。それを言葉にしてみれば「依存!」とでもなるでしょう。つまりネコは、かなり抽象的な、関係内部のパターンについて語っている。ふたりの関係は、今こういうパターンにあるのだと主張している。それを受けとめて、抽象から具象へと演繹し、「ミルク」なり「レバー」なりを言い当てることが、あなたにかかってくるわけだ。人間が、ネコが「ミュー」と鳴く声そのものから、ネコが何を伝えているのかを正確に受信することはできない。しかしネコが「ミュー」と鳴く声に「ミルク!」というメタメッセージを含んでいるのを――実際は「ミルク!」というメタメッセージは含まれていないのに――人間は受信することができる。これは人間が、ネコが発する――たとえば「依存!」などという――μファンクションを察知することで、「ミルク!」という具象的なメタメッセージを導き出しているからである。つまり、言語を扱えない動物がコミュニケーションを成立させる場合には、相互の関係を第一に考えて、声という――情報を含まない――伝達手段に「関係のパターン」、すなわちμファンクションを伝達情報として取り入れることが欠かせないのである。(もしかしたらネコよりもイルカのほうが好例であったかもしれない)
a その他のコミュニケーションに関するもの
a-1 パラ言語
話し手が聞き手に与える言語情報のうち、イントネーション、リズム、ポーズ、声質といった言語の周辺的側面(文字によっては伝達されない情報)
a-2 キネシクス
言葉を使わずに意思を伝達する身振りについての研究。動作学
パターンと冗長性
たとえば、「文章」というものは、パターンづけられたものである。工学的に言えば、文章は「冗長性」を含む。英語文を構成する文字列のある位置にkが登場するというのは、純粋にランダムな出来事ではない。他の25の文字が同じ確率で登場することができるのなら純粋にランダムだといえるが、そうではない。英語には多く登場する文字とそうでない文字があり、また多く現われる文字の組み合わせとそうでない文字の組み合わせがある。ということは、英文の文字列のどのスロットにも、そこにくる文字の可能性を絞り込むパターン化の作用がはたらいているということだ。これをメッセージの受け手の側から見ると、彼は一ヵ所kの文字が欠けているメッセージを受け取ったときに、欠けているのがkだということを、ランダム以上の確率で推測できるということになる。そしてその推測が容易な程度に応じて、(この受け手にとって)実際現われたkの文字が他の25の文字を排除する度合いが弱まる。なぜなら残りの文字列が、すでに他の文字をある程度まで排除していたのだから――。こうした「パターンの卓越の程度」、言いかえれば「出来事の集団の中である特定の出来事が起こる予測の容易さの度」が、「冗長性」の名で呼ばれるものである
(例)
完全にランダムなアルファベット文字列のどこかに現われたeの文字はlog^2 26ビットの情報量を担う。これが英語の文章であり、英語の文字列にはeの現われる確率が平均より高いことを知っている受信者または機械にとって、その情報量は減少する。英語であるという事実が、その文字列に冗長性を与えるわけだ。もしその受信者が、完全に英語が読める場合、たとえばr□dun-dancyと続く文字列の□の位置にくるのがeであることは、ほぼ百パーセントの確率で推測が可能だ。このとき、実際に現われたeの文字が担う情報量は、ほぼゼロに等しい
――
このような、メッセージをつくる事物の連なりを、同じ時・同じ場所に存在するメッセージをつくらない事物と区別する基準となるのは、SN比(シグナルとノイズの比率)などの特性である。シグナルは見えている部分、ノイズは見えていない、欠けている部分。パターン=情報はその両者どちらにも存在するものだ。メッセージの素材のシークェンスを、一部欠けたままの状態で受信したとき、その欠けた項目を受信した部分の情報から、ランダムな当て推量以上の確率で推測できる場合、そのメッセージ素材は「冗長性」を持つといわれる。ということは、「冗長的である」ことと「パターン化している」こととが同義であるということだ。メッセージ素材におけるパターンの存在が、受信者がシグナルとノイズを区別する助けになる。またはこうも言えるだろう。受信者がメッセージの欠落部分を推定できるというのは、すでに受信した部分が、まだ受信していない部分について何かしら言及しているから、それについての情報を運んでいるからである。さらにいえば、それについての意味を運んでいるから、である
コミュニケーションにおける主―述のフレーム
まずはじめに「直示的」というのは、それ自体をもってそれ自体を示す方法のことである。向こうからやってくるAの姿がAがやってくることを示しているとき、Aの姿は直示的なコミュニケーションにかり出されていることになる
相手の言動に怒って表情を変え、拳をにぎる人は、相手に対する攻撃の部分をもって「怒った」ことを示すわけだが、怒ったのが「怒り」を示している当人であることは、直示的に示されている。しかし、もし相手がその動作を真似るとき、そこで示されるのは「オレはこうだ」ではなく「オマエはこうだ」である。「アイツはコクマルガラスを食べるぞ」ということを、もし、コクマルガラスが仲間の誰かを食べるジェスチャーによって示すことができるとしたら、その場合もメッセージ内容の“主語”は、「オレ」から「アイツ」に移行している。つまり、コミュニケーションの宇宙に「真似」が発生するとき、“主語”は、直示的に自分であることから解放される。この“主語の解放”が、演戯の発生と否定の発生とひとつに絡んだ出来事だというのは、重要なポイントだ。動物間のコミュニケーションで、ある動物がまわりで起こる現象の「真似」を始めるとき、それまでは必ず自分が中心になっていた主(語)―述(語)のフレームが、真似られる対象を中心とするものへ移行しうるようになる。つまり自分が相手を真似ることで、述(語)―主(語)のフレームに移行する。このときイコン的なコード化は、そのまま変わらない
観念の柔軟性
私たちの思考能力や健康な文明システム、あらゆる心身の進化についてなど、そういったものを昇華するために必要不可欠な要素がある。それが「柔軟性と硬直性(特殊性)」である。硬直性についてはここでは説明を省く。柔軟性については「思考の柔軟性」といってもよい。これは「どんな方向にも向けられていない潜在的な可変性」と定義することができる。この柔軟性の要素は、あまねく様々な負のエントロピーを負う事態にも対処できると思われる。たとえば対称型関係と相補型関係(“グレゴリー・ベイトソン書付”)がもっている病的発展性を秘めた一方向的変化についても、柔軟性という薬はひしひしと病状の改善に役立てられるだろう
/a 柔軟性の分配
ここからは柔軟性の分配について述べていく。柔軟性をシステム各部分にどのように分配するか。理想として掲げる健康な文明システムというのは、高く張られたロープの上で、巧みにバランスを取る軽業師にたとえられるかもしれない。軽業師は一つの不安定な状態から次の不安定な状態へ動き続けながら、もっとも基本的な命題――「わたしは綱の上に立っている」――が真である状態を保っている。このとき、腕の位置や腕の動きの速度等の諸変数に非常に大きな柔軟性が与えられている。それらの変数値を自在に変化させながら、軽業師はより根本的で一般的なレベルでの安定を得ているわけだ。腕が固定されていたり、マヒしていたりして、腕と身体全体とのコミュニケーション経路が断たれた状態では、落下は避けられない
いまの例を頭において、われわれの法システムのエコロジーを考えると面白い。まず明らかなように、社会システム全体のありかたを決める倫理的・抽象的な諸前提は、法によっては制御しにくいものだ。一方、より断片的で表面的なレベルの人間行動を法によって固定するのは容易である。ということはつまり、法律が蔓延してくるにつれて、綱渡りするわれわれの社会の「腕」の動きの自由がしだいに奪われていくということを意味するようである。綱から落ちる自由の方は、野放しになったままで
「綱渡り」のアナロジーを、もう一段高い論理レベルへ持ち込んでみよう。腕の正しい動かし方が身につくまで、綱渡りの練習は下に網を張って行われるが、この網は、まさに「落下する自由」を与えるためのものである。文明が新しいシステムを身につけ生みだすまでは、そのもっとも根底的な変数に、自由と柔軟性が与えられなくてはならない、ということなのだろうか
/b 文化の基本をなす観念
文化を動かす観念は、具体から一般へのあらゆるレベルにわたっている。それらの観念は人間の行動と相互作用のなかに発現する。表立って出てくる観念もあれば、内に秘められたままのものもある。意識され、はっきりと定義されている観念もあれば、意識されないまま作動している観念も多くある。文明全体にわたって広く共有されている観念もあれば、社会のサブシステムの間で多様に分化している観念もある。<環境=文明>の作動の仕方をわれわれが理解するには、なによりも柔軟性の予算配分に目を向ける必要がある。また柔軟性の予算配分を誤れば、システムのなかにある種の病理が必然的に発生する。健康なシステムの理論においてもその実践においても、観念の柔軟性が重要な役割を果たすことは間違いないようだ。文化の基本をなす観念とはどういうものか、例をいくつか挙げてみよう
(α) 「黄金律」、「目には目を」、「正義の裁き」等の文化的規範
・黄金律…他人にしてもらいたいと思うような行為をせよ
・目には目を…同害(目には目)より大きな報復をしてはいけない。害に対する報復や益に対する返礼には、同程度の返報をすべきである
・正義の裁き…正義不義の定義づけ
(β) 「節約のコモンセンス」とこれに対する「豊かさのコモンセンス」
・両者のコモンセンスが文化的規範として並存している点。そして、両者のコモンセンス間にダブルバインド(“グレゴリー・ベイトソン書付”)が発生している点
(γ) 「あのモノの名前は<イス>だ」というふうに世界を切り取る、言語の持つ物象化の諸前提
(δ) 「最適者の生存」とこれに対する「有機体プラス環境の生存」
・最適…本質、弱肉強食、性別、天性、などの不変性
・有機体プラス環境・・・進化、社交的、愛想が良い、成績が良い、仕事能率、などの環境適応性
(ε) 大量生産、チャレンジ精神、プライド等々の諸前提
(ζ) 「転移」の観念を成り立たせるもの、何が性格を決定づけるかについての観念、教育の理論、等々
・「転移(“用語解説”)」の観念…観念や精神の伝達およびインタラクションについての法則
(η) 個人間のパターン、支配、愛、等々
―
文明のなかで生起する観念は、(他のあらゆる変数と同様に)相互に結ばれあっている。互いを結びつけているのはある部分では心的ロジック(たとえば祈りや儀式など)であり、ある部分では行為のもたらす(擬似的に)有形の結果についてのコンセンサスである。そのコンセンサスは、たとえば「バチがあたる」というときの「バチ」の観念などを考えてみると、文化内での観念のネットワークについての理解が容易になると思う
/c 観念と行為の複重的決定網
これらの観念(と行為)の決定網の特徴として次の点が挙げられる。――各観念を結ぶ糸の一本一本は弱いものであっても、それが多数の観念の間にくまなく張りめぐらされる結果、各観念が揺るがなく規定されるということ――。われわれは寝るときに部屋のライトを消すが、この行為を支えているのも単に節約の原理だけではない。転移の諸前提も、プライバシーの観念も、感覚入力を減らすことが安眠の条件であるとする心理も、みなそこに絡んでいるわけだ。こうした「複重的決定網」は、生命世界のあらゆる領域に見られるものである。動物と植物の各器官の構造においても、行動の各細目においても、すべては(遺伝子レベルでも生理的レベルでも)多数の要因の相互作用のなかから決定づけられている。また、生態系内でたゆみなく進行する多数のプロセスも、その一つ一つがこのような「複重」の決定を受けている。生命システムにおける決定機構は「複重的」であるとともに「間接的」にはたらくという点にも注意しておきたい。生物界で、なんらかの必要が直接的に満たされるケースというのはごく稀にしか見当たらないのだ。ものを食べるという行動を引き起こすものは、「飢え」ではなく、食欲と習慣と社会慣習である。呼吸活動は、酸素の欠乏ではなく二酸化炭素の過剰によって活性化される。これに対して、人間社会の設計者やエンジニアは、特定の必要をきわめて直接的なやり方で満たそうとする。彼らの作り出すものの生存性が低い原因は、そこにあるのだろう。食餌行動というような生命のためにきわめて重要な行動を、きわめて広い状況で、さまざまな圧力の下で、間違いなく生じさせるには、多数の異なった誘因を作っておくことが必要である。もし食餌行動の引金を引くものが「血糖値の低下」だけだったとしたら、その単一のコミュニケーション経路に異常が起こっただけで、生命が危険にさらされてしまう。生命にとって本質的な機能は、単一の変数の支配に任されてはならない
/d 観念の節約原理
単純な学習実験でも(実生活のどんな経験でも)、生物、とりわけ人間が得る情報は、実に多様なものだ。実験室特有の臭いを知る学習も、実験を行う人間の行動パターンを知る学習も起こるだろうし、実験をうまくこなすことができるかどうかという自分の能力についての学習も起こるだろう。「正しい」と「間違っている」の別があることも、多くの場合学習されるはずである。それを経た後で、別の実験(ないし実生活の出来事)にさらされるとすると、そこでまた新しい情報が入手されるはずである。その中には、最初の実験で得た情報の正しさを確証するものも、それと反目し、はじめのものを蹴落とすものもあるはずである。すなわち、最初の実験で得られた観念の中のあるものだけが第二の実験を生きながらえるということだ。「永く生きる観念は、永く生きない観念より永く生きる」――このトートロジカルな真実を間違いなく遂行するのが「自然選択」である
しかし精神の進化にはまた、「柔軟性の経済」というものも働いている。繰り返し使用に耐えた観念と、新しい観念とでは、扱われ方に差ができる。すなわち習慣形成の現象が、何度も使われそれを生き延びた観念を別なカテゴリーに分別するのである。こうして信頼性を獲得した観念は、思考の検閲をパスして直接的に発動するようになる。要するにそのぶん柔軟性が節約されるわけで、ここで得られた利得を精神は新しい事柄を処理するのに使えるわけである。言い換えれば、a―観念の生態系(Mind)においては、観念の使用頻度が、その観念の生存を決定する要因になること、そして、b―一定頻度の使用に耐えた観念は、習慣形成によって、もはや批判の目の届かないところにしまいこまれ、その生存をさらに安定させるということだ
しかしまた、一つの観念の生存は、他の観念との相互関係によっても決定される。観念の組み合わせのなかには、互いに支え合う種類のものもあれば、両立しない種類のものもある。互いに容易に結びつくものもあれば、そうでないものもある。二極の対立システムをつくり、互いに反目しつつ複雑に影響し合うものもある。幾たびもの使用に耐える観念というのは、ふつう一般化された、抽象的な観念である。それらの一般化された観念は、より個別的な観念をその上に乗せる下地(前提)になる。思考の前提となる観念は、思考される観念より柔軟性が低い。要するに、観念の生態系では、柔軟性の節約原理にのっとった進化のプロセスがあり、このプロセスによって、どの観念がハードプログラムされるのか決まって行くわけである。ハードプログラムされ、システムの深みに落ちた観念は、観念系全体の「核」または「結節点」の位置に収まる。というのも、システムの「表面」にある変わりやすい観念の生存が、ハードプログラムされた観念にどうフィットするかという点にかかってくるからだ。このフィットという意味は、生物のエコロジーを語るときも観念のエコロジーを語るときも、「柔軟性のマッチ」と完全に同義である。そしてハードプログラムされた観念が少しでも変化すると、それと結ばれた観念の全体が変化に巻き込まれることになる
観念と知の生態
/a 基底の知
まず始めに、定義づけをしたり法則を新たに作ったり、何かをある説明原理に従って説明するという科学的証明が行われるときには、「真である命題」を出発点として説明していく必要がある。これは「最初の前提が誤りだったとしたら、そこから導き出される解答は正しくない」という一つの「真である命題」を説明原理に用いている。この「真である命題」を「基底の知」と呼ぶことにしたい。これには二種類あって、その一つが「真である以外ない」命題または命題系、もう一つが、どのようなケースにも一般に真である命題――いわゆる「法則」――である。前者の「真である以外ない」ものというのは、人間の定めた公理と定義の通用する範囲のなかだけで同義反復的に成り立つ命題のことだ。数学の、いわゆる「永遠の真理」は、ここに含まれる。「もし数というものが適切に定義され、もし足し算の演算法が適切に定義されたなら、その仮定のもとでは、5+7=12である」ということであるわけだ
/b “研究促進的”概念
一方、科学者が数々の概念やアナロジーを組み立てていく際に、根源的な前提として信頼を置いているのが、データすなわち経験である。データというのは、事象や対象そのものではなく、つねに事象と対象の記録、記述、記憶であるという点をここではっきりと確認しておきたい。科学者と対象の間には、つねになまの事象を変換し、別のコードに移し変えるプロセスが介在する。物体の重さは他の物体の重さとの比較によって、または計量器による測定によって得られる。人間の声は、テープの上の磁気的な変化として記録される。そのうえ、手にしたデータがつねになんらかの選択を経た後のものだということも避けられないようだ。“なまの”データというものは、存在しない。すべての記録は、何らかのかたちで、人間か器具による編集と変換を受けたあとのものである。データだけに限られたことではないが、そういった定義が不完全のまま一般に用いられている説明原理のかずかずを「“研究促進的”概念」と呼ぶことにしたい。これらの概念は一般にデータから出発し帰納的に説明原理を生みだす手法に寄っている
/c 観念の生態[誘眠的仮説]
これらa,bの二つの画定から、科学という営みの全体について、また個々の研究が立つ位置とそれが向かう方向について、多くのことがいえるようになる。「説明」とは「基底の知」の上にデータをのせて地図を描くことだ、とか、しかし科学の究極の目標は基底的レベルでの知識を増やすことにある、とか。科学研究の進行プロセスが圧倒的に帰納的である、また科学は帰納的に進んでいくべきだと信じている研究者が多く見られる。彼らは“なまの”データを検討し、そこから“研究促進的”概念に移行していくことが進歩なのだ、と考えていることになる。それら“研究促進的”概念は、“いまだ検証中”の仮説であって、さらに多くのデータによってテストしていかなくてはならないけれども、そうやって徐々に修正と改良を加えていけば、最後には「基底の知」のリストに加えて恥ずかしくないものが完成する、というわけだ。ところが現実はどうだったか。何千という頭脳明晰な人間が五十年あまりにも、そのやり方で研究に励んだ結果、できたのは数百に及ぶ“研究促進的”概念の山ばかりではなかったか。真に基底的な知が、ひとつなりとも生まれただろうか
ある喜劇の一場面にこんなシーンがある。医師資格試験で、お偉い先生方が受験生を取り囲み、「アヘンを服用すると眠くなるのはなぜか、その“原因理由”を述べよ」と質問するのだが、それに受験生がめちゃくちゃのラテン語で、誇らしげにこう答えるのだ。「それはアヘンが、誘眠素を含有するからであります!」
まずアヘンと人間がつくるシステムが存在するが、「アヘンを服用すると眠くなる」という相互作用がシステムに変化を生じさせる。システムに変化が生じると、科学者(ここでは受験生)はシステムのどちらか一方の側に架空の“原因(誘眠素)”を措定し、それで変化が説明できたと考えがちだ。つまりアヘンが誘眠作用を物象化した物質を含むか、それとも、人間が“向眠体”とかいう睡眠の欲求を物象化した物質を含み、それがアヘンに反応して“発現”するのか、そのどちらかだ、と。こういった“誘眠的”な仮説(架空の仮説)を立てたところでシステムの変化が説明できたことになるだろうか。いや、これらはまだ原理を複雑に敷延しただけにすぎない。アヘンがなぜ誘眠素を含むのか、なぜ人間はその誘眠素に反応するのか、そもそも誘眠素とはどんな性質をもつ物質なのだろうか。これらを基底な知から帰納的に研究していくことがまっとうな科学であると思う。データから誘眠的仮説に進み、そこからまたデータに戻っていくという研究の構え、あるいは思考の習慣は、おのずと強化されていく性質をもつものだ。科学者はみな予測が立つということに高い価値を置く。実際、現象が予測できるということは好ましい。しかし予測が可能になったからといって、その仮説が正しいということにはならない。その仮説が“誘眠的”なものである場合はなおさらだ。アヘンが誘眠素を含むと主張するものは、この“素”の研究に一生を捧げることも可能だろう。誘眠仮説の蔓延は、今日の科学が「帰納性の偏重」に病んでいることのあらわれである。基底的な知からまったく浮き上がったところで、いくらデータを集めてみても、まっとうな科学は始まらない。ひとりよがりの理論的考察がはびこるばかりだ。われわれはもう一度科学的思考の土台に立ち戻って、“研究促進的”な仮説の良否をきちんとチェックすることができるような、頼りになる基本観念のセットを探しださなくてはならない。そう急ぐことはあるまい、と考えるむきもあるだろう。科学の基本原理はすべて経験から、帰納的に導きだされたものなのだから、今後とも帰納的なやりかたで、じっくりと本源的なレベルをうかがっていけばそれでよいのだ、と。しかし、科学における根底的な知というのは、そもそも帰納的に導きだされたものなのだろうか。われわれの思考が立脚するその土台を探るのならば、科学的、哲学的思考の始源にまで立ち返る必要があるのではないだろうか。例として、ユダヤ=キリスト教分化における創世神話の中核部分を取り上げてみよう。それに関わっている、哲学的・科学的な根本問題は何なのか
「はじめに神は、天と地をつくりたもうた。地はかたちなく空しく、淵のおもてはやみであった。そして神の霊が、水のおもてを動いておられた。そして神が言いたもうた。光あれ。そして光があった。神、光を見て、これを良しとなされた・・・(中略)・・・そして神が言いたもうた。天の下の水はひとつ所にあつまり、かわいた地よ、現われいでよ。そしてみことばのとおりになった。そして神は、かわいた地を陸と、水のあつまりを海と名づけたもうた。そしてこれを良しと見たもうた。」
これはちょっと不気味なことだが、この古代の文書が土台としている考えの多くは、今日の科学の土台にあるもの――あるいは今日の科学が問題としているもの――と変わりないのだ
(1) 物質の起源と本性の問題。これはまとめて脇にのけられている
(2) 秩序の起源という問題。こちらはていねいに扱っている
(3) このふたつの問題が、分離している
(4) 世界の分類をめぐる謎が、区分けの行為によって説明されている。そしてそのあとから、「名づけ」という、すばらしく人間的な達成がきている
(5) 知覚される以前の世界が、分類されていると考えることはできない。また、世界がどう分類されるかには、言語と文化が深く絡んでおり、いわば「名づけ」が世界を分類するという面を見逃せない
以上が、この創世神話を構成する要素だが(5以外)、どうだろう、これがすべて経験から帰納的に引きだされた考えだと言い切れるだろうか。科学と哲学が混然としたこのプリミティブな段階で、その基底観念が経験的なデータから帰納的に導かれたものかどうかは実に疑わしい。そもそも、実体と形式とは別物であるという認識が、帰納的方法から出てくるとは考えにくい。かたちのない、分けられていない物質というものを実際に見たことがある人間などいないわけだし。「かたちなく空しい」、つまり形式も実体も存在しない宇宙というものが、帰納的に得られたとするなら、それは途方もない――おそらくは誤った――外挿的推論によったとしか考えられない。古代から二分されている形式と実体のうちの、誤った片割れの方に橋をかけようとしてはいけない。もちろんどれが形式でどれが実体かをとり違えてもならない。エネルギーと質量保存の法則は、形式ではなく実体の世界にかかわるものだ。しかし精神プロセス、観念、コミュニケーション、組織化、差異化、パターン等々は、あくまでも実体ではなく形式にかかわるものである。形式に関する部分は、サイバネティックスとシステム理論の誕生によって、ずいぶん豊かになってきている。これからは形式と実体の間に正しい橋を架けていくことが求められると思う
クレアトゥーラとプレローマ
クレアトゥーラ[ユングより]とは、生あるものの世界。区切りが引かれ、差異が一つの原因となりうるような世界。たとえば生物や美。生きたカニとゆでたてのカニ(生物の死骸)の間には一つの差異が起きている
一方、プレローマ[ユングより]とは、生なきものの世界。ビリヤード球や銀河系のような、力と衝撃こそが出来事の原因となる世界
/a 相同[ホモロジー]
相同[そうどう]とは、Aにおけるある部分間の関係が、Bにおける対応する部分間の関係に類似する時、その形態上の類似をいう。このような形態上の類似は、進化上両者が何らかの関係にあった証拠と考えられる。生物学上では「系統発生的相同」とよばれる。人の手と手、カニのハサミとハサミは左右対称の関係にある。これらの相同を系統発生的相同の「第一次の結びつき」という。また、人間の手と足が対応している形態と、馬の手と足が対応している形態、カニの肢とエビの肢とで、両者に系統発生的相同の「第二次の結びつき」がみられる
/b プロクロニズム
生物はその形態の中に過去の成長の証拠を留める、という一般的真実。プロクロニズムは、一個の生物がその発生過程から、いかなるパターン形成をもって形態上の問題を解決し続けてきたかの記録となりうる。プロクロニズムと個体発生との関係は、相同と系統発生との関係に等しい
誰もが学校で習うこと
「誰もが学校で習うこと」は、グレゴリー・ベイトソン著の『精神と自然』の中のある一章のこと。その章ではすべての精神が必然的に拠って立つ基本前提がいくつか述べられている
/a 科学は何も証明しない
「科学は証明しない。探索するのみ」
これの理由について考察していこう
a-1 知覚に転移する「思考」では真であることを証明できない
科学には仮説を向上させたり、その誤りを立証したりすることはできる。しかし仮説の正しさを立証することは、完全に抽象的なトートロジーの領域以外では、恐らく不可能だ。科学は出来事から仮説をつくるが、我々はその出来事を――どんな秩序でそれが真であるのかという――「思考された真」のコンテクストを通してしか「出来事」と知覚することができない。これらの行為を「転移」というが、それについては転移(“用語解説”)を参照されたい。その理由を示すには、次の方法によるのが一般的だ。まず私が一つのシークウェンス[連続]を一部お見せして、それがある秩序に従っているという前提を与える
「2,4,6,8,10,12」
この数列で次に来る数は何か? 恐らくみなさんは「14」と答えるだろう。そしたら私はこう答える。「残念でした。次に来るのは27です」。みなさんは最初の6列だけから得たデータに基づいて、これが偶数の数列であるという一般化を行った。そしてそれが誤りだったということが、次の出来事によって判明する
「2,4,6,8,10,12,27,2,4,6,8,10,12,27,2,4,6,8,10,12,27」
ここで次に来る数を聞いたとすれば、みなさんは恐らく「2」と答えるだろう。2から27までの繰り返しが三度も続いたのだから。これが単純化の原則とよばれる前提である。つまり、(今分かっている時点で)事実に適する諸仮定のうち、最も簡単なものをベストであると願う願望だ。次に来る事実を前もって入手できるなどということはけっしてありえない。われわれに持つことができるのは、単純であってくれという願望だけなのだ。このような単純化の原則などの諸前提が知覚のコンテクストにぴったり随伴する(転移する)ことで、前提が繰り返され、だんだんと無意識の深みに落ちていく。初めは習慣、そして無意識へといくように。したがって次のようなトートロジーが成り立つ。「真であることを知ることが、真であることを知れないことであるかぎり、真であることを知ることはできない」。真であることを証明するために「思考」が必要だが、その「思考」というツールでは真であることを証明できないために、ゆえに証明することができないということだ。絶対確実な予測はけっしてあり得ない。したがって、科学は一般化された命題をけっして証明することはできない。記述された内容をテストしていくことによって最終的な真実に到達することはできない
a-2 知覚できないことを知ることはできない
「思考」が知覚に転移する理由は、知覚から“意味”(と呼びならされているもの)を作っていく必要があるからだ。ところが差異のないところに知覚は生じない。人の顔はみなあれほど違うのに、ハエの顔はみな同じに見える。つまり知覚される差異(外界の差異)がそのまま情報となる。われわれが受け取る情報はいかなる場合にも差異の知らせにほかならない。その差異の知覚は、しかし閾[いき]というものによって限定されている。あまりにも微少な差異や、あまりにゆっくりと現われる差異は、知覚されない。それらは知覚の食物ではないのだ。いつの時代でも、入手可能な知識の量は、その時代が持っている知覚手段に固有な閾によって決定されている。顕微鏡、望遠鏡、十億分の一秒まで計れる計時装置、百万分の一グラムまで計れる計量装置――これらの精巧な知覚装置が明らかにしたことを、以前の時代の知覚レベルから予測することは、まったく不可能だった。一瞬先のことが予測できないのと同様、知覚の届く一歩先にある極微の世界も、宇宙の彼方の出来事も、地質学的に遠すぎる次代のことも、要するに観察できないものについて前もって知ることはできない。知覚による方法にほかならぬ科学には、真実かもしれないことの外在的で可視的な“しるし”を集め回る以上のことはできないのだ
a-3 人間が“真であること”を証明できる可能性について
真であることを証明するために「思考」が必要だが、その「思考」というツールは真であることを証明できないために、ゆえに証明することができない、ということを先ほど述べた。結論からいって、人間が“真であること”を証明できる可能性はかなり難しい。だが100%不可能ではないということは言える。真であることを証明するためにKFS(キー・サクセス・ファクター。実現のための最重要要素)となるのは「知覚」である。まず知覚が用いられない場合、上のa-2の理由から、真であることを証明することはできない。次に知覚が用いられた場合、思考による転移が起こり、そうなると上のa-1の理由から、真であることを証明することはできない。ただしこれは「思考」が真であることを証明できないからであって、純粋に「知覚」のみが取り出された場合にも、真であることを証明できないと言うことはできない。ただ「知覚」単体では真であることを証明することはできないようなので、証明するためには「知覚プラス(思考ではない)何か」という新しいセットを考え出さなくてはならない。これが真であることを証明できるとっても微少な可能性の事柄である。ここでこの可能性が抱える問題点を述べておこう
(α) 現時点では、知覚に対する思考の転移を妨げる術がない
(β) 真であることを証明する際に、「思考」を用いないようにするために証明への新たなアプローチの仕方を決めるわけだが、そのためにはゴール(どこへアプローチするのか)を定めなくてはいけない。そのゴールとはつまり「真であることの“真”とは何か」という定義づけを行わなくてはならないということなのだが、その定義づけに「思考」と「前提の築き」が用いられる
―
以上が、人間が“真であること”を証明できないことを改めて裏付ける点だ。これをうかがうかぎり、確かに証明するのはほとんど不可能に近い。人によっては不可能だと結論づける人もいるだろうと思う。これは手足を使ってはいけないというルールのもとで、人がクマを倒そうとするようなものだ。手足を使えないということは斧や銃といったどんなに優秀な道具があっても使えない。一見これではクマを倒すのは不可能に思える。ところで不可能というのは、人間が現時点で知覚できる範囲の中で想像した上で、「不可能」なだけだということは忘れなくてもよいだろう
/b 地図は土地そのものではない
「地図は土地そのものではなく、ものの名前は名づけられたものではない」=「豚やココナツのことを考えている人間の頭の中に、豚やココナツはない」
これを抽象的なレベルでは、「すべての思考、知覚、情報伝達において、報告されるもの(物それ自体)と報告との間に一種の変換、すなわち記号化が起こる」という内容ももっている。実はこのことを一番言いたかったのだ。すべてのものが報告される過程において記号化という変換が起こっているのであれば、誰も“もの”の変換前の姿をそのまま捉えることはできない。それは“見る”にしてもだ。豚やココナツを見ている人は、豚やココナツそのものを見ているわけではない。脳によって記号化の変換がされたあとの豚やココナツを見ているのだ。その記号化といっても様々ある。実体的なものもあるし形式的なものもある。形式的な変換とは、たとえば汚れている豚を見て「臭い!」という情報を発生させたりするものだ。その人が元から持っていた「汚れている=臭い」という情報が変換時に豚(に対する脳の捉え方)に組み込まれた結果、「汚れている豚が臭い」と思うのだ。豚が臭いわけではない。言ってしまえば、豚も汚れているわけではないのだ。それは「観察者(人間)の定義において、豚は汚れているようにみえる」と言うのが正しいエピステモロジーである
/c 客観的経験は存在しない
すべての経験は客観的である。この命題は「われわれが“知覚”したと思うものは脳が作りあげたイメージである」という命題の一つの単純な系にすぎない。すべての知覚――意識されるすべての知覚――がイメージの特性を備えていることは重要な意味を持つ。外界の経験には常にある特定の感覚器と神経経路が介在しているのだ。そのかぎりにおいて、ものとは私の創造物であり、ものの経験は主観的であって客観的でない。そして主観的な見方でしかものを見ることができない人間が客観的な見方をできることはない
/d 数と量とは別物である
生物間または生物内で起こる事を生物の思考プロセスの一部として思い描くとき、数と量の相違という問題が必ずその根本に関わってくる。<数>は数えるという行為の産物。<量>は測定するという行為の産物。数を数えるとき、われわれは各整数の間を飛び移っていく。二つ、三つの間には飛躍がある。隣り合った整数間のこの非連続が、数がきっちり正確たりうることの理由となっている。ところが量の場合にはこのような飛躍は存在しない。そして飛躍が存在しないという理由から、いかなる量もちょうどぴったりということはあり得ない。トマトがちょうど三個あるということはあるが、水がちょうど三リットルあるということはない。量に関して、われわれはいつも、およその話ですましている。数はパターンとゲシュタルトとデジタル計算の世界に属し、量はアナログ計算、確率計算の世界に属す。両者の違いはデジタル・システム(オンかオフの二者択一的特性をもつもの)とアナログ・システム(出来事の強度に応じて連続的に変化するもの)の違いだ。デジタル・システムは数を含むシステムに類似し、アナログ・システムは量により強く依存している。デジタル値で測れるというと1,2,3…、またはYes,No、ON,OFFなどで示される数で表わすものである。アナログ値で測れるものは、三リットルなどの連続的な変化によって示される数で表わす。ちょうど二つの隣り合った整数間が非連続であるように、デジタル・システムにおける“反応”と“無反応”の間は非連続である。“イエス”と“ノウ”の間は非連続である
/e 量はパターンを決定しない
単一の量を持ち出してパターンを説明することは、原理的に不可能だ。一見したところ、量の作用でパターンが生み出されるかのように思えるケースがある。しかしその場合、そのパターンは量的な働きかけを受ける以前から、システム内に潜在しているのだ。例えば強い引張力を受けて鎖が切れるという場合。鎖の形態はたしかにパターンの変化を被った。しかしこのとき鎖の切れた箇所は、引っぱる前から一番弱かったのだ。つまりこれは、あらかじめ潜在していた差異が、引張力の量的変化の下で顕在化したというだけの話である。パターンの発生原因を説明する文の中に「引っぱる力」や「エネルギー」など、量的な変化が持ち込まれる傾向が一般に強く見られるが、これらは誤りであると思う
/f 生物界に単調な価値は存在しない
単調な価値とは、上昇または下降を続ける値をいう。その曲線にはこぶがない、つまり上昇から下降へ、下降から上昇へと転じることがない。生物が欲求する物質、物体、パターン、あるいは生物が何らかの意味で“いい”と感じる経験――食物、生活条件、温度、楽しみ、セックス等――に関しては、多ければ多いだけいいというようなことはけっしてあり得ない。つまり物質や経験の最も好ましい量というものが存在する。その量を超えてしまうと、毒性が生じ、その量から落ち込むと欠乏感が生じる。カルシウムの量が多ければ多いほどいいということはない。各生物にとって、摂取すべきカルシウムの最適量というものが存在する。この量を超えると、カルシウムも毒性を持つようになる。戦いのない関係は生気がなく、戦いの多すぎる関係は毒性をもつ。単調な価値ではない最適値があるものは生物学的で、単調な価値――多ければ多いほどいいというような――ものは非生物学的であるといえる。しかし単調な価値とは例えば何か、といったことはわれわれは知ることができない。それに私はそのようなものは存在しないと考えている。「価値」という属性はもともと対象に備わっているものではなく、人間が持っているものだからだ。人間がそういうフィルターを通してしかものを知覚することができないという性質をもつためだ。金銭は多ければ多いほどよいとされている。千一ドルの方が千ドルより常に好まれる。しかし、かといって金銭が単調な価値をもっているわけではない。金銭には「価値」という概念すら存在しない。それに、金銭も、それが所有者に及ぼす作用を考えるときには、やはりある限度を超えると毒性に転じるといえよう。その先にあるのは無力感だ。ただ金銭は他のものと取り替える――金銭と食物、金銭とセックスなど――という多様な価値と交換することができる性質を人間から引き出す性質を備えている。この性質に関しては非生物学的といえるだろう。食物は満腹とか空腹とかに関する満足しか与えてくれない。食物が温度的な満足や性欲も満たしてくれるわけではない
/g 論理に因果は語りきれない
われわれは論理的連鎖にも、因果関係の連鎖にも、同じ語を用いる。「ユークリッドの諸定義と諸公理を受け入れる“ならば”、三辺の長さがそれぞれ等しい二つの三角形は合同である」という一方で、「温度が摂氏100度以下になる“ならば”、水は凍り始める」とも言う。しかし三段論法で使うような論理の「ならば」と、因果関係における「ならば」とは、まったく異質のものである。ごく普通のブザー回路を例に、パラドクス発生のしくみをみていこう。あるブザー回路では、接極子がA点の電極につながったときに電流が流れる。ところが電流が流れると電磁石が動いて、接極子を引き離し、A点での接触が切れる。すると電流が回路を流れなくなって、電磁石の働きは止まり、接極子はA点に戻って電極と接し、このサイクルをまたはじめから繰り返すことになる。このサイクルを因果の連鎖として一つ一つ記述してみれば、次のようになる
(1) A点で接触がなされれば、磁石は働く
(2) 磁石が働けば、A点の接触は切れる
(3) A点の接触が切れれば、磁石は働かなくなる
(4) 磁石が働かなくなれば、A点で接触がなされる
ここで「ならば」という接続辞が因果的なものであるということがしっかりと了解されているかぎり、問題はない。ところが、この因果的な「ならば」を、論理の世界で使われる「ならば」と取り違えてしまうと、とんでものない混乱を招く結果になる
――接触がなされれば、接触は切れる。(Pならば、Pではない)――
因果関係を表わす「・・・ならば・・・である(ない)」には時間が含まれているが、論理の「・・・ならば・・・である(ない)」は無時間的なものである。この事実は、論理が因果関係のモデルとしては不完全なものであるということを示している
/h 因果関係は逆向きには働かない
論理の世界では「逆もまた真」ということがよくあるが、結果は絶対に原因に先行することはできない
説明とトートロジーのいい加減さについて
説明とは、結局のところトートロジーの網を張っていく作業であると思う。そのトートロジー内の結び目が自分にとって自明と思えるほどの妥当性を持つことを確認しながら、しかしその妥当性は決して完璧なものにはなり得ない。後にどんな発見がなされるか、誰にもわからないからである。もし説明というものが、この通りのものであるとするならば、こんな七面倒臭い、しかも無益と思える手続きから、一体人間は何の得をするのかという疑問が当然わいてくるだろう。これは自然史学上の問題である。人間が説明の基盤とするトートロジーをどれほどいい加減に組み立てているかを見れば、この疑問はある程度解消されると私は思う。いい加減なトートロジーに基づいた“理解”など、むしろない方がいいと思われるかもしれない。だが、あまりにも安易で、人に迷信を植えつける役しかなさないような説明が、かくも大きな人気を博しているところを見ると、そう考えるべきではなさそうだ
精神
グレゴリー・ベイトソンが定義した精神(マインド)の定義。ベイトソンは精神と身体を別物として考える二元論を否定し、世界を二元化しない精神の基準を述べている。ここでは(a)~(f)に6つの基準を述べ、「(g)精神システムの定義」に6つの基準を包括した内容を記述する
/a 精神とは相互作用するパーツ(構成要素)の集まりである
端的に言って、原子を構成する一個の素粒子が、私の言う意味での“精神”にあたるとは私は考えない。精神プロセスとは常にパーツ間の相互反応の連続と考える。精神現象を説明しようというのであれば、常に、複数の部分の組織のされ方、相互反応の仕方について語るのでなくてはならない。ここでは、マインドのはたらきが、その差異づけられた“部分(パーツ)”間の相互作用の中に内在するという前提を立てる。そのような相互作用が組み合わさっていった上にはじめて“全体”が顔を見せるのだ。ラマルクは比較心理学なる学問の公準を定めるにあたって、「いかなる精神活動も、その活動を生み出すに十分複雑な神経システムを備えていないような生物においては起こりえない」という規則を据えた。私はむしろ彼の見解に従うものである
/b 精神の各部分間の相互作用の引き金は、差異(ちがい)によって引かれる
差異とは時間上にも空間上にも位置づけられない非実体的な現象である。差異はエネルギーにではなく、負のエントロピー/エントロピーに関係する。エントロピーの度合いが差異の大きさを決定し、その差異の大きさは人の知覚の可能不可能を決定する。変化しないものは、われわれの方でそれに対して動かない限り知覚されない。世界に描かれる区切りは、われわれが引き出す区切りなのだ。引き出されない区切りは存在しない。バークリーは知覚されたもののみ“リアル”なのであって、誰にも音を聞かれることなく倒れた木は音を立てなかったのだと論じた。それを私流に言い換えれば、「隠された差異、つまり理由はともかくちがいを生まぬ差異、は情報ではない」となる。ちなみにアトニーヴィは、情報(知覚される差異または区切り)が必然的に輪郭に集中すると述べている。差異が小さければ、われわれの生きる環境の変化の傾向が、ほとんど意識されないということは、見方によっては恐ろしいことである。水を入れた鍋の中にカエルをそっと坐らせておき、今こそ飛び出す時だと悟られぬように、極めてゆっくりかつスムーズに温度を上げていくと、カエルは結局飛び出さずにゆで上がってしまうという擬似科学的な作り話があるが、われわれ人類も、そんな鍋の中に置かれていて、徐々に進行する公害環境を汚染し、徐々に墜落していく宗教と教育で精神を腐らせつつあるのだろうか? 差異とは関係に属する事がらなのであるから、時間上にも空間上にも位置づけられない――空間や時間の観念の中になら位置づけられようが。私なりあなたなりのニューロンの中の変化が、森の中で一本の木が倒れたという変化を「表す」。ニューロンが、差異を変換したかたちで代行してくれる。物理的な出来事がそのまま伝わるのではない。物理的な出来事を意味する観念になって伝わっていくのだ。ところで“エネルギー”という概念。これは厳密に何を指しているのだろう? エネルギーの定義。それはエネルギーが“物質”なるものと抽象の次元を同じくするというものだ。両者とも何らかの意味で実体であって、相互変換が可能だとされる。ところが差異とは、まさに実体ならざるものなのだ。ではエネルギーは実体なのか。エネルギーは実体の世界にあって、その測り方も“量”によるとされる。一方、差異は量ではなく質である。私にとって、刺激という語は、感覚器官を通して入ってくる類に属する情報、という意味しかもたない。ところがそれを“エネルギー”の一押し、または注入として論じる人が世の中には多い。どうやら差異と情報は、けっして“エネルギー”とは相容れない観念であるようだ。納得されない読者は、ゼロもまた反応の引き金を引く、という事実に目を向けて頂きたい。理由はゼロがイチとの間に差異をつくるからだ。飢えたアメーバは食物を求めて、より活動的になる。成長期にある植物は暗闇(光のなさ)に背を向けて曲がる。税務署の人間は申告書が送られて“来ない”と腰を上げる。すべて起こるべきことが起こらなかったというところに差異が生じたゆえの反応である。存在しない出来事からエネルギーが引き出せるはずはないだろう
/c 精神過程はエネルギー系の随伴を必要とする
反応を生じさせるエネルギーは、引き金となる出来事が起こる前に、反応者の中に用意されている。石を蹴るとしよう。石は私が与えたエネルギーで飛んでいく。次にイヌを蹴るとする。イヌは部分的にはニュートン力学に従う。もし蹴りが十分に強烈であれば、ニュートン的軌跡を描いて飛んでいくだろう。しかしそのことが、イヌを蹴ることの本質ではない。重要なのは、蹴られたイヌが、イヌ自身の物質交代から得られたエネルギーをもって反応する、という点である。出来事が情報によって、“制御”される時、結果する“行動”のエネルギーは、衝撃が与えられる以前に、反応者の中にすでに用意されているのだ
生命とその営みの持つ一つの典型的な特徴は、そこに二つのエネルギー・システムが相互依存の状態で存在することである。その一つは栓なり扉なり継電器なりを開閉するエネルギー・システム。もう一つは栓や扉が開の状態にある時に、そこに流れるエネルギーのシステム。“オン”の状態になるスイッチは、よそで生じたエネルギーの流路となる。蛇口の栓をひねる時、われわれは水をひねり出すわけではない。水を出す仕事は、あくまでもポンプや動力によってなされる。栓がひねられることによって、そうした力が解き放たれるのだ。栓を“制御”する者は、“許可”か“禁止”かどちらかの立場に立つだけで、水を流すエネルギーを与える者は別にいる。栓を握っている者が部分的にでも決定できることは、水が流れるとしたら、どういう経路で流れるかということだけで、実際流れるかどうかには口出しできない。この二つのシステム(決定の機構とエネルギー源)が合体した時、それぞれが分担範囲を持ち、その中で動くという全体的関係が形成される。馬を水辺に連れていくことはできるが、馬に水飲みを強いることはできない。水を飲むか飲まぬかは馬が決める。しかしいくら喉の渇いた馬でも、こちらが水辺に連れて行かねば水は飲めない。連れていくかいかぬかはこちらが決める
/d 精神過程は、再帰的な(あるいはそれ以上に複雑な)決定の連鎖を必要とする
生存競争への参加の仕方について、生物は変化を修正する、変化に合わせて自分自身を変化させる、自らの中に永続的変化を編み込む、等の方法によって変化を逃れている。“安定”はかたくなさによっても得られるが、小さな変化がサイクルをなして永続的に繰り返され、その中で撹乱を受ける以前の状態が常に取り戻される、という形でも得られるのだ。自然や生物は、つかのまの変化を受け入れることによって、非可逆と思える変化を(一時的なりと)避けている。ちょうど――日本の比喩表現を借りて言えば――「竹が風にしなう」ように。つまり生き物は再帰的またはそれ以上に複雑な決定の連鎖によって組織されている
/e 精神過程では、差異のもたらす結果を、先行する出来事の変換形(コード化されたもの)と見ることができる
差異がいかにして情報、情報重複(リダンダンシー)、パターン等を形づくるのかという問題に踏み込んでいこう。変換のルールは、比較的(すなわち変換される内容より)安定したものでなくてはならないが、それ自体変換を被ることもありうることを前提にしておきたい。最初におさえておくべきことは、いわゆる“外界”におけるいかなる物体も出来事も差異も、それらに応じて変化するだけの柔軟性をそなえたネットワークの中にとり込まれさえすれば、情報の源(ソース)となりうる、ということである。この意味では、日食も、馬のヒズメの跡も、葉の形も――それらがもともと何物であるかはともかくとして――そのような結果の連鎖を生じさせさえすれば、精神の中に組み込まれうると言ってよい。あるしなやかなシステムに両方が取り込まれたときに、原因と結果との間に差異が生じるが、これは変換またはコード化と呼ばれるプロセスの存在があるからだ
変換(コード化)の諸形体のうち、あまり単純であるがゆえによく見落とされている一つの情報伝達の形態に、“直示的”と呼ばれるものがある。「直示的」というのは、それ自体をもってそれ自体を示す方法のことである。一匹のネコを指して「ネコとはこういうものだ」と言う時、そのネコは直示的なコミュニケーションの材料として借り出されたことになる。街で向こうから歩いてくる友人を見かけて「おっ、ビルだ」と言う時、彼から(その容貌、歩き方等から)“直示的”的に情報を得たことになる。その情報を彼が伝えようと意図したかどうかにかかわらず。この種のコミュニケーションが言語習得の場で果たしている役割は特筆に値する。直示的な伝達が著しく限定された状況で外国語を教えなければならないとしたらどうか。例えばAがBに、電話で、Bのまったく知らない言語を教えなくてはならない、しかもAとBとが共通に理解できる言葉がない、とする。音声やイントネーションの特徴なら恐らく伝達可能だろう。ひょっとして文法の特性まで一部伝えられるかも知れない。しかしある語が、ごく一般的な意味で何を“意味”するのかを伝えることは不可能である。Bにしてみればどの言葉も空虚な文法的存在に留まり、物の名前として何かを指し示したりすることはない。イントネーション、言葉の連なり方等は、その情報が電話で伝えられる音の連続の中に存在するので、理屈上“直示する”つまり教えることができるわけだ。言語のみならず、いかなる変換、いかなるコードについて学習する際にも、直示によるコミュニケーションは必要なのではないか。例えばどんな学習実験にも、正しい反応を大まかに指示する方法として、強化とおあずけの方法がつきものだ。動物に芸をしこむ時には、より正確な指示を与える必要から、数々の小道具がもちだされる。芸を正しく行ったその瞬間に笛をピリッと鳴らすことによって、調教師は、その時の動物の行動をもって、「そう、これが正しい反応だ」と指し示しているのである。直示的なコード化の、たいそう原初的な例をもう一つ披露しよう。それは部分に全体の情報がこもるというものである。例えば一本のセコイアの木が地面に立っているのを見れば、その知覚だけから、そこの地面の下には根があることまで伝わってくる。一つの文の冒頭を聞いただけで、残りの部分の文法構造や、そこにどんな言葉や観念が含まれているかということまでおおよそ伝わってくる。われわれの生活の中では、知覚は恐らく常に部分の知覚である。部分を知覚して、そこから全体を推測する。そして、後に他の部分が提示されるに及んで、その推測が確証されたり崩されたりする――すべてその繰り返しである。われわれの前に全体が提示されることはあり得ない。全体が提示されるには、情報が変換されないコミュニケーションに依らなくてはならない
/f 変換プロセスの記述と分類は、その現象に内在する論理階型のヒエラルキーをあらわす
この説明については、学習とコミュニケーションの階型論(“グレゴリー・ベイトソン書付”)を参照されたい
/g 精神システムの定義
精神システムにはどのような特性が備わっているのか
(α) 「自律(自己制御)」システムを備えている。すなわち自己修正的システム
(β) 目的指向性と選択の能力を――自己修正的であるところから――備えている
(γ) 安定状態を保つことも、ランナウェイ現象に走ることも、両者をとりまぜることも可能
(δ) “地図”に影響されるのであって、“土地”そのものに影響されることは決してない
(ε) したがって受信した情報をもとに、まわりの世界や自分自身について何かを証明することはできない。部分が全体を証明することはできないから
(ζ) 精神は複数の部分から成り、その分解はすなわち「死」を意味する。死とは循環の崩壊、自律の破綻である
(η) このシステムに可能なことは、学習、記憶、負のエントロピーの蓄積。これらはみな、試行錯誤と呼ばれるストカスティック(語源であるギリシャ語のstochazeinは「的をみがけて弓を射る」の意。そこから、出来事をある程度ランダムにばらまいて、そのなかのいくつかが期待される結果を生むように図るという意に転じられる)なゲームを通して経験的に行われる
(θ) このシステムはエネルギーを蓄積する
(ι) このシステムの中では、すべてのメッセージが不可避的に論理階型のどこかのレベルにはめこまれる。ために、階型づけに混乱をきたす可能性が常につきまとう
(κ) そしてこのシステムは、類似したシステムと合体して、より大きな全体を形成することが可能である
論理階型
/a 概要
(1)
論理の記述には、ふさわしい階層というものがある。土地は地図ではない。両者の違いは何か。土地は土地そのものだが、地図は土地の情報を変換した産物で、土地の関係を表わしたものが地図である。さらに土地が名づけられたものが地図である。地図は土地より一段高い、別の論理階型に属する
(2)
両者が論理階型の関係を結ばれるには、この時点、階型の抽象度を問わず、同じ関係上にマップされる全体のうちのいずれかに帰属することが条件である。つまりある両者が論理階型の上下の関係性を持つには、どのクラスに帰属するかに拠らず、上下の関係として同じ全体の中に属している必要がある。円形・三角形・四角形はそれぞれ別の性質を持つ概念であるが、一段上の階型に「図形」を設定した場合、図形のクラスの中に(つまり下に)メンバーとして円形・三角形・四角形らが設定されることになる。メンバーが設定される規則はメンバーを包括するクラスの設定の際の前提条件に含まれる。高次から地図⇒土地の論理階型を設定した場合、その全体(論理階型)に“リンゴ”が入り込む余地はないが、物体⇒地図、土地の階型ならば、地図や土地のメンバーにリンゴが加わることになる。このように設定されたある論理階型全体に属している諸要素のことを「これらは互いに論理階型全体の関係を持つ」という。その中でそれぞれ、上下の関係をもつ両者は「上下の論理階型の関係を持つ」、横上すなわちメンバー同士である両者は「横上の論理階型の関係を持つ」という。物体⇒地図、土地、リンゴの論理階型であれば、それぞれはそれぞれに対して「互いに論理階型全体の関係を持つ」。物体―地図、土地、リンゴ間では上下の関係にあるため、両者は互いに「上下の論理階型の関係を持つ」。地図―土地―リンゴ間では同じメンバーに属する項同士にあるため、それぞれ「横上の論理階型の関係を持つ」というような記述の仕方になる
(3) 上下の論理階型の関係性
(3-a) 高次の論理階型は低次の階型より、普遍的・前提的(抽象的)・多様的・制御する関係を持つ。対して低次の論理階型の高次の階型に対する関係は対称になり、低次に向かうにつれて個別的・具体的・単一的・制御される関係を持つ
(3-b) また、クラスはそれ自身のメンバーになることはできないし、メンバーがそれ自身のクラスになることはできない。高次の階型から順番に図形⇒円形、三角形、四角形の論理階型を設定した場合、クラスである図形がその下のメンバーらの中に加わることはできないし、同様にメンバーである三角形がその上の図形のクラスに肩を並べることはできない
(3-c) 高次の論理階型に属するメッセージは、低次の論理階型の変数を変えるにあたって、その変数を直接的に指定しない(する必要がない)。記述するのは“関係”のみで、ゆえにそれだけが決定される。例えばDNAからソマティックな変数の変域を変えるとき。夢の隠喩(ものを指し示すことをしない)的記述
(3-d) それぞれのレベルは、上位レベルによって下位レベルにある情報が秩序付けられるもしくは制御されるように効果を発揮する。つまり、上位レベルの変更は、必然的に下位レベルの変更を伴う。しかし、下位レベルの変更が“必ずしも”上位レベルに影響を与えるとは限らない
(4) 横上の論理階型の関係性
つまりメンバー同士の関係性ということになろうが、前述のとおりメンバーが設定される規則はメンバーを包括するクラスの設定の際の前提条件に含まれる。高次の階型から地図⇒土地と設定された論理階型の場合、「地図」の関係制御下にメンバーとして「土地」があり、土地がメンバーとして設定される規則は高次の階型の「地図」の設定条件に依拠する。この論理階型に「リンゴ」は加わることはできない。一方、物体⇒地図、土地、リンゴの論理階型にリンゴがメンバーとして加わることができるのはリンゴが物体の一つであるからだ。このようにメンバーが設定される条件は高次の階型の設定条件によって異なり、したがってメンバー同士の関係性も、高次の階型が設定された際に決定される
/b 具体例
その一連の例を示す
b-1 ものの名前は名づけられたものとは違う。ものの名前は名づけられたものより一段高い、別の論理階型に属する
b-2 クラスはそのメンバーより一段高い、別の論理階型に属する
b-3 室内温度調節装置のバイアスから出される指令、またはそこから生じる温度調節は、直接的な温度調節よりも高次の論理階型に属する(バイアスとは壁に取りつけられたダイアル装置で、それを適当な温度にセットすることにより、家の温度はその前後を上下する)
b-4 タンブルウィード(秋に根元から折れて地上を転がる雑草)という言葉は、潅木(低い木)とか木とかいう言葉と同じ論理階型に属する。それは植物の種や属の名前ではない。成長のしかたや種子散布の型によって分類されたものである以上、綱の名前である
b-5 加速度は速度より高次の論理階型に属する
b-6 言葉には表面に現れないメタメッセージ(メッセージのメッセージ)が存在する。われわれは日常の会話の中で、絶えず相手が言う言葉の含蓄を理解しようと努めている。われわれはもし相手の言っている意味が分からないときはすぐさまその真意を明らかにしようと再び尋ねる。「それはどういう意味ですか?」と。ダブルバインドの例では語り側の発する言葉に含蓄されるメタメッセージが、行動あるいはもう一つのメタメッセージと相反するために、聴衆(その多くは子ども)が二重拘束の精神状態に陥ることが起きる。ダブルバインドは言葉にメタメッセージがあることを明らかにし、ひとえに言葉の表面上の意味をいくら理解したとしても、理解されない別の次元の意味があることを教えてくれる
別の例を示そう。思春期の非行少女が教師に「死にたい」とこぼしたとき、教師はその言葉をどう把捉するだろう。同じ「死にたい」という言葉でも「寂しい」の死にたいなのか「助けて」の死にたいなのか、はたまた本当に死にたいの意味なのか、さまざまだ。これらのメタメッセージは言葉と同じメンバーではなく、一段上の論理階型に属する。これは夢が見る者のイメージに直接事物を指し示すことをせずに、隠喩的表現すなわち関係のみを表わす下位制御の仕方と同じである
b-7 暗黙知の説明に駆り出される例に階層的な二重制御がある。例えば言語行動を考えてみよう。それは五つのレベルを含んでいる。すなわち、(1)声を出す。(2)言葉を選ぶ。(3)文を作る。(4)文体を案出する。(5)文学作品を創出する。それぞれのレベルはそれぞれ自らの規制に従属している。すなわち、それぞれ以下のものに規定されているのだ。(1)音声学、(2)辞書学、(3)文法、(4)文体論、(5)文芸批評。この五つのレベルは包括的存在の階層を形成する。なぜなら、各レベルの原理は、自分のすぐ上のレベルに制御されて機能するからだ。発せられた声は語彙によって単語へと形作られる。語彙は文法に従って文へと形作られる。そして文は文体へと整えられて、ついには文学的観念を持つようになる。かくして、それぞれのレベルは二重の制御の下に置かれることになる。第一に、各レベルの諸要素それ自体に適用される規則によって、第二に、諸要素によって形成される包括的存在を制御する規則によって。したがって、より高位層の活動を、そのすぐ下位置に当たる諸要素を統括する規則によっては、説明できない。音声学から語彙を導くこととは不可能なのだ。同様に、語彙から文法を導くことはできないし、文法が正しいからといって良い文体が出来上がるわけでもない。また、良い文体が文章の内容を授けてくれるわけでもない。つまり上位の階型は下位の階型を関係によってのみ制御することになる
/c 誤った論理階型の例
両者の論理階型の関係に不確実性の要素があって曖昧なものは論理階型の関係を持たない。その典型的な例が人間的観念の介入である。人の解釈によって、時と場合によって両者の関係の程度が変わるような流動的な関係は、それを論理階型の関係に用いるには危険だ。暫時的に不確実性が取り除かれた場合の構造を切り取って、その構造において言うならば、それは論理階型の関係を持つと定義しても問題なかろう
c-1
人間的観念の介入――両者に直接的な因果関係がみられない場合において、その両者が結果的に因果関係を構築する現象について
c-1-a 程度――これは人間的観念の典型的な例だ。これから説明する程度の持つ属性を人間的観念の属性に置き換えてみると理解が早かろう
程度と決定(確率と成否)は、互いに論理階型の関係を持たない。神様も宗教も信じない人が、奇跡や偶然が二回三回と重なったことで、神様を信じるようになる。しかし奇跡といっても、その人の主観的な解釈という前提の上で喜ばしい結果となるわけであり、それは、その出来事自体が他の人にとって奇跡ではないということを見れば明らかである。後半は蛇足気味だが、この例では程度の高低差が決定の属性に影響を及ぼしている。しかしこの両者は論理階型の関係にあるわけではない。第一に何をもって決定されるかは人の解釈によるものだ。程度がいつでも決定を制御するわけではない。第二にある出来事が奇跡や偶然かどうかは、その人の主観感覚によって喜ばしければそうなるものであるし、その人にとってまったく関係がなければただの出来事の意味しか持たない。第三に決定を制御する程度の制御確実性が低い。その変数は時と場合によって、つまり人の感覚判断によって異なる値を採るものだからだ。仮に程度が100%の値を取ったときにでも、それが決定の表裏をひっくり返すかどうかは100%ではない。奇跡の出来事も、当事者がそれを神が起こしてくれたという理由に結びつけなければ、ただの奇跡の出来事であり続けるだけなのだから
例えば物事の成否と、人の「できる」とか「できない」とかいう思い、両者は直接的な結びつきはない。しかしつながっているようだ。それは人に願望の現実効果(“依存”)があるからだと思う。しかしそもそも物事の成否と人のもつそれらの思いに、因果関係がみられないとする点に疑問を向けることも忘れてならない
c-1-b 記憶する速度が速いのと、頭が良いとは別物で、本来はそれぞれは互いに一切影響を及ぼさない。しかし人が与える観念すなわち情報が、両者を相互作用の関係にすることはできる。この観念には二つの意味が含まれる。一つは、“頭が良い”の意味が、人の解釈によってさまざまな意味を持ちえるといった、定義域の幅があることについて。もう一つは、仮に“頭が良い”の意味が定義付けられたとした場合、それに即した情報が教えられる、すなわち教えられる情報の質を操作することができることについて
ところでそもそも、両者の存在は人によるものなのだけれど(この点については消えていく概念と消えていかない概念(“形式”)を参照されたい)
c-1-c 外形形態と関係形式(“形式”)は、互いに論理階型の関係を持たない。それはとりわけ、関係形式の形体が人為的解釈に従属するからである
c-2 その他
c-2-a 量と質は、互いに上下の論理階型の関係を持たない。これらはそれぞれ関連のない別の性質を持つ異なる概念であり、したがって同じ階型の上下の関係を持つことができない。加速度と速度はそれぞれ制御の関係をもち、「速さ」の論理階型全体に帰属し、かつ上下の階型の関係をもつ。しかし量と質はそれぞれ一方が変更されても他方にその影響が与えられないため、高次の階型の設定される条件によっては同じ階型の全体に帰属する、ここではすなわち横上の階型の関係をもつことはできても、上下の階型の関係を持つことはできないのだ
c-2-b
「AがATMから1円をおろしたとき、出てきたのは一万円と1円の領収書だった。すぐさま通帳を確認してみたが、たしかに口座上で引き落とされていたのは1円だった。Aは考えた。これは窃盗ではないのか? いや、そんなものではない、とすぐに自分を納得させた。この金はわざと盗ったのではなく、転がりこんできただけだ。それに、ほかの人から盗ったのではないから、盗まれた人は誰もいない。銀行にしてみれば、こんなのはほんのはした金だし、どちらにせよ、損害を出したのは向こうの責任であって、もっと安全なシステムを備えているべきだったのだ。そう、これは窃盗ではない。これまでの人生で最大の幸福というだけだ」
Aが考えている問題は「これは窃盗か、そうでないか」についてだ。しかしAは弁明のところで「銀行にしてみれば、こんなのはほんのはした金だし・・・」と言っている。これは本来の問題の論点がずれている。窃盗か、そうでないかは「客観的・公平的に見て、1円と1万円の違いが分かっている上でその間違いを申告しないのかどうか」あるいは「窃盗とは何か」など、あくまで“中心的な”出来事を客観的に考察することが正しい。「相手が銀行だから」「自分が故意に盗ったわけではないし」など、そのときの“周りの”状況を考慮に含めるのは、本来の問題からずれている
汝自身を知れ
「汝自身を知れ」
古代ギリシャのこの忠言には、様々なレベルの神秘霊妙な智慧が込められていようが、同時にこの忠言は、極めて単純で普遍的で、実用的とすら言える側面を持ち合わせている。己を知らなくては、他のいかなることも、十分に知ることができないのだ
私が暗闇で手を伸ばすとする。手が電燈のスイッチに触れる。「おっ、ここにあったのか」と私は胸の中でつぶやく。「これでワタシはソレをつけることができる。」だが電燈をつけることが目的なのであれば、何もスイッチの位置と私の手の位置を知っている必要はないのではないか。手をスイッチとが接触したことを感覚器官が報告してくれれば、それで十分ではないのか。「ここにあったのか」という私の認識がまったく誤りであったとしても、手はとにかくスイッチに触れていたのだから、電燈をつけることはできたわけだ。私の手はどこだ? これが問題なのである。自分の手の位置を知るという己を知ることの一項目が、スイッチを捜すこと、スイッチがどこにあるのか知ることに対して、極めて重要かつ特異な関わり合い方をしている
例えば私が催眠術にかかっていて、現実には真直ぐ前に伸びている手が、頭上に伸びていると信じ込んでいたとしよう。この場合、私はスイッチが頭の上にあると思ったことだろう。そればかりか、首尾よく電燈がついたことで、スイッチの位置についての考えの正しさを立証したとすら思ったかもしれない。われわれは自分たちについて様々な見解を外界に投影している。誤った見解を持つことも往々にしてあるようだが、それでもその誤った見解を基盤として、結構うまく動き回ったり、たちふるまったり、友人と相互作用したりしている。この“自分”というもの、これは一体何なのか?
手が頭上に、スイッチが肩の高さにあると私が“知って”いるとする。そしてスイッチに関しては正しいが、手の位置に関しては誤っているとする。この場合、いくらスイッチを捜しても、手がスイッチに触れることはあるまい。スイッチの位置をなまじ“知って”いることが禍いしているのだ。“知って”いなければ、ランダムな試行錯誤の繰り返しの中で、手がスイッチに触れることもあるだろうに。では自分について知るべきか知るべきでないかの基準は一体どこにあるのか? 誤った見解を持つより、何も知らない方が(実際的な見地から)よいのはどういう場合か? 己を知っていることが実際的見地から必要なのはどういう場合か? こういうことは知らなくても、考えさえしなくても、人の暮らしは成り立つもののようである
もっと謙虚な疑問をもって、問題にアプローチしていこう。そもそもイヌは自己を認識しているのか? 自分について何も知らないイヌが、ウサギを追いかけることは可能だろうか? 「汝自身を知れ」とかまびすしく叫び立てるあの命令の山は、われわれが抱え込んだ意識というものが、その数々の矛盾のつぎ当てにせっせと織り紡いでいる、途方もない幻想のもつれにすぎないのだろうか? ここでイヌとウサギとが、それぞれ独立した別個の生物であるという見方を捨てて、<ウサギ―イヌ>の全体を一つのシステムと見よう。すると問いは、こんなふうに形を変える――この部分があの部分を追いかけることが可能であるためには、システム内にどんな情報重複[リダンダンシー]が存在しなくてはならないか? そして追いかけぬわけにはいかなくなるためには? こう考えると答えもかなり形相を変える。そこで必要とされる情報(ないしは冗長性)は関係についてのものに限られるのだ。ウサギは逃げることで、イヌに対し、追いかけろというシグナルを出したのかどうか? 電燈の例が参考になる。手(“私”の手?)がスイッチに触れた時、そこに手とスイッチとの関係についての情報が生じた。そしてその情報さえあれば、電燈をつけることは可能だった。私、私の手、スイッチについての個別情報は一切不要だった
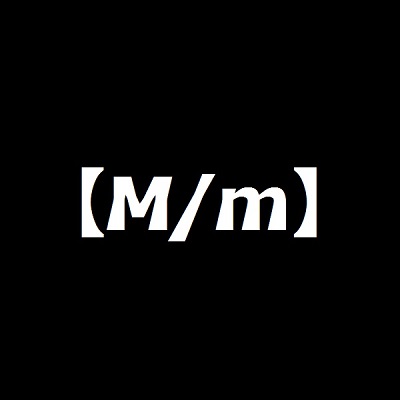

 TOP
TOP