暗黙知
a 概要
暗黙知とは、経験的学習の瞬間的想起される知のこと。ある人の顔を知っているとき、私たちはその顔を千人、いや百万人の中からでも見分けることができる。しかし、通常、私たちは、どのようにして自分が知っている顔を見分けるのか分からない。だからこうした認知の多くは言葉に置き換えられないのだ。このような、言葉に置き換えられない経験的・潜在的な知のことを暗黙知という。マイケル・ポランニーは暗黙知のことについて、私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができるといっている。暗黙知の別の一例として、「内面化」と呼ばれるものがある。内面化するとは、自己と当該の内容(教育内容、他人の意見など何でも)を同一化することである。ペットの肉を食べてはいけないとする教えを、道徳的規範に従って自分が納得するのでもそうだ。その内容(=ペットの肉を食べてはいけないとする教え)を理解するために、何らかの理論(=道徳的規範)を枠組みとして使い、その理論に依拠するとは、それを内面化することなのである。なぜなら、私たちは理論から、その理論の観点で見られた事物へと、注意を移動させ、さらに、そうした具合に理論を活用しながら、理論が説明しようと努めている事物の姿を介して、理論を感知しているからである
b 仕組み
技術的な面からみて、暗黙知の知の質が高められていく様には、習慣化のメカニズム[遺伝子型レベルでの学習(“連合の心理”)]が備わった、思考や行動の準固定化がみられる。準固定化とは、学習されるモノの、学習の表面は書き換えられたりするものの、結果的に上書きされて、知の質が高められながら、固定化の様相を成していくタイプの固定化のことである。確かに暗黙知の変化の様は、習慣化のメカニズムとよく似ている
私たちは、技能の遂行に注意を払うために、一連の筋肉の動作を感知し、その感覚に依存している。私たちは、小さな個々の運動からそれらの共同目的の達成に向かって注意を払うのであり、それゆえ、たいていは個々の筋肉運動それ自体を明らかにすることはできないのだ。だがもし仮に筋肉の使い方を知らなければ、目的達成うんぬんよりもまず筋肉の動かし方について意識しなければならないだろう。これは習慣化のメカニズム、つまり“慣れ”の属性が暗黙知に関連していることの徴ではないだろうか。もう一つ、この例から見られることがある。ある技能が実践されている場合に、私たちは、自分の注意が向けられている技能の手際を介して(経由して)、個々の筋肉の動作を感知している。つまりA(筋肉の動作)からB(共同目的の達成)に向かって注意を移し、Bの様相の中にAを感知するというルートが見られるのだ。身体から注目が移っていく外部の事物を介して(経由して)自らの身体の働きを感知する。これは暗黙知の現象的構造あるいは機能的関係とでも言うべきものだろう
ここで暗黙知の機能および構造について整理しておこう。二点指摘する。【】内は存在論的に言い換えたもの
(1) 首尾一貫した存在を暗黙裡に認識するには、まず具体的な諸要素を感知して、その感覚に依拠しながら、その存在に注意を向けていく。【包括的存在を制御する諸原理は、具体的な諸要素をそれ自体として統治している諸規則に依拠して、機能するだろう】
(2) もし個々の諸要素に注意を移したなら、諸要素の持っている(1)の機能は失われ、それまで注意を向けていた包括的存在を見失う。【(1)と同時に、諸要素をそれ自体として統治している諸規則は、諸要素が構成する、より高次の存在(包括的存在)の組織原理の何たるかを、明らかにするものでは決してないだろう】
(2-例) 階層的な二重制御
例えば言語行動を考えてみよう。それは五つのレベルを含んでいる。すなわち、(1)声を出す。(2)言葉を選ぶ。(3)文を作る。(4)文体を案出する。(5)文学作品を創出する。それぞれのレベルはそれぞれ自らの規制に従属している。すなわち、それぞれ以下のものに規定されているのだ。(1)音声学、(2)辞書学、(3)文法、(4)文体論、(5)文芸批評。この五つのレベルは包括的存在の階層を形成する。なぜなら、各レベルの原理は、自分のすぐ上のレベルに制御されて機能するからだ。発せられた声は語彙によって単語へと形作られる。語彙は文法に従って文へと形作られる。そして文は文体へと整えられて、ついには文学的観念を持つようになる。かくして、それぞれのレベルは二重の制御の下に置かれることになる。第一に、各レベルの諸要素それ自体に適用される規則によって、第二に、諸要素によって形成される包括的存在を制御する規則によって。したがって、より高位層の活動を、そのすぐ下位置に当たる諸要素を統括する規則によっては、説明できない。音声学から語彙を導くこととは不可能なのだ。同様に、語彙から文法を導くことはできないし、文法が正しいからといって良い文体が出来上がるわけでもない。また、良い文体が文章の内容を授けてくれるわけでもない。つまり、個々の諸要素を統括する規則によって、より高位層の組織原理を表すことはできないのだ。包括的存在を個々の諸要素に分解すると個々の諸要素は深く理解されるだろうが、その部分に意識を集中してしまうと、今度は包括的存在を上手く表すことができなくなる。そこで、個々の諸要素を理解するために、意識を一度潜入したあと、再び包括的存在へと立ち戻ることで、それまでの個々の諸要素を理解していなかったときよりも、包括的存在を上手く表すことができるようになる。このところはゲシュタルト心理学と似通うところがある。ゲシュタルト心理学では、精神を、要素の集合とみなす従来の構成主義的な考え方を否定して、ゲシュタルト(全体的構造/形態)とみる特徴がある。ゲシュタルトとは、緊密なまとまりと相互関連性を帯びた全体としての構造を意味し、要素に分解しようとすれば直ちにこの構造は失われ、要素は要素としての意味を持たなくなる
c 暗黙知と私的経験
暗黙知の他者への伝達については、言葉に置き換えられないと言われてきたが、だからといって、暗黙知が他者へ伝達することができないわけではないと思う。ポランニーもそのことは支持している。また彼はそれを承知した上で、それでも言えることは、私たちが、その方法以前に、言葉にできるより多くのことを確かに知っていた、ということであると述べている。暗黙知に関して例えば、単語をどのように扱うかについて考えてみよう。「コンテクスト」という単語をただ辞書で引いてその意味を知っているというだけでは、それは単に提示されたときに、その意味が、理解できるという意味の「知っている」にすぎない。「コンテクスト」の単語を、文を書き上げる際にどのような場面でどのように用いるか、そして実際に用いられるのには、「コンテクスト」の単語に対する暗黙知を会得した意味での「知っている」のレベルが必要になる。「知っている」というのと「できる」というのは、抽象階層においては「知る」という意味で同じだけれども、実際的にはやはり違う。ただ、ここで発生している暗黙知は、単に文のどのような場面でどのように用いるかの決定機構に用いられる、同種の暗黙知の、直接的な結果を表わしている。文字どおり、文のどのような場面でどのように用いるかの暗黙知を体現している人は、「コンテクスト」の単語を実際に文中に用いているという可視的事象をもって確認することができる。しかしだからといって、それぞれの人が会得している「コンテクスト」の暗黙知の中身が、同じだということはできない。その部分は専ら、主観の中の私的経験と呼ばれるところに属する。つまりなぜ暗黙知を他者に伝達することができないのか、その理由について私は、暗黙知が私的経験の属であるからと言っているのである。私的経験は、自己以外の外部に、それを伝達することはできない。赤色が、自分にとってどのように見えるかを他者に伝える努力をしたとしても、実際に自分が、赤色がどう見えているのかを、他者が知ることはできないのと同じように(この点についてより詳しくは、あなたと私が見る赤色は本当に同じ赤色か(“形式”)を参照されたい)。そう考えてくると、暗黙知の性質に関する一つの結論が提示できる。すなわち他者への伝達不可能性というのは、私的経験が有す性質ではなく、人の技術的達成の程度に帰結するものであるという考えから、暗黙知の他者への伝達不可能性に関する説明も、それと同じように言うことができるのではないだろうか。これで問題提起の(d-1)に対する説明は一応できたと言えそうだ。つまり暗黙知は決して伝達不可能なものではないと思う。まあ確かに、今の表現力では伝達することは難しいのでしょうけども
d 問題提起
d-1 暗黙知が他者間で伝達不能とされるそうだが、暗黙知の定義をする上で、ここの認識論は重要な場面だろう。もし暗黙知が他者間で伝達不能なら、その原因を突き止めなければ、暗黙知の実体を知ることはできない。暗黙知を会得する対象の事物と、自己の間では、暗黙知の伝達が起こっているのに、なぜ、その暗黙知を、他者に伝達することができないのか。もしかしたらそれは、暗黙知が伝達不可能の性質を有しているからではなく、人が暗黙知を伝達できるだけの技術力(とりわけ表現力)をまだ持っていないからではないのか
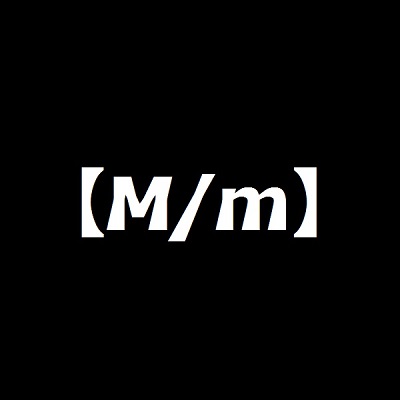

 TOP
TOP