“社会的証明”が集団であるのに対して、対人的証明は人(個人)が個人に与える影響のことをいう。または人同士(個人対個人)の関係性のことをいう。原理は社会的証明と全く同じである
目次
ピグマリオン効果/ローゼンタール効果
教師の期待によって学習者の成績が向上すること。別名、教師期待効果。ホーソン効果。その原理は、人は一般的に関心を持つ人や期待する人の心に答えようとする傾向がある
a 例えば期待させる時に、「期待しているよ」と言ったほうがいいのか、言わないほうがいいのか
ゴーレム効果
ピグマリオン効果とは逆に、教師が期待しないことで成績が下がること
サプライズ効果
どのような結果をもたらすいかんに関わらず、相手にどれだけ影響を与えることができるか、というのは重要な項目である。それを考えれば、サプライズという手法は時に有効である
a サプライズの強調効果
サプライズ効果によって物事や状況をさらに強調させることができる。これをサプライズの強調効果という
新規項目追加の承諾効果
現状の状況において、新規の項目を追加することで承諾効果が高まる。これを新規項目追加の承諾効果という。最初から全ての項目を追加しておく場合に比べて、随時の項目追加は相手の状況判断を狂わせる効果がある
行動と内的属性の一致
観察者が抱くバイアスの一つ。ある人物の行動を見た観察者は、その出来事に明らかに外的な要因(その場の雰囲気、状況、制約など)が存在している場合でも、その外的要因を軽視して、その人物の行動がその内的属性(性格が明るい、態度が陰険など)と一致していると思う傾向がある。これを行動と内的属性の一致という。人の情報処理の容量不足から派生する現象である
好意のサイン
人は好きな人を前にすると、何だかいつもの自分ではないような行動をとってしまいがちである。しかし実はそれが、相手への“あなたは特別”というサインなのであり、好意を伝達することにもなるのだ。お互いに好意を抱いている男女の会話を観察した実験によると、両者はいろいろなサインを送っていた。好きな人への好意のサインは男女でそれぞれ違う
・男性の好意のサイン
自分が話しているときよりも、相手の女性の話を聞いているときのほうが相手の目をよく見ている。何人かでいるとき、当の相手が一時その場を外したときのほうが口数が多くなる。また、相手に対して一方的に話している傾向がある
・女性の好意のサイン
基本的に男性とすべてが反対である。自分が話しているときのほうが相手の目をよく見る。何人かでいるとき、当の相手がその場を外すと口数も少なくなる。また、相手から話を促されるまでは話し続けることをしない傾向にある
パーソナルスペース
パーソナルスペースとは、人が自分のプライバシーを守るためのテリトリーとは別に、自分を中心として輪を描く空間的なテリトリーのことである。パーソナルスペースに入られると相手を意識する効果をもたらす。ただし例外はある(後述)。相手への意識は、その相手との人間関係によって決まる。例えば、相手との人間関係が希薄、つまり他人の場合には、パーソナルスペースに侵入されると嫌悪感情をもたらし、逆に自分が相手のパーソナルスペースに入ることを嫌う。例えば、空いた[すいた]電車の席で、一人が端に座れば、もう一人は反対側の端に、そして三人目は二人から離れて真ん中に座るでしょう。相手との人間関係が濃くなっていくほど、侵入されたときの感情は、嫌悪⇒無関心⇒嬉々へと変化する。また、この三つのどの感情をもたらすかは相手との人間関係以外にも異性か同姓かなども関係している。他にもたくさんの要素が侵入感情に影響を及ぼしていると考えられる
/a パーソナルスペースのフィードバック
パーソナルスペースに侵入されたときに嬉々の感情をもたらす要因は、その人が相手に少しでも好意を抱いているからであるといえる。恋人同士ではいつもくっつき合っていて、お互いのパーソナルスペース侵入に嫌悪の感情を抱く場合はないだろう。つまり、好意⇒頻繁に侵入を許している、この構図をフィードバックするのである。パーソナルスペースに侵入した状態で話をすることで、相手を自分へと意識させ、恋人関係の距離を先につくることを、パーソナルスペースのフィードバックという。この心理を使うには、例えばお店などに好意をもっている相手と行ったとき、テーブル席よりカウンター席のようななるべく身体的に相手に接近できる状態を維持できるような席にするのが効果的である。相手の話に身を乗り出す、一枚の書類に一緒に目を通すといったことから、相手の懐に飛び込むことである
最小の原理
大きな力をもつものが一方のものに利用されるような場合、一方のものが自身より大きな力をもつという関係になる。これを最小の原理という。この原理によれば、たとえ最小のものであっても、利用する力(操る力)さえあれば最大の力をもつことが可能である。利用されるというところには、最小側が利用する力をもっていたり、最大側のもつ力に最小側がもつ力が影響を与えるものであったり、最大側のもつ力を最小側に依存させる、つまり力のベクトル(方向)を最小側に向かせるものだったりと、さまざまな要因がある。特にこの要因においては、“依存”がもっともその例として多い。依存をしてしまうがゆえに、一方のものに自分が依存されているということを逆手に取って相手を利用するのである。狭義では、最小側とそれに依存するような力をもつ最大側の両者においては、最小側が最大側のもつ力を操ることができる関係性がある、ということになるでしょう
(例)
恋愛において、相手を好きであればあるほど、人は相手との関係を失うことを恐れる。恐れるあまり、相手のなすがままにならざるを得なくなる。こういう場合、主導権は完全にもう一方の手の内にあるといえる。依存される側の最小の愛(相手を引き止めている最小の互恵性)が最大の力を振るい、依存している側の最大の愛は、相手のなすがままに操られる最小の力となる。しかしこういう関係は長続きしない。恋愛は、お互いが必要とし必要とされる好意のバランス(好意の互恵性)が大事だからである。依存している側の愛が薄まるか、最大の力を出し続けていることに疲れるかで終わりを迎えることが多い
自己内完結的
「相手を思う心」が不安に変わるとき、思いが通じていないとネガティブにとらえてしまう。そしてたいていはそれを確信へと自己の中で勝手に決め付けてしまう。このような心理的展開を自己内完結的という。自己内完結的が起こると、それが相手にもネガティブな影響を与え、お互いにネガティブ感情を抱いたまま思いがすれ違ってしまう場合が少なくない。なぜなら、お互い自分の中では理由が確信に近いものになっているからである
(例)
デートで子連れの若い夫婦を見かけて、「私も結婚したら、旦那さんと子どもと一緒に、あんなふうにショッピングに出かけたいわ」とあなた(彼女)がいったとき、彼が何も答えなかったとしたら、あなたにどんな感情が起こるだろうか
おそらく、「彼はそれほど私のことを思っていない。結婚する気はないのだ」と思い込むでしょう。これは、彼を大事な人と思えば思うほど、その人の一挙手一投足が自分に関係することだと思いがちな女性心理のなせる業[わざ]である。思いが通じないと思うとしっかりとした確認をする前に先にネガティブにとらえて、たちまち悲劇のヒロインになってしまう。ネガティブな感情が先入観になっていては、当然否定的な結論しか出てこない。彼女は「私のことが重荷なの?」といった発言をしてしまう。一方、彼のほうは彼女がそんな心理状態にあることは分かっていないため、突然「私のことが重荷なの?」などといわれたりすると驚き、それから自分のことを信じてもらえていなかったのだと感じる。彼女を大切に思っている自分の気持ちまで侮辱されたように思えてくるのである。こうして彼女のネガティブ感情が彼にも悪い影響を与え、お互いネガティブ感情をもつことになってしまうのだ
/a 防衛法
このように、恋愛にかぎらず対人関係においては、ネガティブな態度は否定的な反応を呼ぶものである。自己内完結的はお互いの思いが通じていないためにすれ違った状態でお互いに悪影響を及ぼしている。初めはちょっとした不安や誤解から始まったことも、態度によって関係は悪化してしまう。否定的な感情をもつことは仕方ない。それは相手を思うがゆえに心配していることでもあるのだから。しかし否定的な感情をもっても結論を自分の中で出そうするのには全く意味がない。いくら自分がこう考えていても、それが相手についての考えであるならば、相手に確認することでしか真実は得られない。否定的な感情をもって勝手に自己内完結するまえに、相手が本当にその通りであるか確認するべきである。また、併せてこれも心にとめておくとよい。前提が間違っていれば導き出される答えも正しくはない
対人優位性
人は、特に男性は、同性の人間関係を優劣関係でとらえる傾向が強く、相手より常に優位でいたいとする心理傾向を強くもっている。これを対人優位性という。この心理はさまざまなものに影響を波及する。例えば、相手を称賛したとき、誰かが自分の知人を称賛したとき、相手に称賛されたとき、何か好ましいことが起きたとき、何か不幸なことが起きたとき、などさまざまである
/a 称賛と劣等感の相対関係
対人優位性の心理では、人は相手より常に優位でいたいと思っているため、相手をほめたり評価しようとすると、自分の評価が下がったような感覚になり、相対的に劣等感を覚える。これを称賛と劣等感の相対関係という。例えば、ライバルである同僚や、自分より下の部下をほめたり評価することは、心理的に大きな負担になっているといえる。仕事のあとにお酒を飲むという場では、人のうわさ話が多くなるのが普通だが、誰かがある人をほめると、それだけで不愉快になる人がいる。不愉快になると反論したり批判し始めたりする人もいる。自分がここにいるのに別の誰かがほめられるというのは、自分が低い評価を受けているのと同じ心理なのである
/b 劣等感とライバル関係
上記の称賛と劣等感の相対関係からみえてくるものがある。誰かがある人をほめる場合において、ほめられた人に対して不快の念をあらわにしたり、自分ではない人がほめられている事に対して反論したり批判したりする人というのは、得てしてその人はほめられていた人とライバル関係である場合が多い。なぜライバル意識をもっているのか。それは、ほめられていた人と自分との関係性が近かったり、ほめられている事が“自分がほめられていてもおかしくない”、つまり自分にも当てはめられるような内容だった場合、そこで自分ではない人がほめられたことにより、相対的に自分が低められたように感じるからである。しかし、ライバル同士はいつのときにも必ずお互いを批判的に見ているという点は見直さなければならないと思うことである
認知的枠組み[スキーマ]
スキーマとは、その人がもっているものや人を見るときの認知の枠組みのこと。その人のスキーマによって、同じものを見ても見え方は違ってくる
/a 対人的スキーマ[ヒューリスティックス]
自分の外の世界をとらえて判断するときに、その人が何を基準にするかという見方において、自分の中にある意識している部分や敏感になっている部分を強く基準にして、それをもって相手の性格や人格を判断しようとする傾向がある。これを対人的スキーマという。例えば、人を見るとき、「相手が感情的であるかそうでないか」と考える人は、自分自身が感情的であるか否かということに関心が強いといえる。相手が意地悪かそうでないかと考える人は、自分のなかにある意地悪な部分を意識しているか、あるいは意地悪に敏感になっているものである。自分のもつ基本的な姿勢や規範を、知らず知らずのうちに他人を判断することに使っているのだ。これは非常に偏った見方である。対人好悪においても、いったん嫌いになるとすべてが気にくわないものに思えて、長所を見つけることが難しくなる。確かに、長所があるから好きになった、短所ばかりだから嫌いになったのだから、そう考えるのが知的にもっともバランスがいいといえる。しかしいくら好きだからといって全部長所、嫌いだから全部嫌いというのはあまりにも短絡的すぎる。これもまた対人的スキーマの一例である
/b 高汎用ヒューリスティックス
対人的スキーマによれば、人は自分の中にある意識している部分や敏感になっている部分を強く基準にして、それをもって相手の性格や人格を判断しようとする傾向があるといえるが、特徴で分類された人たちにはそれぞれ有効的な判断材料を用いることで意図的な印象形成が可能である。これには人の普遍的な性質をもとに考えていくのがよい。例えば男性は異性を品定めするときでも見た目によって即決的に判断してしまう即断傾向があるので、この場合であれば男性には服装による印象形成が効果的である。メガネをかけた人は真面目な人、胸のカットの大きい人はセクシーな人という印象を簡単に植え付け、操作することができる
/c カラーバス効果
意識していることほど関係する情報が自分のところに舞い込んでくるようになる。これをカラーバス効果という。対人的スキーマとの違いは、単に対人的であるか否かということだけ
c-例1 手洗いとうがいをしっかりすることが風邪予防になると信じている人は、誰かが風邪をひくと「風邪の原因は手洗いとうがいをしなかったからだ」と思い込む
c-例2 「今日のラッキーカラーは赤」といわれると、街でその色ばかりに目が行く
「生理的に嫌い」と感じる理由
見るのも考えるのもイヤだ、説明はつかないけどとにかくイヤだ、と感じることが生理的に嫌いということだと思うが、見るのも考えるのもイヤなことは、自分自身がもっとも避けたいことであり、そのことに自我が強く関わっているということである。人は誰でも、自分のなかのイヤな部分を認めたがらないものだ。わかってはいるけれど否定したい。そんな複雑な深層心理が、そのイヤな部分を表に出している人物に対して過剰反応を起こすのである。それは自分自身の深層にある自分の短所で、自分で直視したくないような部分である。例えば、相手のキザなところに対して生理的嫌悪感を抱いているとすれば、その人は心のなかに「キザになりたい願望」があり、でもその感情を嫌悪しているのかもしれない。男性にこびる女性が生理的に嫌いという女性は、どこかしら自分にもそういう部分があり、心の奥のその部分と表の自分とが対立している。もし誰かに嫌悪の感情を抱いたとき、その理由を考えてみてすぐに分かるなら単にイヤということだけかもしれないが、理由が分からないときは自分のなかのイヤな部分をその人が投影している場合がある
対人好悪と距離
人は、嫌いな人が近くにいると嫌悪感を募らせ、遠くにいると嫌悪感は急激に薄れる。好きな人の場合でも同じ原理である。これは、好悪が意識されるかどうかによってその好悪感情が強くなったり弱くなったりすることが原理で、意識するほどに近くにいたり、意識しないほどに遠くにいたりするといったような心理的距離が関係しているからである。このように、距離が対人好悪感情に強弱をもたらすことを対人好悪と距離という。嫌いな人というのは自分を成長させてくれる種だからあまりおすすめはしないが、どうしても嫌いな人と関わり合いたくない場合は、とにかくできるだけその人から離れて、意識しないようにするのが望ましい。視界に入らないように物理的距離をおけば、自然と心理的距離も離れるようになり、嫌悪感を抱かずにすむようになる
イデオシンクラシー・クレジット(その人の個人特有の信用)
人はたとえ自分が悪いと思っていても、注意されたり批判されたりすると、その相手のことを快く思わないのが普通である。ところが、欠点を指摘されて相手への尊敬を深めたり、「なぐられて痛かったけれど、あの人の本心を理解できた」といって好意を抱くケースが一つだけある。それは、相手の人に対して個人的な信用をもっている場合である。この信用は、それまでの人間関係によって蓄えられ、培われるもので、預金にたとえられる。長い付き合いのなかで、相手の人に「信用」というお金をたくさん貯金していれば、そこで多少批判してその預金を引き出しても、まだ預金のあるうちは大丈夫なのだ。例えば、初対面の場合、預金がないために、批判されるといきなり預金残高がマイナスとなり、二人の関係は険悪になってしまう。この信用は、自分が確認できるものではなく、相手の感情の中にある。どれだけ預金があるか、つまりどれだけ相手に自分は信用されているのか、ということは日常生活から察するしかない。または、フックとしての批判をすることで信用を図ってみるのもよいかもしれない。どの程度の批判をしたらどのような反応をするのか、それを見ることで相手の自分に対しての信用という預金を大まかに知ることができる
この心理から分かることは、批判は信用と相対関係にあり、信用の度合いによって、批判が二人の人間関係を一層深めるのか、それとも険悪にさせてしまうのかが決まるということだ。これは批判によって相手に悪く思われてしまわないような防衛法の手がかりを示してくれている。批判は出会ってから信用が醸成されるまでは人間関係に悪影響を与えるので控えたほうが望ましい。逆に、ある程度の信用が醸成されてからの批判は、より相手との人間関係を親密なものにさせていく手段となり得る。この状態での批判というのは、単に信用という預金を引き出す支出の要素だけではなく、むしろ人間関係がより親密になって預金がさらに増大する役割をもっている
社会的交換理論
人は人間関係において交換的やりとりをベースにしている。例えば、社会的に見れば市場経済はお金の等価交換をしている。会社と社員の関係は、仕事とお金の交換である。情報産業の最先端の人を大学教授として迎える大学は、情報と地位の交換である。このような人間関係における交換的やりとりを社会的交換理論という。このような交換的やりとりは古くから人間関係のベースとして根付いている。こちらの交換要求(実際の表現はもっとやわらかだが要求していることには変わらない)に応じてくれる人とつき合い、応じてくれない人とはつき合わないのが社会的に画一されている
/a 心理的報酬
社会的要素が希薄になった対人関係、例えば友人同士の関係や、恋愛関係などにおいては、物質的交換のやりとりに加え、心理的満足を交換する要素が存在する。これを心理的報酬という。この心理的報酬はまさに満足が物質などとともに等価交換されているのである。心理的報酬には、愛情、サービス、物品、お金、情報、地位の六つがある。これらがお互いに等価交換されているのだが、互換性が高いわけではないので必ずしも等価で許されるわけではない。例えば、バレンタインデーにチョコレートをもらった男性は、ホワイトデーのお返しに頭を悩ませる。愛情はものではないから交換的と考えなくてもよさそうだが、それでは二人の関係は悪くなるだろう。女性のチョコレートに対して愛情だけでお返ししようとするのは無理がある。逆に満足に対するお返しが物質となるのはむしろ喜ばれるケースが多いようだが。本来恋人関係はもっとも情的で交換的ではないはずだ。だが実際はかなり交換的であるといえる。会社と社員の関係、企業と大学の関係からも分かるように、人によって求める報酬は異なる。これはその人が何を重視しているか、ということである。地位や名誉が主要という人もいれば、愛情を第一と思う人もいる。社会的交換理論が根付いた人間関係をスムーズに進めるためには、相手が何を重視しているのかを知ることが大事である。相手が重視していることを知り、それを用意することによって、交換的やりとりの原理ではこちらの要求も叶えられるということになるのである
インフォーマルな関係とフォーマルな関係
人間関係にはウラとオモテがある。フォーマル(形式的)な関係とは仕事上の人間関係などをいう。組織としての会社はフォーマル・グループで、その組織上の人間関係もフォーマルな関係である。この関係では、失敗がないように常に自己を抑えていて、人に対しているときも、緊張し、身構えるものである。一方、友達や恋人、飲み会などはインフォーマル(非形式的)な関係である。この関係では相手を身内のように感じていて、フォーマルな関係よりもリラックスし、安心して本来の自分をさらけ出している傾向がある。またインフォーマルな関係は、お互いの感情がつき合いの中心になるため、フォーマルな関係よりも親しくなったり好意を抱いたりしやすいといえる
プライドと好悪
プライドのあまり高くない人や正義感があまり強くない人は、人を嫌ったりけなしたりしても、自分も同じようにダメな人間だと思っているので、お互いさま、といいながら気安く悪口をいえる。しかし、プライドの高い人や正義感の強い人は、相手を悪く評価したりけなすことは、きちんとした理由がないといけないと思っているため、加害行為をしたり悪口をいってしまったあとの心理的葛藤(不協和)は大きいと考えられる。この心理的葛藤が大きいと、その分、悪評価したときの心理メカニズムがより強く働き、自分の行為を正当化するために「相手はもともと悪い人なんだ」と考えるようになる(自己正当化)。対してプライドがそれほど高くない人は、悪口をいったことを無理に正当化する必要がないので大きな心理的葛藤はなく、そのために無理やり人を嫌いになることもない。こう考えると、プライドの高い人ほど、加害行為や悪口をいったあと、当の本人を嫌う傾向があるといえる。確かに正義感や公正感が強いというのは、一般的には望ましい社会的性格である。しかし、あまりかたくなに正義感を振りかざすと、それによって自分を縛りかねない。特に日本社会はタテの人間関係が強いので、自分のプライドの高さを守るために、周囲との人間関係がうまくいかなくなってしまわないように気をつけるほうがよい
対人対比の基準
人は好悪を決めるときに好き・嫌いの対比の基準というものがあり、それによって好悪を決めている。これを対人対比の基準という。この対比の基準はどのようにして作られているのか。まず、人は「これに比べては劣っているな」「あれに比べてはすごいな」というような“対比”によって物事との関係を判断している部分がある。人間関係も同じで、いつも仲のよい仲間だけとつき合い、一緒に仕事をしていると、「あいつに比べては馬が合わないな」というように、対比基準が仲間内という狭い範囲で形成されることになる。一般に基準の範囲が狭いと幅も狭まるように、対人対比での基準が狭いと仲間の間の小さな差や小さな好悪にも目がいくようになる。仲のよい仲間でも、互いにイヤな点や気に入らない点はあるものだ。また、人が三人寄れば派閥ができるといわれるように、その仲間内にも好き嫌いの程度の差があり、サブ・グループが意識されるようになる。つまり、仲間内を基準にするので、仲間内で比較して好き・嫌いを対比し、分けていく心理が働き始めるのである。これはいわば「井の中の蛙大海を知らず」というようなもので、人間関係の面においても非常に損をしているといえる。好意の範囲は広いほうが多くの人に寛容になれ、むかつくようなことも少なくなるし、何より好意的人間関係を築けるというものである。つまり、対人対比の基準はある程度広いほうが好ましく、広くさせるためには対比基準を決めるきっかけを増やすことが大切である。それはつまり色んな人と交流をもつことである。多くの人と交流することで自分の見識や経験も深めることができるため、まさに一石二鳥ではないだろうか。特に対比基準に大きな影響を与える人というのは、初めて会う他人より嫌いな人のほうであるといえる。嫌いな人と仕事をしたり、しばらく一緒につき合わなければならなくなったとすると、とたんに対比の基準は大きく変化することになる。「この人たちに比べたら、自分たちの仲間内の好き嫌いなど、目くじら立てて区別するほどのことはないな」と思うようになる。比較の対象が嫌いな人たちとなるために、自分たちの仲間のよさが改めて確認される、というわけである。嫌いな人とつき合うとこんな効用もあり、この心理作用が仲間意識を育てるのにも役立つのだ
体験承諾
実体験は心を変える効果がある。そこには、言葉だけの説明では便利さが実感できないものであっても、実際にそれを「体感」すると、その品物がないと不便に感じるようになる心理がある。この心理を承諾誘導に応用したのが体験承諾である。「百聞は一見にしかず」というが、「一見」よりも「一体験」のほうがより強力な影響力を持っているといえる。実際にやってみせる、させることには不思議な力があるものだ
(例)
セールス業界にとって、いかにして製品を実際に見てもらうか、いかにして商品に触れてもらうかは、消費者を動かすための大きな課題であり、そのためにさまざまな方法が講じられている。デパートやスーパーに行くと、店員さんから「一つ食べてみてください」「手に取ってみてください」と言葉をかけられるのは典型的な体験承諾である
二重拘束
相手にとって矛盾するような感情を表すしぐさを同時に行うと、受け手の側は混乱する。絶えず矛盾する振る舞いをされれば、常に緊張していなければならない。やがて、矛盾する情報に折り合いをつけられずに、自分の判断に自信をなくし、結果、相手に振り回されるようになってしまう。このような状況を二重拘束という。例えば、交渉の場なら口では「イエス」といいながら、視線を合わせずに腕組みでもして「ノー」の意思表示をしてみたり、意見を次々に変えていって相手を混乱させるなど。紙一重で不快感を与えかねない危険性はあるが、成功すれば効果は大きいといえる。原理はダブルバインド(“グレゴリー・ベイトソン書付”)
(例-a) 量販店に行って、「このパソコン、もう少し安くならないかなあ」と値引きを要求する際に、欲しくないような素振りをしながら、関心があることをほのめかす。これも店員を二重拘束することになる
(例-b) 脅したりすかしたりというテクニックは、セールスマンがよく使うものである。お客の優柔不断さに業を煮やした様子で、「そんなに迷われるなら結構です」と立ち去ったあとに、もう一度引き返して、「ちょっと説明し忘れたことがありました」といった具合に話を続けると、客のほうは翻弄される
頼む頼まれるの心理
人に頼みごとをする、されるという人間関係は、個人レベルで考えると、マイナス効果のみをもたらすように思えて躊躇しがちだが、二人の関係レベルで考えるとマイナスではなく、むしろプラスの効果をもつものである
/a 頼まれる人の心理
依頼されたこと自体は、たしかに自分の時間を割かれ、心的苦労もかかるわけだからマイナスとなる。しかし、私たちは信頼していない人にはものを頼まない。「信頼しているからこそ、その人に頼む」といった人間関係に対する暗黙の了解がある。人から依頼されたということは、依頼者に信頼・信用されていることの証明になっているのだ。それを頼まれた側も無意識的に認識しているから決して悪い気はしない
/b 頼む人の心理
頼みごとをするのはたいていの人なら気が重いものだ。それは、相手から評価を下げられるのではないかという懸念や、断られたときの自己嫌悪感など、頼みごとをすることによるマイナス効果が頭に浮かんでくるからである。しかし、頼まれる人の心理を理解していれば決してそのマイナス面だけではないことがわかる
/c 頼みごとの承諾率を上げる伝導的喚起
頼むことのプラスの面を分かっていれば、相手に「自分は信頼されているからこそ頼まれているんだ。それでは断れないな」ということを強調するためにある“伝導的喚起”を施すことで承諾率を上げることができるはずである。それはつまり、頼む相手に「たしかに信頼されている」という確証を持たせるきっかけとなる思考因子を作り出すことである。例えば普段から、よく頼みごとをする、自分(頼む人)にとって大事な頼みごとをする、「尊敬している」など言葉によって信頼されていることを認識させておく、対象の人がいないときに周りに公言することによって、公言を聞いた人が対象の人に話すなどの間接的伝達を図る、などである
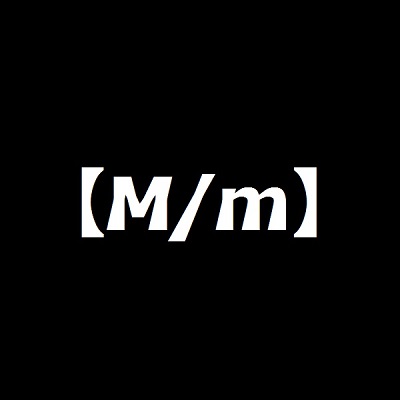

 TOP
TOP