目次
心的現実と原光景
a 心的現実
体験には、客観的な観点からとらえた事実と、個人の主観的体験の二つがある。このうち、個人の主観的体験のことを心的現実という。本人が体験をどうとらえたかが、体験した個人の自我(意識)と無意識を分けているのである
b 原光景
心的現実の元となったかつての体験のことを原光景という。たとえば、心的現実のなかにトラウマ(心的外傷)があるが、いわゆる「狼男の症例」では、「狼に食べられる」という患者の不安は、父親に食べられてしまう不安を意味し、それは早期幼少期に、両親の性行為場面を目撃したことによって父親に対して抱いた恐怖の再現であり、かつての体験がトラウマとして心に根づいているゆえの不安だと解釈される。このうちの両親の性行為場面の目撃体験が、いわゆる患者の原光景である
b-1 狼男の症例
狼男の症例というのは、1910年に約5年間にわたってフロイトの治療を受けたロシア人青年のことである。その治療のうち、狼恐怖を主症状とする幼児期の神経症に対する分析が、フロイトの論文によってよく知られている
その青年は、4歳ごろ「6匹か7匹の真っ白い狼が窓の向こうの大きな胡桃の木に座っている」という不安夢を見て以来、狼に食べられてしまうのではないかという恐怖症にかかってしまった。フロイトによれば、この狼に対する不安は、「父親に食べられてしまう」不安であり、それはかつて彼が両親の性行為場面を目撃したときの、父親に対する恐怖の再現だという。つまり、自分も父親から母親と同じように愛されたいという同性愛的な愛情欲求を抱きながら、一方では、もし母親のように愛されたら、男性としての自分がなくなってしまうのではないかという不安を抱いた、その葛藤の結果としての食べられる不安なのだと解釈されている
失錯行為[錯誤行為/自発的ダブルバインド]
日常生活において、言い間違い、書き間違い、読み間違い、ど忘れなどのしくじりは誰にでもある。私たちはふつうそれらを偶然の出来事か、あるいは疲労や不注意、軽率のせいにしてしまって、それ以上深く追求しようとはしない。しかし、これらのしくじりには無意識的な心的過程、言いかえれば、隠された別の意図の現われであると考えられる。このような行為を失錯行為という。やらなければならないと思っていても、なかなかやり始めることができないといった場合はよくあることと思う。こういった場合、無意識では「やりたくない」という心理がはたらいている。しかし本人はそれを認めたくないために自覚しないのだ。だから自分でも気づかない。たとえば、言い間違いや書き間違いは、しばしば無意識の願望などを完全に抑圧することに失敗した結果であるといえる。ある会議で開会を宣言しようとした司会者が、心の内では早く終わりたいという無意識が作用して、「開会します」というところを間違って「閉会します」といってしまった例がある。一方、ど忘れは、しばしば抑圧の直接的な結果であると考えられているが、その意味が容易に推測できるとはかぎらない。たとえば、患者A氏はよく知っているはずのB氏に出会ったとき、その名前を思い出すことができない。A氏に時間をかけて自由連想法を施したところ、理由が判明した。かつてB氏と同じ名前の人を知っていて、A氏は、その人に強い憎悪の感情をもっていたが、その後、Bという名前をみるといいようのない罪悪感に襲われるようになった。その結果、B氏に出会ったとき、罪悪感を感じさせるほどの憎悪の感情が意識に入りこむのを防ぐために、Bという名前が抑圧(忘却)されてしまったと考えられる
読みまちがいが起きた場合、多くの場合には置き換えた語というのは、その人がよく連想させやすいものであることがわかる。よく連想させやすいというのは、たとえば常々繰り返し考えることであるとか、置き換えられる語の両端から連想されやすい語でいわゆる“通例”と呼ばれるようなものなどを指している。たとえば、戦時下では都市の名や司令官の名、および耳にたこができるほど聞かされる軍隊用語などは、それにちょっと似かよった構造の語をみさえすれば、すぐに読みまちがえをしてしまう。人の関心をひき、注意をひくものが、こうして自分に関係のうすいものや関心の少ないものの代わりとなる。思想の残像が新しい知覚を曇らしてしまうわけだ
事故や災難も私たちにとっては避けられない日常の出来事である。この場合にも、精神分析的には、もし予測可能であった災難が、ある行為を行う人が無意識的に意図したものであったと仮定せざるを得ないのだ。果たしてそんなことがありうるのか
(例)
今は幸せな母親である30代女性の独身時代の話。彼女は、両親が結婚してから何年もの後に、待望の子として誕生した一人っ子で、子どものころから母親に大事に可愛がられていたが、大人になった彼女は、煩わしくなった母親から逃れたいのに逃れられないという葛藤に苦しんでいた。ある日、その彼女が母親に怪我をさせてしまった。母親を買い物に連れて行って、スーパーの前で車から降ろすとき、母親が車から降りきらないうちに発車させようとしたからである。母親の怪我はたいしたことはなかったものの、自分ではどうしてそんなことになったのか、そのときはまったく理解できなかった。しかし、後になって、自分が母親の死を願っていたのだということに気づいた。そして、それよりずっと以前にも、母親が車の後ろにいることがわかっているのに車をバックさせたことがあるのを思い出したという。その場にいた人々は、彼女のことを、どうしてそんなにぼんやりしていたのかとしか考えなかったに違いない。だが、どうしてそうなったのかは、彼女自身がよく知っていた
事実とはその場に起きた現象だけとは限らない。様々な人の思いが交錯しているのもまた事実である。現象だけから事実を読み解くのは容易ではない
a 口調について
しくじり行為が起きる原因は、意図を忘れる場合には反対意思があるからだということが多くの例について実証される。ここにしぐじり行為の原理がみられるのだが、その原理と申すのは、不快な感情と結びついているため、それを思い出すと不快感がよみがえってくるようなものは、記憶がこれを思い出すことを好まないということだ。想起あるいはその他の心的行為にともなう不快を回避しようとするこの意図は、不快からの心理的逃走でもあり、私どもはこれを名前のもの忘れのみならず、怠慢、誤解(見当ちがい)などのような多くのしくじり行為に対する究極的に有効な動機だと認めざるをえない
言いまちがいが、言おうと思っていた意味に第二の意味をつけ加えるだけのこともある。この場合、言いちがえた文章は、いくつかの文章の短縮、省略、凝縮であるように聞こえる。かかあ天下の婦人が言った、「夫は<私の>好きなものはなにを飲み食いしてもいい」は、あたかも、「夫は飲んだり食べたりしてよいのです。しかし、夫の好きなものを決めるのは私なのです」と言っているようなものだ。言いまちがいはよくこのような省略の印象を与える。たとえば、ある解剖学の教授が鼻腔についての講義を終えてから、学生によく分かったかどうかをたずねたのだが、みながよくわかったと答えると、つづけて、こう口にしたという。「私には信じられないですね。鼻腔のことがよくわかる人は、百万の市民がいるこの大都会でも、ただ<一本の指>……いや、失敬、五本の指で数えるくらいしかいないんだから」。この省略された話の意味するところは、鼻腔のことがよくわかっているのは「この私一人だけだ」ということなのだ
意味がとくにあいまいで見通しのつきにくいしくじり行為、つまり、紛失と置き忘れに目を転じてみよう。物を紛失することは偶発的な出来事としてひどく悩まされるものだ。この場合にもある意図が関与していると申し上げたい。ある青年はたいせつに扱っていたクレヨンをなくした。彼は、その前日に義兄から手紙を受け取っていて、君の浮薄さと怠惰を考えると、当分援助などはする気もないし、そんな暇もない、というのがその結びの文句だった。ところで、クレヨンはまさにその義兄の贈り物だった。このような事実の一致があってこそ、この紛失に、こんなクレヨンなど捨ててしまおうという意図が加わっていたと断言することができる。物を紛失するのは、その贈り主と不仲になり、その人を思い出すことを好まないときとか、あるいはまたその品物自体がもはや気に入らなくなって、別のもっとよいものととりかえる口実がほしいと思っているときなどに起こる。物に対して紛失の場合と同じような気持ちがあると、もちろんまた、落としたり、こわしたり、傷つけたりすることも起こってくる。小学校に行っている子どもが誕生日の前日に、自分の持ち物、たとえば鞄や懐中時計をなくしたり、だめにしたり、傷つけたりするのは偶然だといえるだろうか
最後に、さまざまな種類のしくじり行為がつぎつぎとつづくと、そのしくじり行為にとってもっとも重要で本質的なものがなんであるかがはっきりしてくる。すなわち、しくじり行為の形式やしくじり行為が利用する手段などではなくて、しくじり行為そのものを利用し、どんな道を通ってでも目的地に到達しようとする意図が、しくじり行為の重要な本質なのだ。ここで、もの忘れがくりかえされる例を一つ示すことにしよう。E・ジョーンズがこんなことを言った
「あるとき、どんな動機からかは自分にもわからないが、手紙を投函せず、数日のあいだ、机の上に置いたままにしたことがあった。やっと決心してそれを投函したが、宛先人不明で返送されてきた。宛名を書くのを忘れたのだった。宛名を書いて、ポストにもって行ったらこんどは切手を貼り忘れていた。そこで、もともと自分はこの手紙を出したくなかったのだ、ということを認めざるをえなかった」
しくじり行為が教えてくれるのは、自分に都合の悪いもの信じたくないもの嫌いなものなどの不快感情や不快感情を連想させるようなものは、自分自身ではそう簡単に制御できない無意識の作用によって、忘れてしまいやすくなるということだ。不愉快な印象が忘れられやすいことは疑いえない事実だと考えている――つまりは不快な記憶を忘れることによって防衛するという原理によって。いろいろな心理学者がこの事実を注目してきているし、チャールズ・ダーウィンもこのことから強い印象を受け、自分の理論にとって都合のよくない観察は、とくに注意してノートをとっておくという黄金律をたてたといわれている。自分に都合の悪い観察となると、なかなか記憶に残りにくいものだということを、彼は確信していたのだ
しくじり行為にみられることだけじゃなく、広く人の表にあらわれる行動の、そのいちいちの原因について興味をよせてみることは非常に有益なアプローチだと思う。今回その一つの例としてあげておくのは「口調」についてである。言葉が声に出されるときの言葉というものは、いわゆる文字だけの言葉に人間固有の要素が上乗せされて表現されるので、言葉の裏に隠されたメタメッセージが文字だけの言葉の場合より読み取りやすくなる。こういった人間固有の要素からつむぎ出されるメタメッセージが、人間固有のそこしかに限定されていることから、そういった種のメタメッセージは文字だけの言葉の場合に読み取れるメタメッセージとは種を異にするという向きもある。しかし私は本来メタメッセージというのは一つの概念として定義されるものだと思っているから、どこからそれが出てくるのかの出自の違いによって、メタメッセージをどんな意味にしろ、分けてしまうことはふさわしくないと思うし、また安易にそういうことができるものでもないと思う。今回この「口調」からは、どのような口調によってどのようなメタメッセージが推察されるかを、しくじり行為と同じ解明のしかたにもとづいて解明していくのを提案している。たとえばどのような口調が実際みられるか――(1)とぎれとぎれにみられる間。(2)部分強調(マスキングの意図)。(3)基準声量からの強弱度。(1)について――人が話すときは、機械が棒読みするような区切りのない口調ではけしてなく、必ずといっていいほど、区切りがあるとぎれとぎれの口調になることが知られている。それは文字における“、”のような一瞬の間なのだが、この間が必ずしも一つの原因によって発生するわけではないことを皆さんに少し考えてみてもらいたい。たとえば、文字における“、”のように文脈を分かりやすくするために区切る意図もあれば、次に話す言葉を逡巡するような思考のために起こる間、言葉の連結を文法に則って収めるための文法構成のための思考の間、そして次が一番注目すべきことなのだが、特定の語を強調する目的で意図的にとぎれとぎれの間を作るという強調のための間など、ほかにも色々な理由からの間があるだろうが、とりあえず複数あることが見てとれる。最後に申した語を強調するためにあえて間をつくってみせるという意図には、それこそ抑制の作用ではないにしろ、無意識の要請からくるという点ではしくじり行為と同じ心的作用が見られる。もとより無意識の要請の原理にもとづいてみれば、実際に表出される口調のなめらかさには極に対称なものの、同じ説明によってこれらは明らかにしてやることができるのではないだろうか。たとえばこれは反対の例であるが、強調したいがためにあえてとぎれとぎれに語を区切りながら話すことで強調の意向を暗に示しているのならば、言いたくないことをどうしても言わなければならない場合には、その部分をまわりくどく言おうとしてみせたり、スムースに、あるいは小さい声で言いこなすといったような傾向が出ると見当をつけることもできる。(2)について――これも主に(1)にかかずらうものになっている。特定の語を強調するためのいろいろな手法がここで試みられるのであるが、この手法はもっぱら言葉を感情にのせて「表現」するところの領域に属する。したがって、どのような意図があるのかを調べてみることとは、この領域から得られるものではない。強調する手法のその手段についての説明はまず次のことを説明してからにしておきたい。すなわち、強調の理由だが、これは一見すると、別の意味で一瞬あたまに?[はてな]が浮かぶほど説明に紙数を費やす必要はないとお感じになるかもしれない。強調の理由とたずねられてもそれは、単にその部分あるいは語をしっかり伝えたいからという意図があるだけではないのかと、まあそうすぐに締めくくってしまう前に、ここでマスキングという言葉を机上にこしらえておきたい。マスキングとは、隠したいものを隠すために別のなにかを故意に発動することによって、意図的に隠す手法のこと。ところで、その別の何かの手段として、しばしば「強調」表現が用いられることがある。例えば普通に考えられることとして、片方の耳に当てた電話口からの声をもっとよく聞き取れるようにするために、反対の耳を押さえることはよくある。マスキングの場合には、ある音を聞こえないようにするために、その音よりも大きい音を聞かせることで、音を上書きして、聞こえないようにさせる手法である。ある一方の耳で聞こうとしている音を、もう片方の耳で聞こえないようにするために、その耳にだけ雑音を聞かせることで、実際には片方からしかその音を聞こえさせないようにすることができる。学校のしーんと静まり返ったテストの時の教室でひとりごとをつぶやくと皆に聞こえてしまって恥ずかしいが、わいわいがやがやにぎわう休み時間の教室では、彼のひとりごとなど虫の息ほどにとるにたりない。私がここで言いたいのは、ひとえに強調表現とよぶものの中にも、その意図は強調がための意図や、マスキングの意図など、しかし多義的であって、そこを安易に見過ごしておくのは人間の心の解明においてはちょっともったいないことだということである。知的好奇心にかられている皆さんはきっと、この主張にしっかりうなずいてくれることでしょう。さて、先ほどから取っておいた語の強調表現のそのいくつかの手法についてであるが、これを調べてみれば、その数が限られていることがまずお分かりだろう。(1)のときれとぎれの間がこの強調表現になっている例、それから(3)の声量の大きい小さいによっても強調不強調は確かに表現される。とここで(3)について――基準声量からの強弱度の、すなわち基準とは何の基準かというと、それは話し手の「声量に対する意識(声量の強弱の意識度)」の平均の値になるのだが、ただその基準を知ろうといっても、彼の意識度をじろじろとのぞきこむことなどかなわないことなので、これはやや難しいところではある。その難しい理由の一つに、彼の意識が「私的経験」の属であるからということがある。この基準をわれわれが知りえる今のところの唯一の方法は、聞き手による彼の声量の平均を基準とするものだ。聞き手にとって、話し手の声が“通常(この場合{ケース}について限定である意)”より小さいか大きいかをおおよそで把握することが、その結果として、基準声量からの強弱度を決定するデータになりえている。ただし気をつけておきたいのが、この“通常”があくまで話し手にとっての声量が通常であるということと、場合ごとについての声量の通常を、そのときの基準とすること限定であること。喫茶店でそのとき彼が発する言葉の声量と、街中の場面で発した声量はそれぞれ時と場所、場合によって違うのだから、その時々の場合について一々の声量の通常を定める必要があって、これをまた基準とすること、その意味で「(この場合について)限定」と言っているわけである。またこうして彼の場合限定の基準を定めて、なるたけ主観的見方を排して客観的にこれを計ろうと努めても、完全に彼の私的経験、すなわち彼の声量に対する意識に取って代われる代物になることは不可能で、それはなぜかというと、そもそも彼の発した声量から、彼の声量への意識度を推しはかって知ることが、正確に出来るわけではないからだ。彼から言わせれば、彼は確かにこの部分を強調するために声量を上げようと意識したのであるが、しかし実際には思ったほどの大きな声が発せられなかった場合もある。これは意識が足りなかったというよりも、自分が意図していた、期待していたほどの声量が出なかった(そして彼自身これに驚いた)と考えるべきが自然ではないだろうか。そう考えると、この事例が示しているとおり、客観的事象から主体の意識度を狂いなく正確に割り出すことは、ちょっと難しいやり方だと言わざるをえない――しかしそれが本来の正しいやり方ではないゆえのこと。しかしそれでも、客観的事象からおおまかながら推知できることもあるのだということを、忘れないためにも併せて示しておきたい
ここまで説明してきたのは、言葉の表現の中でも「口調」にだけ絞ったつもりでやってきたわけだが、もちろん言葉の表現、また広く言い換えれば感情表現の(これはちょっと広すぎたか)手法には、「口調」以外のそれが他にもあることを、ここで簡潔に示しておきたい。総括したら、いわゆるこれは「非言語コミュニケーション」と呼ばれているものたちなのだが、たとえば話しているときの目の泳ぎかた、仕草(身振り手振りや、またそれ以外の部分<手のもじもじ、足の組み方、自分の体躯のどこかの部分を触るなど>)、表情、姿勢、髪型や服装などの諸細目がいくつかある。これらのなにげない所作と言葉表現の意図との関係についての研究は、一般心理学との学際の域になるだろうが(どこからどこまでがそういう心理学の範囲かなど、そんなものは私の知るところではない)、しくじり行為も、口調も、この非言語コミュニケーションの研究も、人の心の解明に十分有益なるものを授けてくれることだろうことは確かであると思っている
出産外傷と去勢不安
フロイトは、不安の起源は出産外傷と去勢不安であると考えた。すなわち、出産時の苦しい体験は母親からの分離(母親の喪失)を意味し、その不安体験が原型となって、後に大切なものの喪失や危険な状況にさらされたとき、つねに不安状態として再生産されるのだ。こうしたフロイトの理論はその後の精神分析の発展過程で、母親に拒否されることが不安の原体験となるという解釈で、臨床的に広く受け入れられるようになった
自分を知る[自己分析]
自己分析とは、自分で自分の無意識を洞察し、よりよき自己支配を得る試みのこと。自己分析の構えについては下のフロイトの例の後に書く
/a エディプス・コンプレックス
フロイトが彼の理論の中心となるエディプス・コンプレックスを発見したのは、最愛の父親を亡くした後の心境を、親友フリースへの三年間にわたる284通の手紙で語りかけ、そのなかで自分を被分析者の立場において、夢による自己分析をした結果からだった
40歳で父親を亡くすまでのフロイトは、慈愛と威厳に満ちた父親に対して畏敬の念を抱き、ひたすら尊敬と愛情を捧げてきた。しかし、父の没後、自分のなかに父への憎しみが潜んでいたことに気づき、また、母親に強い愛着をもっていて、乳児期に母親の裸体をみて性的に興奮した記憶があることを思い出し、これらのことから、近親相姦願望と同性の親への両極感情が併存する心理状態にギリシャ神話にちなんだエディプス・コンプレックスの名を与えた。このフロイトのいう、人が生まれながらにしてもっている近親相姦願望、母への愛が、恋愛や母親固着の元になっているのではないか。/対して、女児が父親に対してもつ、母親に代わって父を独占したいと思う願望のことをエレクトラ・コンプレックスという
―
男の子が抱く母親への愛着と父親への嫉妬心のことを「エディプス・コンプレックス」という。男の子は異性である母親を独占したいと考えるために、父親に対して嫉妬をはじめるが、しかしまた、その父親に対しては同時に愛情の心も抱いているため、自分でも自分の気持ちがよくわからないうやむやの状態になっている。しかし独占の気持ちが大きくなると乗じて嫉妬心も大きくなり、父親に対する嫉妬心と愛情の均衡がしだいに破れてくる。そうなってくると男の子は「去勢不安」と呼ばれるような、もし母親にこれ以上の愛情を抱いてしまったら父親に去勢されてしまうのではないかという不安を抱えるようになる。この去勢不安は、男の子が、父親に対して嫉妬や抵抗する感情をもつことへの罪悪感のあらわれなのだ。こうして去勢不安によってエディプス・コンプレックスは抑圧され、「~してはいけない、~すべきだ」といった道徳的倫理観をつかさどる超自我が首尾よく形成されるもとになる
一方、女の子のほうはどうかというと、最初に男女の違いがわかってきたとき、男の子にだけあるペニスの存在に気づき、それをうらやましく思うようになって「男根羨望」と呼ばれるような感情を抱く。そこで女の子は、男の子と同様に異性(つまり女の子の場合は父親)に対して愛情を抱くようになる。これをエディプスに対置させて女の子固有の「エレクトラ・コンプレックス」という。エレクトラ・コンプレックスは男根羨望によって形成されるのである。そこでは、ペニスがない母親や自分に対しての価値を下げ、父親に愛情を強く向かわせることになる。しかし女の子の場合はそこで男の子のような抑圧はされないので、その後の超自我の形成はあいまいになる。女の子は育っていくなかでペニスがないことを理解するのだが、しかしペニスがうらやましいと思う気持ちはなくなるわけではなく、その思いは無意識のうちにエスに抑圧され、その後の自我の形成にさまざまな形で影響を与えることになる。その自我の態度は大きく三つに分けられるだろう
1 ペニスがないことが認められず、ペニスのある男になりたいという思いから、男らしい態度をとるようになる。物事に対して積極的で、自ら指導的立場に立とうとするような性格傾向をはぐくむ。しかしここで男性になりたいという気持ちが強くなりすぎると、自我がそれをしっかり抑圧することが難しくなり、結果として神経症の症候が現れたりするようになる
2 ペニスがうらやましく思うことで、次の四つの性格傾向が現われる。(1)ペニスが無い自分に失望し、自分の価値が下がり、性に対して不快感を持つ性格傾向を生む。(2)他人が持っていて自分が持っていない事に嫉妬し、他人と比較したがる性格傾向を生む。(3)ペニスがない自分を生んだ母親を恨み、ひがみっぽい性格を持つ性格傾向を生む。(4)ペニスがほしいという願望を持つ性格傾向を生む。この「父親のペニスがほしい」という願望は、のちに「父親の子どもがほしい」に変わり、さらに「愛する男性の子どもがほしい」にかわる
3 中でも(2)の4の発展はほとんどの女の子に顕著に起こると考えられるが、その結果というのは、愛する男性の子どもを生み育てたいというようないわゆる女性らしい性格傾向を形作ることになる
――
自己分析の構えについては本来の自由連想と同じで、これを妨げる最大の敵は、つねにその人の内にある。自分はなぜそうなのか、自分は本当にどう感じているのか、あるがままの自分を余す所なく明るみに出すべきである。そして、自分の気持ちの奥へ奥へ、すなわち無意識へと踏み込む勇気をもつことだ。日常的な対人関係のレベルでのある人への敵意や嫉妬、愛や甘え、依存心など、行き着いたところで自分に向き合ってみる。ふだんから自分の心の動きを細大もらさず観察する。原因がすぐわからない場合は、心のおもむくままにまかせて自由連想する。実際行動に移す。人の批評・悪口・叱責などは分析の解釈だと思うこと。そして、治るのは自分自身の力なのだと信じること。それが自分を束縛している正体をみる手段ではないだろうか
人格の三領域説[人格の三層説]
フロイトは人間の心の働きを一つの装置、すなわち顕微鏡や写真機のような組み立て道具になぞらえ、心の働きを全体として捉える心的装置論を提唱した。つまり、各部品の連繋作業によって一つの機械が動くように、人間の心の働きも、さまざまな心的要素が相互に関連しあって生じると仮定すれば、その複雑さが明らかにできると考えたのである。そこで、彼は、人間の心はエス(イド)、自我(エゴ)、超自我(スーパーエゴ)と名づけられる三つの部分からなり、それぞれ別々の機能をもつと仮定した。エスは「私は~したい」という、ただ欲するだけの本能的衝動からなる部分で、心の基底をなす。自我はそれに対し、「私は~するつもり、~しよう」といった環境と関係するときの意志の発動である。そして超自我は、「私は~すべきだ、~しなければならない、~してはならない」というような、理想的抱負や道徳的命令・禁止からなっている。フロイトは、これら三つの部分の相互作用の結果として、人間の行動が理解されると述べている。エス、自我、超自我という心の三つの部分は生まれたときからすべて機能しているわけではない。出生時には衝動が存在すると仮定してよいので、最初はエスのみが確認できる。その後、5~6ヶ月ごろになるとエスから自我の分化が始まり、3~4歳ごろになると、今度は自我から超自我が分化しはじめ、思春期前に確立すると考えられている。このように心の部分は発達の時期が異なり、発達の早い部分から層をなす。そして三つの部分がすべて発達した後に、心は自我を主体として調和のとれた全体として機能するとフロイトは考えた
/a エス
エスとは原始的な欲望が渦巻く世界で、それ自体は無意識的なものといえる。エスは、内的・外的な刺激によって衝動が生じるとただちにその満足を求め、個人を活動へと駆り立てるのが特徴だが、この場合の衝動とは興奮状態もしくは緊張状態が生じることを指す。私たちにとって興奮や緊張は苦痛や不快として体験されるため、エスはつねに緊張の即時解消を求める。つまり、衝動の満足とは、緊張が解消されることなのである。そこでフロイトは、このようなエスの働きを快感原則と呼んだ。もっぱら衝動を満足させることを求めるエスは、論理や理性、道徳、時間などには一切関知しない。こうした人間の心理過程を一次過程という。衝動がそのまま行動となって現われる新生児の存在は、エスそのものであるといっても過言ではない。つまり、意志する“わたし”というものが出現する以前からエスは無意識的に存在しているものであるといえる
/b 自我
自我は私たちのあらゆる心的活動の中心におかれる概念である。フロイトは自我を行動の主体として仮定している。衝動を満足させるためには、外部環境が必要になってくるが、その環境と関わる心の部分が知覚を媒介にして外界の影響を受け、徐々に自我として発達する。自我は現実に照らし、現実の規制を受け入れながらエスの衝動を満たすよう努力するので、その働きを現実原則と呼ぶ。そして、この原則による心理過程を二次過程という。生後まもない乳児は快感原則に支配されているといえる。たとえば、空腹になるとお乳がもらえるまで泣き続けて不快感を表現する。しかし、5~6ヶ月になると、母親に抱かれてお乳がもらえそうな気配を感ずれば泣き止むようになる。すぐに満足が得られなくとも、満足の予測ができ、衝動満足の一時延期ができるように自我が成長しているからである。こうして自我はエスをコントロールしながら外界への適応の役目を果たしている
/c 超自我
超自我は道徳原則、すなわち道徳観や価値観に支配された部分である。誕生直後からずっと両親に依存している子どもは、親の愛を失わないため、自分を禁止したり褒めたりする理想の両親像に自己を同一化し、その躾[しつけ]の内容を自我のなかに取り入れる。超自我には、「~であれ」という親の期待が内面化された自我理想と、「~してはならない」という親の禁止が内面化された良心とが含まれる。超自我が形成されると、両親に代わって自我を監視するようになり、自我に対して理想的に行動するよう要求し、エスの衝動を禁止する命令を発する。したがって、超自我が形成されると、親ではなく自分自身が自分に禁止や命令を下すことができるようになるのである。フロイトはこの超自我の起源をエディプス・コンプレックス(“ジークムント・フロイト書付”)に求めた。3~4歳頃に芽生える子どもの性愛感情は最初は異性の両親に向けられるが、同性の親の禁止によってその満足は妨げられる。子どもは禁止する親に敵意を抱くが、これを抑圧して逆に、その親に同一化し、自我のなかに取りこみ、超自我の中核を形成する。したがって超自我の厳しい人は、それだけ親の禁止が厳しく、かつ、自分が親に対して強い攻撃感情を抱いていたことを意味する
/d 人格の三領域説からみる性格判断
たとえば、あなたが若い成人であり、電車に乗っているという状況を想定してみよう。そこで、電車のシルバー席をめぐってどのような行動パターンをとるのかによって、それぞれの性格の違いを見てみる
d-1 自我の強い人
ガラ空きの電車や満員の電車で、周囲にお年寄りがいないとわかったら座る。そして、お年寄りがそばにやってきたら席を譲る
⇒つねに現実の客観状況に合わせて行動する、現実主義的な性格。合理的・理性的で、衝動に突き動かされての行動は少ない。かといって、規範にがんじがらめになることもない。衝動の解放も規則の固守も状況次第
d-2 超自我の強すぎる人
シルバー席はお年寄りの席という規則だから、空いた電車でも、自分が眠っている間にお年寄りが乗って来るかもしれないので、決して座らない
⇒良心的で、倫理観が強く、自己規制が過剰。理想や規則に忠実で、非難されるような行動は絶対に避ける完璧主義的な性格。ノイローゼ傾向がある
d-3 エスの強すぎる人
シルバー席であろうとなかろうとかまわない。自分が座りたければ座る。周囲には目もくれない
⇒衝動性が強く、現実認識が足りない。規則などもおかまいなしで、自分の欲求中心に行動する幼児的な性格。反社会的になりやすい
劣等感
劣等感には主観的な劣等感と客観的な劣等感があるが、両者はかならずしも対応しない。問題なのは、客観的な劣等性に対してそれを著しく気に病む場合である。なぜなら、劣等性を客観的に認識すること(劣等意識)は、人間にとってむしろ必要なことでもあるからだ。フロイトによれば、劣等感は、自我が自我理想の要求に沿えないときに感じるものだとしている。つまり、自我のあるがままと、「~あるべき」姿とのギャップが劣等感を生み出しているのだ。過度な劣等感は無能感を呼び起こし、かえって人間の成長を妨げる結果となる。そのときの劣等感の病的な状態を劣等コンプレックスという。フロイトの理論では、自我理想が要求水準を自我の現実水準からかけ離れて高くしたり、自我の現実を他人と比較して取るに足りないものと判断したりと、自我理想が自我に対してもっとよくなれと強要する場合には、自我は合理的な行動がとれず、自信を失い、劣等コンプレックスを形成するようになるとしている
リビドー
フロイトは、人間には思春期の性的成熟以前から広い意味での「性的」衝動が存在するといっている。リビドーと呼ばれるこの性的衝動は、最初は乳児期の栄養摂取の満足と結びついている。たとえば、乳を吸っているとき、同時に吸う行為自体に満足を味わっている。それが後に一つの自律した衝動として分離するのである。そのとき、性的衝動とは、あらゆる肉体的な快感を求める衝動にほかならない。リビドーは主に、口唇、肛門、性器の部位を通して満たされるが、ある時期には一つの部位に集中し、その部位(性感帯)は発達にともなって変化する特徴がある。ちなみに、小児にも性欲があるとする考えはフロイトによる仮説で、これを小児性欲という
a 口唇期―生後1歳半まで
乳房を吸うこと、噛むことなどによって満足を得る。子どもが十分に乳房を吸う経験が与えられるかどうかが問題となる。これがうまくいくかどうかで、受容、加虐、拒絶など、多様な心理側面を発達させることになる
b 肛門期―2~4歳頃
肛門の括約筋が発達し、排泄機能によるリビドー満足。大便の保持、貯留、排泄に関心をもつ。子どもは出すか出さないかの心理的葛藤を経験するので、排泄訓練の際のしつけの仕方が心理的な発達に影響を及ぼす
c 男根期[だんこんき](エディプス期)―3~4、5歳頃
この時期は、リビドーは性器に集中する。子どもの性的好奇心が芽生え、性愛感情を異性の親に向け、その愛を得ることに積極的になる。たとえば男児は母親の愛を獲得することに注力するようになる。女児においては男児と全く正反対で、男根期に固着すると、父親や父親に似た存在に強く惹かれるようになる。これはいわゆるファーザーコンプレックスである。また女児はペニスを持ち続けていると勘違いする事があり、これはエディプスコンプレックスの未解決に由来すると言われている。つまり男根に固着しているという事であり、こうなると女性は男性的な性格を身に付けたり、自分は男性であると考えるようになる。またその正反対にペニスが常に去勢されるという不安に怯えていると、自分は力のない女性であると考えるようになる。この子どもの異性の親に対する性的好奇心が芽生えることがエディプス・コンプレックスおよびエレクトラ・コンプレックスを成立させるが、結果的には男児も女児もそれらを抑圧し、その後、本来の性的活動が開始される思春期までの間、比較的長いリビドーの潜伏期に入る
――
男根期のあとは潜伏期、性器期(思春期)の全五段階に区別される。この発達段階を経て人間は成熟に達するとフロイトは考えた
快・不快原理―現実原理―涅槃原理
不快原理とは、快・不快原理ともいう。欲求・欲動などが発散を求めて、心的な緊張が高まっているときは不快感が感じられる。緊張をやわらげるときは快感が感じられる。個体の行動はできるだけ快を求め不快をさけようとする原理にしたがってなされる、とするのがフロイトの考えであった。フロイトは、快・不快原理はリビドーの要求およびその修正を代表するものであるとしている。これと並ぶ原理として、死の本能(サナトス)の傾向を示す涅槃原理がある(ねはんげんり。ニルヴァーナ原理とも。あらゆる興奮や内的・外的なエネルギーを無に、もしくは可能な限り最も低くしようとする心理的機能の原則{つまり「死の欲動の発現」}を指したジークムント・フロイトによる精神分析学の概念である)。また現実世界の影響によって、快・不快原理にもとづく内的な要求の充足は修正を求められ、現実適応を結果させられるが、その根底にあるものは現実原理であるとしている。健康な個体の行動はこの三原則の統合の結果と考えられている
夢
/a 夢
覚えている夢は本来のものではなく、本来のものの歪められた代理のものです。この代理物は、私どもが別の代理物を呼び起こして、本来のものに接近すること、すなわち夢の無意識的なものを意識化することに必ず役だちます。したがって、私どもの記憶が正確でなかったとすれば、それはこの代理のものがいっそう歪曲されているということであり、これにもなにかの動機があるはずです
夢は、全体として或る他のもの、すなわち無意識的なものの代理であり、夢の解釈の課題はこの無意識的なものを発見することであるということになるでしょう。そこから、すぐ導き出されてくるのは、夢の解釈の仕事をしているときにしたがわなければならぬ三つの重要な原則です
1 一見、夢がもっているようにみえる意味には心をわずらわさないこと。たとえそれが、わかりよいものだろうと、不条理のものだろうと、はっきりしたものだろうと混乱したものだろうとです。それは、けっして私どもの求めている無意識的なものではないからです――この原則には、おのずからやがて制限が加えられざるをえないことになりますが
2 われわれは夢の解釈の仕事をそれぞれの要素に対する代理表象を呼び起こすだけにとどめ、その代理表象について熟考したり、なにか適切なものを含んではいないかなどと吟味したりせず、また、それらの表象がいかに夢の要素からかけ離れていても気にしないこと
3 隠されており、求められている無意識的なものがみずから姿をみせるまでは、じっと待つこと
a-例 Tisch
ある患者がかなり長くつづく夢をみた。特殊な形をしたTisch[ティッシュ](テーブル)を囲んで自分の家族のものが何人か掛けている。このテーブルを見て、彼は、このような家具を見たのはある家庭をたずねたときだったな、と思い出した。それから彼はさらに考えをすすめて、その家庭では父と息子のあいだに特別な関係があったこと、そしてすぐにもともと同様の事情は自分と父親のあいだにもあるのだ、ということを付言した。つまり、テーブルはこの並行関係を示すために用いられたのだった。この夢についてフロイトはこう付け加えている
「この夢をみた人は、夢の解釈をずっと前からよく知っていました。そうでなければ、テーブルの形などという小さなことを研究の対象とすることに腹を立てたことでしょう。私どもは、実際に、夢のなかのものはなにひとつ偶然的なもの、どうでもよいもの、とは考えず、このようななんの動機もないようにみえる小さなことの解明から、夢の意味がわかってくることを期待しているのです。みなさんは、まだ、夢の働きが、『自分と父のあいだも彼らの場合と同様だ』という考えをあらわすのに、テーブルを利用したことを怪しんでおられることでしょう。しかし、その家族の姓がTischler[ティッシュラー]ということをおききになれば、それもおわかりになるでしょう。夢をみた人は、自分の家族たちにこのテーブル(Tisch)を囲んで席をとらせることにより、自分たちもまたティッシュラー(Tischler)なのだ、と語っているのです。それにしても、このような夢の解釈の報告には、いやおうなしに秘密をうちあけなくてはならないことに、みなさんは気づかれると思います」
/b 顕在内容と潜在思想
夢の物語るものを「夢の顕在内容」と呼び、いろいろ思い浮かぶことを追求して到達できるはずの隠されているものを「夢の潜在思想」と呼ぶ。夢の解釈することとは、まさにこの二つのあいだの関係に目を向けることなのだ。夢が潜在思想(の小一部分)を歪曲して顕在させる働きの、その歪曲の一つの仕方は、断片やほのめかしによる代理形成である。先の一例で考えてみると、家族がテーブルを取り囲む一連の夢の顕在内容が示している潜在思想とは、Tischlerの家族の父と息子の関係は私たちの家族と同様の事情であるということを物語っている。夢の顕在内容においては、この関係を示すために、私たちの家族がTischというテーブルを取り囲んでいる描写を映したと思われる
b-1 顕在内容と潜在思想の関係<夢の解釈>
無意識の潜在思想が夢を媒介にして顕在されるわけですが、ここで現われてくる顕在内容は潜在思想のなにを示していて、また潜在思想はどのようにして自身を顕在化するのかという点は、私たちがもっとも注目しているところであり、ゆえにこれは夢の解釈の目的となっています。この二つのものの関係をあらわにしてみましょう
1 潜在思想のなかで、何かしらの要素に強いアクセントが置かれますが、顕在する夢ではそれがまったくみられないという点です。主要な点そのもの、すなわち無意識的な思想の中心そのものが、顕在する夢のなかには出てこないことがありうるようです。このために、夢全体から受ける印象は根本的に変えられざるをえないのです
2 夢のなかでは、しばしば現実では起こりえないようなおかしな、意味のわからない組み合わせがみられます。たとえば夢の潜在思想のなかに<(結婚をそんなに急いで)ばかだった>という命題があるとしたとき、夢はこの「ばかだった」ということを直示的に表現することはしないのです。ではどのように表現されるのか。この「ばかだった」という思想が、顕在夢のなかへは、たとえば不条理な要素をとりこむことによって表現されるというわけです
3 顕在要素と潜在要素との関係はけっして単純なものではなく、一つの顕在要素がいつも一つの潜在要素を代表し、また逆にある潜在要素は複数の顕在要素によって置きかえられるというように、両群間の集団関係でなければならないのです
/c 夢のはたらき
夢のはたらきを知るのに、小児の夢はあきらかに単純であるから、これは恰好の研究材料といえます。一つ例を示しましょう
<三歳三ヶ月の一幼女がはじめて湖水を船でわたることになりました。船を降りるときに、幼女は船から降りるのをいやがり、激しく泣きました。湖水をわたる時間が彼女には短かすぎるように思われたからです。つぎの朝、彼女は言いました。「私は昨夜、湖をわたったの」。たぶん、私たちはこの船旅の時間はずっと長かったと推測してもよいだろうと思います>
この例からわかる夢のはたらきとはなにか
1 小児の夢は夢の歪みを欠いています。ですから、解釈の必要はないのです。顕在夢と潜在夢は合致しています。したがって、夢の歪みはけっして夢の本質を形づくるものではないわけです
2 小児の夢は残念な気持、憧れ、満たされなかった願望などをあとに残すような日中の体験に対する反応なのです。夢はこの願望に、直接的であらわな充足をもたらします
3 願望が夢を誘発すること、そして、この願望の充足が夢の内容であること、以上は夢の主要な性格の一つです。同じように不変なもう一つの性格は、夢は単純にある思想を表現するものではなく、幻覚的な体験で、この願望を満たされたものとして表現する、ということです。<湖を船でわたりたい>というのが夢をひき起こす願望の内容であり、夢そのものの内容は<私は湖を船でわたっている>ということになります。潜在夢と顕在夢との差異、すなわち夢の潜在思想の歪みは、このように小児の簡単な夢にもやはりあるのです。つまり、思想を体験に置き換えることがそれです
4 夢はこの種の刺激――つまり願望やコンプレックス――を単純に再現しただけのように見えますが、実際はそれだけではなく、その再現によってその刺激を廃棄し、かたづけ、解消するのだということです
5 眠っているときにはたらきかけられる刺激や願望は、当人を今すぐに起き上がらせて意識させようとしたり、充足させようとしているので、これらは眠りをさまたげる意向になっています。一方夢はこの意向に対称で、すなわち眠りをさまたげようとする意向を解消するはたらきをもちます。一見すると、夢は眠りをさまたげる意向のはたらきのようにも思われますが、実際には夢は私たちの気づかないところで私たちの眠ろうとする意識の味方をしてくれているのです。夕食に強く辛味をきかした食物を食べた人は、夜になって渇きをおぼえて、とかく自分が水を飲んでいる夢をみがちなものです。もちろん、食べものや飲みものへの激しい要求は夢によって解消はされません。このような夢からのどが渇いて目がさめ、こんどはほんとうの水を飲まなければならないのです。夢の働きはこのような場合には、ほんとうは大したことはありませんが、それでも目をさまして行動を起こさせようとする刺激に対して、眠りを保持しようとするために夢が招集されているのだ、ということは同じようにはっきりしています。これらの欲求がもっと弱いものであると、欲求充足の夢がしばしばこれを取り除いてくれるというわけです。私たちがともかくある程度まで熟睡できるのは、むしろ夢のおかげなのです。騒音をたてて私たちの安息をさまたげる連中を追い払うために、夜警がすこしぐらい騒々しい音をたてるのはやむをえないのと同じで、夢も多少じゃまになるのは仕方がありません
性的倒錯
私たちが成人の生活のなかで「性的倒錯」と呼ぶものは、正常のものとはつぎの点でちがっています。すなわち、第一には種の限界(人間と動物とのあいだの深淵)を無視していること、第二には嫌悪感の限界を超えていること、第三には近親相姦の限界(血縁者に性的満足を求めてはならないという禁制)をふみ超えていること、第四には同性愛をなんとも思わないこと、第五には性器の役割を他の器官や身体部位に置きかえていることです。これらの制限は実は最初から存在するものではなく、幼児の発達と教育のなかでおもむろに形成されてくるものです。幼児はこのような制限にはとらわれてはいません。幼児は多形倒錯のものと呼ぶことができるのです
フロイトのお話
フロイトは厳格だがとても理知的です。そしてメタ認知に長けています。以下はフロイトが自身の体験とそれについての考えを述べたものです
多忙な精神分析医の場合ですら(自分を指している)、診察時間はあまりにぎやかでないのが普通だと聞かされても、べつにみなさんはふしぎとは思われないはずです。私は、待合室から診察室とを兼ねた室へ行くあいだのドアを二重にし、それにフェルトを張って丈夫にいたしました。このちょっとした仕掛けの目的につきましては、もちろん疑問の余地はないでしょう。ところで、私が待合室から呼び入れる人たちは、いつも必ず自分の後ろのドアを閉めるのを忘れます。しかも、ほとんどいつも二重のドアの両方ともあけっぱなしにするのです。それに気づくと私は、はいってくる患者に、それがエレガントな紳士であろうと、大いに着飾った婦人であろうと、かなり無愛想な調子で、もどってドアを閉めるように要求します。これは度のすぎた几帳面さという印象をあたえます。患者のこうした不注意なふるまいは、待合室にいるのが自分一人で、自分が出て行けば部屋がからっぽになるという場合にだけ起こるのです。ほかの人、すなわち、未知の人がいるときにはけっして起こりません。だれかいる場合、患者は自分と医師との話を盗み聞きされないように、心を配らねばならないことをよく知っていて、二つのドアを丁寧に閉めることをけっして忘れないのです。そういうわけですから、患者の手ぬかりは、けっして、偶然でもなければ無意味なことでもなく、ましてや重要でないどころの話ではありません。というのはこの行為が、部屋にはいってくる患者の医師に対する間柄を明らかにするものだからです。患者の大多数は、斯界[しかい]の権威者の世間的名声にあこがれて、眩惑され威圧されたがっています。患者はきっと電話で、いつうかがえばすぐ会ってもらえるかと問い合わせ、ユリウス・マインル(オーストリアの食品輸入販売業者)の支店の前のように、治療を求める人々が群がっているさまを覚悟していたことでしょう。ところが、いざ来てみると待合室はからっぽで、そのうえ、家具調度もみすぼらしいのでがっかりしてしまいます。彼は、こんな医者によけいな尊敬を捧げようとしたことのしかえしをしようというわけなのです。――そこで待合室と診察室とのあいだのドアを閉めることを怠るのです。彼はそうすることによって、医者に対して、「なんだ、ここにはだれもいないな。自分がここにいるあいだにも、たぶんだれ一人来やしないだろう」と言っているつもりなのです。ですから、即座に彼のこの思いあがった気持にきつい訓戒をあたえて押えておかなければ、治療の話し合いの最中に、無作法で不謹慎なふるまいをするにちがいありません
ノイローゼ
a ノイローゼの症例
患者は三十近い婦人で、強度の強迫現象に悩んでいました。この婦人はほかの症状もありましたが、とくにつぎのような注目すべき強迫行為を日に何回もしていたのです。彼女は自分の部屋から隣の部屋に駆け込んでゆき、その部屋のまんなかにあるテーブルのそばの一定の場所に立ち、ベルを鳴らして女中を呼び、どうでもよいような用事を言いつけるか、なにも言いつけないままでひきとらせてから、またもとの部屋に駆けもどるのです。これは重大な病気の症状でないことは確かでしたが、それにしても好奇心を刺激せずにはおきませんでした
私が患者に、「なぜあなたはそんなことをするのですか、それはどんな意味なのですか」ときくたびに、彼女は「わかりません」と答えました。ところが、ある日、私が彼女の心の底にある、行為に関係あることを物語るようになりました。十年以上も前に、彼女はずっと年上の夫と結婚したのでした。ところが、婚礼の夜に夫がインポテンツであることがわかりました。その夜、夫は何度も自分の部屋から彼女の部屋に駆け込んできては、くりかえし試みましたが、すべては失敗に終わったのです。つぎの朝、彼は腹だたしげに、「こんなことでは、女中が寝床をかたづけるときに恥をかかなければなるまい」と言いながら、たまたま、部屋においてあった赤インキの瓶をつかんで、その中身をシーツの上にこぼしました。しかしそれは、その種のしみが当然つくべき場所につかなかったのです
最初のうち、私はこの記憶が問題の強迫行為とどう関係するのかがわかりませんでした。私は一つの部屋から他の部屋へ何度も駆け込むということと、そのほかに女中が登場するということに一致点をみただけだったからです。そのとき患者は、私を隣の部屋のテーブルのところにつれてゆきました。テーブル掛けには一つの大きなしみがついていたのです。彼女は、「私は、呼びつけた女中がこのしみを見のがさないような位置に立つのです」と説明しました。こうなれば、結婚初夜の情景と現在の彼女の強迫行為とのあいだに、密接な関係があることはもはや疑う余地もありませんでしたし、その上にまたこれによって、いろいろなことを学ぶことができたのです
とくにはっきりしているのは、患者が自分を夫と同一視していることです。現に、彼女は、一つの部屋から別の部屋へ駆け込むという動作をまねることによって、夫の役を演じています。それから、あくまで同一視という観点に立てば、彼女がテーブルとテーブル掛けとをベッドとシーツの代理にしていることを認めなければなりません。これは恣意的な現象のようにみえるかもしれませんが、私どもは夢の象徴性の研究をいたずらにしたわけではないのです。夢のなかでも、同じように、非常にしばしばテーブルが出てきますが、テーブルにはベッドと解釈することができます。テーブルとベッドは一組となって夫婦関係を意味しますから、その一方は容易に他方の代わりになるのです
この婦人の強迫行為の核心は、明らかに「これでは女中の前で恥をかかなければなるまい」と言った夫のことばとは裏腹に、女中を呼びつけて、しみを見せつけることにあります。つまり夫は――彼女がその役を演じているのですが――女中に対して恥をかかないように、しみは正しい場所につけてあるのです。ですから、彼女はある場所をただ単に反復していたのではなく、その場面の先をさらにつづけながらこれを修正し、正しい方向に向けていることがわかります。こうすることで彼女は、また同時に、あの夜赤インキによってその場しのぎをする必要があった痛ましい事実、すなわち夫のインポテンツをも修正しているのです
つまり、この強迫行為の言いたいことはこうです。「いいえ、それは真実ではありません。夫は女中に対して恥をかくことはなかったのです。夫はインポテンツではありません」ということです。彼女はこの願望を、夢の場合のやり方にしたがって、現在の行為のなかで、すでに実現されたものとして表現しています。彼女は夫をあのときの不運からのがれさせたいという気持に奉仕しているのです
疾病利得
疾病利得とは、たとえば、病気を理由に適応困難な現実からの逃避が許されるように、病気であるために得られる利得をさします。疾病利得をさらに二つに分けてみると、両方とも自分が病気であることを口実に利得を得ようとする点においては同じですが、まず個人的充足のための利得をもくろむ「一次的疾病利得」と、それから近所や社会にうまく適応するための利得をもくろむ「二次的疾病利得」があります。一次的疾病利得が無意識・短絡的、そして快感原則にのっとっているのにたいして、二次的疾病利得はより現実適応的、計画的、社会的な意味を帯びています。また一次的疾病利得のほうは、もっぱら個人的な願望充足のためだけにはたらくものでいわゆる“逃げ道”にしかならず、現実的には非適応行動という結果になります。例を示しましょう
/a 一次的疾病利得[個人的充足]の例
夫に手荒く取り扱われ、手心を加えることなくこき使われる妻で、ノイローゼになる素質がある場合、またはひそかにほかに好きな男性をつくってみずからを慰めるというにはあまりにも臆病であるとか、あるいはあまりに貞淑である場合、そして、あらゆる外的なじゃまを排して夫と別れきるほどには強くもなく、自活したり、もっとましな夫を得るとかいう見込みがないうえに、彼女が性的な愉悦のために、なおこの残酷な夫に執着をもっている場合には、ほとんどきまったようにノイローゼに逃げ道を求めるものです。彼女の病気は、いまや強すぎる夫に対して戦う武器になります。この武器を彼女は自分をまもるためにも用いますが、復讐のためにも用いることができます。彼女はおそらく自分の結婚生活について訴えることは許されなかったでしょうが、自分の病症について訴えることは許されるわけなのです。つまり彼女は救いを医師に見いだし、ふだんは自分をかまってくれない夫に、自分をいたわるようにさせ、自分のために費用を出させ、自分が家を留守にして結婚生活の抑圧から自由になる時間をもつことを、許さざるをえないようにさせているのです。このような外的あるいは偶然的な疾病利得がほんとうに莫大なものであり、現実にその代償を見いだしえないほどのものである場合には、<みなさんはみなさんの療法によってノイローゼに影響を与える可能性を、大きく見積もってはならないでしょう>
/b 二次的疾病利得[適応的利用]の例
自分の生活の資をかせいでいるある有能な労働者が、仕事中に事故にあい、障害者になったとしましょう。いまはもう労働はできません。しかし、結局のところ、彼はわずかながら傷害年金を受けつつ、自分の障害を利用して乞食をすることを覚えるようになったとします。彼の新しい生活は零落したものではありますが、そのよりどころは、ほかでものない彼の最初の生活を奪ったものなのです。もしみなさんが彼の障害を除きえたとすると、さしあたりは、彼の生活の資を奪うことになってしまいます。というのは、彼には以前の労働をふたたびとりあげるだけの能力がまだあるかどうか、という問題が起こってくるからです
フロイトの言葉
「夢は眠りをさまたげる刺激に対する反応です」<ジークムント・フロイト>
自由連想法について――
「思いつきには選択の自由があるようにみえるけれども、実際にはどんな名前であれ、それを思いつくときには被験者の手近の事情、特異性およびその瞬間の状況に強く制約されていることがわかるものだ」<ジークムント・フロイト>
「『小児はエゴイズムによって愛することを学びとった』。小児は最初はまさしく自分自身を愛するのです。はじめから小児が愛するようにみえる人物であっても、実は彼にとってその人物が必要だし、欠くことができないものだから愛するのです。それは大人になっても変わることはありません」<ジークムント・フロイト>
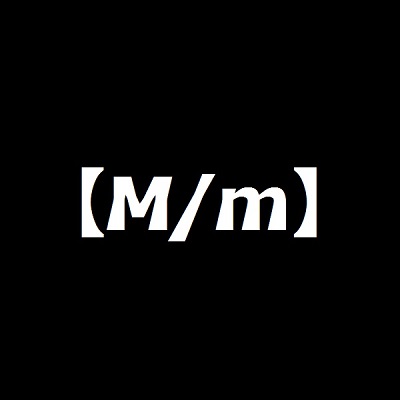

 TOP
TOP