【お知らせ】「ユーモア」を追記しました(2016/09/06)
ここでは、形式、関係、差異、観念、精神、思想、情報、論理などについて書く
目次
分別生成の相互要因
「あれは~だ」というような類の言葉には「分別」という属性が備わっている。分別的説明には二種類あって、あれを指すものが直接何らかの事物である場合と、単に線を引くだけの分別である場合である。どちらにおいても分別属性には少なくとも二つの立場からの考察がみられる。一つは“あれ(分別対象)”の待遇変化。もう一つはあれ以外の外部分別対象(分別対象B)の待遇変化。分別によって生じる少なくとも二つの変化は、相補的に一つの目的を結実している。その目的というのが分別なのである。ただし意図的な分別においては、これはあくまで環境変化後に形成される目的であって、分別要因そのものになりうるわけではない。自然発生的な分別の場合は、それぞれの分別対象の待遇変化を帰納的に考えることによって分別要因をはっきりさせる方法がとれる
(例) 分裂生成のプロセスには、異常者の社会不適応を引き起こした重要な要因としてだけでなく、正常者を適応者の集団に同化させた要因としても考察されることになる
/a 二重の情報性
先ほどは相互要因の話をしたが、相互要因がみられるということは、言い換えれば二つの要因を説明できるようになるということだ。一つの分別的説明が二つの要因を生む。これは分別的説明だけに限らずほかのことでも言うことができる。例えば、Aが心のなかで思うものを、Bが質問しながら当てていくゲームをする場合。「あした」というのが答えだとする。Bは最初に「それは抽象的なものですか?」ときく。Aは「イエス」と答える。その答えで、Bには二重の情報が手に入る。抽象的なものだということと、具象的なものではないということの二つがいっぺんにわかるわけだ。一つの質問で、二つの情報が手に入る。よって二つのうちから答えが選べる。二つめの質問で、今度は4つのうちから答えが選べる。知識の世界はこのように掛け算で進んでいく性質をもっている。ちなみにこれは知識とは何か、についての知識(一つ上の論理階型の「メタ知識」)の一つをかすめとっている例でもある
主客観認識論
幅広く全体を把握するには、主観的観点と全体の関係性(客観的観点)の二つの視点からみることが重要である。人は意識しなければ、自分中心の――または相手の立場に立った――主観的観点で物事をみる癖がある。なので今回は、全体の関係性を見る見方、「客観認識論」を主役に論じていきたいと思う
まずは主観的観点と客観的観点の違いを洗いざらしておこう。AがBを引っ叩いてBが泣く例を考えてみよう。主観的観点では、AとBのそれぞれの視点から捉える。Aの視点は「私はBを叩いた」、Bの視点は「私はAに叩かれて泣かされた」。次に客観的観点では、AとBに起きた出来事のインタラクション(相互間情報)を記述する。「AがBを叩いてBが泣いた」。重要なのは、客観的観点では感情移入や偏見が介入することはないということだ。あくまで相互に起きた出来事のインタラクションのみを述べることに徹底される。科学や法律など、中立的で広い概観を見渡す立場が求められる分野では、感情移入や偏見を排除できる客観的観点が重宝される。しかし重要なのは、主観的観点と客観的観点のどちらも活用する必要があるというところである。その理由は、両者が相補的な関係にあるからだ。無感情な主観的観点は、単純であり、その場合は二つの――または複数の――主観的視点は、その出来事の一つの客観的視点とイコールになる。先の例でいうと、主観的観点の「私はBを叩いた」「私はAに叩かれて泣かされた」と、「AがBを叩いてBが泣いた」という客観的観点は、互いに同じ出来事についてのみの記述に終始している。主観的観点の特性が現われていないこの限りでは、単に客観的観点のほうがより簡便だという結論に至るのみだ。主観的観点の特性とは、それぞれの視点に立つからこそ得られる「非画一的な感情的視点」である。この特性は、場合によって長所ともなるし短所ともなる。Aの視点からは「私はBを軽く叩いた」であるかもしれない。Bは「Aに強くぶん殴られた」であるかもしれないのだ。こういった非画一的な感情はほんとうに重要だと思う。生物学の分野では、コクマルガラスが相手を睨む行為にはどういう意図があるのかを解明するには、コクマルガラスからの主観的視点に立ってみないと一向に分からない。いくら客観的観点からコクマルガラスが睨んでいたと証明することはできても、なぜ睨むのかという疑問には、主観的視点からでないと証明できない。ある程度は客観的観点から「なぜ睨むのか」という問いに答えを与えることはできるだろう。相手が攻撃してきたからとか、エサを奪うためだとか、確かにもっともらしい答えであるし、おそらくそれが本当の答えだろう。だが百%ではない。百%でない以上、解明したことにはならない。これは主観的観点を取り込めない場合全てに当てはまる公理である。その意味では「科学」にも当てはまる。科学は決して万能ではない。なぜなら、科学は光の速度が速いことは証明できても、なぜ光はそれほど速いのか、という問いには答えられないからだ
/a 主観的観点と客観的観点の相補的関係
主観的観点がもつ独自の特性が、「非画一的な感情的視点」であることは説明した。では客観的観点がもつ独自の特性とは何だろうか。それは主観的観点の特性の正反対の特性である。つまり、感情移入や偏見がない「画一的な視点」ということだ。両方の視点から同時にみることで、お互いがあぶり出す長短からそれぞれ短所だけを相殺する働きがある。客観的観点が、主観的観点による「事実を歪ませるほどの強い偏見」をけん制する。逆に主観的観点は、客観的観点からはみえない「非画一的な感情的視点」という新しい一面で、空いている事実の穴を埋める。このような相補的関係が成り立っているからこそ、お互いの存在なしには前進することができないのだ
/b 高次の認識論
ゲシュタルトな認識論は論理的である。それは主観的観点と客観的観点を融合して昇華させた高次の認識論ともいえよう。それを説明する前に、主観的観点と客観的観点の関係について少し述べておきたい。まず、複数の主観は、一つの客観に包摂されており、その一つの客観はまた一つの主観である、ということができる。このような論理階型の概念が、主観―客観の関係のコンテクストに存在している。そのコンテクストというのは、主観―客観という一つの階型に付加する一つのコンテクストである。そこで主観と客観は同じ階型に属する対概念ということになるのだが、それは実にも真実といえるだろう。しかし私には、主観と客観の間には対等ではない上下関係があると感じられる。高次の認識論を語るまえに、我々には「客観的観点」だけでも少し高次の認識論のように感じられてしまう、一つの主観的偏重について考察しておく必要がある。その主観的偏重の要因について、理由をいくつか述べておこう
(1) 客観的観点には、主観的観点にみられる重複のμファンクション(“グレゴリー・ベイトソン書付”)がないため簡便である。「私はBを叩いた」、「私はAに叩かれた」という二つの主観的視点は重複したμファンクションである(かといって主観的観点は、主観的観点であるがゆえに、μファンクションが重複するメッセージそのものを削るわけにはいかない)。一方、客観的観点では「AがBを叩いた」という一文のみでインタラクションが成立する。ただしこれは、「非画一的な感情的視点」が発生しない単純な主観的観点が用いられる場合についてのみ成立することを確認のこと
(2) 全体の把握において特に重要なのは、あくまで全体の関係性を考慮に入れることであり、その意味で主観的観点にはその特性がほとんどみられない。主観的観点の中でも、立場話法(“話法”)は客観的観点に近いといえる。客観的観点によるメッセージには、μファンクションが前面に出るという独自の特性がある
(3) 人は意識しなければ、自分中心の――または相手の立場に立った――主観的観点で物事をみる癖があるため、どうしても主観的観点を多用しがちだ。そういう意味で、客観的観点にまだまだ未開拓なところが多いというところをみても、希少価値が高い
―
以上が、客観的観点が少し高次の認識論であると思うことの理由である。さて、この項で述べたいのはさらに上の高次の認識論についてだ。それが主観的観点と客観的観点を融合した昇華物であることは先に少し触れた。複数の主観的視点からの考察と、ゲシュタルトをみる客観的観点からの考察、これらを同時に行うことで、一つ上の階型の「メタ観点」を新たに作り出す。これを私は「主客観認識論」と呼びたいと思う。この高次の認識論は、主観でも客観でもない。哲学上では主観ということになるだろうが、私が言いたいのはそういうことではない。どちらの観点かということではない。どちらかではなく、どちらもなのだ。主客観認識論の構成としては、その都度、複数の主観的視点と一つの客観的観点を合わせて組み立てるので、そんな観点は構成不可能だという人もいるだろう。しかし論理的には可能なはずだ。確かにできないことはない。だが未完全なシロモノとして役に立たないということが多く出てくることはあるかもしれない。それらがもはや、主客観認識論として定義づけられないということになるかもしれない。おそらくその失敗は免れないだろう。主客観認識論の未熟な点を次に述べていこう
/c 客観はいくつあるか
まず、「主客観認識論」とは何を目的とするかを考えてみよう。この認識論の目的とは、幅広く全体を把握する――おおよそ全体の関係性と複数の感情的視点による――ことで、より事実に近いことを把握しようとすること、であると思う。これは、幅広く把握することでより事実に近づける、すなわち「部分は(部分である限り)全体を知ることができない(全体が部分を知る)」という公理に基づいている。もちろん、この公理そのものに疑いの目を向けることは明達なことだ。だが未熟な点はそれだけではない。主客観認識論の一部をなす「客観的観点」、この客観とはそもそも何なのか。ここの概念は、誤解の余地のないほど明快に定めておく必要がある。我々は客観、客観とまるでカラスがわめくように繰り返し多用するが、そもそも客観とは何か。最初に客観的観点について定義したのは次の項目だった
・相互の出来事のインタラクション(相互間情報)を述べる。つまり全体の関係性のみを記述する
・情報の中でも、主観的観点にみられる「非画一的な感情」を排除した類のコンテクストを扱う。そうすることで、感情移入や偏見を避け、できる限り中立的な立場をとる
「コクマルガラスは黒い」。これは一つの客観的観点だ。では客観というものの見方はいくつあるか。別の第三者は「いや、コクマルガラスは白い」というかもしれない。このような客観的な見方は果たして中立的といえるだろうか。「私にとってはコクマルガラスは黒く見えたんだけど、あの人にとっては白く見えたんだろう」。情報を生み出すには、“あるものはあるもの”と画する「定義づけ」が必要である。ただし基底的情報というものがあり、それについては例外である。「あるものを見た」、この時点では“あるもの”に対して定義づけを行っていないので、私が「あるものを目にした」という単なる出来事にすぎない。この際、“あるもの”に「“あるもの”という情報がない」という情報を付加させている。これを「基底的情報」と呼びたい。これは無意識の脳の働きである。さて、では「定義づけ」とはどのようなものを指すか。私が「あるものを目にした」という出来事において、“あるもの”に、私が“コクマルガラス”という情報を付加させる。これが「定義づけられた情報」であり、基底的情報以外の情報は全てこれを指す。つまり、情報を生み出すことから、一つの客観的観点の始原となるのだ。様々な人間がいる中では、さまざまな情報(偏重)が生み出され、それにともなって複数の客観的観点が生まれることになる。これでは客観的観点によって中立的な立場が取れないため、人間は中立的な客観的観点を保持するために「定義づけられた情報」にさらに定義づけを行う。こうして中立的とする線引きを行い、それを大衆化させることで、より多くの人が一つの客観的観点を共通認識するように固まっていく。こうして、一本にしっかり線引きされた情報が、普遍的客観となって、やがて常識化していくのだ。科学分野や法律などがその代表的な例だろう。私が言いたいのは、客観は複数の主観から成っており、その意味では客観は、「客観というお面をかぶった主観」であるということだ。したがって、「画一的な感情」のコンテクストだとか、全体の関係性のみを記述する中立的な立場だとかいう客観の定義づけは、あくまで理想のお話の中にすぎない概念ということである。また、そもそも客観的観点というものの見方を人がすることは不可能だという二つ目の問題点も挙げることができる。この点については、客観的経験は存在しない(“グレゴリー・ベイトソン書付”)を参照されたい。「主客観認識論」は、このようなあやふやな概念らの上に立つものである以上、未熟な問題点を差し置いておくわけにはいかないのだ
性質と情報の出自とパターンとその認識論的誤謬について
性質と情報とは何か。その出自と性質について考察する。その上で厳密的基底的な人の認識論の誤りについても指摘したい
/a 情報とは何か
(1) 情報とは出自が対象との間の関係上にあるもので、対象同士が関係し合っている状態のときにしか存在しない(この点はd-1に詳しく述べる)。ただし対象の一方は知覚機能を有している生物であること
(2) 情報は性質の点と点を結ぶ(この点はcに詳しく述べる)
(3) 情報が発生するのは両者の性質が共に知覚可能であること。知覚可能な性質とは、観察者によって「差異(の知らせ)」が知覚できるほどの程度か否かによって決まる。人の顔はみなあれほど違うのに、ハエの顔はみな同じに見える。知覚される差異(外界の差異)がそのまま情報となる
(4) 情報は対象同士を結びつける、ということだけに存在理由がある
/b 性質とは何か
(1) 性質とは出自をそれぞれの対象が持つ形式のことで、いわゆる属性と呼ばれるもの。性質は情報とは違い、常に対象の中にあるものだが、外部に対して何らかの働きかけを行うものではない。したがって外部から感応されない限り、それは(存在はしているが)存在しないようなものである
(2) また、性質は情報(相互作用)を結ぶ点となる(分かりやすいように「点」と表現した。点といっても実体でもなければどこにあるのかという問いも存在しない)。性質以外のところは外部から知覚されない。性質以外の部分があるのかさえ私にはわからない
(3) 知覚機能を有している生物の、「思考」に対する性質の性質(メタ性質)について一つの特徴が述べられる。それは性質が“<その>情報が反応しやすい性質”をもっているということ。このメタ性質こそが性質を性質たらしめる所以であると思う(この点についてはd-2に具体的に述べる)
/c 情報は性質の点と点を結ぶ
リンゴを想像せずに赤を想像することはできる。それは「赤」という色についての情報を人が記憶しているから。しかし「リンゴの赤」の“赤”という情報については、リンゴを想像しなければ得ることはできない。赤を想像して「これがリンゴの赤だろう」と思ったとしても、その時点でリンゴについて想像していることになる。これは正確さの問題ではない。リンゴという情報を間接的にでも認識しているならば、色が緑だろうと紫だろうとそれはその人にとってのリンゴで、その場合リンゴとその人の間には「情報」という概念でもって相互作用が働いている。リンゴを考えるにはリンゴを知覚しなければならない。言い換えれば、リンゴの情報を発生させるには、リンゴの性質を思考しなければならない(あえて「思考」という表現をとった。性質は知覚し思考されてはじめて認識に至ると考えられるため)。このように、「情報」は互いの性質――人の「リンゴについての情報の認識」と、リンゴの「<その>情報が反応しやすいある種の性質(リンゴがリンゴと知覚される性質)」――が関係を持ったときに発生する。ということは、「情報」という概念は、互いの性質が関係を持っているときにしか発生しない
/d リンゴはなぜリンゴなのか
「(人が)リンゴを見て赤いと感じた」
上の例を使って「性質」と「情報」を具体的に説明していきたいと思う。前提として、リンゴという対象は知覚される性質(という基本的な性質)をもっている、ということを確認のこと
d-1 リンゴはこのリンゴの情報と一致する
まずは情報について。情報の出自が対象との間の関係上に存在することを証明する。「リンゴが赤い」というのは、リンゴが赤いのか、それとも人がリンゴを赤いと認識するのか。まず「リンゴが赤い」というのは人がリンゴに対して持つ情報の一つにすぎない。リンゴは赤くない。リンゴが“「赤い」という情報が反応しやすい性質を持っている”と言うのが正しい(かといって実際リンゴが人に対して何らかの働きかけを行うわけではないが)。リンゴは人との相互作用を持たなければ、ただそこに“ある”だけなのだ。なんの理由もない。なんの情報も持っていない。いかなる性質も外部に対して働きかけを行わない。だから「リンゴが赤い」というのは厳密的基底的には――「赤い」というのはあくまで人の認識上であって――「リンゴそのものが実際に赤い」わけではない。つまりここで言っているのは、リンゴが対象に知覚されるということと、<その>情報が反応しやすい性質を有していなければ、人はリンゴについての情報を引き出すことはできないし、人が、リンゴのその性質を知覚し、<その>情報が反応する性質を有していなければ、リンゴがいくら素晴らしいモノでも、その存在を知覚することはできないということだ。お互いの性質が相互に働きかけを行わないのにもかかわらず、結ばれ合うことができる原理が少しお分かりだろうか。物理的空間的な見方で言えば、お互いは磁石のような動きでもって一方が一方に(お互いに)同時に働きかけを行っているようにみえる。しかし形式的概念的記述でいえば(性質と情報と関係は実体ではなく形式であるため、こちらの記述のほうが実際はより正確なのだが)、お互いの性質のベクトル(理由)が一致しているため、お互いが「働きかけ」という運動をわざわざ行わなくても、両者は必然的な理由をもって必然的に関係を持つという状態に成り得るのである。ところで、「情報」が互いの性質が関係を持っているときにしか発生しない以上、情報をどちらか片方の側が持っていると考えるのはおかしい。これが関係の原則である。つまり「関係」という概念がどちらの側にあるのか、などという問いはナンセンスだということだ。「関係」はそのどちら側にあるというものではなく、両者の間の関係上にあるある種の“つなぎの概念”と呼ばれるようなものなのだ。そして「情報」は少なくともその特徴を含んでいる。「情報」もまた「関係」と同じカテゴリーに属する類の概念であるということができる
d-2 リンゴをリンゴと認識する過程
双方の性質の点と、それを結ぶ「情報」の働きについて述べる。リンゴをリンゴと認識する過程はどういうものか
(α) 人の側の性質――人の中に、リンゴについての情報がありその情報が反応するものである、という性質。この性質があるから人の側でリンゴが認識できるのだ。リンゴについての情報が全くないということはあり得ない。リンゴを見たことがない原始人でもだ。リンゴを見る前に、土地を見て実体の概念を知覚し、土地の色を見て色の概念を知覚しているからだ。したがってリンゴそのものが初見であっても、リンゴが持つその類の性質――実体や色といった多くのモノが持つような普遍性の高い性質――をすでに知覚しているため、リンゴについての情報が全くないということはあり得ない
(β) リンゴ側の性質――“(人が)<その>情報が反応しやすい性質”をリンゴが持っている、という性質。“その情報”とは、リンゴをリンゴとして認識する要因となった、人の中にあるリンゴについての情報のこと。間違ってほしくないのは、“リンゴをリンゴとして認識した情報(たとえば「あれは、リンゴだ!」)”は含まれない。その事後情報を引き出すきっかけとなった“リンゴについての情報”が“その情報”なのである
―
先ほど私は、情報は性質の点と点を結ぶと述べた。つまり上の(α)と(β)両方の性質が存在し、かつ(必然的)相互作用が働いてはじめて、人はリンゴをリンゴと認識でき、同時にリンゴはリンゴとして知覚される、という過程が成り立つのである。ここで相互間で情報が発生しているのにも注目されたい。もし人の側で“リンゴについての情報”があったとしても、リンゴ側のほうで“その情報が反応しやすい性質”をもっていなければいかにしてリンゴをリンゴと認識することができようか。リンゴは人にとってリンゴであるからリンゴなのだ。リンゴがリンゴとして認識されなければ、リンゴはリンゴではない。ただし、リンゴとして認識されなかったとしても、その“もの”はそこに存在する。したがって、リンゴその“もの”は実体であり、認識されようとされまいとその“もの”はそこに存在する。だが一般にわれわれが指すリンゴの、赤いという「色」や丸いという「形」や250gという「重さ」や美味しいという「食味」は、リンゴそのものではなくリンゴに対する(勝手な尺度の結果の)情報そのものを指しているだけなのだ
/e 価値
私たちが示している価値は常に相対的である。価値には相対性[基準]がなければならない。強いというのはどんな基準に対して強いのか、何に対して強いのか、そのような基準を設けなければ価値は仮定できない。価値とは、優劣という基準を含ませた情報である。したがって価値の持つ相対性とは、「差異の知らせ=関係」そのものを表している
強い・弱いは価値の一例であるが、これらが絶対的な値をとることはない。今回の台風は前回の台風に比べて勢力が強いといったとき、今回の台風は“強い”という価値を与えられる。ところが次に来る台風は今回の台風よりも強いかもしれない。もし本当にそうだとしたら、今回の台風は次に来る台風よりも弱いと言う必要が出てくる。価値は相対性を持つがゆえに、またそれが関係であるがゆえに、その示し方はいつも同じではない。性質のように絶対的な値で示せるものではない
ものの価値が人によって変わるものであるなら、そのものに価値はない。あるのは性質だけだ。情報、関係、価値は、あくまで性質を計る手段にすぎない
外形形態と関係形式
(例-a)
「鶏肉のシチューを食べる」「ペットのニワトリの肉と、スーパーで売られている鶏肉は同じ鶏肉か」
この異なる二つの文がもし関係付けられるとして、その要因で考えられるのは、文字や単語などの「外形形態」か、意味やメッセージなどの「関係形式」の主に二通りがある。たとえばこの例で、外形形態として挙げられるものは“鶏肉”という語。“鶏肉”という単語は両方の文に共通して含まれている。ゆえに“鶏肉”という外形形態によって両者は関係づけることができる。一方、関係形式として挙げられるものは“意味”や“メッセージ”と呼ばれる部分だ。ここではその具体的な内容は省くが、意味やメッセージは外形形態とは違って目に見えるものではないため、両者が関係づけられるかどうかは、その時その人の主観にそれぞれ拠るものである。この外形形態と関係形式は、それぞれ別の論理階型に属する
(例-b)
「理解されてなおだろう」の文が、「理解されていないだろう」の誤変換ではないかと疑った場合。声に出して読み上げたときの発音の類似を、その理由と挙げる方法が外形形態である。一方、“なお”が“いない”をタイプミスしたものなのかどうかを証明するために、キーボードのタイプによる類似――“なお”なら「nao」、“いない”なら「inai」――を見るやり方が関係形式ということになる
――
外形形態と関係形式は物事の印象形成の基礎のはたらきの一つである。人は関連性の高い二つの物事に対しては、ほかにも共通する点があるはずだと思い込むことがある。ひるがえっていえば、ある物事と類似する別の物事の性質は、ある物事の特徴づけに関して重大な影響を与えるということである。これは印象形成の基礎になっている。しかしその基礎の原理はおよそ合理的とは言いがたい
消えていく概念と消えていかない概念
消えていく概念――概念とは性質が宿る主体の意で、そこには情報や関係といったものも含まれる――と消えていかない概念がある
消えていく概念とは、たとえば記憶する速度、頭が良い[天才]、善悪、好悪、優劣などを指すが、これらの概念の正体は、情報や観念と同じように、もとは概念そのものも人が作り出した人工形体だったのだろう。もちろん消えていく概念に付属する性質も、人による解釈の産物だと思われる。例えば頭が良いという性質は、その時々で、人の解釈によって定義付けられる意味が異なる。その性質が発生するときも人の都合によるものだし、またその性質が変化するとき(別の意味を持つとき)、その性質が消失するときも、やはり人の都合に左右される。これはなぜなのか。それは、その類の概念・性質が人間の観念の一部だからだ
一方消えていかない概念とは、記憶(思い出に関する情報)、(差異の知らせの)差異、物体同士が関連されたときのその何らかの不可視的あるいは形体的なつながり(人々はそれをエネルギーと呼ぶ)などを指す。つまり消えていかない概念が消えていかないわけは、人がその概念を知覚できようとできまいと、そこに存在している(はずである)概念だからだ。リンゴ特有のあの赤色は、人がそれを知覚すれば「リンゴは赤い」と認識するだろうが、人がリンゴを知覚しないからといってリンゴの赤は消えてなくなるわけではない。なぜならリンゴの赤色そのものは、人の観念ではなく、リンゴの性質であるからだ――厳密には赤色はリンゴの性質ではないのだが、ここではそれ以上言及しない
生きるうえで必要のないこと
「誰もいない森の中で樹が倒れたら、音はするのだろうか?」と物理学者に聞けば、「そんなことはどうでも良いでしょう。誰も見てないんだから」と答えるそうだが、生きるうえで必要のないこと、それはもしかしたら、それを必要とする者は科学者や哲学者に限られるのかもしれない。わたしたちは知っている。満足した猫は悩みを抱えた芸術家よりよき人生を送ることを。それでも、真理を追究しようとする人がいるのも、わたしたちは知っている
/a 性質の誤りやすい例
仮に輪廻転生がほんとうだったとして、世代間をこえてある種の魂(いったいどんな種だというのだろう)が受け継がれているのだとしたら、その魂は“受け継がれていること=つながり”を証明しなければならない。なぜなら、輪廻転生を証明するのは魂ではなく、魂が持つ“つながり”という性質だからだ。自己が継続して存在するかどうかは、心理的な継続性によるのであって、魂などというあやしげな非物質の実体によるものではない。これは、あらゆる物事について述べている。この事実がわかられるには、やはり実体と性質の意味が理解されてなおだろう
/b あなたと私が見る赤色は本当に同じ赤色か
この問いを考察するにあたって、皆さんにまず理解してもらいたいのは、前提いかんによって答えは異なるということで、それはつまり、皆さんが指す「赤色」が、どういう意味の赤色かによるわけなのだ。その赤色が、そのものの性質を指す、あるいは、差異の知らせとしての情報を指す、これがまず一つの主観である。そして、赤色がわれわれにとってどう見えるのか、その見え方の違いについての主観、これがもう一つの前提条件である。とりあえずおしなべて説明できることは、性質と差異[情報]の違い、そしてそこに関わってくる主観の係わり方のシークェンスについてだ。まずリンゴが存在するとしたとき、人はそのリンゴが赤いということをどうやって知ることができるのか。同じように、人が泣いているのを、どうやって泣いていると知ることができるのか。それはもちろん、目で見るからだ。リンゴが赤色をしているから、それを見て赤色と知る。人が涙を流してあるいは声を出して泣いている素振りを見ることができるから、泣いているのかと、知ることができる。それゆえに、リンゴは赤色の性質を持っていると言えるだろう。では、私たちが見ている赤色は、リンゴの性質そのものだろうか。性質は目に見えて、あるいは匂いで感じたり、雰囲気から感じたりなど、感覚器官で、直接認識できる対象のものだろうか。もしリンゴの皮が絵の具で白く塗りつぶされたとしたら、それでもリンゴが赤色の性質を持っていると知ることはできるだろうか。いや、できない。性質は目に見えるものではないし、感覚器官で認識できるものではない。だが、ちょっと待ってほしい、白く塗りつぶされたリンゴは、白い性質を持ったリンゴになるのではないか、と言われるかもしれない。つまり、性質を、自分たちが見えるように、感じるたびに、新しく作り出していけばよいと。しかし、性質がそんなに、人によって変わるものでよいのだろうか。リンゴの性質はリンゴが持っている性質なのに、人それぞれの見え方、感じ方の感受性の違いによって定義づけして良いものだろうか。白く塗りつぶしたリンゴが白い性質を新たに持つというのは、色覚異常の人が、リンゴが青色に見えていたらそのリンゴは青色の性質を持つのか、というのと同じなように思える。つまりその人がどう見えるか、どう感じるかによって、勝手にリンゴの性質を変改しているのだ。これは明らかに人為的解釈の片割れである。ものの性質は人為的に変改されない。彼らが同じリンゴを見ても、それぞれ違うリンゴに見えるのは、おそらくそれは、情報の取り込み変換の違いが表れるからだ。情報とは何か。おそらく、性質をそのまんま知覚できる手段がある。それが差異[情報]である。われわれの感覚器官が受け取るものは、性質そのものではなく、性質を表わす情報なのだ。赤色などの類はまさしく色についての一つの情報に過ぎない。だからわれわれが受け取れるのは情報のみで、ほんとうの性質の実体がどういうものなのかは、知るすべがない。厳密的・基底的に言えばそういうことになる。われわれが情報を知る手段は、一般に五感と呼ばれる感覚手段のみであり、それをもって知れることが、われわれにとっての情報の全てなのだ。それから、同じ情報でも人によって受け取るものは同じとは限らない。泣いている人を見ても、その人が悲しくて泣いているのか、嬉し泣きなのか、はたまた嘘泣きなのかは、観察者側の受け取り方、すなわち主観に委ねられる。つまり、人は、情報をそのまま取り入れているのではなく、先入観や微妙な違いによって、それぞれはそれぞれの「解釈」をするというある種の変換が、取り込みの際に行われているのである。もしこのことが事実なら、あなたと私が見る赤色が本当に同じ赤色なのかどうかも、どうやら疑わしくなってくる。これは、赤色という同じ差異[情報]について述べているのであり、したがって情報としては同じ赤色なのに、取り込みの変換によってそれがどのような赤色になるのかは、それぞれの私的経験(主観)から見ることでしか得られない。では私的経験によって、差異がねじ曲げて解釈されるものだとしたら、いったい差異は、何を表わすというのか
差異は、規則と、場合によっては特定の性質も表わすが、しかし差異は、観察者の主観を指し示すことはない。あなたが世界をどう見ていようと、知覚する色と物の組み合わせが、わたしと同じく規則的であるかぎり、どんな言葉をもってしても、その違いをあらわにすることはできないからだ。どちらにとっても、緑は芝生やレタスやエンドウ豆や一ドル紙幣の色だ。オレンジはオレンジ色だし、怒りは赤に見えるだろうし、歌手はブルーな気分を歌うだろう。わたしたちが色を示す言葉を正確に使いわけるのは、公共の対象物を示し合うことによってのみであり、「私的経験」によってではない。ほかの人の目のうしろに回って、その人には実際に赤がどんなふうに見えているか、知ることはできない。自分も相手も生物学的にほぼ同じなのだから、晴れ渡った夏空の見えかたも、たいして違わないだろうと推測するしかないのだ。それなら、色覚異常の人をどうやって見つけだせるのか、と疑問が湧くかもしれない。その答えは、正常な色覚の人ならはっきり見わけられるふたつの色の違いを区別できないからだ。たとえば、大多数の人と違って、色覚異常の人は背景が緑だと赤を識別できない。それを見わけるテストは、感覚経験という私的経験に関わるものではない。色の違いを公共的に判断する能力があるかないかを決めているだけだ。だから、ほかの人たちと同じように色の違いを区別できさえすれば、わたしたちと比べて実際にその人には色がどう見えていようと、やはり気づくことはできない
赤色が性質上違っているのかの観点から見たときに、観察者が異なるからといって、赤色が実際に違う色を示すわけではない。赤色それ自体は、観察者が変わったからといって、赤色の色も変わるわけではない。しかしだからといって、その赤色が、見る人にとって同じ赤色だと言えるわけではない。この違いが分かるだろうか。赤色の性質は確かに変わらない。だがその性質をどう認識するかの違いが、観察者によって必ずしも同じとは言えないため、結果的に――赤色の持つ性質それ自体は変わらないのにもかかわらず――見る人にとっては、見える赤色はそれぞれ違うかもしれないのだ。日の丸国旗の真ん中の色を指差して「これは何色か」と聞き、AとBの二人が、やはりどちらも「赤だ」と答えた場合でも、同じことが言える。確かに、Aにとっては赤だし、そしてBにとってもそれは赤だ。だがAやB、皆が同じ赤色だと言うのと、実際にその人たちにとって見えている赤が同じ赤色かどうかとは、また違う問題なのだ。規則や性質や公共判断は、観察者によってその赤色がどう見えるかということまではさし示しはしない。それを指し示すのは唯一、その人の主観観点である「私的経験」だけなのだから
ただ、皆さんを混乱させる言い回しを使うことには注意を払わなければならない。こういった類の説明を行うときに、非常に多くの論者はよくニ極論に走る。例えば彼らは、「もし、わたしがあなたの目を通してみたら、沈む夕陽がわたしにとっての青に見えはしないだろうか?」とこう言うのだ。彼らはニ極論的レトリックに溺れて、本当に伝えるべき重要な問いを伝えようとする努力をないがしろにしている。われわれが本当に伝えるべきは、「それは本当は事実ではない」と言うことだけだ。賢明な聴衆なら、そう言っただけで十分理解してくれるだろうが、まだちょっとよく分からないという聴衆のためにも、しっかりこう付け加えておくといい。「それは本当は事実ではない。だから間違っている可能性がある。だがそれは間違っていると言っているのではなく、間違っていないのかもしれないし、でも間違っているかもしれないと、そういうことを言いたいのだ。だが一つだけ、それは確実に間違っていると私が言えるのは、間違っているかもしれないことを間違っていないと信じる、その心だ」もし語り側がこのあとに外挿的推論に頼るのであれば、それを、自分自身が明確に意識するのがまず得策だと思う――例えば“おそらく”と使うような。試しにまず私が、今回の項を例にして述べてみよう。先ほどの二極論的レトリックの言い方と何が違うか―――観察者の立場がある限り、それぞれの人が言う赤色が同じ赤色を指し示したとしても、それが、――たとえ見られる赤色そのものが同じ赤色だとしても――見える赤色が同じかどうかを証明することにはならない
三角形を成す周りの三辺が決まれば、どのような形の三角形が出来上がるかを知ることができる。規則さえ決まれば、ものの形は決まる。規則さえ分かれば、ものの形も分かる。だが今回述べているのは、それらのどれでもなく、観察者という新たな観点から生まれるものの見方についてのものなのだ
全体の関係性を見ることがどうして重要なのか
グレゴリー・ベイトソンは、物事は常に全体の関係性を見るべきだと言った。全体の関係性を見ることがどうして重要なのか、その理由を、自分なりに解釈して考えてみたいと思う。まず問いかけたいのは、片方の視点からのみ、物事全体の概観を捉える――すなわち「部分」が「全体」を知り得る――ことなどできるのだろうか
「死んだペットを食べる」という行為についてを例に挙げてみよう。多くの人は、ペットを食べるのは、人とペットとの信頼関係を裏切る行為だ、と主張するだろう。動物の友であり保護者であったはずが、突然、畜産農家のように振る舞うことなどできない。それは心理的に難しいだけでなく、人間と動物との関係の土台を損なうものだからだ。これは、道徳にもとづいた判断なのか、それとも文化として刷りこまれた条件反射なのだろうか。あらゆる肉食を間違いとみなす倫理的ベジタリアンでもないかぎり、道徳性がそこにどう関わってくるか、見きわめるのは難しい。ただもし、ペットを食べることに反対する人たちが、前述の「ペットとの信頼関係を裏切る」と同じ理由であったなら、その考えを主張する理由は、人として一種の道徳性に反するからだという理由になる。つまり、道徳性に反しているからペットを食べることなどありえないと。その主張はそれで良いと思う。問題は、もし自分の立場が正しい=道徳的だからといって、相手の立場を聞かずに、相手が正しくない=不道徳だと結論づけるなどということがなされるのだとしたら、それはずいぶん性急ではないかということだ。私が気にかかるのは、その結論が、主張からどのようなルートを通ってなされたのかということだ。そのルートは三つの可能性から選択されるものだと思う。すなわち、自分の立場が道徳的=だから相手の立場が不道徳なのか、相手の立場が不道徳=だから自分の立場が道徳的なのか、あるいは自分の立場と相手の立場を考慮した上で=相手の立場よりも自分の立場のほうが道徳的だったのか。もしあなたが自分の立場のことだけではなく、相手の立場も考えた上で、自分の立場のほうが道徳的だと結論付けたのなら、そこで一種のジレンマに陥っているはずだ。しかしこのジレンマは、物事をより慎重にあるいは幅広く思考するために必要なジレンマなのだ。外にご飯を食べに行ったとき、周りの人たちが食べ物を残しているのを見て「もったいない」と思ったことはないだろうか。(自分の立場とは別の)相手の立場からすると、ペットを食べることもまた道徳的と言えることがあるかもしれないと、一瞬でも考慮に入れることは、はたしてそんなに間違ったことなのだろうか。もしこの言い方が穏便で分かりにくかったら、このように言ったほうが分かりやすいかもしれない。「むしろペットを食べるほうが、道徳的なのかもしれない」と(しかしこの言い方は非常に無智でばかげている。世界中に貧しい人がたくさんいるのに、資源をみすみす無駄にするのは不道徳だとわたしたちは考えている。だから、もし肉を食べるのが悪いことではなく、肉という資源が有効利用できるのなら、間違っているのはそれを食べることではなく、捨てることのほうだと思える。その観点から見れば、ペットの肉を食べるというのも、それは一種の道徳的英雄であって、大半の人はその勇気がないのだ。したがって、動物が友だちか食べ物かという問題は、どちらかを選ぶこと自体が間違っているのかもしれない。自分の立場が道徳的だから、だから相手の立場は不道徳なのだと単純に見なすのではなく、どちらも道徳的ではない(道徳的かどうかという指標で測ろうとすること自体が物事を単に難しくしているだけなのか)、あるいはどちらも道徳的なのかもしれないという疑いも持つべきだ
ユーモア
a 仕組み
(1) 人は他人の失敗や恥ずかし目を嘲笑する本能がある。この本能は自尊心や攻撃欲求に基づいている。人は誰しも周りからよく思われたいと考えている。だからこそその裏返しとして自分が他人の前で失敗したときは、評価が下がってしまったとか、自分はダメ人間だとくよくよし、また実際周りは彼の失敗を嘲笑するので、彼はさらに自尊心を傷つけられ恥ずかしい気持ちを抱く。こうしたことに基づいて、反対に誰かが失敗したときは、その人を嘲笑することで自分の自尊心や優位性を暗に強調しているとも考えられる。つまり、自分に自信のない子がいじめっ子に転じるように、他人を貶めることでその分自分の優位性が保てるという錯覚心理が、他人の失敗を嘲笑する「攻撃欲求」の核であると考えられる。/お笑い芸人は転ぶことでお客さんが笑うことを知っているし、自分の頭がハゲていることはお客さんを笑わせる武器になることを知っている。ユーモアを作り出す「侮辱」は、主に自分自身をイジる「自分侮辱」と、他人をイジる「他人侮辱」の二種類がある
(2) すでに有る価値[=既存価値]から適度に離れたところにユーモアがある。例えば常識域は既存の社会的価値。そこから適度に離れたところにユーモアがある。これが離れすぎると“シャレにならない”とよばれる状態になる
b ユーモアの例
b-1 既存価値の由来と逆行する価値
b-1-例 「恋人からよろしくお願いします」「恋人から!?」
既存価値→「友達」
既存価値と逆行する価値→「恋人」
b-1-a 既存価値との対比の一例:「常識を取っ払う」
b-1-a-例 「√8」これに対する常識を取っ払うと、「何やこれ。8に何してくれとんねん」とこうなる
b-2 侮辱仮定
b-2-例 「私にキャスティング権などあるわけない。もしあったら○○さんは呼んでなかったでしょ」
→提示された述語[方向]を否定し、その上でもしそうだったとしたら~だっただろうと仮定している。この仮定に侮辱が用いられる
b-3 当たり前ではないことをあたかも当たり前のように扱う
b-3-例 「だいたい忙しいって、遊ぶだけなんだろうが」「アルバイトですよ! カニの甲羅にカニかまを詰めなきゃいけないんですよ」「それは偽装だろ」
b-4 恥を強調してさらす「自分侮辱」
自分に恥をかかせたり失敗させたり侮辱させたりする機会を自ら作り出してユーモアを生み出す
b-5 真似と誇張再現
面白おかしく真似をするときは誇張再現がかかっていると侮辱度が増しユーモアが生まれる。反対にその真似によって特定の人を傷つけすぎるものはユーモアが半減する
b-6 自嘲的な意味を含む皮肉[シュールな世界]
自分たち以外の立場に立って自分たちの世界をシュールに捉えることが多い
b-6-例 飼い主のチャーリー・ブラウンがスヌーピーのところへご飯を持ってくる。スヌーピーは「いい子、いい子…」とつぶやく
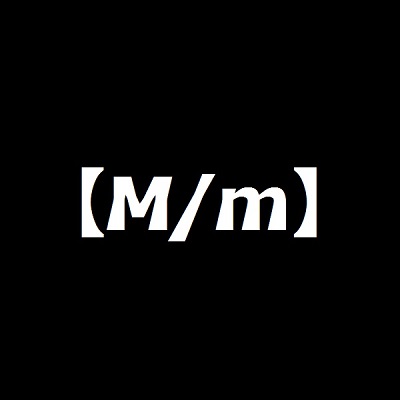

 TOP
TOP