【お知らせ】「本格派」を追記しました(2016/09/21)
・「思考学」カテで使われる用語や関連する用語を展開しています
・古い順
目次
- 1 代償行為
- 2 人工空間
- 3 仮想空間
- 4 記銘
- 5 アフォーダンス
- 6 ステレオタイプ
- 7 引き金特徴
- 8 ノエマ
- 9 思考因子[ノエシス]
- 10 種石
- 11 布石
- 12 欲求の段階
- 13 メラビアンの法則
- 14 POXモデル
- 15 印象形成/初頭効果
- 16 対人魅力の3つの要因
- 17 説得的コミュニケーション
- 18 M/F/FM/K/S
- 19 達成度[差異]
- 20 先入観
- 21 純粋意識
- 22 新規思考
- 23 既知思考
- 24 【旧文】追随思考
- 25 無心思考/有心思考
- 26 直接型思考/間接型思考
- 27 ピックアップ思考
- 28 仮定思考
- 29 関係思考
- 30 手ざわり思考
- 31 置換思考
- 32 その他の思考
- 33 ヒューリスティック学習[発見的学習]
- 34 受動反応
- 35 可変本能/絶対本能
- 36 被体意識/加体意識
- 37 万学[ばんがく]
- 38 相存理論[相反同系列存在理論]
- 39 心じない
- 40 二極論
- 41 記憶の重要的簡略化
- 42 無意識的願望/無意識的思考
- 43 後退空想/過去の感情の転移
- 44 アナログ的/デジタル的
- 45 ジェームズ=ランゲ=サザランド説
- 46 牧場を作る
- 47 複合原因/複合的強調/有効原因
- 48 好望悪
- 49 思索目
- 50 [賛/保/反]かつ[多/小/不]
- 51 自然/故意
- 52 エントロピー[正/負]
- 53 冗長性/SN比
- 54 直示的
- 55 転移
- 56 コンプレックス
- 57 就眠儀礼
- 58 リビドー
- 59 論理階型
- 60 中庸
- 61 本格派
代償行為
代償行為
ある欲求を置き換えて代償的に欲求を満たすこと。つまり、直接に欲求を解消できない時、別の何かでその欲求を満たそうとすること。この心理を応用したものが「代償満足」である
代償満足
考えさせたくないことがあったとする。その根本の原動力を他で消費させることで、人は考えたと満足する
a 満足感の分配原理(“満足感”)
達成することが目的でも、達成したときに満足感が訪れるのではなく、達成への道を歩いているときにも満足感は感じている。これを満足感の分配原理という
a-応用 なにかを阻止したいとき、そこにたどり着くまでの距離を長くすると、十分な満足感を得られ、達成そのものへの意欲が低下する
人工空間
[養老孟司より]
人間が作った空間。都市や家など。物は人工物体。人工空間は人の脳が作り出したものなのだから、人の脳の中である、という比喩もある
仮想空間
[養老孟司より]
人間の知性を空間としてとらえた場合のその空間のこと。たとえば、教授が死んだらその後任を探す。これは死んだ教授ではなく、「教授」という地位(空間)が存在しているからなのである。つまりこの例の官僚制も構造的にとらえた場合、仮想空間であるといえる
記銘
記憶の第一段階。新しい経験を受け入れ、それを覚え込むこと
アフォーダンス
[ギブソンより]
アフォーダンスとは、環境が動物に対して与える「意味」のことである。アフォーダンスは、環境に実在する動物(有機体)がその生活する環境を探索することによって獲得することができる意味/価値であると定義される。ギブソンの提唱した本来の意味でのアフォーダンスとは「動物と物の間に存在する行為についての関係性そのもの」である。例えば引き手のついたタンスについて語るのであれば、「“私”はそのタンスについて引いて開けるという行為が可能である」、この可能性が存在するという関係を「このタンスと私には引いて開けるというアフォーダンスが存在する」あるいは「このタンスが引いて開けるという行為をアフォードする」と表現するのである。要点は行為の可能性そのものであるため、タンスに取り付けられているのが「引き手に見えない、あるいは引き手として使用できそうもない引き手」であっても、“私”に引いて開ける事が可能ならば、その両者の間にアフォーダンスは存在するのである
(誤用)
ドナルド・ノーマンはデザインの認知心理学的研究の中で、モノに備わった、ヒトが知覚できる「行為の可能性」という意味でアフォーダンスを用いた。アフォーダンスは、物をどう取り扱ったらよいかについての強い手がかりを示してくれる。例えば、ドアノブがなく平らな金属片が付いたドアは、その金属片を押せばよいことを示している。逆に、引き手のついたタンスは、引けばよいことを示している。これらは、体験に基づいて、説明なしで取り扱うことができる。「人をある行為に誘導するためのヒントを示す事」というような意味で使用される事がかなり多い。この誤用を結果的に世に広めてしまったドナルド・ノーマン自身も後年にそれを認めており、「自分の著書において使用されているアフォーダンスという語については、本来のアフォーダンスではなく、知覚されたアフォーダンスと読むべきである」という旨のコメントをしている。現状では特に注釈なくこれら二つが入り交じって使用されている(むしろノーマンによる誤用がより広く浸透している傾向がある)ため、十分な注意が必要である
―
日常行われる一般的な思考のほとんどは、アフォーダンスと引き金特徴によって思考されているのではないか。そうでないときというのは、新規思考や熟考しているときや迷っているときなどに限られると思う
アフォーダンス的思考
アフォーダンスが用いられた思考(ステレオタイプ/引き金特徴)
非アフォーダンス的思考
アフォーダンスを用いない思考ということは、ノエマからはなにも先入観を受け取ることがない思考であるといえる。これに他の加体意識または被体意識(“用語解説”)を除いて思考を行うと無心思考(“用語解説”)という思考法にすることができる
ステレオタイプ
様々な情報が氾濫する今日、人はメディアを通してしか事物を知ることはできない。そして、普通の市民は事物について多様な情報を吟味し、正しく事物を知るだけの余裕を持たない。メディアが伝えるイメージが固定化し、人は思考を省略してそのようなイメージに基づいて認識、判断を行うようになる。そのような固定化されたイメージをステレオタイプと呼ぶ。また、ステレオタイプを共有することは、人が社会の多数派に同調する際に必要となる。同調主義がステレオタイプを通して蔓延することが理解できるだろう。これを権力者の側から見れば、ステレオタイプを作り出すことは世論を操作し、自らに対する支持を拡大する上で有効な手段ということになる
日常行われる一般的な思考のほとんどは、アフォーダンスと引き金特徴によって思考されているのではないか。そうでないときというのは、新規思考や熟考しているときや迷っているときなどに限られると思う
(応用-a) ステレオタイプを有効に使う。例えば、高価なもの=品質の良いもの、というステレオタイプを引き出すには、価格を上げればいい
(応用-b) ステレオタイプと逼迫[ひっぱく]
切迫詰まった状況で専門家や上司などから言われた事は、ステレオタイプや引き金特徴(簡便法)を発動させやすく、内容を重視しなくなる傾向がある
引き金特徴
[ロバート・B・チャルディーニより]
ステレオタイプ(“用語解説”直上)を引き起こす原因そのもの。物やイメージなど、その姿は様々である
ノエマ
思考された対象
思考因子[ノエシス]
思考する原因となった対象そのもの
たとえばコクマルガラスを目にして、そこから色々と思考した場合の思考因子は「コクマルガラス」である。赤色を思い浮かべてそこから炎を連想した場合の思考因子は「赤色」(のイメージ)である。「アヘンがこの種の誘眠素を含むのはなぜか?」という疑問提起に際して、アヘンについて考えたり誘眠素について考えたりしたときの思考因子は「アヘンがこの種の誘眠素を含むのはなぜか?」という一文そのものである
種石
将来に影響を与える過去の事物
布石
将来に備えてあらかじめ整えておく手はず。善い種石
欲求の段階
①第一次欲求:生理的欲求(食欲・睡眠・性欲)
②第二次欲求:安全性欲求(住居・衣服・貯金)
③第三次欲求:社会的欲求,つながり(友情・協同・人間関係)
④第四次欲求:自我の欲求,社会ステイタス(他人からの尊敬・評価される・昇進)
⑤第五次欲求:自己実現欲求(潜在能力を最大限発揮して思うがままに動かす)
↑睡眠欲[①]
│食欲[①]
│大義踏襲化(先入観)[⑤]
│自己実現―純一(善)[⑤],社会的地位[②],損[④]
│愛欲―性欲[①],孤独[③],愛[③](愛が因子の経済的安定[③])
↓経済的安定―金欲[②],秩序共鳴(偽善)[③],社会的地位[④],利[②③④]
――
自らが自らによって自らを明白に表すことを自明の理という。自分の感情を把握することを自己知覚という
メラビアンの法則
[メラビアンより]
メラビアンの法則とは、アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが1971年に提唱した法則で、声の感じで、「maybe」(かもしれない)といった文がどの程度、「そうかもしれない」かを判断する実験で、力強い口調の場合は、普通の口調よりも、「そうかもしれない」と感じたということが立証できたという実験だと言われている
感情や態度について矛盾したメッセージが発せられたときの人の受けとめ方について、人の行動が他人にどのように影響を及ぼすかというと、話の内容などの言語情報が7%、口調や話の早さなどの聴覚情報が38%、見た目などの視覚情報が55%の割合であった
この割合から「7-38-55のルール」とも言われる。「言語情報=Verbal」「聴覚情報=Vocal」「視覚情報=Visual」の頭文字を取って「3Vの法則」ともいわれている
俗流解釈
この内容が次第に一人歩きをし、この法則から「見た目が一番重要」あるいは「話の内容よりも喋り方のテクニックが重要」という結論が導き出されると言う解釈が有名になっている
ただしこの実験は「好意・反感などの態度や感情のコミュニケーション」において「メッセージの送り手がどちらとも取れるメッセージを送った」場合、「メッセージの受け手が声の調子や身体言語といったものを重視する」という事を言っているに過ぎない
よって単に事実のみを伝えたり要望をしたりするコミュニケーションの場合には触れておらず、コミュニケーション全般においてこの法則が適用されると言うような解釈はメラビアン本人が提唱したものとは異なるものである
POXモデル
[ハイダーより]
私たちは、自分とかかわりのある他者について、その人がどのような人なのか強い関心をもつ傾向がある
これは対人認知といい、きわめて切実な問題といえる
この対人認知は、もちろん「好き――嫌い」という判断に行き着くのだが、その関係のしくみをハイダーは調和しているバランス状態と、不調和なインバランス状態があると考えた
インバランス状態になると心に葛藤が生じて、バランス状態になるように内的な力が働くと考えた。それぞれを紹介していこう
Pは自分、Oは相手、XはPと関係のある対象のこととする
例:P君はOさんという女の子が大好きです。Xは歌手です。O君がXを好きであれば+、嫌いであれば-です
方向性は、
P
↓ ↓
O → X
【バランス状態】
P
+ ① +
O + X
P
+ ② -
O - X
P
- ③ +
O - X
P
- ④ -
O + X
【インバランス状態】
P
- ⑤ -
O - X
P
- ⑥ +
O + X
P
+ ⑦ -
O + X
P
+ ⑧ +
O - X
たとえば⑦を例にしてみよう
P君はOさんという女の子が大好きです。ところが、OさんはP君の大嫌いなXという歌手の大ファンだ
P君は不快になり、認知を変えようとする
つまり、Oさんを嫌いになるか(④)、Xという歌手を好きになるか(①)、ということである
印象形成/初頭効果
[アッシュより]
私たちは、人に出会ったり、未知の人の話を聞いたりしたとき、大ざっぱであっても、その人のイメージをつくる。これを印象形成という。特に初対面の人に対するイメージは第一印象という
この印象形成についての実験結果がある
二人の人物の特徴を、別々のグループの人に見せた
A氏:知的な―器用な―勤勉な―温かい―決断力のある―実際的な―用心深い
B氏:知的な―器用な―勤勉な―冷たい―決断力のある―実際的な―用心深い
4番目の温かいと冷たいしか違っていないにも関わらず、A氏については好意的、B氏については非好意的という印象をもった
アッシュは特定の情報が印象形成に大きな影響を及ぼしたのだと解釈した
今度は情報の提示順序を変えてみる
C氏:知的な―勤勉な―衝動的な―批判力のある―強情な―しっと深い
D氏:しっと深い―強情な―批判力のある―衝動的な―勤勉な―知的な
同じリストだが順序を逆にして最初に始まるイメージを「知的な」と「しっと深い」で違いをつけたところ、C氏のほうが好意的にとらえられた
アッシュは最初のイメージが後のイメージに強く影響を残したと解釈した
このように、一度形成されてしまったイメージがなかなか修正されずに後々まで影響を及ぼす効果を初頭効果という
対人魅力の3つの要因
[ニューカムより]
私たちは多くの人と関わりをもつ中で、あるひとには魅力を感じ、ある人には魅力を感じない
なにが他者を魅力に感じる要因なのか。ニューカムは三つの要因を考える
①自分が好ましいと思っているものを相手がもっていると思い込むと魅力を感じる
好ましく思うものは、相手のスタイルだけでなく性格や行動、態度や言葉づかいにまで及ぶ。ただこの場合、相手の気持ちを考えることなく、一方的に成立することが特徴だ
②自分を認めてくれる人を好み、自尊心を傷つけるような人を嫌う
他者から好ましいと評価されることは、自分のさまざまな欲求を満足させる契機になるからだ。つまりは、他者を認め、褒めるということ
「君は気づいてないだろうけど、~」と、相手の盲点の領域に変化させてから言うのも対人魅力を高めるものになると思う
③他者が自分と類似した態度や行動を示すとき、魅力を感じる
類似した行動をとるということは、自分の態度がもっともらしいことを保証してくれる。同じ結論であることで、自分に自信を持とうとするのだ。また、自分を見つめる目で相手をとらえることができる。このような親近感がわく関係は魅力ある関係といえる。この関係は、お互いが相互扶助の関係である
説得的コミュニケーション
自分の思っている意見を相手に話し、それによって相手の意見を変える、同意に導く話法。日常でよく使われている
説得的コミュニケーションで大切なことは、”説得された”という気持ちを相手にいだかせないこと
もともと人間は、自分の行動は自分の意思で決定し、実行したいと考えているので、説得の押し付けは相手に嫌悪感をいだかせる
たとえば、「おれのいうことが聞けないのか」と職場で部下を怒っている上司を見ることがあるが、このような場合、部下は表面的には従うが本当は納得せず、心のなかでの反発は大きい
つまり説得で心がけることは、相手に相談し、できるだけその意見を取り入れてもらい、その人の発案として実行してもらうことだ
M/F/FM/K/S
M:もう一人の自分
F:未来の自分
FM:未来のもう一人の自分
K:彼ら(高等監察院[アスタリスク]、年表干渉者[インターセプタ])
S:創造者
達成度[差異]
簡単に言うと、対象の間にある差異の関係性のこと。主観での目標達成の難易の度合い。高低差。自身がある目標を達成するとき、その時点の自らの技術とその技術を持ってして目標を達成することの難しさは、前の達成度と比較して、低かったり、高かったり、一定だったりする。またこれは客観では見定めにくい。なぜなら、その達成度は難しいことに挑戦するからといって必ずしも高いとは言えないからだ。原理は、高い技術者が簡単な目標を達成するのはたやすいが、低い技術者にとっては難しいことだからである。また、目標というのは自分がどの位置の技術者であろうが常に上にある。だから、技術の高低差と達成度に直接の関係はない
この達成度を普段から思考に染み込ませていれば、自己容認あるいは自己満足という自己肯定的な考え方になる。しかもこの考え方は非常に客観的であるといえるし、ゆえにメタ認知の第一歩といってもいい。達成度という考え方を忘れないでおきたいと思う
(例-a) 公平な不平等
ジョンとマーガレットは息子たちへのクリスマスプレゼントを買いに出かけた。息子は三人で、マシューは14歳、マークは12歳、ルークは10歳だ。愛情深い両親は、三人をつねに平等に扱うよう心がけていた。今年のプレゼント用予算はひとりにつき100ポンド、とすでに決まっている。今回の買い物には、なんの問題もなさそうにみえた。目当ての品物はすぐに見つかった。携帯式の“プレイボーイ”ゲーム機で、ひとつ100ポンドだ。ゲーム機三つをふたりでレジに持っていこうとしたとき、ジョンが店内に貼られたお知らせに気づいた。ひとつ150ポンドの最新機能型“プレイボーイ・プラス・マックス”をふたつ買えば、オリジナルのプレイボーイ機が無料でもらえるという。払う金額は同じで、もっと上等の品が手に入るのだ。「それはできないわ」マーガレットが言った。「不公平だもの。誰かひとりが、ほかのふたりより劣った物をもらうことになるのよ」。「でも、マーガレット」ジョンは息子たちから最新型のゲーム機を借りることを考えて、わくわくしていた。「どうして不公平なんだい? もともともらえるはずだった物より劣る物は誰ももらわないし、三人のうちふたりはもっといい物をもらえるんだ。もしこれを利用しないと、ふたりはもらえるはずの上等な物をもらえなくなる」。「わたしは三人を平等に扱いたいわ」マーガレットが答えた。「その結果、損をすることになってもかい?」
――
ここは達成度の項なのでそれに即した考察をしていきたいと思う。まず今回の例でジョンとマーガレットが問題にしているのは、「平等の品を三つ買うことと、同じお金でより性能が高い、しかし格差のある品を三つ買うことでは、どちらが平等か」というものだ。ここでジョンとマーガレットが衝突しているわけは、「平等とはどういう意味か」の根本的な考え方に相違が生じているからだ。ジョンとマーガレットのどちらが正しいかは別として、平等という概念への基本的な考察の取り組み方について述べておきたい。客観的な視点から、平等の意味を探ることを試みよう。考察点は二つ
(1) まず平等という概念は、人間側の感情にすぎない。ゆえに平等か不平等かを考えるときは、マーガレットのように、人間が平等かそうでないかの視点で見るほうが自然だ。ジョンのように、平等かそうでないかを物質的な側面から見るのは問いの論点からずれている
(2) さっそくこの例で達成度[差異]を用いてみよう。そもそも達成度は、物質が持つ性質ではなく、物質同士の間に発生する関係性の類である。しかしまあ、ここでは人の感情的概念の一つと言っても差し支えないだろう。ただ達成度の概念は人が物質(対象)に対して感応するものであるため、必然的に達成度の開きは対象同士の優劣を反映する。したがって達成度の差異の無さがイコール平等であるということができる。最初の選択だった、携帯式の“プレイボーイ”ゲーム機を三品ということであれば、三人の子どもたちに達成度の開きはない。では最新機能型“プレイボーイ・プラス・マックス”をふたつと、オリジナルのプレイボーイ機をひとつではどうだろうか。この三つの品は、二つが性能の良い品で、一つはその二つに比べて劣る。であれば残りの一つの品と、他の性能が良い二つの品との間には達成度(差異)の開きが発生する。ではどちらが平等かと言えば、最初の同じ性能三品のほうがそうだと言えることになる。「平等とはどういう意味か」、この問いについてのジョンとマーガレットの考え方の相違が浮き彫りになってきたようである。マーガレットによる平等の考え方とは、一つの選択と一つの選択、それぞれどちらがより子どもにとって平等に近いか、という捉え方。対してジョンによる平等とは、一つの選択と一つの選択それぞれの性能は、子どもにとって喜ばしいか、という捉え方だ。ジョンは、平等を重視するというのに、達成度という平等の側面より、性能という物質的な側面に傾いているのだ
―
もともとのプレゼント計画に沿っていれば、三人の状況はそれぞれが損も得もしない、階級なき社会の縮図だった。ところが、プレイボーイ・プラス・マックスを手に入れることにすると、たしかにふたりは得をするが、そのことは、残りのひとりにとってはなんの慰めにもならない。とすればこの計画は、全体的に見て、もっとも恵まれない人の利益になっているとほんとうにいえるのだろうか? 同じことは政治の世界でもたしかにいえる。不平等に反対する理由のひとつは、それがまさしく社会の団結力を損ねたり、貧しい人たちの自尊心を傷つけたりするからだ。社会心理学者たちが指摘しているように、人は、たとえ自分が物理的にはなんの損害も被らないとしても、もし隣人が経済的負担もなしに金持ちになったとしたら、心理的には貧富の差に対する意識が強くなって、苦しむ可能性がある。したがって、平等と不平等をただ物質的な側面からしか考えないと、政治の場合も家族の場合も、ひどい間違いを犯すことになりかねない
(例-b) 事象渦絶対透視機
「事象渦絶対透視機(トータル・パースペクティブ・ヴォルテックス)。この機械はもともと、20世紀後半の、あるラジオ番組向けSF小説の題材としてフェリエが思いついたもので、中に入れば誰でも、宇宙の中で自分が占めるほんとうの大きさを知ることができるというものだ。フェリエはこの機械を作るとき、ちょっと手を加えて、誰もが同じものを見るようにした。多かれ少なかれ、わたしたちはみな、取るに足りない存在だと考えたからだ。オリジナルの小説では、この機械を使った人は、自分がいかに取るに足りない存在かを強烈に思い知らされるため、心を打ち砕かれてしまう。しかしその中で、あるひとりの人物だけは、その経験をうまく切り抜ける。その人物、ゼイフォード・ビーブルブロックスは静かに機械から出てきて、自分はなんと『すばらしくてすごい奴』かがわかった、と言う。しかし、読者はビーブルブロックスがほんとうにその機械に耐えられたのかどうかわからないし、自分が重要だという解釈が歪んだものだったのかどうかもわからない」
―
何かに価値があったり、重要だったりするのはどういうことか考えてみよう。何が重要かそうでないかは、客観的価値で考えるならば、それは相対的に導き出せるものだろう。友人同士のゴルフコンペでは重要な出来事も、プロの国際試合に比べればささいなことだ。しかし、USオープンで何が起きようと、人類の歴史から見れば取るに足りない。そして、地球上で何が起きようと、宇宙全体を視野に入れてみれば、小さなことだ。しかし、その人にとって何が重要かそうでないかは、客観的視点からはまったく知ることができない。ビーブルブロックスは透視機と向き合って、ほんとうに他の人たちと同じものを見ているのだろうか。他の人たちが自分のあまりの小ささに絶望しているのに、彼は小さいわりに自分はなんと重要なのかと驚いているではないか。ここまでくると、透視機というアイデアは一貫性を失う。人の重要性を示そうとしているのだが、具体的には何も示していないのだ。その人にとって重要かどうかを知るのは、その人の主観的視点からしか分かりえない。愛する人と一緒にいるためだけに、人は富も名声も投げうつということを考えてほしい。宇宙の壮大さに比べれば、自分たちの愛などちっぽけだとしても、彼らにとっては、互いの存在は宇宙の存在と同じくらい重要なのかもしれない
(例-c) 一つ前の前提にさかのぼってみた場合の達成度
「破廉恥に対する羞恥心も、美を求める努力も、ともに欠けているようでは、国家にしろ個人にしろ、偉大な美しい行為を果たすことはできない」
<プラトン>
この命題の一文をとりまいて対立する人がいた場合、その両者のことをひとまず、この命題に賛成の人をプラトン派、反対の人を懐疑派と呼んでおく(プラトン派の意味は、たんにこの命題に賛成できるような共通思想の持ち主という意味で使う)。懐疑派の人は反対のわけをたとえばこう述べる――<「偉大な行為とは、美しい行為をさすことではない」「美しい行為は国家も個人も救わない」「美しい行為とはなにか。また、それがなぜ美しいというのか」>。“美”にたいして、プラトン派は“美”から“羞恥心”をつけ、“求める努力”をつけ、それが“欠けていた場合”を仮定し、“国家と個人”をつけ、“偉大な行為を果たせるかどうか”を決める、といったように、“美”からいくつかの前提を築いてみた。一方、懐疑派は、プラトン派が築いたこれらの諸前提をばらばらとくずして、ある者は“美とは何か”を問い、またある者は“反論”というかたちで別の諸前提をきずいている。プラトン派は懐疑派を「(“美”の考えかたについて)劣っている」と言い、しかしまた懐疑派もプラトン派のことを「劣っている」と言う。実際にはどちらとも、自分のものさしで“美”をはかっているだけにすぎず、彼女らがつかうものさしは“美”そのものの価値をはかれる代物ではない。だからもし彼女らが「優れている」と興奮して叫ぶものがあるとすれば、それはいつでも自分たちの思想を支持してくれるものだけなのだ。/そしてまた彼女らはつねに主観立場にたっているので、自分たちの考えも相手の考えも、「それはどちらもちがう」と言う。しかしそもそも、これらの考えの組み立てられかたや結論はたしかに違うけれども、<積み木をつみ立てる>ことや、あるいは<自分のものさしではかっていること(つまり優劣をつける試みということ)>という事実をみれば、両者とも同類なのである。考え方や結論は違うけれども、やっていることは同じなのだ。つまり両者とも同じ関係であり、同じ達成度だということである。彼女らと同じ達成度にならない者がいるとすれば、その人は完全懐疑主義とでもよべるような、すなわちなんの意見も確信せずただ「美とは何か」を問うような人たちで、ただその人たちのなかでも、自身の考えと彼女らの考えに優劣をつけない人が、そういう者になるようである。この者から私たちが学べることは、学問をするうえで大切なことは、うぬぼれではなく謙虚な疑問なのだといったようなことかもしれない。/このように達成度は、表面のあれこれにとらわれず関係をみるという点で、ひとまず客観性がたかいといえるのではないだろうか
先入観
原本では「先入観」と「先入観α」に分立しているが、現在は一つにまとめている。一般の意味としては、先入観は特定の物事に関する個々人の観念[記憶情報]を指す。たとえばサラダは好きか嫌いかという観念、ブルーの色を見ると落ち着くという観念、ブルーを表わす色を“ブルー”という単語と結びつける観念など。受動反応(“用語解説”)と同義。狭義としては、純粋意識(“用語解説”直下)以外の意識のことであり、外部意識によって形成される自己意識を指す。自己意識は多くの場合、外部意識が内在しているものがほとんどだと考えられる
メンタルモデル
どのような人であっても、知らず知らずのうちに、ある「想定」に固執している。「システム」の土台となっている「想定」を「メンタルモデル」という
例えば、約束を破る人が、自分の周りにあまりにも多いとしたら、そんな人を引き寄せる自分に何か原因があるとは考えられないだろうか
純粋意識
純粋意識とは、外界の事物に関する情報やそれからの連想に全く拠らない自己の純粋な観念のこと。これは仮説である。先入観(“用語解説”直上)を外部意識によって形成される自己意識という意でとらえた場合、純粋意識は内部意識(外部意識によるもの以外の自己意識)であり、そういう意味では先入観の対義語ともいえる
たとえば赤色は炎を連想させたり、またその炎から熱いとか情熱とかのイメージも共に連想させることがある。これは炎という外界の事物を経由して連想されたものであり、その情報が外界について触れられているから、それは外部意識[先入観]であるといえる。一方、赤色が好きか嫌いかという情報は自分自身にとってのものであるから、おおむね純粋意識であるといえる。しかしその好悪にかんしても、たとえば赤色が嫌いだとしたら、嫌いなのはなぜか、としっかり理由を突き詰めていくと、それが完全に純粋意識であるかどうかは分からないものである。そこにある外界の事物との根深い連想が横たわっているのかもしれないし、もしそうだとしたらそれについての情報は外部意識も混ざっているのだと言わなければならない
私の現時点での仮説としては、自己意識は多くの場合、外部意識が内在しているものがほとんどだと考えられるとしている
新規思考
新しい物事に対峙したときの思考
既知思考
すでに一度思考したことのあるものについての再思考
【旧文】追随思考
既知思考からさらに直接型思考をする思考法
無心思考/有心思考
無心思考とは、文字通り無心の状態からの思考。無心とは先入観がない状態のことをいう
⇔「有心思考」…先入観のある状態からの思考
直接型思考/間接型思考
直接型思考とは、思考因子(その思考のきっかけとなるもの)もしくは疑問提起と同じ問題についての思考。対象の表面、つまり思考因子そのものについての思考法
間接型思考とは、思考因子または思考因子の問題とは違うことについての思考。対象からは異なることを思考する
(例-a) たとえば赤色を見たり思い浮かべたりしたあとに、その赤色にまつわる思考をするのは直接型思考といえる。赤色から炎を連想して、その炎について色々と考えるのは間接型思考である
(例-b) 「アヘンがこの種の誘眠素を含むのはなぜか?」
この疑問提起に対してなぜだろうと正面的な思考をするのは直接型思考といえる。対して、そもそもアヘンはなぜ誘眠素を含んでいるのか、誘眠素とは何か、この問題を解くのはどれほど難しいか、なぜこの問題を解かなければならないのか、といった緒思考は間接型思考であるといえる。このうち特に、そもそもアヘンはなぜ誘眠素を含んでいるのか、誘眠素とは何か、といった思考関係のことをピックアップ思考(“用語解説”直下)という
(例-c) 「皆が誰か別の人の上に立つなら、一番底の人は何の上に立つのか?」
<サミュエル・バトラー>
一体何の上に立つのか、と考えるのは直接型思考である。この一文から海に浮かぶピラミッドを想像するのは間接型思考である。どうして人は人の上に立ちたがるのか、と別なところに疑問を抱くのも間接型思考といえる。どのような振る舞いをしたら“立つ”となるのか、一番底の人はどんな人か、という疑問はピックアップ思考といえる。ただ間接型思考とピックアップ思考の区別はそれほど厳密にする必要はないと思う。なぜならその意義がないからだ
a 間接型思考とピックアップ思考の違い
ピックアップ思考は文章中の単語についての由しなし事。間接型思考はそういった思考因子とは関連の低い事柄を思い浮かべたときのそれについての由しなし事
間接型思考とピックアップ思考は似たような形態の思考法です。ただここで厳密に言い分けるならば、間接型思考の中の一種類としてピックアップ思考があるという体系になります。ですからピックアップ思考は間接型思考の一つです
(a-例) 「多数の友を持つ者は、一人の友も持たない」
<アリストテレス>
ピックアップ思考は単語(部分)の一々、たとえば多数、友、人、持つ、持たないなどについての思考です。たとえば“多数の友を持つ”という部分について、(α)多数の友を持つ=社交的だとするならば社交的とは何か、あるいは社交的な者はどんなメリットがあってどんなデメリットがあるか。他方、一人の友をもつことのメリットとデメリットはなにがあるか、あるいはそのメリットとデメリットは誰がそうと決めるのか、あるいはそれはほんとうにメリットとデメリットなのか、それがもとづく根拠はなんだろう……
間接型思考はたとえば、(β)浅く広くを求める者は深きものを求めることが難しいのだとするならば、それはどうしてか、あるいは深きにも種類が――たとえば深さの具合とか――はあるのか、あるいは深いとはどういう意味で仮定されているのか、物事が深いというときの深いの意味となにが違うのか、あるいは深いというのは誰が決めるのか
(α)はピックアップ思考から思考(あるいは連想など)が始まっている、すなわちそれは元の文からのピックアップ思考ということである例です。(β)は全体の文の言わんとしていることを勝手に関係として抜き出す関係思考からの直接型思考や間接型思考、すなわちそれは元の文からの間接型思考ということです
ピックアップ思考は実際にそこにある単語の一々についてという限定的な意味がありますが、間接型思考は無限のバリエーションがあります。なぜなら、何を思考しても、それはたしかに元の思考因子から思考された思考ということには変わりないからです。だから極端な話、本を手に取ったとき、そこに『エレホン』という言葉が書かれていてそれを目にしたときに――それがどういう思考回路を経てきたのかは知らないけれども――「猫」について考えるということもそれは間接型思考であるといえます。この例の間接型思考では『エレホン』から「猫」が連想されたわけですが、連想とは「想像」のことです
ピックアップ思考
間接型思考(“用語解説”直上)の一種。思考において、別の箇所の詳細に対する思考⇒さらにそこからまた別の箇所の詳細に対する思考、と、どんどんピックアップしていく思考法。前提の遡行の場合もこのピックアップ思考が用いられる
私が思考をしているときによく――良い意味でも悪い意味でも――陥るのが、ピックアップ思考と呼ばれるものだ。このピックアップ思考は、物事の前提から前提へ遡って行く形式である。前提を、疑問や結論と置き換えてもいいと思う。そして最終的には、基底的な前提にたどり着くのがほとんどだ。遡行の途中、同じ前提が二度三度と現れてくる循環的なケースもある
私はシャワーをしているときによく色んなことを思考する。頭を洗って身体を洗ってという今さらの慣れた動作をしていると、私の意識は色々な事を考え始めるようだ。そこでのピックアップ思考の一例を挙げてみよう。ちなみに私自身、自分の思考をこのような形式的な記述で表わそうとしたことは今回が初めてである
ある冬の夜のシャワーの時にて――
対概念の性質のアブダクション――その性質が他の場合においても適用されることを証明に、性質そのものの存在意義を確認する――についての思考から始まる。ここでいう対概念の性質とは、一方がある場所で「存在」するとき、他方も同時に「存在」しうる、というもの。たとえば、見る―見られるの対概念において、「見る」が発生したとき、同時に「見られる」も出現する。イヌがネコに「攻撃」するとき、同時にネコのほうで「守備[被攻撃]」の出現が起きている
⇒相存理論(“用語解説”)についての思考
⇒AとBを対概念として指定するにはどんな定義づけが必要か。また、「存在する」とはどういう状態を言うのか。もし形式概念(有限―無限など)の存在証明であれば、どんな根拠をもって「存在する」と言えるのか。また、明確な定義づけがなされていない、さらに対概念の定義づけも曖昧なままなのに、帰納的に法則のほうが先行しているというこの奇妙な状況はどうしてだろう
⇒あらゆる法則も三段論法の「~ならば・・・である」という前提の上でしか語りえない。真の命題など何一つ分からないままではないか
⇒しかし科学は“誘眠的仮説(“グレゴリー・ベイトソン書付”)[架空の仮説]”に頼ることによってとりあえず前進を試みている。分析し、予想し、それを結果と照合し、再び修正し、また分析するという「自己修復的」な機能を備えることによって、「真の命題への推進」と、フィードバック機構のある「安定のホメオスタシス(安定させたいことを、動かずにいることで「安定」を図る類のものではなく、“動く”ことで安定させるようにするという種の「安定」)」の二つの機能を手にしている。それらは一見、合目的的であるかのように思える。なぜなら実際多くのことが、それによって達成されているからだ
⇒しかし前提が間違っていれば導き出される答えも正しくはならない。不明瞭な前提を妄信することは危ないのではないか。ベイトソンに言わせれば、前提が間違っていることもあり得るのだという観念を一切欠いた人間は、ノウハウしか学ぶことができないのだから。また、科学は一体何を目的としているのか。真理を暴くことが目的ならば、その達成とは何についてのものだろうか。あらゆる予想が、何がしかの法則によって正確無比に記述できたとしたら、それを達成と呼ぶのだろうか。それとも「実現したいものを実現する」という最終物理的なことを達成とするのか。あるいはその両方なのか
⇒未来のことは何も分からない。予想は予想であるしかない
⇒知覚できないものはわれわれは知ることができない
⇒将来、科学がもし時間的な概念を取り払えることが達成できたとしたら、時間的な概念は省かれることになるのだろうか。時間の存在意義を考えると、どうだろう。可能は可能だが、それをすることはできないのかもしれない。自らの存在がなくなってしまうから
⇒しかしここでは自らの存在という幾何か形而下な観念が、存在できるかできないかという論争は、また無意味なもののように思える。現時点でたとえば不可能だと説明する「記述」自体が、将来もなおそれを妥当に成さしめることができる根拠は、残念ながら薄弱と言わざるをえない
⇒科学はなにを可能にし、なにを不可能にするかは語れないようだ。しかし科学が何かを可能にし、何かを不可能にすることは確実だ
⇒その根拠は何か。それは科学が何かを可能にしようとしているから。少なくとも今の科学が、可能―不可能を成功―失敗の指標としていることは明白な事実だ
⇒再び相存理論に回帰したようだ。それともう一つ思った。何だかんだ言って私は科学が好きなんだと
――
シャワー中に思考の内容を忘れまいとメモしたわけではないので、これらの記述は正確に示されたものではない。それから所々、ピックアップ思考から逸脱しているところも見受けられる(例えば、知覚できないものはわれわれは知ることができない⇒将来、科学がもし・・・)。まあ、逆に思考の形態がよく秩序立っていてもそれはそれでおかしかろう。下に述べたのは別の例のピックアップ思考である。下の例はより思考の過程が分かりやすいように作ったつもりだ(“<>”で括っている部分はまさにピックアップしたところである)。先ほどの例より理解しやすいだろう
リンゴはなぜ赤いのか
⇒<赤いとはどういう意味か。>赤いとは色の形体のこと
⇒<色とは何か。色とは実体か、それとも形式か、それとも情報か。>答えを探すにあたって、まずは分かっている色の特徴を挙げてみよう。色には赤や黒などの「色調」と呼ばれるものがある。そしてそれは特定の生物に知覚されるものである
⇒<なぜ「色調」は生物に知覚されるか。>それは赤と黒(各色調)の間には差異(違い)が存在するからだ
⇒<なぜ差異は生物に知覚されるのか。>それは生物が何かを知覚する際に、五感に多く頼っていて、その五感が「差異」という情報の知らせを元に外界を感知するからだ。知覚する助けとなるものは視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などの五感と呼ばれるものであるが、今回はその中の「視覚」を考えてみよう。形も大きさも色もまったく同じ木を、瞬間的に入れ替えるようにして一分間に千本見せられたところで、被験者の目にはまったく変わらぬ世界が展開されているであろう。それは見せられる木と木の間に違い(差異)がないからである。動画カメラがずっと同じ場所を映しているときに、それがまったく動かない一枚の写真のように見えるのと同じ原理だ。人の顔は一人一人違って見える。それは人の顔が実際に皆違うからだ。しかしハエの顔はどれも同じに見える。ではハエの顔には差異がまったくないのだろうか。いや、差異というものは、両者の間の差異が小さければ小さいほど、知覚されないだけなのだ。知覚には、その差異が分かるか分からないかの閾値があると考えられる
⇒<どうして「色調」の差異が木、人の顔、ハエの顔の差異と同じ差異であると言えるのか。>それは差異に差異がないからだ
⇒<差異がないことを知覚できないのに、どうして差異に差異がないということが分かるのか。>それは差異が「関係上の産物」だからだ。それはつまり情報であって、情報に差異は存在しない。あるのは「知らせ」だけだ。かといってそれらが自ら働きかけを行うわけではないのだが
⇒<「差異」と「情報」が同じグループの産物(形式)であると言える理由は?>それは、両者が同じ特性を有しているからだ。その特性とは例えば「“それ”を知らせるという形式」、「単体では存在しえない」、「性質と性質を結ぶ関係上に発生する」など
⇒<つまりあなたは、両者が同じ性質を有しているから、ゆえに両者は同じカテゴリーに括ることができると。するとそれは、アブダクション・システムが相同証明の根拠となりうるのかなりえないのかという脆弱性を認識した上で、述べているということだろうか。>それは、もちろんそうだ。少なくとも物理的な類の系統発生的相同(例えば人の手と手、カニのハサミとハサミは左右対称の関係にあるというような)よりは、性質・特性という形式的なアブダクションのほうが正確だと感じるのだがどうだろうか
⇒<ではグループの定義とは何か。>類似した特性、形体などを元に、われわれが正のエントロピーを極力避けるために、分かりやすいように括った人工的セグメント
⇒<エントロピーとは誰の都合か。>われわれ人間
⇒<人間は正のエントロピーが自然界に存在することを否定しているのか。>していない
⇒<それならば正のエントロピーを排除することは人為的解釈の片割れではないのか。>区別することは事実をねじ曲げることにはならない。個々の特性は忠実に記述し、それが解答となるわけであって、区別することと解答との間には直接的な相関関係はない
⇒<その層の世界の解答において、何が影響を及ぼし、何が影響を及ぼさないかの内実が、人間にはっきりと把握されているのか。>いや、されていない
⇒<では区別というスキーマが、その層の世界の解答を導き出すのに一切影響を及ぼさないと言い切れるのか。>それは言い切れない
⇒<ではなぜそれを用いているのか。>それは「区別」が「解答」に影響を及ぼさないとわれわれが信じているからだ
⇒<なぜ信じるのか>・・・・・(行き詰まり)
―
いつも、最後はこうして煮詰まることになる。今回の例において最後は、人の論理的理性的な思考の基底的な土台部分が、「信じるか信じないか」という恐ろしく感情的生物的な前提の上に成り立っていることを指摘している。とまあこんなことを指摘するのが重要なことだったわけではないのだが。ただ私がピックアップ思考で、最終的にこの種の指摘に陥ることが多いのは現状としてある。また活発なピックアップ思考のときによく見られる現象が、問い2~問い3にまたがる部分に表れている。問い2の答えは答えになっていない。色が実体か、形式か、情報か、それについての解答を示していない。問い2の解答は、解答を示そうと模索している途中で、問い3の出現によって阻まれている。このように一つの思考が終わりきらないうちに、また新しいピックアップがポンポンとなされるケースも非常に多い。ちなみにこの上の例は「性質と情報の出自とパターンとその認識論的誤謬について(“形式”)」の理論の骨子になっている。そちらの記事もリンクからお読みいただきたいと思う
―
下校中の小学生が、自問自答の形式で面白いゲームをしているのを見かけた
「外はどうして寒いの? それは北風が吹いているから!北風はどうして寒いの? えーっと、最初の質問は何だったっけ・・・」
子どもの旺盛な好奇心を見て微笑ましく思った。君よ、その好奇心をいつまでも忘れないでほしい
仮定思考
仮定思考とは、命題を構成する前提を肯定と仮定することで、全体的な思考をするための思考法のこと。一つの物事や一つの命題のなかにも、いくつかの前提が仮定されている。もしこの中のどれか一つの前提に疑問を抱いてしまうと、語り手が総意として伝えたいことを理解するのをさまたげてしまう。下記の例題を見てみよう
「思考とは、最小のエネルギーでおこなわれる実験的試みである」
<アンナ・フロイト>
たとえば“ほんとうに思考が最小のエネルギーなのだろうか、ほかに最小のエネルギーで何かをなせることはあるだろうか”と疑問をもつことや、“実験的試みとはなにを意味するのか、その試みはなにを目的とするのだろうか”と間接型思考をしてしまうと、この命題の理解のよどみない進行をさまたげてしまう。このとき、アンナ・フロイトの言いたいこと、つまりこの命題にかけた彼女が伝えたいことを理解するためには、どうしても一々の前提のフックにひっかかってしまったところから自分の服をほどいてやらねばならない。その解決方法はただ一つ、ひとまず前提の疑問をおいといて、それがそうであると仮定することである。前提を彼女のいうとおりのものだとして仮定する、すなわち前提を故意に通過することで、命題に対する全体的な思考、いいかえれば直接型思考をする土台をつくるのである。したがって、仮定思考の目的は、語り手の述べることをひとまず理解するための手段にほかならない
関係思考
関係をぬきだしてそれを敷延する思考のやり方。その一文のアブダクション[ある規則の地固めを行うとき、他に関連した現象を求め、これも同一の規則の下に収まり、同一のトートロジーの上にマップすることが可能だと論じていく作業のこと。ある記述における抽象的要素を横へ横へと広げていくこと]をこころみるときには必ずおこなわれる思考法です
他の物事に当てはめてみてそれがどのような意味をもちうるか、というようにノエマを敷延する思考のこと。関係の抜き出し[アブダクション]もその内に含まれます
(例-a)
「悪法もまた法なり」
<ソクラテス>
ソクラテスのこの文の関係をぬきだすと、たとえば「善いものも悪いものも、しかしそれであることには変わらない」といったぐあいになります
(例-b)
「大切なのは普通の語で非凡なことを言うことである」
<ショーペンハウアー>
この文の関係をぬき出すと、たとえば次のようになります
・「美文やレトリックは主の思想の価値を高めるものではない。それはただ表現の手段にほかならない」<私≪21才・夏≫>
・「大切なのはあくまで思想の中身である」
―
この例で注目なのは、この関係を抜き出したあとの記述があくまで関係をぬき出すことだけに終始していて、ショーペンハウアーが言ったことに難癖をつけたり自分の意見をおりまぜたりしていないというところです。純粋な関係思考の例といえます
(例-c)
「定義をしようと試みればいつでも困難におちいる」
<ジークムント・フロイト>
今度は、この文から関係をぬき出すのではなく、この文をすでに関係をぬきだした文として考えてみます。するとこの関係[文]からさまざまな具体例が生み出されます
・「愛とは何かを考えても、その導き出された結論が本当の答えであるかどうかなどはどうして知り得ようか」<私≪21才・夏≫>
・「明断されたものがいつでもその真であるとはかぎらないものだ。それでも私たちはいつもハンカチの結び目をぎゅっときつく締めることを怠らない」<私≪21才・夏≫>
【この場合の困難とは、自分で自分の首をしめていることに気づかないという意味を含ませたものです】
・「明瞭化された物事というのは、見ている私たちにとっても実にすっきりしていて気持ちがよいものです。しかし、二極論は、その圧倒的な明快さとひきかえに、物事のより正確な把握と判断を支払っています」<私≪21才・夏≫[極論づけることについて]>
・「答えがないところで答えを考え続けるのは愚かな事かもしれません。しかし答えがないことを知っている人はいないのです。しかしだからといって愚かではなかったとされるわけではありません。そうされるのは答えがあるのが真実である場合だけです」<私≪21才・春≫>
・「一見して人生には何の意味もない。しかし一つの意味もないということはあり得ない」<アインシュタイン>
(例-d)
「満足は自然の与える富である」
<ソクラテス>
この一文は、今の時代、あるいは他の物事でどのような意味をもちうるだろうかと敷延してみる。私たちのまわりで満足をとりまくもの、出来事、意味、先入観、コンセンサス、理念、はては富をとりまくもの、出来事、意味、先入観、コンセンサス、理念、それらから浮き上がってくる具体的な数々にはどのようなものがあるか、自然についても然り。そしてそのような具体例のいくつかにこの一文を当てはめてみるとどうか
(例-e)
「結果は手段を正当化しない」
おそらくこの一文からも下の(例-f)の一文からも、多くの敷延が望めるはずです。答えを探すことが一生懸命になりすぎると答えを用意していると言われがちですが、大事なのは答えを用意することではなく答えを探すことです。ただし探すということにうぬぼれて、探せば必ず答えは手に入ると錯覚してはなりません。そのようなうぬぼれは果実が手に入らなかったときに探すという行為を否定してしまいます。せめて自分自身に対しては謙虚で素直に受けとめることが健全です
(例-f)
「おそらく、他人にわかるのは、わたしがどんな人物かではなく、どんな人物に見えるかだけだ」
この一文からどのようなアブダクションの関係思考ができるか
a 関係思考の自由
関係をぬきだす関係思考にもその程度の度合いというものがあります。そもそも実際によくある関係思考のパターンとして、ぬきだした関係を他の物事のどこにどのように敷延するか、というのがあります。豊かな関係思考をめざすにあたって大切なのは、自由という名の柔軟性を高めることです。ここで一つ例を出しておきます
「かつてある本で読んだことがあるが、出生にたいする胎児の考えは、死にたいするわれわれの考えと同じだそうである。胎児は出生を大変動――胎児の現在の生命の終結、および、腹のかなたの世界への動き――と考え、外の世界についてはほとんどなにも見当がつかず、そのために、胎児は出生を死と呼んでいる」
<サミュエル・バトラー>
たとえば単語には意味があります。その意味の捉えかたにかんして、単語を意味でどのくらい強く縛りつけるのか、言いかえれば単語と意味の結びつきの強さに強弱があるわけです。もちろんその前段階にはどのような意味を単語にあてがうかという前提があります。“死”という単語に“生命の終結”という意味をあてがうのはいいのですが、その両者のあいだに結びつきの強弱があって、たとえばそれが強いとその意味は文字通り“生命の終結=死”であるということにしかならないが、逆に弱いとその意味は“生命の終結(に対置する)=生”でもある、という見方にもなるわけです。ここで重要なのは、結びつきの強弱というのはあくまで示された結果であり、その強弱をつける始原は単語の意味に帰属する、というところです。“死”という単語にどんな意味を与えているか、仮に“生命の終結”という言葉の上では同じものでも、その意味がどんなとらえかたをされているかによってその意味と単語のあいだの柔軟性に違いが出るのです。その柔軟性の高低差が関係思考の敷延のされかたを決定しています。サミュエル・バトラーが引き合いに出した本の著者の場合、彼女の死にたいする考えこそ世人と同じであるかもしれないが、その柔軟性が世人よりあきらかに高いことが証明されるはずです。これは私の憶測ですが、彼女はまたこうも言いたかったのかもしれません
「死=生命の終結であるが、生命の終結=死だけの意味であるとはかぎらない。生命の終結という点だけを支点にして考えてみれば、生もまた生命の終結であるということが言えるかもしれないからである」
手ざわり思考
[グレゴリー・ベイトソンより]
手ざわりというのはゆるい、ゆるめるということ。それは意図的にゆるめられるわけなので、したがって手ざわりという言葉が適切だと思った。ある漠然とした概念が現われて、それを厳密に言い固めてしまうことは、意味のしっかりした用語をいきなり与えて事態(解釈)を間違った方向へ持っていってしまう弊害が起こる。そうならないように、ある「ゆるい」表現をその概念にくっつけておく。これが手ざわりという表現になるし、それをそのまま意識付けしたゆるい思考として概念化されるものでいい。それを使っている間は、それが指している概念が曖昧であり、さらに分析が必要だということを意識させられる。これはハンカチを結んでおくトリックのようなものだが、これの利点はちょっと強引にいけば、ハンカチをそのまま他の目的に使えるという点にある。その曖昧な概念を非常に重要な緩められた思考の過程で使い続けていくことができる。この思考は人の、物事をすぐにはっきり分けたがるという癖に対抗するものなので、自分が今やっているのはゆるい思考なのだということを意識させる必要があるし、おそらく最初はその練習が必要だろう
グレゴリー・ベイトソンは科学の進歩について次のように述べている
「科学の進歩を遅らせないという消極的なことだけではなく、積極的にプロセスの促進を図っていくべきです。今日わたしはその方法をふたつほど提案しました。ひとつは、過去の科学を訪ねて現在の研究題材に適用できる大胆なアナロジーを見つけること、そうやって大胆な勘による『ゆるい』思考からはじめて、しだいに思考を厳密化する訓練をみずからに施すことです。もうひとつは、厳密な定式化の済んでいないところには、忘れずにハンカチを結んでおくこと。定式化を急ぐことはないけれども、いま使っている用語が試験的なものにすぎないということはいつも明らかにしておかないといけません。仮のものにすぎない言葉が、まだ知られていないことを後の研究者に見えなくするフェンスになってはならない、むしろそれらは『この先未踏の地』と書かれた標識として使われるべきです」
a 前提のゆるめ
どんな物事からでも学ぶことはできる、というこの偉大な金言の意味を言います。物事を捉える視点が決して一つだけではないことを分かっていながらであれば、自分が最初に捉えた全体の意味や単語単位でのその意味の以外のとらえかたができる可能性を信じて、他の視点からもとらえてみようと考えてみる[前提のゆるめ]その素晴らしい姿勢にまず価値があることが一つと、それから、実際に、その結果が用意されている事実がもう一つであります
たとえば「止揚[しよう]」という言葉があります。止揚とは、――あるものを否定しつつも、より高次の統一の段階で生かし保存すること。〈否定する〉〈高める〉〈保存する〉の三つの意味を含める。高次の統一。揚棄。アウフヘーベン――ということです。止揚にはこのような三段階のステップがあって、とくに今回その中で注目なのは<否定>したあとに<高める>という段階があることです。<高める>というからには否定者は別の答えを用意しているということです――たとえば反対者の意見に反対する賛成者の意見とかです。さて、前提のゆるめはこの<高める>ことをせず、すなわち他の意見を持ち合わせずにただ否定だけするのです。これは文字通り、前提をただゆるめておくこと、前提をくずすことです――このことがありましたから最初、前提のゆるめの命名のときは「前止揚」にしようかとも思ったいきさつがあります
それともう一つ「前提のゆるめ」が「止揚」と異なる点は、止揚は前提に限らず全体でもどんなものにでもかの意味をあてがいますが、前提のゆるめは前提だけがその対象だということです
世人の中には、否定するに値する十分な根拠として、別の答えを持ち合わせていなければならない、という者がおります。つまり止揚でいう「高める」[別の考えを主張する]ことをしなければならないと言っているわけです。どうしてすぐそのような二極論に走ってしまうのでしょうか。どうして常に答えを決め立てておかないといけないのでしょうか。彼女らはより正しい答えを探究することよりも、間違った答えでもいいから何か解答を用意しておくことのほうが重大なのでしょうか。別の答えがあることが、否定することが正当化される根拠になるわけではありません。反対に、代わりとなる答えがないという理由からその否定が正当ではないと言われるのも間違っています。否定することが正当性をもつのは、ただ唯一その否定の内容によってだけ図られるものです。否定ばかりして代わりの主張を用意しない人に対して、その否定が的を得ていないものだと言うのは論点がずれています
(a-例) 「満足は自然の与える富である」
<ソクラテス>
思考のバリエーションはいくつかあるでしょう。例えば、(1)どうして満足は自然の与える富なのだろう、というような全体的な思考[直接型思考(“用語解説”)]。(2)満足とはどういう意味だろう、ひいてはソクラテスにとって満足とはどういう意味だったのだろう、あるいは自分にとって満足とはどういう意味になるだろう、というような部分的な思考[ピックアップ思考(“用語解説”)]。(3)一文を肯定したうえで、ではそれは今の時代、あるいは他の物事でどのような意味をもちうるだろう、と敷延せしめる思考[仮定思考+関係思考(“用語解説”直上)]。(3-a)一文のアブダクションをこころみるときに、関係をぬきだしてそれを敷延する思考のやり方[関係思考]
「悪法もまた法なり」
<ソクラテス>
この文の関係をぬきだすと「善いものも悪いものも、しかしそれであることには変わらない」といったぐあいになります
とりわけ(2)については、部分の前提をさぐる試み、つまり固定されていた前提というハンカチの結び目をゆるめた状態にしたのです
置換思考
物に対して持つ先入観を消すために、物を別の物であると仮定して考える思考法
例えば、サッカーにおけるゴールを挨拶と置き換える、と置き換え思考すれば、挨拶に持っている先入観「必ずしなければならない」をゴールの先入観と置き換えることができる
また、分かりにくいものを一旦分かりやすいものに置き換えて全体を作り上げ、完成してから置き換えたものを元に戻す置き換え思考もある
その他の思考
解決思考
解決思考とは、解決するためにする思考のこと。ある問題提起について、何らかの答えを出す目的がある。例えば、みかんを二人で分けて食べるとき、「半分こする」と答えを出すことは解決思考である。解決思考の反対が前提をさかのぼっていく疑問思考(“用語解説”)である。疑問思考の特徴は疑問を生み出すことで、それはいわば問題提起をしている状態である
ビジネスの世界では必ずしも答えありきではない。迅速な解決が求められるときもあれば、頭をひねって何か新しいことを生み出したり問題を改善したりすることも求められるからだ。先の例で、みかんを二人で分けて食べるとき、疑問思考であれば「なぜ欲しいのか?」と問う。答えが先行していると、みかんについての思考をしなくなる。安易な正解や、最初から決まっている答えを踏襲しない。先にあるのは答えではなく、仮説もしくは選択肢であり、ケースバイケースでいちいちジャッジメントすることが必要である
後退思考/再構成思考
後退思考とは、行き詰まりをみせた問題から前の問題へ立ち戻って再び問い直すことで行きづまりを解消する思考法のこと。後退思考の原理は、後ろに下がると視野が広がる、というもの。行き詰ったら、少し引いて考えてみることである
再構成思考とは、行き詰まったときに既存の問題に立ち戻るのではなく、既存の問題を改めて問い直すことによって問題そのものを再構成する思考法のこと。再構成思考の原理は、分からなくなったら分かりきったことに疑問を当ててみる、というもの
後悔無し思考
後悔無し思考とは、後悔しないためを第一の優先順位にもってくることで、学びの収穫を増やすことと、心の平安を得ることを目的とする思考法のこと。思いついたこと、やってみたいことを全て実行するのが原則のため、作業の量としては多くなる一方、それによる収穫も増す
後悔無し思考は行動によく影響し表れる。後で後悔するくらいなら当たって砕ければいい。そのほうが多くを学べる。聞きたいと思ったら聞くことだ。行動を起こさなければなんも始まらない。一番の後悔はなんもしなかったこと
(コツ) 常に後悔しないかどうか自分に問いかける。周りの弊害は一切気にせず、自分の気持ちに正直に
原因多角思考
原因を見つけるには多角的な視点からの解析が必要である。これを原因多角思考という
(例-a) 白い紙にペンで文字が書けなかったら黒い紙に書こうと思うこと。あらゆるものを疑ってみること
(例-b) ビジネスの世界において
C級社員にこそ多くの目を向けるようにしてみること。原因はどこにあるか分からない
立場交換思考
立場交換思考とは、立場を故意に置き換える思考法。その目的の多くは、相手の立場をより理解するためである
相手の気持ちが考えても分からないなら、相手と同じことをしてみること。小売業の経営者は、お客のニーズを知るために大衆食堂で食事をする
そして思考
ビジネスの世界でよく使われる、「不安だから仕事がうまくいかない」
“だから”を使うと過去にしばられるから使わない。二つの治療法がある。一つの方法に固定しないで予測不可能な場面を作ってみるということと、“だから”を“そして”に変えることである[そして思考]
外部要因思考/内部要因思考
うまくいかなかった原因は、往々にしてたった一つだけである場合は少ない。原因は複数あるのが普通である。たとえばある失敗をしたとき、その失敗の要因は自分にもあるが同時に周りや相手にあることもある。このとき失敗を引きずらないために、ミスを自分のせいにするか[内部要因思考]、自分のせいにしないか[外部要因思考]
不満建設思考[だからこそ思考]
ビジネスの世界でよく使われる。不満を建設的に生かす思考法
人のため息を自分のチャンスに変えることを考える。不満になることでも、「だからこそ」と言い、建設的に生かすことを考える
感情付加思考
多角的な視点の一つには、対象がもし人だったら、という視点もある。つまり、対象に感情を持たせてみるのです。これが感情付加思考である
純粋価値思考
ものの持つ純粋な価値をできる限り見つけ出し、それを主体に思考するのが純粋価値思考である。もの自体をしっかり見て据えていれば、時間の経過だけでなんとなく判断をかえることにもならないだろうし、小さな影響による変化も、単に属性が付加しただけで、そのものには何の変化もないことにも気づけるはずである
ものの持つ純粋な価値を知覚するためには、まず客観的な見方ができることが重要である。ここでいう客観的の意味は、すなわち感情的観念を除くという意味であることを特に強調させておきたい。感情的な視点は物事の捉え方(結論)の決定に大きく影響している。この点について関連の深い事例を述べておきたい
(例) この例の全体的な過程はこうだ。まず議題が「生物の行為はすべて、何かしら試行錯誤的な(ストカスティックな)面を持つ。」についてで、その理由を述べている。その理由を書き上げる前に「間違った理由」があり、それを「理由」の後に書き連ねる。その「間違った理由」の中に、私が気づいた事柄があり、それが「感情的な視点は物事の捉え方の決定(結論)に大きく影響する」という説明に深く関係しているものである。ではまず過程通りに「議題」と「理由」から述べていこう
―
「生物の行為はすべて、何かしら試行錯誤的な(ストカスティックな)面を持つ。新しいことをためしてみるには、その行動に、多少なりとも場当たり的な、ランダムなところがなくてはならない。できると思われる、という確証が、実際にできるかどうかの成否を決めているわけではない。成功しそうか失敗しそうかという確率的要素に基づいて、どんな『方法』を採るか、という方法を採っている様子に試行錯誤的な面がみえる。試みられる行為が、すでに十分調べ尽くされた行為のクラスに属するものであっても、はじめての試みである以上は、『こういうふうにやるものだ』という命題の確証あるいは掘り下げに幾分かは役立つはずである」
―
上記の「理由」を書き上げる過程で、私は一つ思考の寄り道をした。それを下に述べる
―
このように言われても、私には「生物の行為がすべて試行錯誤的な面を持つ」ということがどうにも理解しがたかった。何かを成すときでも、人は一つの方法をもって成そうとする。つまり何かを成すには、必ず(最低でも一つの)「方法」というものを選び、採用しなければならない。この「方法」を選択する方法について、人は経験や環境などから――最もそれがうまくいくとされるだろう――「最良と思われる方法」を選択する、という方法を採る。確かにこの方法をみれば、その方法が試行錯誤的なものであるとは考えにくい。それが私が理解しがたかった要因なのだろう。しかしこの問題を精察してみると、どうやら私は自身の盲点に気づく。物事を成すための「方法」を選択する方法、そのプロセスにおいて――「最もそれがうまくいくとされる“だろう”」という――主観的・感情的な要素が介在している点である。本来の提起は「生物の行為はすべて、何かしら試行錯誤的な(ストカスティックな)面を持つ。」というものだった。この問題は客観的・統一的に立つ形式であるため、そこに感情的観念の介入の余地は許されない。ということはその要素を除去しなければならないのだが、そうなるとどういう記述になるか。もし人が「方法」の選択肢を用意する際に主観的・感情的な要素が取り除かれたとしたら、――実際的に選択肢が出せるか出せないかに関わらず――選択肢を用意する過程は完全に客観的立場に拠るものではないだろうか
―
上記のいわば「間違った理由」を私は考えたわけだが、少しこの理由について考察してみよう。この理由が間違ったものであるとするわけは、おおむね三項見受けられる
(1) 選択肢を用意する過程の前提条件は、選択肢が用意されるということである。選択肢が用意されなければ過程そのものが存在し得ないからだ。これは単純なことだ。選択肢を用意する過程の説明に、“実際的に選択肢が出せるか出せないかに関わらず過程は成立しうる”という単純な矛盾が生じている
(2) 議題の「生物の行為がすべて試行錯誤的な面を持つ」と言っているところが言及しているのは、「物事の成否」というクラスにおいてだ。しかし「間違った理由」では「“方法”の選択肢を用意する方法」について焦点を合わせている。これは誤った問題の捉え方である
(3) 「最良と思われる方法」を選択する方法を採ることについて、それは試行錯誤的ではないと述べたが、ここで私は「試行錯誤」の意味を履き違えていたようだ。この試行錯誤という意味を、なんの意図も企みもないある意味完全なるランダムな選択方法という意味で捉えていたのだ。そうつまり、「試行錯誤」を「ストカスティック(語源であるギリシャ語のstochazeinは「的をみがけて弓を射る」の意。そこから、出来事をある程度ランダムにばらまいて、そのなかのいくつかが期待される結果を生むように図るという意に転じられる)」と同じ意味だと勘違いしていたのだ。試行錯誤は、十分に(結果通りになるだろうという)意図が含まれた結果、失敗の連続が続く、その中で成功という結果を追求するというのが本来の意味なのではないだろうか
私がこの例で言いたいことは、誤った思考からでも収穫は得られるということである。寄り道はそんなに悪くないと思う。少なくとも思考の寄り道は、寄り道をするということに意義がある。今回の収穫は、この寄り道における思考がもたらした、より抽象的なトートロージーである。では試しにこう考えてもらいたい。もし上記の間違った理由が正しいとしたら、どのような収穫が得られそうか。私が一つ考えたことは、結論が導き出される要因に着目した結果的対比という視点である。「間違った理由」の思考において、人の感情的観念の存在は議題の結論を左右するものだった。人の感情的観念が除去されると、それはたちまち客観的観念となる。客観的観念が主観的観念より公平で、ゆえに真実に近いと信じる私はこう思った。感情的視点を排除することで、よりものの持つ純粋な価値を取り出すことができ、「純粋価値思考」の達成に近づくのではないか。まあそれだけではなく、前提の正否が結論の正否を左右するということも改めて学んだわけだが。ということで今回の例で得た収穫を簡単に列挙しようと思う
(1) 誤った思考からでも収穫は得られるということ
(2) 感情的視点を排除することは、純粋価値思考の達成に近づく
(3) 前提(焦点)の正否が結論の正否を左右する
疑問思考/重要思考
ある料理を作るために材料を買う。その材料は「この料理を作らなければいけない」という意志の原動力になる。「なぜこの料理を作らなければいけないのか」という問いには「材料を買ってしまったから」と答えるだろう。だがそれは本当の答えではない。単純思考で終わらせないためには、回答に対して「なぜ」を付加して疑問形にする“疑問思考”と、どれほど重要なのかを問題にする“重要思考”の二つがある。今回の例だと、「材料を買ってしまったから」という返答には、疑問思考だと「なぜ材料を買ってしまったのか」となり、重要思考だと「材料が重要な理由はなにか」となる。また、前者だと個人的価値へ向かう傾向があるのに対し、後者は社会的価値に向かう傾向がある。疑問思考はアイロニー話法(“話法”)の原型である
(例) 疑問思考が有効な自己命題が信仰によることの証明
これは日常においてよくあることだと思うが、例えばプロクロニズムと個体発生の関係といったすばらしく論理的に導き出された考えも、このキノコはいい匂いだからきっと食べることができるだろうといった単純な考えも、両者は「優劣」という視点で評価されることがしばしばある。深いとか、単純だとか、ばかだとか、考え方というのは、よくそのような類の評価を他人から受ける。しかしどんな考え方でも疑問思考を用いて元を辿っていけば、その本人が「絶対真実と信じる」事柄が=自己命題であることに気づかれるだろう。つまり結局は誰しも、何かを信じないと自分の考えを持てないのだ。信仰は人の思考の基盤である
ゼロ思考
まず、いまいる地点をゼロに合わせてみる。最悪のいまを、ゼロと考えるのだ。誰かのせいにして責めることも、苦しみを嘆く必要もない。それは、ゼロよりももっと低い位置のマイナスにいることになる。それでは苦痛ばかりにとらわれて、ますます動けなくなってしまう
まずは、すべてを見切って受けとめること。それが、これ以上事態を悪化させず、先に進んでいくための心構えである。ゼロは、マイナスではなく、スタートなのだ
人というのは、最低を保障されて、はじめて安心を得ることができる。最悪を最悪と思わず、これ以上最悪なことはないのだからと考えて、この地点をゼロとすることをゼロ思考という
対思考[ついしこう]
自分の出した答えは信じることが大切です。でもそれは絶対ではありません。ベストと思ったAという回答と、もう一つまったくさかさまに見たBという二つの回答を用意しておくのです。考える角度が広がり、同時に安心感も生まれる。自分とまったく逆の考えも認めるということだから、人に対して寛容にもなれる
「チャールズ・ダーウィンは、自分の理論にとって都合のよくない観察は、とくに注意してノートをとっておくという黄金律をたてたといわれている。自分に都合の悪い観察となると、なかなか記憶に残りにくいものだということを、彼は確信していたのだ」
<ジークムント・フロイト[ダーウィンについて]>
ダーウィンのこの姿勢に本当に共感するのであれば、彼の姿勢を真似するのでなくてはなりません。ただダーウィンのように器用に抜け目なくできる人はなかなか少ないかもしれません。しかし大事なことは、自分にとって都合の良くない事から逃げ出さないことです。これを実践するためにも対思考は役に立つと思います
ジークムント・フロイトは精神分析学入門の著で、自分の考えに批判的な人や懐疑的な人や、初心者が言いそうなことを文章の合間に挟んでその質問や意見に自分が答えていくという対話形式で本を書きました。賢者はしかしこのような一面も持っているべきです
ヒューリスティック学習[発見的学習]
ヒューリスティック学習とは、試行錯誤の中で、失敗から誤りを起こす「違い」を発見し、それを避けることでよりうまくできるように(発明できるように)発展させていく学習過程法のこと。ヒューリスティック学習では「違い」を、「なにが良くてなにが誤りかという基準によってシステムを知ろうとするときの情報」として重要視する。「違い」が情報においてなぜ重要なのか。これについては違いを作る違い(“グレゴリー・ベイトソン書付”)から引用したい
「違いを作る違い」とは、グレゴリー・ベイトソンが気に入っていた言葉で、言い直すと「違っていることが『わかる』ほどの違い」。「違い」を見つけるには、「違い」が知覚されなければならない。なので「違いの分かる違い」が情報になる。たとえ、「違い」は存在していても、それが観察者に知覚されなければ、「情報」にならない。情報にならないということは観察者にとって「存在しない」ということである。システムというのは、いろいろな情報が伝わったり、途絶えたりして生きている。情報は「違い」で伝達されるため、「違い」がなければ情報にならない。「他と違う」ことが情報なのだから、違っていることは重要なことなのだ
そして、違いを発見するための試行錯誤においては、ストカスティック的(語源であるギリシャ語のstochazeinは「的をみがけて弓を射る」の意。そこから、出来事をある程度ランダムにばらまいて、そのなかのいくつかが期待される結果を生むように図るという意に転じられる)な精神が必要とされる。要は「なにが違うのか」=「それはどんな情報か」ということを意識するということだ。ある程度の知識をいれて、実際の運用はその知識を基準に対処させ、想定していないことが起こったときにも自ら判断して対処する方法は、発見的であるといえる。対して、コンビニのマニュアルのように、この場合はこうすると、場合分けしてきっちり決めることをアルゴリズムという。コンピューターのプログラムはアルゴリズムだといえる
受動反応
《元々は「反応反射【旧文】」から》個々の人の裡にある固有の観念のこと。別の言い方をすれば、先入観(“用語解説”)、あるいは第一実体/第二実体(“アリストテレス書付”)ともいいます
たとえば、赤色というのが何か知っている人たちは、そのなかでもほぼ全ての人が同じ観念(=情報)を脳から引っぱり出します。それは彼らが、赤色というものに対して同じ観念をすでに用意していたからです。これを第二実体といいます。第二実体は確かに同じ観念を有してはいたが、しかしそれは共有しなければならなかったものではなく、実際は個々の観念であるので、これも受動反応の一つです。また第一実体とは個物や個々の意識のことを指します。赤色は赤色だが、赤色を好きか嫌いかという問題は個人的な感情であり、第一実体はこの個々意識を指します。この第一実体も第二実体と同じく個々の観念の結晶であるので受動反応の一部にはいります
受動反応は単語や五感等[⇒観念表現]と結びつきますが、単語などが知覚されないときは記憶される情報として脳内に保存されていて、また結びつくときは記憶を媒体にします。赤色が好きという観念は赤色のことを考えなくなっても消えるわけではなく、その観念は記憶され、再び赤色を見たり考えたりしたときに思い出されることになるのです
【旧文】反応反射/否定反射
反応反射
相手の言った言葉について(その多くは言葉の上辺である)、何よりもまず先に理解されるもの。思考はこの反応反射の後で行われる。これが起こる原因は元から言葉自体に意味があるから、そのために、会話の前後・状況・雰囲気などを無視してひとつの言葉単位で認識し、評価してしまうからだ。これによって最終的な評価が変わってくる
これが良いのか悪いのかは知らないが、一つ大きなデメリットがある。それは、この反応反射が先入観となって、無心思考をする障害になるということだ。そして反応反射(後の先入観)を完全に取り除くのはGを食べるよりも難しいことなのである。これが、無心思考が難しいといわれるゆえんでもあるのだ
否定反射
相手に不本意な言葉を言われたとき、「君の言っている事は私が思っていることと違う」という否定の反応反射。特徴は反応反射と同じである。⇔「肯定反射」
可変本能/絶対本能
可変本能
人間の本能のうち、努力によって抑えることや変えることができる本能のこと。性欲や愛、常識や根底感情(うれしさ、悲しさ、やさしさ、怒りなど)など
絶対本能
人間が生きている限り、必ずしてしまう、本能のこと。食べること、寝ること
被体意識/加体意識
被体意識[被体性質]
ノエマ[思考された対象]のもつ意識や性質など
加体意識[加体性質]
思考する側のもつ意識や性質など
万学[ばんがく]
どんな事からでも自らのとらえ方や思考しだいで学ぶことができる、という自身の志をもって万物から学ぶこと。又、その精神
相存理論[相反同系列存在理論]
そうぞん理論。相反定義した二つの概念は、セットで同系列(世界)に存在するという理論。例えば、「有限」と「無限」を相反なものとして定義したら、この二つは不離不別のセットとなり世界に存在していることになる。また、一方の存在が確定すればもう一方も明らかとなる。つまり有限が存在すれば無限も存在するということになるのがこの理論の特徴である
対概念
a 純対概念と人為的対概念
対概念としてセットした両者には二つのタイプがみられる。例えば、見る―見られる、攻撃―守備などの対概念は、確かに、一方が存在したら同時に他方も存在するというそうぞん理論の特徴がみられる。このタイプの対概念のことを純対概念と呼ぶことにしよう。もう一つのタイプの対概念は、例えば合理―不合理などがある。こちらはそうぞん理論で説明することはできないが、合理的ではないからといって不合理だということにはならない、というような説明ができるだろう。こちらのタイプは人為的対概念と呼ぶことにしよう。この両者の違いは何か。そうぞん理論が成り立たない対概念は正しい対概念とは言えないのだろうか。それとも、両者を峻別する理由が他にあるということだろうか
心じない
心持ない[こころじない]。心の支持がないの略語。普通ひらがなで用いる――心持[こころもち]と混同しないために。次のような意味。科学のように、確かに長所もあるしできることもあるからやってもいいよ、でも、それをやればやるほど失っていくものや見えなくなっていってしまうものもあるために、それに身をゆだねることを完全支持するわけではないよ
二極論
二極論とは、ある物事の結論に関して、YesかNoか、是か非か、白か黒か、はっきりと判断する思考法の一つ
いかな結論にも理由が必要なそのわけについて
私は、現代の私たちが、物事を判断するときにどのようなプロセスを採っているかについて、最近少し気にかかったところであります。たとえば私を例にとってみても、物事を判断するときはきまって、まず認識し、思考し、そして判断しています。認識の過程は個人的には興味深いと思うものの、それについて皆さんと一緒に積み木を積むのは別の機会にするつもりです。今回は、私たちが主に用いている思考の一形態、すなわち二極論について、気になった特徴を積み木の材料としたいのです。結論と申すからには、この思考法が判断をも決定することを念頭に置いておいていただいて、そこのところは後々にふれる折があるでしょう
そもそも二極論とはなにか。簡単なものです。ある物事をYesかNoか、是か非か、優か劣か、存か否か、白か黒か、はっきりと極論づける判断方法です。現代においては特に多くみられるこの二極論、たとえばビジネスの世界、法の世界、お金の世界などは言わずもがなといったところでしょう。明瞭化された物事というのは、見ている私たちにとっても実にすっきりしていて気持ちがよいものです。しかし、二極論は、その圧倒的な明快さとひきかえに、物事のより正確な把握と判断を支払っています。そして確実に、正確な判断というものが今の世の中から求められていることも、どうやら事実なようです。ということは、私たちは当然ながら、二極論だけに頼るわけにもゆかず、また二極論をまったく頼らないわけにもゆきません。この点についてはどうやら二極論が活躍する場ではないようですね。そこで私は、物事をたとえ大きく大別するにしても、賛成と反対のほかに中立も導入するべきだと思うのです。しかし中立を導入することは、とくにその中立に対して、なぜなのかの理由も併せて導入する必要があります。なぜか。ここは佳境だからはっきりさせておきましょう。二極論が活用されない場面や不要な場面があるのは、けしてこの判断法そのものが使えないわけでも、悪いわけでもない。そこにはただたんに理由が必要なだけです。ここで皆さんには、頭に一本の線をイメージしてもらいたい。一本の線の極、つまり端と端が、この場合でいう二極論なのです。だとするとそれ以外の部分の位置とは、いったいなんでありましょうか。そう、つまりたんに二極論ではない結論ということになります。悪いけど良い部分もある、完全にYesとは言えないところだ、など、いわゆる中庸とよばれるゾーンに彼らは腰を落ち着けているのです。ことにこのような場面は私たちの日常生活でもよくあることだとは思うのですが、この中庸と二極論の違いは結論の違いだけであって、それ以外のなにものでもありません。つまりは両者とも一本の線上にあり、何かしらの拍子によって、すぐにお互いにとってかわることもできるような、同じカテゴリーに属しているということです。だとするならば、私が最初に申し上げた二極論の至らぬ点の一々について、これを非難し、同時に中庸を説くなどというまねはばかげた行為になるでしょう。さはさりとて私が先ほどにこれをやってみせたのには、いかにもそれなりの理由があってのことです。つまり中立の導入にあたって、理由の導入も併わせて提案したのには、中立にしても中庸にしても、それは二極論となんら変わらない手法であって、さてそれでは根本的なブレークスルーとなるものは何かというと、それは「理由」による位置情報の表示であり、これが物事の正確無比な把握に資するものだと考えているからであります。判断がなぜその判断になっているのかについて、私たちは申し開きを述べるべきで、これによって、私や彼女らの意向がはっきりつかめるわけなのです。それだから、もし理由というものがなかったとしたら、私たちは豚の鳴き声のごとくただただ結論を述べるばかりで、そこに多くの秘めやかな謎が生まれてしまうことは説明にかたくないでしょう。そもそも理由があってこその結論なのですから、理由があるならば、本来のところ私たちは、結論の是非を問うべきではないとさえ思えるのです。つまり理由には理由があるということです。ここに環境的風土が多く関わっているのだということを忘れないでいただきたい。もちろん「理由の理由」には、およそ容易には知りつくせそうもないいくつかの要素が、アナログ的な参加の関わり方によって、複合されているものではあるでしょうけども
自然な結論というのは、結論が二極的結論であろうとほどよい程度のものであろうとそんなものは関係なくて、ただただ導かれかたを示す「理由」が同時に示されることが、自然な結論というものではないでしょうか。ショーペンハウアーは、「自分の家から一歩も出なくても、人生に大切なものの答えは自分のなかにある」といいましたが、この二極論の完成度のいかに高いことかを知るのは有意なことでありましょう。これは偉大な金言となっていることと同時に、しっかりと論理的思考がなされているところにも注目です。といっても私は、ここでこの金言の正しさを支持しようというのではありません。私がここで皆さんに固唾をのんで注目してもらいたいのは、いうまでもなく彼の(答えに対する)理由の示しかたです。ひとまず彼が“答え”とよぶものが何か漠然としないものではあるでしょうが、しかしすでにこの時点で“答え”について分かることは、答えを探求するために必要な要素です。それとはすなわち、答えのオーディション(答えを決めるためのオーディション)を受ける材料であり、その材料の量と質です。何を答えとしたかは彼の決めたことでありますから、それはそれでおいといて、しかしそれでも、答えとなるものの材料が必要なことはわかります。どのくらいの数の材料がオーディションに参加するかという、まずこの材料の量と、それから、誰が合格となるかを選定する基準とでもよびましょうか、その基準から近いか遠いかという、すなわち材料の質です。この質と量はともに、材料に付随する観念の概念ではあるのですが、これらはけして一緒くたにできるものではありません。ですから安易にこれを混同してしまうと、申し述べることの筋が論理的におかしなものになってしまいます。では今回の例で、量と質とはなにに値するか。“答え”に付随する量と質ですから、まず質にかんしては、これは皆さんよくお分かりになるはずです――すなわち材料の質そのものということです。この質の高いと低いを運動させる要素は、彼の考えている選定基準に完全にゆだねられます。この点に関しては彼以外の人があれこれとやかくいうことはできません。しかし量に関してのことなら、われわれも少しは口をはさむ余地があるように感じます。なぜか。この例においての量とは、答えになりうる可能性をもつ材料の数々をあらわすものではありますが、この量を変動させる直接の原因となるものは、つまりいうところの思考因子(思考するきっかけ)であり、この因子の数は、いかにも環境によって変わるところが多少なりともあるからです。しかしそうはいっても、環境の違いの影響がすべての人に対して同じ及ぼしかたをする、とまで言ってはなりません。人によっては、外で人と交流していたほうが思考因子は多いのだという人もいれば、反対に家にこもりっきりのほうがよりその人らしい思索にふけることができるのだという場合もあります。これは彼女らの思考の形態と内容と質によるところでありますから、一概に外のほうが色々考えるきっかけがあるとか言うことはできません。つまり、環境の違いは、たしかに思考因子の数に変動をもたらすものではあるが、しかしどのような変動がはたらくのかということにまで言い及ぼせるほどの確かさは、太陽が天に昇り、月が満ちるのとまったく変わらぬ確かさの比ではありません。家にこもっているときと――当然ですが彼が家でなにをするかによって思考因子の数は変わるものですが、そういうこともふまえての事情であります――、外で友人とお茶をしたり人と交流しているとき、他にも多くの環境の違いがありますが、そういった環境の違いによって、彼が何を、どれほど、どれくらい考えるかは、常に変動してくるものです。ここで彼が最初に言ったことをふりかえってみると、思考因子の数に関して彼は「自分の家から一歩も出なくても」と平然といってのけております。この点に関して、私たちの通俗的な考えによればこういうことになります――<自分の家にこもったままだと環境の変化が少なくて、思考因子も減ってしまうではないか。そうなるとオーディション全体の質もさがってしまう>。この考えはずいぶんと奇妙なものに感じられます。つまりこの考えが主張しているのは、数が減ると質も低まると、こう言っているわけです(そもそも「自分の家にこもったままだと環境の変化が少なくて、思考因子も減ってしまう」と主張するこれの誤謬については前に述べた説明をもってかえさせていただきます)。しかしなにを根拠にそんなことを申しているのでしょうか。そもそも質は彼自身のみに完全にゆだねられるものであるから、そう考えると、数が質に影響を及ぼすこと、しかも今回の場合それがはっきり比例するように、直接度の高い大いなる影響力を与えると言っているように思えるところからみて、これはちょっと救いがたい誤謬だと顔をしかめるばかりです。たしかに外界を遮断すると、思考因子の数、つまりオーディションに参加する材料たちの数は減るかもしれませんが(この点も、必ず減ると断言できるものではありません)、しかしだからといって、それらの質が低められる必然の根拠などどこにもありません。量と質は比例関係にはない。ですから、量も質に対しては当然それでありますから、サイも角を突き立てようがなく、虎も爪の立てようがないわけです。皆さんの中にはどうも腑に落ちない感じをいだく方もおられるかもしれません。しかしその理由は明白であると思います。つまりはこういう事情があるからではないでしょうか――実際には、まったく両者が影響を及ぼさないことはない。その通り。しかしここで私たちは注意しなければなりませんが、両者がかならずしも影響を及ぼし合わないことはないからといって、両者が確実に影響を及ぼし合うと結論づけるような、安易な二極論に走ってはなりません。事実に即して、なぜこうなっているのかの理由を解明することが私たちには求められます。そこには必ず何かしらの理由があるとすることは、唯一推薦に値する主張になりえましょう。「自分の家から一歩も出なくても、人生に大切なものの答えは自分のなかにある」と言ったショーペンハウアーは、答えは“そこ”にあることを確信していて、それがたまたま、家から出るとか出ないとかにかかわらなかったというだけのことでしょう。“そこ”について彼は“自分のなか”と言っているが、その絶対的な根拠はただ一つだけです――すなわち、自分のなかに人生に大切なものの答えがあることをたんに彼が信じていたから、だけです
二極論に拠ろうとも、中庸を支持しようとも、そこに「理由」がなければ、どちらもただの結論にすぎません。そこでどちらが優位であるかなどと決めようとするのは不毛です。このことはショーペンハウアーが二極的結論を用いてそつなく証明されました。理由があってこその結論ですから、逆にいえば、私たちも、結論だけをきいて早計に耳をふさごうとなどというまるでばかげた行いをふみとどめて、ひとまず理由も聞いてみようかなと、そのような慎重な姿勢に信を置こうとなさるべきです。何も考えずにただ手だけ動かす働き蟻のようにせっせと生きているだけでは、ステレオタイプにわが心をばゆだねることと何のお変わりがありましょうか。自分の考えもたいしてもたず、ただ社会のお弁当になり下がっているようなミーハーな人たちほど、悲しいものはありません。結論だけを聞いてあきれる人や、ことによったら理由を聞いてあきれる人もいるだろうが、そういう方たちがあふれかえっているこの現代において、私は理由の思考、それもとくと考えることを提案しておきます
二極論に走ってしまうわけ
a 一つには、極端な例も可能性として考えられるから、という考えが内にあるからです。人は、起こりうるかもしれないことは、起こることとして考慮しなければいけないという思いにかられます。その感情体現が不安です。この種の不安には今のところ二つの意味が内包しています
b もう一つは「可能性として考えられることはすべて考慮しなければいけない」という理性的要請です――<この要請は幼児期から積もり積もってきた不安に対する防衛法のひとつです。つまり都度的なものではなく不安に対してはいつでも反射的に要請されるものだということです>
c 三つめは、個々の事例の極端な場合に対する都度的な不安で、それは具体的不安ともよべるようなものです。具体的不安は、ある事例の極端な例が実現する可能性の度合いと、その例が起きた場合の損失と不幸の度合いによって、いつでもその不安の大きさが変わります
――
結局はこの種の不安を広くみれば、それは出された結論や例は本当に問題がないのか、私たちに損失と不幸をもたらさないか、あるいはどれほどもたらすのか、などに関する不安であるとも言えます。だとすれば、その不安がもとにおこなわれる二極論はまさにその不安を少しでも取り除いておこうとする防衛法であるのかもしれません。ある意味でそれは議論を先取りしているようにもみえます
二極論が染みこんだ私たちの精神世界
二極論という考え方は、私たちが思っている以上に深く私たちに根づいています。たとえばある人が何か自論を持ち合わせているとします。世人は自分の意見を否定されることに嫌悪感をもよおしますが、あからさまに否定されなくても、ただ肯定されないというだけでも嫌悪感を抱くものです。彼の自論は肯定されなかった、相手がうーんとうなった、あるいは確かに最初は肯定されたがどうも相手の様子から全面肯定してはいないらしい、ということを彼が少しでも感じとると、すぐさま自分の意見は否定されたと思い込んでしまうのです。彼も世人も、皆自分にとって重要な事柄がせっぱ詰まった状況をむかえると客観的な判断ができなくなってしまったのです。しかし問題なのはそんな今さら分かりきった人間の普遍的な精神心理をいじめることではなく、冷静さを失ってより生物的な段階へと退行した人間がとる行動の中身であります。その中身の一つというのが二極論です。それは二極論という考え方がその深きところにまで到達していた習慣であったということを証明しています。そんな精神の内奥にまで押しやられた原因というのはいくつか考えられるでしょうが、その一つに「みんながやっていたから私もやった」という理由でびっくりするほど同じ行為が何回もくりかえされたために無意識的習慣がしだいに醸成されていったとする原因もおそらくあるはずです
二極論が悪いと言うわけではありません。ただ結論は二つだけではないということを肝心な場面でいつも気づかない私たちのことは、はっきり言って単純であります。そこに中庸を始めとする多様な結論があるという事実に目を向けてみることは、いつもそうするべきです。何事も極端すぎるのは害悪ですし、横暴は良い結果を生まないのがほとんどです。二極論の横暴による害悪は、結論の精度が低められることにあります。そしてその誤った結論を私たちは妄信することにあります。この横暴に歯止めをかけるのは、この横暴がさまざまなものに悪影響を与える弊害であると知り、それが横暴であることに気づくことです。そしてそれを諌めるのは理性です。もともと二極論は幼児期の理性の一つだったのですから、それを本来の表面の場所に戻してあげることができるのが理想であるかもしれません。ただ現時点で、一度根強く習慣化されたものを取りのぞいてやることがほぼ不可能に近いほど難しいということを私たちはうすうす気づいているとは思いますが。ただ根本的な解消は難しくても、それでも水際解決ならばどうにかできるかもしれません。そしてそれがどうにかできた場合には、なかなか素晴らしい効果をあげてくれるだろうことは想像に難くないと思います
「今の私たちにとっては、習慣の除去には、否定の習慣[否定の反復]が効果的な対抗であります」
<私≪21才・夏≫>
程度によって正否は変わるものではないと言うのなら、それは二極論的価値を支持しているのと同じではないか
記憶の重要的簡略化
記憶の重要的簡略化とは、小さいころの記憶でも、一日一日のすべての体験を憶えているわけではなく、転校した初日やトラウマなどの印象強いものだけが記憶に残るといったような、重要な体験のみ強く記憶されていく心的作用のこと
私たちの記憶は、私たちが後年の生活のなかで遭遇するさまざまな印象の材料に対しては、ある処理、すなわち淘汰をおこないます。なんらかの点で重要なものを保持し、重要でないものはふるい落としてしまうのです
忘れられた記憶のことを「隠蔽記憶」という。この用語の語源はフロイトからで、フロイトは小児期の記憶の健忘で、表面上重要とはみえないけれどもじつは重要要素が含まれている心情が重要心情との置き換えになっていることを、隠蔽記憶と呼んだ。小児期の印象は、けっして実際に忘れられていたのではなくて、ただ手のとどかないところにあり、潜在し、無意識的なものに属していただけなのです。ところで、これらの印象が無意識から浮かび上がってくることが自然発生的にもあります。しかもそのときは夢に結びついて浮かび上がってくるのです。このことから、夢の活動が、潜在的な小児期の体験へ通じる道を知っていることがわかってきます
無意識的願望/無意識的思考
無意識が幼稚で、純人間的な願望をしばしば意識にはたらきかけてきてくれるように、こうした願望を「無意識的願望」と名づけたい
物事の判断のなかみというのは、おおく理性的・知性的な超自我の意見と、この無意識的願望がある。この二つが衝突して、混ざり合ってできたコンポーゼが一つの判断になるのだと思う。判断といってもそれは二極論的な極端なものだけではなく、おおむねこうだとか、どちらかというとこっちかなというような、縦横無尽の柔軟性を有しているものであり、アナログ的な性質をもっている。つまり衝突の結果が必ず完全勝利と完全敗北にわかれるものではないということである。この衝突によって、無意識的願望が優勢に立った、つまりその判断のなかみが多く無意識的願望が占めているような場合、この判断のことを、またこのような思考傾向のことを「無意識的思考」とよびたい
たとえば12時50分のときに、13時になったら昼食を食べにいくと自分に言い聞かす判断は多分に理性が活躍しているといえるが、13時になってごはんを食べにいく判断は、そのなかみのほとんどが無意識的願望(=食欲)になっているので――またその無意識的願望の台頭に対して超自我の意見はそれを容認しているというような働きをしている――「無意識的思考」だといっても違和感ない
後退空想/過去の感情の転移
[フロイトより]
過去の記憶のなかに、その後の時期または現在の時期の事件を、空想的に織りこんでゆく心的現象。現在の出来事を、類似する過去の記憶に見いだし、そこで一緒に思考される。ここでの一緒に思考された記憶があとになって、しばしば同一の記憶としてミックスされることがあるのだが、後退空想はまさにこの現象のことをいう。反対に、過去の出来事や事件がその人ののちの思想に影響を与えることは「過去の感情の転移」とよばれる。転移という言葉は、本来はもっと広義の意味をもっている[転移(“用語解説”)]
アナログ的/デジタル的
アナログとは連続的な値をさし、デジタルは非連続的な整数をさす
生物間または生物内で起こる事を生物の思考プロセスの一部として思い描くとき、数と量の相違という問題が必ずその根本に関わってくる。<数>は数えるという行為の産物。<量>は測定するという行為の産物。数を数えるとき、われわれは各整数の間を飛び移っていく。二つ、三つの間には飛躍がある。隣り合った整数間のこの非連続が、数がきっちり正確たりうることの理由となっている。ところが量の場合にはこのような飛躍は存在しない。そして飛躍が存在しないという理由から、いかなる量もちょうどぴったりということはあり得ない。トマトがちょうど三個あるということはあるが、水がちょうど三リットルあるということはない。量に関して、われわれはいつも、およその話ですましている。数はパターンとゲシュタルトとデジタル計算の世界に属し、量はアナログ計算、確率計算の世界に属す。両者の違いはデジタル・システム(オンかオフの二者択一的特性をもつもの)とアナログ・システム(出来事の強度に応じて連続的に変化するもの)の違いだ。デジタル・システムは数を含むシステムに類似し、アナログ・システムは量により強く依存している。デジタル値で測れるというと1,2,3…、またはYes,No、ON,OFFなどで示される数で表わすものである。アナログ値で測れるものは、三リットルなどの連続的な変化によって示される数で表わす。ちょうど二つの隣り合った整数間が非連続であるように、デジタル・システムにおける“反応”と“無反応”の間は非連続である。“イエス”と“ノウ”の間は非連続である
a
アナログ⇔デジタル
量的⇔非連続的
―
アナログ的参加⇔デジタル的参加
複合現象⇔択一特性[単一構成]
ジェームズ=ランゲ=サザランド説
アメリカの心理学者、W・ジェームズとコペンハーゲンのC・ランゲが主唱した情動の発生に関する心理学上の主張。あることを知覚したときに情緒が生じ、それがあらわされるのではなく、知覚は身体器官の機能の変化を起こし、これらの諸変化の総和の意識が情緒であるとする。すなわち、悲しいために泣き、恐ろしさにふるえるのではなく、泣くために悲しくなり、ふるえるから恐ろしくなるという末梢起源説である
牧場を作る
[サミュエル・バトラーより]
牧場とは莫大な富の意で、牧場を作るとはビジネスによって莫大な富を手に入れることを意味します。語源はサミュエル・バトラーからです。彼はイギリスのジェントリ階層の生まれで、チャールズ・ダーウィンのように働かなくてもよい階層ではありませんでした。大学卒業後の二十三歳のときに父親の反対を押し切ってニュージーランドに移住し、そこで養羊業を始めました。それから六年間で相当な利益を得てイギリスに帰国しました。しかしそうはいっても一生生計を立てていくだけのお金だったわけではありませんでした。/私はこのバトラーの牧羊場から意味をとったわけですが、私がいう牧場の意味は「生涯生活に困らなくなるほどの莫大な富」です。語源の実例とは多少ことなりますが、それがこの用語の特徴であることを皆さんは今知ったのですから問題はないはずです
(付記) 思い込み――その人の独自の観念
上の用語説明をしたついでに、思い込み(=先入観/受動反応)という観念について簡単に説明しておきましょう。まず「牧場」という単語には本来の意味がありますが――牛・馬・羊などの家畜を放牧する設備をもった場所――、この意味は本来的であるだけでなく、牧場の意味を知っているすべての人が連想するという意味で“普遍性をもつ”ともいえます[⇒第二実体(“アリストテレス書付”)]。私は上の用語説明で、「牧場」の本来の意味を知っていながら、そのうえで(1)バトラーにちなんだ牧場の意味(すなわちバトラーにおける牧場の意味)、をつけ、またその上に(2)私なりの解釈(すなわち莫大な富)、をほどこしました。この(1)と(2)はどちらも「牧場」という語にかかるものであり、また私の独自の観念、すなわち思い込みであることが分かります。思い込みの定義はいくつかありますが、その代表格としては、自身が相手に意味を伝えるか読み取られるかしないかぎり、相手はその意味を知ることができない観念、ということです。思い込みは私たちが見る目では影武者のようなものなので、あまり気づかないところも含めると、私たちの心的生活の広くにわたってその根を張っています。ですから、思い込みはここまで一例だけで説明してきた言葉の意味だけとはかぎりません。たとえば赤色は赤色ですが(この言い方はあまり望ましくありませんが)、赤色が嫌いという感情も思い込みの一つです。赤色が嫌いと申される当の彼女は、<赤色>と<赤色が嫌い>というのは別個のもので、特に後者に関してはそれは自分の感情にすぎないことをよく知っています。ではここでこの彼女が、赤色は嫌いだからなるべく赤色を見ないようにしようと思ったんだけどそれは不可能だから、それなら赤色を見ても<嫌い>という自分の感情を連想させないようにしよう、と思ったと仮定しましょう。はたしてしかし、彼女は自分の感情なのにそれを起きてこないように制御することはできませんでした。思い込みは、自らの意思で意識化しないように制御することはできないのです
神とはなにか。教育とはなにか。これらについて皆さんは普遍的な観念である第二実体にあたる観念を共有していると思いますが、個々の事情を考慮する第一実体の観念、すなわち典型的な思い込みはそれぞれ別であります
では最後を前にしてもう少し奥ばんだ観念を提示してみましょう――すなわち、善とはなにか、悪とはなにか、好きとはなにか、嫌いとはなにか、優れているとはなにか、劣っているとはなにかというものです。皆さんはこれらの本来の意味、つまり第二実体をうまく説明できるでしょうか。おそらくできないでしょう。しようと試みてもすぐに思い込みの観念が邪魔をするのです。たしかに私や皆さんはうまく説明することはできないかもしれませんが、しかし、たしかに第二実体の観念であると確信する観念が内にあることを感じることができるはずです。ただその観念を説明しようと手ですくってみても、それは液体のようなものだったのですからほんの少ししかすくえないというだけのことです。/これら善や悪や、好きや嫌いなどに関する第二実体は、どのように形成されえたのでしょうか。的確にこうだとは言えませんが、それは皆さんが生まれたときから母によって、父によって、兄弟によって、学校の先生によって、友達によって、つまり他人によって漸次的に教化されてきたものなのです。ここで興味深いのは、自分によってという場合が、その始原をたどると実は他人によってという場合であるのではということですが、ここでは言及はそれまでにしておきたいと思います。教化の過程では第一実体も形成されますがそれは第二実体に比べると非習慣的で、いくらか柔軟性が高いといえます。ですから第二実体に押しやられる教えというものは、誰にも否定されることなく高い反復性によって、高コンセンサスになりえたものなのです
最後に観念と単語の関係について軽く足をふみ入れてみようと思います。それまでうえで引き合いに出してきた第二実体や第一実体などの観念にはある特徴がありました――それは必ず単語に従属するという点です。ではそのような特徴である観念とはいつも単語の後追いにすぎず、観念そのものがそれ自体として独立することはできないのでしょうか。ある意味でそれは正解だと思います。ただし、単語は、単語の意義を考えたとき、ある単語に対して皆が共有して同じ観念を持ちだすような第二実体としての意味を持つことが非常に重要なことになってきます。“赤色”という単語に対してまさにその赤を思い浮かばせるような情報を皆が共有できないとなれば、ある人は青色を想像しある人はコクマルガラスを想像してしまうように、もはや“赤色”という単語はその単語としての役割を果たすものではなくなってしまうからです。そのような普遍的な共通観念が、しかしどのように形成されていくものなのかという問題をここで簡単に取り上げてみようと思います。おそらく第二実体の形成のその多くは、辞書に書いてある通りをかいつまんで共有する、ということだと思います。その理由は、辞書に書かれることがそれを読む人たち、すなわち多くの人の、共有する情報であるとされるからです。しかしここでの第二実体の形成の核は辞書に書かれることではなく、共有されえる状態であるということです。ですからここにおいて例外というものが指す事柄は、たとえば辞書に書かれているけれども実際はそれとは違う意味が人々の間で共有される単語がある、という事例であります。辞書のような形式的な共有のされかたや、実際的な使われかたとしての共有のされかたが第二実体を作っているということがここで見受けられるのです。このうち実際的な使われかたによる共有のほうが、辞書に載っている意味が流布されるのよりも広く強く渡られた例[⇒例外]をサミュエル・バトラーがすでに示しています
「自然という言葉は、普通に使われているので、自然の最も興味ある創造物である人間を除外してしまっている。自然は、山、川、雲、野生動物、植物を意味するときに使われる。この自然の半分に私は無関心ではない。しかし、もう一方の半分ほど私の関心を引いてはいない」
<サミュエル・バトラー>
複合原因/複合的強調/有効原因
複合原因[類語⇒観念と行為の複重的決定網(“グレゴリー・ベイトソン書付”)]とは、原因となりうる<選択肢>がいくつかあるという、原因の複合性をさします
原因の選択肢が複合性をもつ事柄の場合、それには複合原因をはじめとした三段階の説明をすることができます
第一次 [複合原因] 原因となりうる選択肢が複数ある
第二次 [複合的強調] 誤って一義的解釈に走ってしまう場合に、複合原因の性質をふたたび強調する
第三次 [有効原因] 原因となりうるいくつかの選択肢のうち、今回実際に有効になっている原因(またそれらの比重[内訳])がはっきりしない
a 複合的強調
それは原因の一つとしては認めるが、あくまで一つの原因として、という意味で認めるということ。その原因も確かにあるかもしれません、いやおそらくあるでしょう。ただその一つの原因をあたかもすべての原因であり、たった一つの原因であるかのように、いちずに認めてしまおうというわけにはゆきません。このことを仮にでも認めてしまうということは、他の原因もあるのではないかという探求の試みをみずから放棄することと同じであり、これはややもすれば私たちの世紀の誤謬になりかねないともいえないからです――ゆえに認めてしまうということは恐ろしいほど重大な決断です。/ですから、一つのいかにももっともらしい原因が提唱されたからといって、もしかしたらこの現象は複合的な原因から成り立っているのではないかという疑いをやめることは、少しももっともらしいとはいえないのです。しかしそうはいっても、提唱された仮説そのものについては認め、それに対して敬意は十分にはらうべきです
私たちは最低限の考える力をもっていなければなりません。たとえば、こうであるからといって、その原因がすべてこうであると言っているわけではない、とかです
b 有効原因
《対義語「無効原因」》原因となりうるいくつかの選択肢がある[複合原因]事柄の場合、実際にそれらの選択肢のうちのどれとどれが原因として有効なものになっているかという問題に際して、有効になっている原因のことを「有効原因」といいます。しかし今、実際は、原因となりうるいくつかの選択肢があることは分かっていても、今回そのうちのどれが原因としてていをなしているのかについてはわからないことがほとんどです。複合原因の性質をもつ場合には原因として考えられるものにいくつかの選択肢があります。原因となりうる選択肢が複数ある[複合原因]ということは分かっているが、原因がどれであるのかははっきりしない段階が第三次段階です
有効原因という単語から、原因が有効か無効かというようなきっぱりしたデジタル的な状態を想像してしまうかもしれませんが、そうではなく、それは常にアナログ値で測られるものです――つまりどれだけ有効か、どれだけ無効かといった指標のほうが的確です
好望悪
好望悪[こうぼうあく]。つぎの意味。やるのが好ましいし、望ましいが、しかしやらないことは別に悪とされるわけではないということ
(例1) 整理力
「私は理解のための整理力には欠けていますが、天才はこれに長けています。私はこの能力を<好望悪>だと思っています。すなわち、科学者や哲学者、論者や思想家はこの能力をきたえるのが好ましいし、望ましいですが、必要のない人たちには確かに必要ないかもしれません」
<私≪21才・春≫>
(例2) 精霊を金で買うこと
精霊[英知]を金で買うことは善良でしょうか、悪いことでしょうか。もしこれが好望悪であるとされるなら、次のような仮定があるからになります
「精霊[英知]は金では買えないが、金が無ければなお手に入らない」
<サミュエル・バトラー>
思索目
思索目[しさくもく]。思考しておきたい事柄のいくつかのリスト、という意。語り手が、この概念あるいはこの箇所について他に考えておきたいもの。語り手がこの思索目を聴衆に発表することをとくに「思索目を提示する」といいます。これは語り手が聴衆に対して思考するきっかけを与えるものでありますし、また、語り手が考えてほしい事柄をしめす思考の道筋でもあります
[賛/保/反]かつ[多/小/不]
AかつB。Aに三通り、Bに三通り、全部で九通りがあります
(A) その言葉にたいして賛成であるか反対であるか、保留[⇒手ざわり思考(“用語解説”)]であるか。略して賛・保[手ざわり]・反
(B) 首肯否定にかかわらず、そこから学べるものがあるか否か。学べることが多かったならば多学、少なかったならば小学、この物事において特に学べなかったならば不学。略して多・小・不
(パターンの数) 賛かつ多、賛かつ小、賛かつ不、保かつ多(手ざわりかつ多)、保かつ小(手ざわりかつ小)、保かつ不(手ざわりかつ不)、反かつ多、反かつ小、反かつ不の全九通り
(例)
「人生、生きる価値ありや否やという問題は、人間の問題ではなく胎児の問題である」
<サミュエル・バトラー>
このアフォリズムに関して、今の私は「手ざわりかつ多」といっておきます。ふつう、もし賛成か反対かという観点だけで見るならば、どうにも素っ気なく思考が終わってしまいます。しかしどんな物事でも、そこから学ぶことができないことなど滅多にありません。なにを知るかも大事かもしれませんが、なにを学ぶか、あるいは何を思うかということも大事です。/世人が人生の生きる価値を決めるものにかんして目をみはるほど実に豊富な種類の価値を持ち出しますが、それらの諸価値はみなどれもこれも人生の生き方に共通しています。その暗黙の域内をひょっこり飛び出してくるバトラーの想像力の不気味さは私たちにはないものです。その昔、私が九点連結問題を初めて解こうとしたときに――解けなかったのですが――痛感させられたあの思いをバトラーはこの言葉によって再び私に味わわせてくれました
自然/故意
<自然の説明>
(1) 二人がすれ違うのが偶然であるならば、すれ違わないのも偶然であるとしなければならない
(2) 一つの奇跡があるとすれば、それ以外の物事が起こることも奇跡であり、また起こらないことも奇跡である、という説明になる。したがって、私たちからみればあるたった一つの物事が起こることが奇跡である場合も、自然からみればどんな物事が起ころうと奇跡であり、また同時に奇跡ではない。全ては必然的に、起こるべくして起こっている
――
自然には、感情(善悪、好悪、優劣など)、故意[思想・意味]、奇跡、成功、失敗、無限、不自然などは存在しない
対概念の関係にあるものとして、自然と故意があります
故意とは、ある要因に作為的な何か、意図があるという意。作為。意図。たとえば神の役割、神話の概念、人がおりなす論理めいた合目的的理論などがそれです
自然とは、故意のなにか手が加えられていない、いわゆる<原因の環境がそうであれば、おのずと結果もそのようになる>というようなある法則[自然法則]にしたがってはたらくことをいうものです。自然法則にかんしては、それが故意の産物であるか否かという問題がありますが、この問題は解決の緒に就くことが難しいので、自然派の世人は「自然」の概念を導入するときに必ず次のことを仮定しなければならなくなります――すなわち、自然法則が故意の産物であるか否かにかかわらず、あくまでそれは「自然」とみなし、そしてこれを「自然」と呼ぶ、ということです。自然における「例外(自然法則に対しての例外)」は不自然とみなされるが、自然派の世人にとって、自然を支持するということは不自然は存在しないと認めることになるために、支持者にとって例外は存在しないということになります。ただしこれは、例外が本当に自然ではないのか、すなわち例外は自然によって説明ができないものであるのか、それとも私たちが<まだ>自然によって説明ができていないだけなのか、ということを明らかにしないかぎり、不自然にまつわるあらゆる議論を先取りしておこなうことはできません――<つまりそれは例外を不自然とみなしたりする理由についても当てはまるものです。ただし不自然があると仮定された場合の、自然を支持すると例外の存在を認めることができない、というこの理由についてはまた別の議論になります。>/自然そのものは母体ではなく属性であり、性質です。/あくまで現時点でのことですが、自然的ではないものの例をいくつか挙げてみましょう。例えば、
・感情――善悪、好悪、優劣……――
・故意[思想・意味]
・無限
・不自然[自然法則ではない法則{例外}]
などがあります
―
ここで上例のうちの感情と意味について、それらが自然的なものと奇妙な懸隔があるのではという疑念をサミュエル・バトラーがほのめかしているので、それだけ取り上げておきたいと思います
「結果は、正しい見解をひきおこした人間の道徳的罪悪感や潔白さとはおよそ関係がないものである。結果は、それがどんなものにせよ、ただもっぱらおこなわれたことしだいによるのだ。同様に、道徳的罪悪感や潔白さは、結果とはなんの関係ももっていない」
<サミュエル・バトラー>
私たちが作り出した感情や意味は、自然とはなんの関係ももっていないことをバトラーは示しています
―
自然もしくは故意が備わる母体、すなわち概念とはこの場合二つありますが、それが「原因」と「過程」です。ということはそれはたとえば、過程は自然ではあるが、原因は故意である、というような場合もあるわけです。ここで一つ例をあげますが、なぜその例にしたのかというところに私の場合の一考えを基[もと]にしてあります。たとえば過程は自然に拠るとしましょう。しかしここで同時に原因をも自然に拠ると認めなければ、どうなるか――たとえば結果をいじるためには、故意があれば原因の環境を変えることができるため、その原因に拠っておのずと結果もそのようにすることができるということです
私意としてここで一つの結論を書いておこうと思います。原因の領域にしろ過程の領域にしろ、両者共々それが自然に拠るものなのか故意に拠るものなのかを結論づけることは、現時点での私たちの乏しい知識ではとても無謀なおこないです。その理由はいくつかあるやもしれませんが、とりあえず私にとって一番大きくて、そして一番身近な弊害だと思っているものは、自然とは何か、自然法則とは何か、という定義づけさえ全然ままなっていない現状です。それは下のコップの例をみてもよく分かると思います
(例) テーブルに置かれたコップ
テーブルにコップが一つ置いてあります。ここにコップが置いてあるということは、誰かがそこにコップを置いたという事実があります。“誰か”とは多くの場合人であると思いますが、必ずしもそうであるというわけではありません。しかしまずここでは人と仮定しておきます。その人はどんな意図があったにしろ、コップを置いたことは唯一確かなことです。なぜなら、そこにコップがあるからです。これが過程における自然です。コップをそこに置けば、そこにコップが置かれる。これが私たちが定義している自然法則の一つです。その人がコップをそこに置いたのにそこにコップがなかったり、その人がコップを庭に投げたのにコップがテーブルの上にあるというのは、私たちが今知るかぎりの知識によればそれは自然では説明がつかないので、不自然ということになります。しかしともあれそれらが不自然であると言えるためには自然法則を理解しないといけないので、それをまだ理解していない私たちは不自然という仮説を定説にすることはできません。/つぎは原因における自然です。これは簡単に言うと、つまりテーブルに置かれたコップを置いた人に意図があったかなかったかという問題で、言い換えればコップがあることの原因、すなわちコップがあるというその環境が故意に拠るものだったのか自然に拠るものだったのかという問題です。コップにかんしていえば、その人にどんな意図があったにしろ、確実に言えることは確かにコップをそこに置くという意図はあったということですから、コップが置かれた原因は故意であったと簡単に言えそうです。つまりこれはどういうことかというと、私たちがその人と同種の生物で、その人がコップを置いたということが分かっていて、その人がコップを置くということには必ず何かしらの意図があるということを知っているからです。ではもし仮に風がコップを偶然そこに置いたのだとして、私たちがそれを見たことで知っていたのだとしたら、それははたして自然なのか故意なのか。私たちは風に意図があるかどうかを知りませんし、風をひき起こした“何か”に意図があったかどうかも分かりません。私たちが知っているのは唯一、風がコップをテーブルに置いたという事実だけです。このこと、つまり原因は自然であるか故意であるかということに関して、ある人はそれは自然であると言い、ある人はそれは神の仕業だと言いますが、彼女らはただ自分の信じたいものを信じているだけで、その主張を裏付ける必然の根拠を持ち合わせているわけではありません。根拠が乏しいのに堂々と主張できるというのは人間の特徴でありますが、その特徴の根底に横たわる「信じる」という心的性質について、これをよく具現化しているものがたとえば神や宗教といったものたちです
私は先ほど、過程においても原因においてもそれは自然に拠っているのではないかとの私意をにおわせていましたが、この見解もその基はたんに信じている、信じたいから、というものにほかなりません。私たちは、ことにそれは自然派の皆さんについて言っておきますが、たとえ自身の中で過程においても原因においても、自然であるのかという疑点を肯定に裏づけるような出来事がしばしば起きたために、故意値より自然値のほうが比重が重くなっていたとしても、そもそもの前提(自然にまつわる数々の前提で、たとえば、それは自然なのかという前提など)がぼろぼろにもろいのだということを知っていなければなりません。なぜなら、前提が間違っていればそこから導き出される答えも正しくはなくなるからです。そしてまた、コップがそこに置いてある、と言えるためには、それがコップであると仮定しなければならないからです。しかしそこでたいていの人は、コップはコップであることは当たり前じゃないか、と言って自らの主張に磨きをかけます。しかし彼女らが往々にして見落としがちなのは、第一に知っている知っていないにかかわらずすでにそれをコップと仮定しているという事実があることと、第二にそれはなぜコップなのかと問うようなぐあいにして前提へ遡行していくと、彼女らはきまって、しだいに口ごもるようになるということです
用意された物について、それが用意されたあとにどうなったのか、どのような変化をきたしたのかということ[過程]については、私たちはその変化が自然的であり、したがって自然法則によって説明ができるのだと断言できる日はそう遠くないかもしれません。私たちは「科学」と「哲学」を中心とした学問による研究から自然法則の解明をせっせと行っていますが、すでに今日、私たちは「過程における全ての変化と現象は自然法則のもとで働いている」と高い確信をもって言うことができるのですから。/これとは対照的に、用意された物を用意した“何か”が、その用意に意図をもっているか、もっていないかという問題[原因]については、私たちは、それが過程よりもずっとずっと神秘的であるためにずいぶん手をこまねいている今日の現状を<素直に>認めなければなりません。多くの世人が認めないから、マナが本来の神秘の域を超えて神が作り出され、宗教などという本態[実情]と想像が倒錯した危なっかしい信仰がそここで縦横無尽に成り上がるのです
「想像が高められすぎて、あたかも事実であるかのように信仰されることほど恐ろしい倒錯例は他にあまり見ない」
<私≪21才・春≫>
“何が[誰が]”用意したのかも知らない、その用意に意図があったのか否かも知らない、これでは手も出せないように見えます。それが本当のところであるなら、素直に認めましょう。ソクラテスが言ったことを思い返すときです
「真の知への探求は、まず自分が無知であることを知ることから始まる」
<ソクラテス>
そしてフロイトがソクラテスのこれに対して穏やかに言及したことも有意なことかもしれません
「悪徳すら無知にもとづく」
<ジークムント・フロイト[ソクラテスの無知の知について述べた言葉]>
エントロピー[正/負]
[グレゴリー・ベイトソンより]
①乱雑さの度合い。差異のなさの程度。予測不能性の程度。これらの程度を表わすものが「エントロピー」であり、このうちどれほど乱雑さの度合いが強いか、差異が大きいか、予測不能性が高いか示すのが「正のエントロピー」です。/対義語「負のエントロピー」…ある集体がどのくらい秩序づけられているか、選り分けられているか、予測可能かという程度を指す
②情報量
冗長性/SN比
たとえば、「文章」というものは、パターンづけられたものである。工学的に言えば、文章は「冗長性」を含む。英語文を構成する文字列のある位置にkが登場するというのは、純粋にランダムな出来事ではない。他の25の文字が同じ確率で登場することができるのなら純粋にランダムだといえるが、そうではない。英語には多く登場する文字とそうでない文字があり、また多く現われる文字の組み合わせとそうでない文字の組み合わせがある。ということは、英文の文字列のどのスロットにも、そこにくる文字の可能性を絞り込むパターン化の作用がはたらいているということだ。これをメッセージの受け手の側から見ると、彼は一ヵ所kの文字が欠けているメッセージを受け取ったときに、欠けているのがkだということを、ランダム以上の確率で推測できるということになる。そしてその推測が容易な程度に応じて、(この受け手にとって)実際現われたkの文字が他の25の文字を排除する度合いが弱まる。なぜなら残りの文字列が、すでに他の文字をある程度まで排除していたのだから――。こうした「パターンの卓越の程度」、言いかえれば「出来事の集団の中である特定の出来事が起こる予測の容易さの度」が、「冗長性」の名で呼ばれるものである。この意味では「負のエントロピー(“用語解説”)直上」と同義である
(例-a)
完全にランダムなアルファベット文字列のどこかに現われたeの文字はlog^2 26ビットの情報量を担う。これが英語の文章であり、英語の文字列にはeの現われる確率が平均より高いことを知っている受信者または機械にとって、その情報量は減少する。英語であるという事実が、その文字列に冗長性を与えるわけだ。もしその受信者が、完全に英語が読める場合、たとえばr□dun-dancyと続く文字列の□の位置にくるのがeであることは、ほぼ百パーセントの確率で推測が可能だ。このとき、実際に現われたeの文字が担う情報量は、ほぼゼロに等しい
――
このような、メッセージをつくる事物の連なりを、同じ時・同じ場所に存在するメッセージをつくらない事物と区別する基準となるのは、SN比(シグナルとノイズの比率)などの特性である。シグナルは見えている部分、ノイズは見えていない、欠けている部分。パターン=情報はその両者どちらにも存在するものだ。メッセージの素材のシークェンスを、一部欠けたままの状態で受信したとき、その欠けた項目を受信した部分の情報から、ランダムな当て推量以上の確率で推測できる場合、そのメッセージ素材は「冗長性」を持つといわれる。ということは、「冗長的である」ことと「パターン化している」こととが同義であるということだ。メッセージ素材におけるパターンの存在が、受信者がシグナルとノイズを区別する助けになる。またはこうも言えるだろう。受信者がメッセージの欠落部分を推定できるというのは、すでに受信した部分が、まだ受信していない部分について何かしら言及しているから、それについての情報を運んでいるからである。さらにいえば、それについての意味を運んでいるから、である
(例-b)
歩いていて雨が後頭部を打ったという事柄が含んでいる情報は、すこし歩くのが遅ければ目や頬に雨が当たったかもしれないし、すこし速かったら身体には当たらなかったかもしれないという情報を含んでいる
直示的
直示的とは、それ自体をもってそれ自体を示す方法のことである。向こうからやってくるA君の姿がA君がやってくることを示しているとき、A君の姿は直示的なコミュニケーションにかり出されていることになる
相手の言動に怒って表情を変え、拳をにぎる人は、相手に対する攻撃の部分をもって「怒った」ことを示すわけだが、怒ったのが「怒り」を示している当人であることは、直示的に示されている
転移
人はすべての物理的観念的(実体形式)なものを知覚または扱ったりするときに、コンテクストという対象用の観念を随伴させる。コンテクストは“意味”のようなもので、対象に背景(輪郭)を与える。逆にコンテクストなしには言葉も行為も物体もまったく意味を持ちえない。新たな他者に出会ったとき、その人がどんな人かというコンテクストを必ず付ける。彼を“父”として見なしたり、もしくは“反父”として見なしたりといったぐあいだ。このような「見なし」を「転移」という。私は転移を「人間のコンテクスト随伴の本能」として広義に定義したい。例えばきのう私たち二人の間に何か起こったとしよう。するとそのことが、今日の互いに対する反応のしかたを形づくるわけだが、これも本質的には、過去の学習からの転移にほかならない
コンテクストは背景そのもので、それは“予測”であり、“期待”である。そして背景を忍ばせる行為のことを転移という。階段をのぼるとき、そこに階段があるということが分かっているからのぼることができるのだ。目の前に階段があってそれをのぼるという一連の行為のなかには、認識のコンテクスト、予測のコンテクスト、そして期待のコンテクストがそれぞれはたらいているのである。これは意思決定のプロセスにつながる
コンプレックス
観念複合体ということもある。父親に対して愛憎の入りまじった複雑な感情をともなう観念群をさす父コンプレックス、エディプス・コンプレックス、去勢コンプレックスなどというように、強い感情をともなった観念の集合体である。このコンプレックスの働きは、その瞬間には本人にはわからない、つまり無意識的なものである。この概念を精神分析学に導入したのはユング
就眠儀礼
就寝の際、鍵を確かめ、ガスの元栓をしめ、時計の位置をなおすなど、ふつう人々のする行為で、それをしないと眠れない習慣をさしている
リビドー
フロイト的解釈
性的衝動を発動させる力、すなわち性的欲望または性衝動のこと
ユング的解釈
すべての本能のエネルギーのこと。私が使うリビドーの意味はふつうこちら
a 対象リビドーと自我リビドー
対象リビドーとは、自己以外の外界の対象に配備された状態のことをいう。これは、自我に配備されているときの自我リビドーと対比される。対象リビドーおよび自我リビドーは、それぞれ、対象へのリビドー配備、自我へのリビドー配備と同義に考えてよい
b-対義語 自我の逆配備
[フロイトより]
自我がエスのリビドーに対して抑圧のために使うエネルギー。意識化されることの好ましくない欲動や観念は抑圧によって意識下に追いやられるが、これらが意識化されるのを防ぐために配置されるエネルギー
論理階型
a 概要
(1) 論理の記述には、ふさわしい階層というものがある。土地は地図ではない。両者の違いは何か。土地は土地そのものだが、地図は土地の情報を変換した産物で、土地の関係を表わしたものが地図である。さらに土地が名づけられたものが地図である。地図は土地より一段高い、別の論理階型に属する
(2) 両者が論理階型の関係を結ばれるには、この時点、階型の抽象度を問わず、同じ関係上にマップされる全体のうちのいずれかに帰属することが条件である。つまりある両者が論理階型の上下の関係性を持つには、どのクラスに帰属するかに拠らず、上下の関係として同じ全体の中に属している必要がある。円形・三角形・四角形はそれぞれ別の性質を持つ概念であるが、一段上の階型に「図形」を設定した場合、図形のクラスの中に(つまり下に)メンバーとして円形・三角形・四角形らが設定されることになる。メンバーが設定される規則はメンバーを包括するクラスの設定の際の前提条件に含まれる。高次から地図⇒土地の論理階型を設定した場合、その全体(論理階型)に“リンゴ”が入り込む余地はないが、物体⇒地図、土地の階型ならば、地図や土地のメンバーにリンゴが加わることになる。このように設定されたある論理階型全体に属している諸要素のことを「これらは互いに論理階型全体の関係を持つ」という。その中でそれぞれ、上下の関係をもつ両者は「上下の論理階型の関係を持つ」、横上すなわちメンバー同士である両者は「横上の論理階型の関係を持つ」という。物体⇒地図、土地、リンゴの論理階型であれば、それぞれはそれぞれに対して「互いに論理階型全体の関係を持つ」。物体―地図、土地、リンゴ間では上下の関係にあるため、両者は互いに「上下の論理階型の関係を持つ」。地図―土地―リンゴ間では同じメンバーに属する項同士にあるため、それぞれ「横上の論理階型の関係を持つ」というような記述の仕方になる
(3) 上下の論理階型の関係性
(3-a) 高次の論理階型は低次の階型より、普遍的・前提的(抽象的)・多様的・制御する関係を持つ。対して低次の論理階型の高次の階型に対する関係は対称になり、低次に向かうにつれて個別的・具体的・単一的・制御される関係を持つ
(3-b) また、クラスはそれ自身のメンバーになることはできないし、メンバーがそれ自身のクラスになることはできない。高次の階型から順番に図形⇒円形、三角形、四角形の論理階型を設定した場合、クラスである図形がその下のメンバーらの中に加わることはできないし、同様にメンバーである三角形がその上の図形のクラスに肩を並べることはできない
(3-c) 高次の論理階型に属するメッセージは、低次の論理階型の変数を変えるにあたって、その変数を直接的に指定しない(する必要がない)。記述するのは“関係”のみで、ゆえにそれだけが決定される。例えばDNAからソマティックな変数の変域を変えるとき。夢の隠喩(ものを指し示すことをしない)的記述
(3-d) それぞれのレベルは、上位レベルによって下位レベルにある情報が秩序付けられるもしくは制御されるように効果を発揮する。つまり、上位レベルの変更は、必然的に下位レベルの変更を伴う。しかし、下位レベルの変更が“必ずしも”上位レベルに影響を与えるとは限らない
(4) 横上の論理階型の関係性
つまりメンバー同士の関係性ということになろうが、前述のとおりメンバーが設定される規則はメンバーを包括するクラスの設定の際の前提条件に含まれる。高次の階型から地図⇒土地と設定された論理階型の場合、「地図」の関係制御下にメンバーとして「土地」があり、土地がメンバーとして設定される規則は高次の階型の「地図」の設定条件に依拠する。この論理階型に「リンゴ」は加わることはできない。一方、物体⇒地図、土地、リンゴの論理階型にリンゴがメンバーとして加わることができるのはリンゴが物体の一つであるからだ。このようにメンバーが設定される条件は高次の階型の設定条件によって異なり、したがってメンバー同士の関係性も、高次の階型が設定された際に決定される
b 具体例
その一連の例を示す
b-1 ものの名前は名づけられたものとは違う。ものの名前は名づけられたものより一段高い、別の論理階型に属する
b-2 クラスはそのメンバーより一段高い、別の論理階型に属する
b-3 室内温度調節装置のバイアスから出される指令、またはそこから生じる温度調節は、直接的な温度調節よりも高次の論理階型に属する(バイアスとは壁に取りつけられたダイアル装置で、それを適当な温度にセットすることにより、家の温度はその前後を上下する)
b-4 タンブルウィード(秋に根元から折れて地上を転がる雑草)という言葉は、潅木(低い木)とか木とかいう言葉と同じ論理階型に属する。それは植物の種や属の名前ではない。成長のしかたや種子散布の型によって分類されたものである以上、綱の名前である
b-5 加速度は速度より高次の論理階型に属する
b-6 言葉には表面に現れないメタメッセージ(メッセージのメッセージ)が存在する。われわれは日常の会話の中で、絶えず相手が言う言葉の含蓄を理解しようと努めている。われわれはもし相手の言っている意味が分からないときはすぐさまその真意を明らかにしようと再び尋ねる。「それはどういう意味ですか?」と。ダブルバインドの例では語り側の発する言葉に含蓄されるメタメッセージが、行動あるいはもう一つのメタメッセージと相反するために、聴衆(その多くは子ども)が二重拘束の精神状態に陥ることが起きる。ダブルバインドは言葉にメタメッセージがあることを明らかにし、ひとえに言葉の表面上の意味をいくら理解したとしても、理解されない別の次元の意味があることを教えてくれる
別の例を示そう。思春期の非行少女が教師に「死にたい」とこぼしたとき、教師はその言葉をどう把捉するだろう。同じ「死にたい」という言葉でも「寂しい」の死にたいなのか「助けて」の死にたいなのか、はたまた本当に死にたいの意味なのか、さまざまだ。これらのメタメッセージは言葉と同じメンバーではなく、一段上の論理階型に属する。これは夢が見る者のイメージに直接事物を指し示すことをせずに、隠喩的表現すなわち関係のみを表わす下位制御の仕方と同じである
b-7 暗黙知の説明に駆り出される例に階層的な二重制御がある。例えば言語行動を考えてみよう。それは五つのレベルを含んでいる。すなわち、(1)声を出す。(2)言葉を選ぶ。(3)文を作る。(4)文体を案出する。(5)文学作品を創出する。それぞれのレベルはそれぞれ自らの規制に従属している。すなわち、それぞれ以下のものに規定されているのだ。(1)音声学、(2)辞書学、(3)文法、(4)文体論、(5)文芸批評。この五つのレベルは包括的存在の階層を形成する。なぜなら、各レベルの原理は、自分のすぐ上のレベルに制御されて機能するからだ。発せられた声は語彙によって単語へと形作られる。語彙は文法に従って文へと形作られる。そして文は文体へと整えられて、ついには文学的観念を持つようになる。かくして、それぞれのレベルは二重の制御の下に置かれることになる。第一に、各レベルの諸要素それ自体に適用される規則によって、第二に、諸要素によって形成される包括的存在を制御する規則によって。したがって、より高位層の活動を、そのすぐ下位置に当たる諸要素を統括する規則によっては、説明できない。音声学から語彙を導くこととは不可能なのだ。同様に、語彙から文法を導くことはできないし、文法が正しいからといって良い文体が出来上がるわけでもない。また、良い文体が文章の内容を授けてくれるわけでもない。つまり上位の階型は下位の階型を関係によってのみ制御することになる
c 誤った論理階型の例
両者の論理階型の関係に不確実性の要素があって曖昧なものは論理階型の関係を持たない。その典型的な例が人間的観念の介入である。人の解釈によって、時と場合によって両者の関係の程度が変わるような流動的な関係は、それを論理階型の関係に用いるには危険だ。暫時的に不確実性が取り除かれた場合の構造を切り取って、その構造において言うならば、それは論理階型の関係を持つと定義しても問題なかろう
c-1 人間的観念の介入――両者に直接的な因果関係がみられない場合において、その両者が結果的に因果関係を構築する現象について
c-1-a 程度――これは人間的観念の典型的な例だ。これから説明する程度の持つ属性を人間的観念の属性に置き換えてみると理解が早かろう
程度と決定(確率と成否)は、互いに論理階型の関係を持たない。神様も宗教も信じない人が、奇跡や偶然が二回三回と重なったことで、神様を信じるようになる。しかし奇跡といっても、その人の主観的な解釈という前提の上で喜ばしい結果となるわけであり、それは、その出来事自体が他の人にとって奇跡ではないということを見れば明らかである。後半は蛇足気味だが、この例では程度の高低差が決定の属性に影響を及ぼしている。しかしこの両者は論理階型の関係にあるわけではない。第一に何をもって決定されるかは人の解釈によるものだ。程度がいつでも決定を制御するわけではない。第二にある出来事が奇跡や偶然かどうかは、その人の主観感覚によって喜ばしければそうなるものであるし、その人にとってまったく関係がなければただの出来事の意味しか持たない。第三に決定を制御する程度の制御確実性が低い。その変数は時と場合によって、つまり人の感覚判断によって異なる値を採るものだからだ。仮に程度が100%の値を取ったときにでも、それが決定の表裏をひっくり返すかどうかは100%ではない。奇跡の出来事も、当事者がそれを神が起こしてくれたという理由に結びつけなければ、ただの奇跡の出来事であり続けるだけなのだから
例えば物事の成否と、人の「できる」とか「できない」とかいう思い、両者は直接的な結びつきはない。しかしつながっているようだ。それは人に願望の現実効果(“依存”)があるからだと思う。しかしそもそも物事の成否と人のもつそれらの思いに、因果関係がみられないとする点に疑問を向けることも忘れてならない
c-1-b 記憶する速度が速いのと、頭が良いとは別物で、本来はそれぞれは互いに一切影響を及ぼさない。しかし人が与える観念すなわち情報が、両者を相互作用の関係にすることはできる。この観念には二つの意味が含まれる。一つは、“頭が良い”の意味が、人の解釈によってさまざまな意味を持ちえるといった、定義域の幅があることについて。もう一つは、仮に“頭が良い”の意味が定義付けられたとした場合、それに即した情報が教えられる、すなわち教えられる情報の質を操作することができることについて
ところでそもそも、両者の存在は人によるものなのだけれど。この点については消えていく概念と消えていかない概念(“形式”)を参照されたい
c-1-c 外形形態と関係形式(“形式”)は、互いに論理階型の関係を持たない。それはとりわけ、関係形式の形体が人為的解釈に従属するからである
c-2 その他
c-2-a 量と質は、互いに上下の論理階型の関係を持たない。これらはそれぞれ関連のない別の性質を持つ異なる概念であり、したがって同じ階型の上下の関係を持つことができない。加速度と速度はそれぞれ制御の関係をもち、「速さ」の論理階型全体に帰属し、かつ上下の階型の関係をもつ。しかし量と質はそれぞれ一方が変更されても他方にその影響が与えられないため、高次の階型の設定される条件によっては同じ階型の全体に帰属する、ここではすなわち横上の階型の関係をもつことはできても、上下の階型の関係を持つことはできないのだ
c-2-b 「AがATMから1円をおろしたとき、出てきたのは一万円と1円の領収書だった。すぐさま通帳を確認してみたが、たしかに口座上で引き落とされていたのは1円だった。Aは考えた。これは窃盗ではないのか? いや、そんなものではない、とすぐに自分を納得させた。この金はわざと盗ったのではなく、転がりこんできただけだ。それに、ほかの人から盗ったのではないから、盗まれた人は誰もいない。銀行にしてみれば、こんなのはほんのはした金だし、どちらにせよ、損害を出したのは向こうの責任であって、もっと安全なシステムを備えているべきだったのだ。そう、これは窃盗ではない。これまでの人生で最大の幸福というだけだ」
Aが考えている問題は「これは窃盗か、そうでないか」についてだ。しかしAは弁明のところで「銀行にしてみれば、こんなのはほんのはした金だし・・・」と言っている。これは本来の問題の論点がずれている。窃盗か、そうでないかは「客観的・公平的に見て、1円と1万円の違いが分かっている上でその間違いを申告しないのかどうか」あるいは「窃盗とは何か」など、あくまで“中心的な”出来事を客観的に考察することが正しい。「相手が銀行だから」「自分が故意に盗ったわけではないし」など、そのときの“周りの”状況を考慮に含めるのは、本来の問題からずれている
中庸
中庸とは、極端な物事の決め方をしない考え方のことをいう。物事にはアナログ的/デジタル的(“用語解説”)の二つがある。私たちが何かを考えるとき、まずその物事がアナログ的なのか、それともデジタルに属するのかを考える必要がある。デジタル的であれば答えはONかOFF、YESかNo、是か非といった二択しかない。ところが私たちはアナログ的な問題を二極論によって答えを導いてしまうケースも多い。これは一つの物事が複数の個々的性質の集合体として成立しているケースで、アナログ的な要素とデジタル的な要素が密接に関わり合っていることを示している。このような集合体はそれを構成する一つ一つの物事[視点]に、間違っている、しかし同時に間違っていない、あるいは、有る、しかし一方で無いものもあるといった「同時混在」が起きている。この同時混在の中にあって、個々的性質の割合ぐあいによって全体傾向[集合体]が決まる
(例) 路面に雨水が深くたまっているところとあまり溜まっていないところがある。凸凹の少ないところは雨水が乾くのも早い。ところが実際の地形では、この凹凸の少ない面一帯は、凸凹な部分と平らな部分が複雑に織りなして形成されているものだ。したがって平らな面というのは、それを構成する個々的性質に比較的平らな面が多いということであって、割合少なからずは凸凹の面もある。個々的性質においての平らな面と凹凸の面の割合が全体傾向[集合体]を構成している。こうしてみると改めて、路面の平らな面というのは比較的平らな面の割合が多いということであって、厳密には完全に平らな面であると言うことはできない
中庸の考え方を意識するとき、物事を構成している一つ一つの個々的性質[ミクロ]を解明し、それらを紙にでも書いて明示化していくことが望ましい。これをいつも賢くこなせたなら、私たちはもっと物事を深く知ることができる
本格派
クセや個性を排除し、純粋に目的のために必要最小限の言動のみを行うことを「本格派」という。一連の問題に挑む考え方や行動を本格派に沿わせるには、一つ一つの言動に意味を見出さなければならない。したがって、事前に意味のある言動を考える必要のある「本格派」は、いわば洗練された一つの規格である
一つ一つの言動の意味を考えることはとても大切なことである。このことは思考学、ひいては日常生活においてもあまねく適用できる
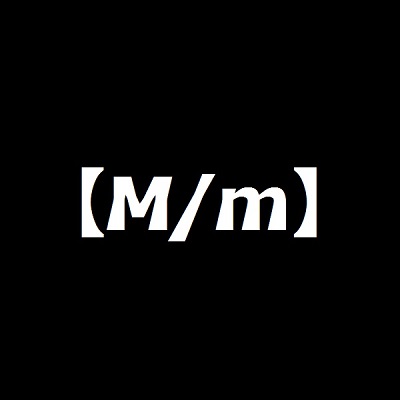

 TOP
TOP