幼い頃に体験した、とても恐ろしい出来事。
その当時私は小学生で、妹,姉,母親と一緒にどこにでもあるような小さいアパートに住んでいた。
夜になったらいつも畳の部屋で家族揃って枕を並べて寝ていた。
ある夜、母親が体調を崩し、母に頼まれて私が消灯をすることになった。
洗面所と居間の電気を消し、テレビなども消して、それから畳の部屋に行き母に家中の電気を全て消した事を伝えてから自分も布団に潜った。横ではすでに妹が寝ている。
普段よりずっと早い就寝だったので、その時私はなかなか眠れず、しばらくの間ぼーっと天井を眺めていた。
すると突然静まり返った部屋で、
「カン、カン」という変な音が響いた。
私は布団からガバッと起き、暗い部屋を見回した。
しかしそこには何もない。
「カン、カン」
少ししてさっきと同じ音がまた聞こえた。どうやら居間の方から鳴ったようだ。
隣にいた姉が、「今の聞こえた?」と訊いてきた。
やはり空耳などではなかったようだ。
もう一度部屋の中を見渡してみたが、妹と母が寝ているだけで、ほかに部屋には何もない。
おかしい・・・確かに金属のような音でそれもかなり近くで聞こえた。
姉もさっきの音が気になったらしく、「居間を見てみる」と言い出した。
私も姉と一緒に寝室から出て、真っ暗な居間へと向かった。
そしてキッチンの近くからそっと居間を覗いてみた。
そこで私達は見てしまった・・・
居間の中央にあるテーブル。
いつも私達が食事を取ったり団欒したりするところだ。
そのテーブルの上に人が座っている。
こちらに背を向けているので顔までは判らない。
でも、腰の辺りまで伸びている長い髪の毛、ほっそりとした体格、身につけている白い浴衣のような着物から、女であるということは判った。
私はぞっとして姉の方を見た。
姉は私の視線には少しも気付かず、その女に見入っていた。
その女は真っ暗な居間の中で背筋をまっすぐに伸ばしたままテーブルの上で正座をしているようで、ぴくりとも動かない。
私は恐ろしさのあまり足をガクガク震わせた。
声を出してはいけない・・・
もし出せば恐ろしい事になる。
その女はこちらには全く振り向く気配もなく、ただ正座をしながら私達にその白い背中を向けているだけだった。
私はとうとう耐え切れず、
「わぁーーーーーっ!!」
と大声で何か叫びながら寝室に飛び込んだ。
母を叩き起こし、「居間に人がいる!」と泣き喚いた。
「どうしたのこんな夜中に」
そう言う母を引っ張って居間に連れていった。
居間の明かりを付けると、姉がテーブルの側に立っていた。
さっきの女はどこにも見当たらない。
テーブルの上もきちんと片付けられていて何もない。
しかしそこにいた姉の目は虚ろだった。
今でもはっきりとその時の姉の表情は覚えている。
私と違って彼女は、何かに怯えている様子は微塵もなく、ただテーブルの上だけをじっと見ていた。
母が姉に何があったのか尋ねてみたところ、「あそこに女の人がいた」とだけ言った。
母は不思議そうな顔をしてテーブルを見ていたが、「早く寝なさい」と言って3人で寝室に戻った。
私は布団の中で考えた。
アレを見て叫び、寝室に行って母を起こして居間に連れてきた少しの間、姉は居間でずっとアレを見ていたんだろうか。
姉の様子は普通じゃなかった。何か恐ろしいものを見たのでは・・・
次の日、姉に尋ねてみた。
「お姉ちゃん、昨日のことなんだけど・・・」
そう訊いても姉は何も答えない。下を向いて沈黙するばかり。
私はしつこく質問した。
すると姉は小さな声でぼそっとつぶやいた。
「あんたが大きな声を出したから・・・」
それ以来、姉は私に対して冷たくなった。
話しかければいつも明るく反応してくれていたのに無視される事が多くなった。
そしてあの時の事を再び口にすることはもうなかった。
あの時私の発した大声で、あの女はたぶん姉の方を振り向いたのだ。
そして姉は女と目が合ってしまった。
きっと、想像出来ない程恐ろしいものを見てしまったのだ。
そう確信していたが、時が経つにつれて次第にそのことも忘れていった。
中学校に上がって受験生になった私は、毎日決まって自分の部屋で勉強するようになった。
姉は県外の高校に進学し寮で生活しているため、家に帰ってくることは滅多になくなった。
ある夜、遅くまで机に向かっていると、扉の方からノックとは違う何かの音が聞こえた。
「カン、カン」
かなり微かな音だ。金属っぽい音。
それが何なのか瞬間的に思い出した私は、全身にどっと冷や汗が吹き出た。
これはアレだ・・・
小さい頃、母が風邪をひいて私が代わって消灯をした時の・・・
「カン、カン」
再び鳴った。
扉の向こうからさっきと全く同じ金属音。
私はいよいよ怖くなり、妹の部屋の壁を叩いて「ちょっと、起きて!」と叫んだ。
しかし妹はもう寝てしまっているのか、何の反応もない。
母はここ最近はずっと早寝している。
とすれば、この家の中でこの音に気付いているのは私だけ・・・
一人だけ取り残されたような気分だった。
そしてもう一度あの音が・・・
「カン、カン」
私はついにその音がどこで鳴っているのか分かってしまった。
ほとんど無意識に、そっと部屋の扉を開けた。
真っ暗な短い廊下の向こう側にある居間。
そこはカーテンから漏れる青白い外の光でぼんやりと照らし出されていた。
キッチンの側から居間を覗くと、テーブルの上にあの女がいた。
幼い頃、姉と共に見た記憶が急速に蘇ってきた。
あの時と同じ姿で、白い着物を着て、すらっとした背筋をピンと立て、テーブルの上できちんと正座し、その後姿だけを私に見せていた。
「カン、カン」
今度ははっきりとその女から聞こえた。
その時私は声を出してしまった。
何と言ったかは覚えてないが、またも声を出してしまったのだ。
すると女はゆっくりと私のほうを振り返った。
女の顔と向き合った瞬間、私はもう気がおかしくなりそうだった。
その女の両目には、ちょうど目の中にぴったり収まる大きさの鉄釘が刺さっていた。
よく見ると両手には鈍器のようなものが握られている。
そして口だけで笑いながらこう言った。
「あなたも・・・あなた達家族もお終いね。ふふふ」
次の日、気がつくと私は自分の部屋のベッドで寝ていた。
私は少しして昨日何があったのか思い出し、母に居間で寝ていた私を部屋まで運んでくれたのかと聞いてみたが、何のことだと言われた。
妹に聞いても同じで、「どーせ寝ぼけてたんでしょーが」とけらけら笑われた。
しかも私が部屋の壁を叩いた時には、妹は既に熟睡してたらしい。
そんなはずない。私は確かに居間でアレを見て、そこで意識を失ったのだ。
誰かが居間で倒れてる私を見つけてベッドに運んだとしか考えられない。
だが改めて思い出そうとしても頭がモヤモヤしてだめだ。
ただ、最後のあのおぞましい表情と、ニヤリと笑った口から出た言葉ははっきりと覚えていた。
私と、家族がお終いだと・・・
異変はその日の内から起こった。
私が夕方頃学校から帰ってきて玄関のドアを開けた時。いつもなら居間には母がいて、キッチンで夕食を作っているはずであるのに、居間の方は電気が消えていて真っ暗だ。
「お母さん、どこにいるのー?」
私は玄関からそう言ったが、家の中はしんと静まりかえっていて、まるで人の気配がしない。
カギは開いているのに・・・掛け忘れて買い物にでも行ったのだろうか。
のんきな母だからたまにこういう事もあるのだ。やれやれと思いながら靴を脱いで家に上がろうとしたそのとき。
「カン、カン」
居間の方であの音がした。
私は全身の血という血が一気に凍りついた。
数年前と、そして昨日と全く同じあの音。
ダメだ! これ以上ここに居てはいけない。
恐怖への本能が理性をかき消した。
ドアを乱暴に開け、無我夢中でアパートの階段を駆けおりた。
一体何があったのだろうか・・・
お母さんはどこにいるの?妹は?
家族の事を考えて、さっきの音を何とかして忘れようとした。
これ以上アレの事を考えていると気が狂ってしまいそうだった。
すっかり暗くなった路地を走りに走ったあげく、私は近くのスーパーに来ていた。
「お母さん、きっと買い物してるよね」
一人でそう呟き、切れた息を取り戻しながら中に入った。時間帯が時間帯なので、店の中にはあまり人がいない。
私と同じくらいの中学生らしき人もいれば、夕食の材料を調達しに来たとみえる主婦っぽい人もいた。
そのいたって普通の光景を見て、少しだけ気分が落ち着いてきた。
私は先ほど家で起こった事を考えた。
真っ暗な居間、開いていたカギ、そしてあの金属音。
家の中には誰もいなかったはず。アレ以外は――
私が玄関先で母を呼んだ時の、あの家の異様な静けさ。
あの状態で人なんかいるはずがない・・・
でも、もし居たら?
私は玄関までしか入っていないのでちゃんと中を見ていない。
ただ電気が消えていただけだった。
もしかすると母はどこかの部屋で寝ていて、私の声に気付かなかっただけかもしれない。
何とかして確かめたい。
そう思い、私は家に電話をかけてみることにした。
スーパーの脇にある公衆電話。
お金を入れ、震える指で慎重に番号を押していく。
受話器を持つ手の震えが止まらない。
1回、2回、3回・・・・
コール音が頭の奥まで鳴り響く。
「ガチャ」
誰かが電話を取った。
私は息を呑んだ。
耐え難い瞬間。
「もしもし、どなたですか」
その声は母だった。
その穏やかな声を聞いて私は少しほっとした。
「もしもし、お母さん?」
「あら、どうしたの。今日は随分と遅いじゃない。何かあったの?」
私の手は再び震え始めた。
手だけじゃない。
足もガクガク震え出して、立っているのがやっとだ。
あまりにもおかしすぎる・・・
いくら冷静さを失っていた私でもこの異常には気付かないはずはない。
「なんで・・・お母さ・・・」
「え?なんでって何が・・・ちょっと、大丈夫?本当にどうしたの?」
母が今、こうやって電話に出れるはずはない。
私の家には居間にしか電話がないのだ。
さっき居間にいたのはお母さんではなく、あのバケモノだったのに。
なのにどうして、この人は平然と電話に出ているのだろう。
それに、今日は随分と遅いじゃない、と。
まるで最初から今までずっと家にいたかのような言い方だ。
私は、電話の向こうで何気なく私と話をしている人物が得体の知れないもののようにしか思えなかった。
そして私は、乾ききった口から、何とかふりしぼって声を出した。
「あなたは、誰なの?」
「え?誰って・・・」
少しの間を置いて、返事が聞こえた。
「あなたのお母さんよ。ふふふ」
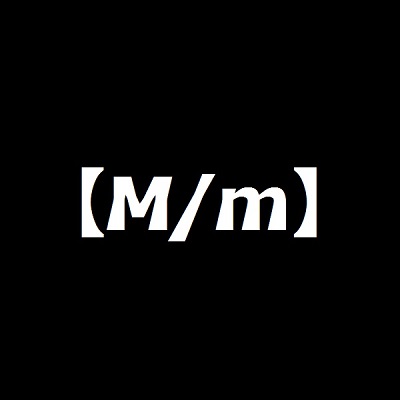

 TOP
TOP